図書館司書の主な仕事内容
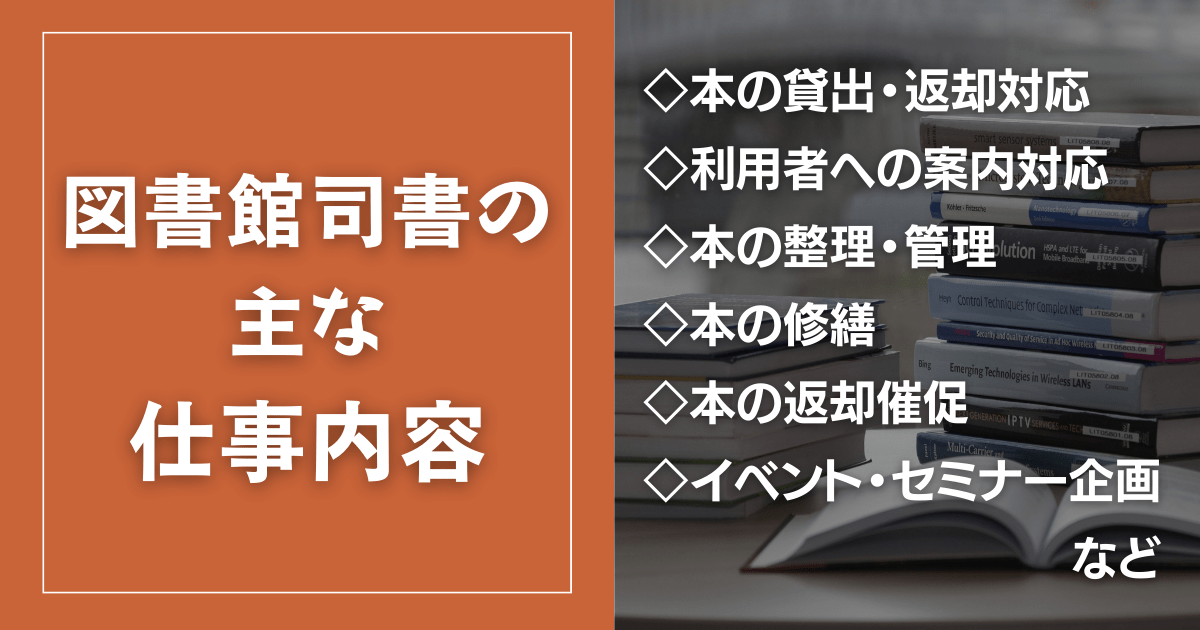
本の貸し出し・返却対応
図書館司書の業務の一つにカウンター業務があります。
これは、多くの方が図書館司書の仕事として最初に思い浮かべる業務かもしれません。
図書館で取り扱っている本や新聞、CD、DVDなどの貸し出し・返却手続きや、はじめて利用する方の利用者情報の登録などをおこないます。
かつては紙で貸し出し記録を管理していましたが、現在はデジタル管理が主流です。
図書館資料の適切な管理に関わる重要な仕事のため、丁寧さと正確さが求められます。
利用者への案内対応
利用者からの質問や相談に対応したり、図書館の利用方法を案内したりする業務も、図書館司書の重要な役割の一つです。
特に、利用者が求めている情報や資料を探し出すレファレンスサービスは、司書としての専門性が発揮される場面でもあります。
たとえば「〇〇について調べたい」「子どもにおすすめの本を知りたい」といった問い合わせに対して、適切な資料や情報を提供します。
このような案内対応は、図書館を利用する方との信頼関係を築くうえでも非常に重要です。
丁寧で親しみやすい対応を心がけることで、図書館の利用促進にもつながります。
本の整理・管理
図書館にある本や資料の整理・管理も、司書の大切な業務のひとつです。
新しく受け入れた資料を所定の棚に配架したり、返却された本を正しい場所に戻したりする作業を通じて、図書館の蔵書を常に整った状態に保ちます。
図書館資料には、ジャンルや内容に応じて請求記号が付けられており、これに従って本を分類・整理することで、利用者が目的の資料をスムーズに見つけられるようになります。
また、資料の正確な配置は、司書自身が蔵書を把握し、適切に管理するうえでも欠かせません。
本の修繕
図書館の本は多くの人に利用されるため、ページが折れたり、破れそうになったりすることがあります。
これらの傷みをそのままにしておくと、状態がさらに悪化し、資料としての価値を損ねてしまいます。
図書館の蔵書は長期間の使用を前提としており、頻繁に買い替えることは想定されていません。
そのため、図書館司書が日々の点検を通じて早い段階で本の修繕をおこない、資料をできるだけ長く使えるよう努めています。
本の返却催促
貸し出された本は必ずしも返却期限内に戻るとは限りません。
人気の本は予約待ちになることもあります。
ほかの利用者のためにも、延滞本の早期返却を促す連絡は、図書館司書の大事な仕事のひとつです。
利用者向けイベントやセミナーの企画実施
図書館司書は、利用者に本の魅力を知ってもらうためのイベントやセミナーの企画もおこないます。
利用者のなかにはイベントを楽しみにしているという方も多いでしょう。
幼児や児童を対象とした本の読み聞かせや有識者を招いてのセミナーなど、さまざまな企画を実施します。
その他の仕事
図書館司書の業務は幅広く、ほかにも以下のような仕事を担当します。
- おすすめ本などの告知ポスター、POPの作成
- 地域への広報活動
- 資料に関するデータ集計・統計作成
- 利用者へのアンケート調査
図書館別の仕事内容について
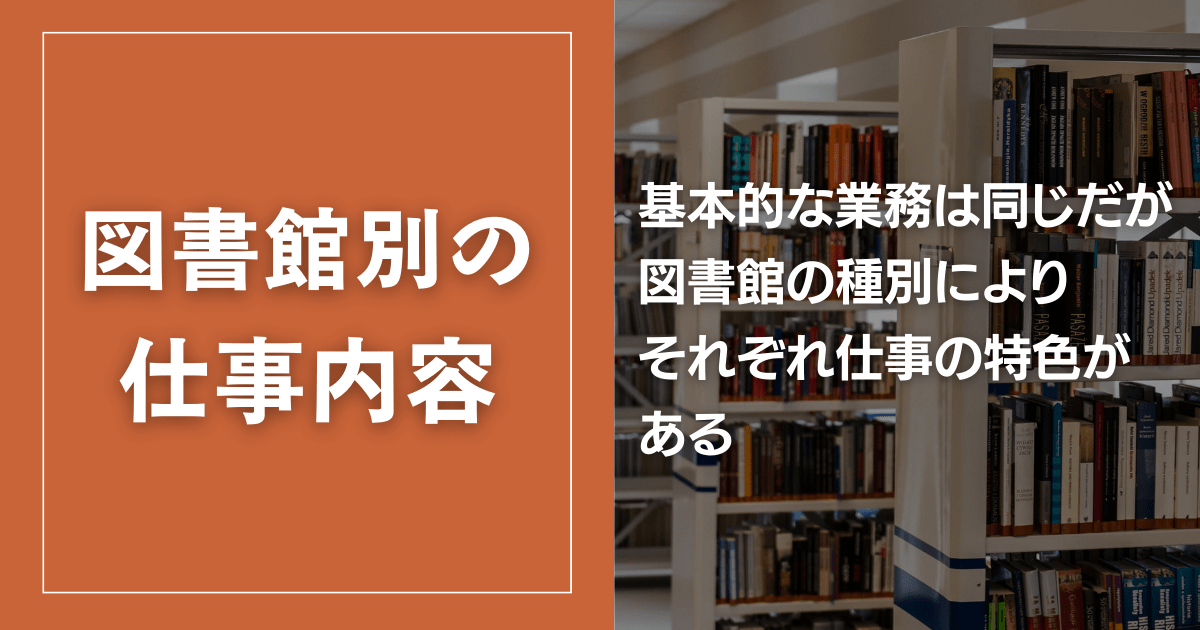
司書が働く図書館の分類
図書館司書が勤務する図書館には、以下のような種類があります。
どの図書館でも共通して行われる業務として、本の貸出・返却、資料の管理といった基本的な図書館運営の業務があります。
しかし、勤務先の種類によって司書が担う役割は異なってきます。
公立図書館の仕事内容
公立図書館は、地方公共団体が運営する図書館です。
都道府県立図書館や市区町村立図書館などが公立図書館に該当します。
公立図書館は住民サービスに特化しており、子どもから高齢者まで幅広い利用者層に対応します。
レファレンスサービス(資料探しや調べものの支援)はもちろん、おはなし会・読書週間などの読書推進イベントや高齢者向けの講座・勉強会など地域住民向けサービスの実施も公立図書館の司書の大事な仕事です。
郷土資料の収集・保存や、地元作家に関する情報の整理など、地域密着の仕事も担うのが公立図書館の特徴と言えるでしょう。
学校・児童館・他市の図書館と連携することもあり、図書館ネットワークや相互貸借の業務もこなします。
参考
公益社団法人日本図書館協会/公共図書館(公立図書館)
豊中市立図書館/図書館の高齢者サービスの先進事例
小中高の学校図書館の仕事内容
学校図書館は、小学校・中学校・高校のなかにある図書館です。
学校図書館は児童・生徒への教育支援を目的に運営されているのが特徴です。
学校図書館に関わる職種には、教員としての立場から読書指導などを行う司書教諭と、図書館の運営や管理を主に担う学校司書の2つがあります。
司書教諭の仕事
司書教諭は学校図書館の運営や児童・生徒への読書指導、学習支援を担う教員のことです。
12学級以上の学校には必ず司書教諭が配置されます。
司書教諭の仕事には、本や資料の選定、収集、提供のほか、生徒に向けた読書週間づくりの指導や調べ学習のサポート、図書館の利用ルールについての周知などがあり、教育活動の一環として図書館運営に関わります。
多くの場合、司書教諭としての仕事のほかに教科指導や学級担任などの業務を兼任しています。
関連記事 司書教諭とは?図書館司書との違いや給料について解説!
学校司書の仕事
教員ではなく、事務職員として採用された方が学校図書館の司書として仕事をする場合は学校司書と呼ばれます。
学校司書は、本の管理や貸出・返却対応など通常の司書としての仕事のほかに、教諭や司書教諭との協力の上、生徒の学習活動のサポートや地域への広報活動をおこないます。
出典
文部科学省/司書教諭 よくある質問集
公益社団法人全国学校図書館協議会/学校司書とは?
大学図書館の仕事内容
大学図書館は、大学の教育・研究活動を支えるために設置された図書館です。
専門的な学習や研究が行われる機関であるため、学術的な専門書や論文を多く所蔵しているのが特徴です。
大学図書館では、他の図書館と資料を貸し借りする相互貸借サービス(ILL:Interlibrary Loan)も重要な業務の一つです。
これは、他大学や他機関から必要な資料を取り寄せたり、自館の資料を提供したりすることで、学術研究を支援する役割を果たしています。
このような資料の相互利用は公立図書館などでも行われていますが、特に大学図書館では研究活動の一環として頻繁に利用される点が特色といえるでしょう。
国会図書館の仕事内容
国会図書館(国立国会図書館/NDL)は、国の機関として国会の活動支援と国民の知的基盤を支える役割を担っており、その中で働く司書の仕事は非常に専門的かつ多岐にわたります。
国会図書館は7つの部局と、行政・司法各部門支部図書館27館とで組織されています。
国会図書館の中心を担う7つの部局での仕事を以下に紹介します。
調査及び立法考査局
国会議員や国会関係者からの調査依頼に対応します。
文献の複写や貸出のほか、政治・経済・社会・文化・科学技術など各分野におけるデータ収集や調査・分析結果の提供、外国の法律・制度に関する比較調査など調査研究の仕事を担っています。
司書というよりもアナリストとしての役割が大きいといえるでしょう。
収集書誌部
国内・海外の出版物を網羅的に収集し、書誌データ等を作成・提供している部局です。
資料を後世に残すための資料保存もおこなっています。
利用者サービス部
国内外の利用者に図書館サービスを提供する部局です。
東京本館で資料の閲覧・複写・レファレンスなどの来館サービスを提供するほか、遠隔複写やデジタル化資料の送信といった来館不要で利用できるサービスも担っています。
また、特色ある資料を紹介する展示会の企画・実施も行っています。
国会図書館の中では比較的、一般の図書館司書に近い仕事をしている部局といえるでしょう。
電子情報部
所蔵資料のデジタル化やネットワークシステムの管理を担当しているのがこの部局です。
国会図書館の次世代サービスを構築するために、調査研究や実験もおこなっています。
関西館
大阪・京都・奈良の文化・学術・研究拠点である関西文化学術研究都市にある関西館では、アジア関係資料や博士論文などの資料収集や整理、保存、資料や情報の提供をおこなっています。
国際子ども図書館
上野公園にある国立の児童書専門図書館です。
国内外の児童書や関連資料の収集等をおこない、児童書の展示や講演会、体験会などのイベントを開催することで広く情報発信をしている部局です。
こちらも一般的な図書館に近い役割を担っているといえるでしょう。
総務部
国会図書館の運営のため、図書館の方針立案・予算管理・人事などを総合して担う部局です。
一般企業でいう労務や経理、人事の部署にあたる部局であり、図書館司書の仕事からは離れた仕事を担当します。
参考 国立国会図書館HP
司書の就職先・転職先
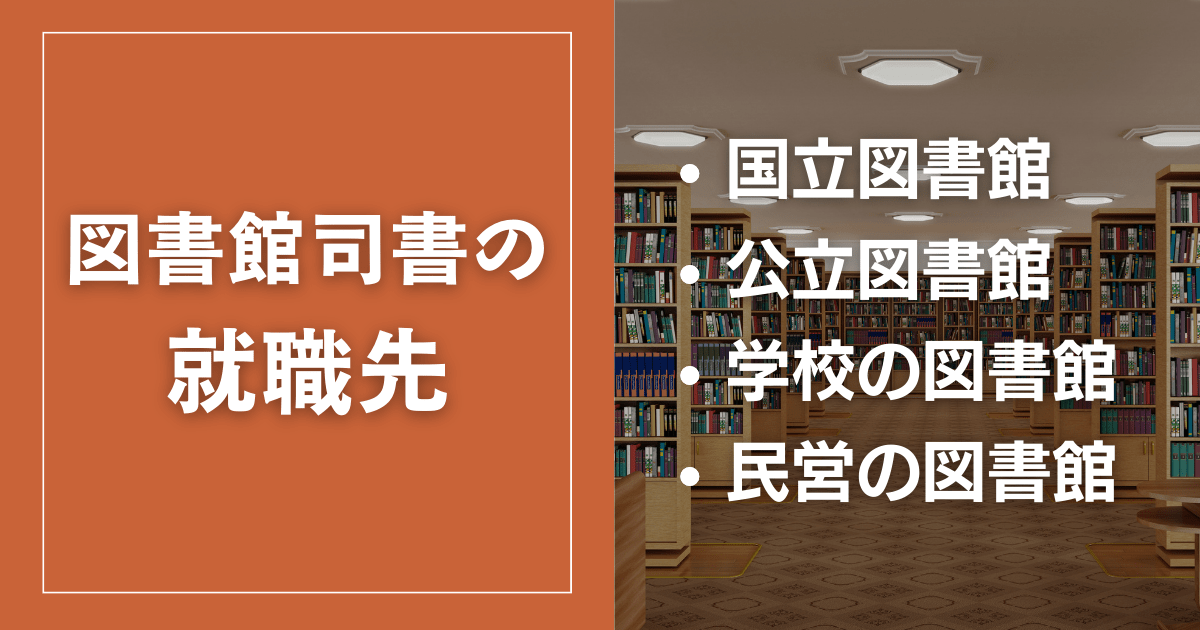
図書館司書の主な就職先・転職先には、次のような例が挙げられます。
公立図書館
公立図書館は全国に広く存在し、自治体の規模に応じて設置数や職員数も多くなるため、司書が勤務する場所としては最も一般的といえるでしょう。
一般行政職としての採用
自治体によっては、図書館職員を一般行政職として採用している場合があります。
一般行政職として採用された場合は地方公務員の扱いとなり、給与や待遇が安定するのが大きなメリットです。
ただし、一般行政職として採用された場合は必ず図書館に配属されるとは限りません。
配属先は自治体内のさまざまな部署の中から決定されるため、図書館での勤務を希望していても別の部署に配属される可能性があります。
一般行政職の採用において司書資格は必須とされていませんが、司書資格を有していることが配属先を決める際に考慮され、図書館への配属につながる可能性はあるでしょう。
専門職としての採用
司書を専門職として採用する自治体も存在します。
この場合は、採用試験の段階から司書職として募集され、一般行政職としての採用とは異なり確実に司書としてのキャリアを積むことができます。
しかし、司書専門職の正規職員の募集は少ないのが現状です。また、司書の仕事を志望する方は多く、非常勤の求人であっても応募が殺到します。
応募に際して司書の資格を求められることが多いため、図書館で専門職として働きたいと考える場合は、あらかじめ司書資格を取得しておくことをおすすめします。
関連記事 図書館司書資格の取得方法
小中高の学校図書館
学校の図書館司書も司書の仕事を目指す人たちに人気の職場です。
学校図書館に関わる職種には司書教諭と学校司書の2つがあります。
司書教諭として就職する
司書教諭として勤務するためには、小・中・高または特別支援学校いずれかの教員免許状の取得と司書教諭講習の受講が必要です。
講習については、文部科学省が指定する司書教諭講習を受講するほか、大学で司書教諭講習に相当する科目を修得することで講習の受講に替えることができます。
大学で教員免許の取得を目指す方は、司書教諭講習科目も合わせて履修しておくといいでしょう。
必要な資格の取得に加えて、教員採用試験に合格して公立学校に教員として採用されることで司書教諭の道を目指すことができます。
なお、司書教諭は、通常のクラスでの教科指導や学級担任などの業務と兼任するのが一般的です。
そのため、司書の仕事のみを担当できるということはほとんどない点に注意が必要です。
学校司書(学校職員)として就職する
学校司書は、学校図書館の運営を担う専門職員です。
応募条件に司書資格が求められることが多く、学校司書を目指す場合は事前に司書資格を取得しておくとよいでしょう。
公立学校の学校司書を目指す場合は、各自治体が実施する採用試験や募集に応募する必要があります。
多くの場合、会計年度任用職員として非常勤で採用され、任期は原則1年ごとの更新制です。また、勤務する学校が年によって変わるなど、異動があるケースもあります。
一方、私立学校の場合は、学校法人が直接採用を行うため、学校ごとの求人情報を確認し、自分で応募します。
契約職員や正職員として採用されるケースもあり、雇用条件や業務内容は学校によってさまざまです。
大学図書館
大学図書館の司書を目指す場合は、各大学や大学法人などが行う採用試験や募集に応募します。
国立大学の附属図書館で正規職員(事務系・図書)として働くには、国立大学法人等職員採用試験を受験し、合格する必要があります。
この試験は全国を複数のエリアブロックに分けて実施されており、受験者は希望するブロックを選んで受験します。
公立大学で正規職員として勤務したい場合は、地方公共団体が実施する採用試験に合格する必要があります。
国立・公立大学とも司書を非常勤として募集していることがあり、この場合は大学や大学法人に直接応募するのが一般的です。
私立大学では、学校法人が独自に職員を募集しており、採用形態や応募条件は大学ごとに異なります。
勤務条件や選考方法なども法人ごとの方針によって異なるため、各大学の採用情報を確認することが必要です。
民間企業に司書として応募する道も
公立図書館や学校図書館などでは、民間企業に図書館業務を委託するケースが増えています。
そのため、自治体や学校法人に直接雇用される以外に、委託先の企業に応募して図書館で働くという道もあります。
委託先で働く場合も、司書資格を持っていると採用されやすくなり、待遇が良くなることもあります。
求人によっては司書資格が応募条件になっていることもあるので、取得しておくと安心です。
また、外部委託による採用は自治体での正規採用に比べて応募しやすいのも特徴です。
未経験から図書館での実務を積みたい方にとって、キャリアの第一歩として有効なルートといえるでしょう。
国会図書館
国会図書館で働く職員は、特別職国家公務員に分類される国会職員です。
採用は国立国会図書館が独自に実施する試験によって行われています。
たとえば令和6年度には総合職の応募者406名に対して採用3名、一般職の応募者593名に対して採用17名という狭き門です。
国立国会図書館の職員を目指す場合は試験内容をふまえた十分な対策が必要になるでしょう。
尚、国立国会図書館の採用試験において司書資格の有無は問われません。
関連記事 司書教諭について詳しく
図書館司書の仕事のおすすめポイント
専門スキルを活かした仕事ができる
図書館司書の仕事では、資料の選定や分類、レファレンス対応など、専門的な知識を活かす場面が多くあります。
図書館は子どもから大人、高齢者まで、さまざまな人の学びを支える場でもあります。本や情報に関する専門性を高め、読書や調べもののプロとして活躍できるやりがいのある仕事といえるでしょう。
落ち着いた職場で仕事ができる
図書館は静かな空間で、事務作業が中心となるため、落ち着いた環境で仕事をしたい方に向いています。
司書の仕事は少人数あるいは一人でおこなうことが多く、比較的ゆるやかな人間関係の中で働ける点も魅力です。
図書館司書を目指す上での注意点
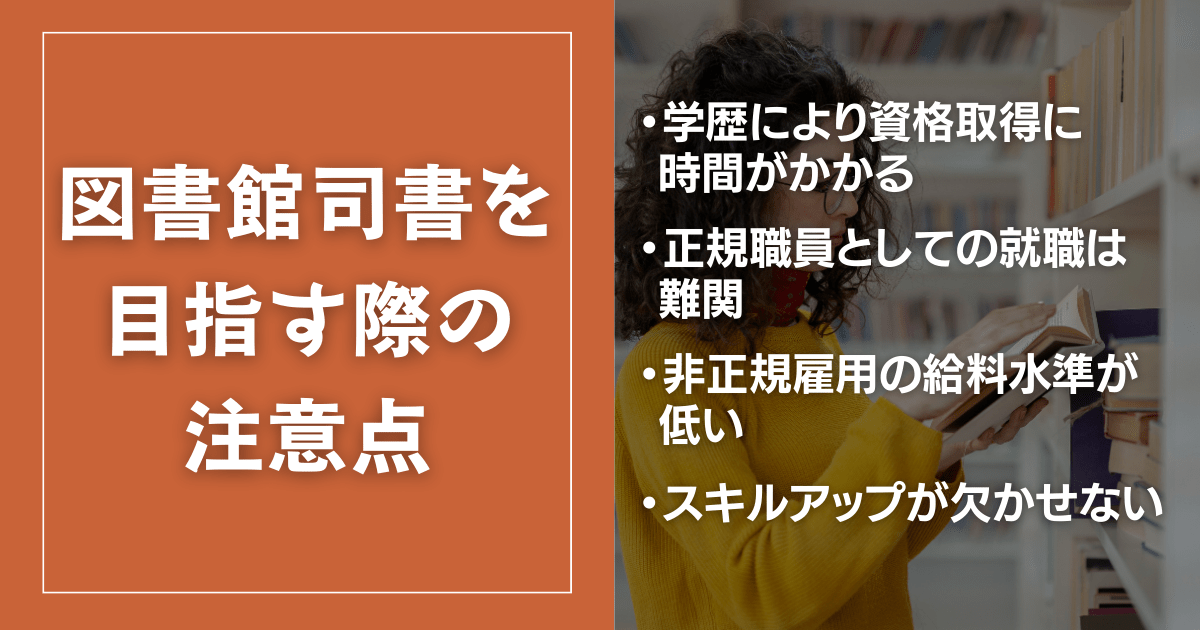
資格取得に時間がかかるケースも
図書館司書を目指すなら司書の資格取得が推奨されますが、資格取得にかかる期間は学歴や経験によって異なります。
たとえば、高校卒業後に司書資格を目指す方は、図書館司書課程のある大学に進学するか、あるいは3年以上司書補としての実務経験を積んでから司書講習を受講するなど、資格取得までに年単位の時間を要します。
なお、すでに大学・短期大学・高等専門学校を卒業している方については、大学で科目等履修生として必要な単位を修得するなどの方法があり、1年以内に資格を取得することも可能です。
資料請求(無料) 司書の資格を取得できる通信制大学のコース一覧
関連記事 働きながら司書資格を取得するには?
正規職員としての就職は難関
図書館司書は人材の流動が少なく、正規職員の募集がとても少ないという現状があります。
また、公立図書館で正規職員としての就職を目指す場合は地方公務員試験の受験が必要になるため、司書資格を持っているだけでは採用されるのが難しいのが現実です。
非正規雇用の給料水準が低い
図書館司書の給与水準が他の職種に比べて低い点も注意したいことの1つです。
雇用形態にもよりますが、図書館司書は非正規職員の数が多く、給与は低い傾向にあります。
関連記事 図書館司書の給料・年収について詳しく
司書を目指せる通信大学はこちら
図書館司書の仕事のやりがい
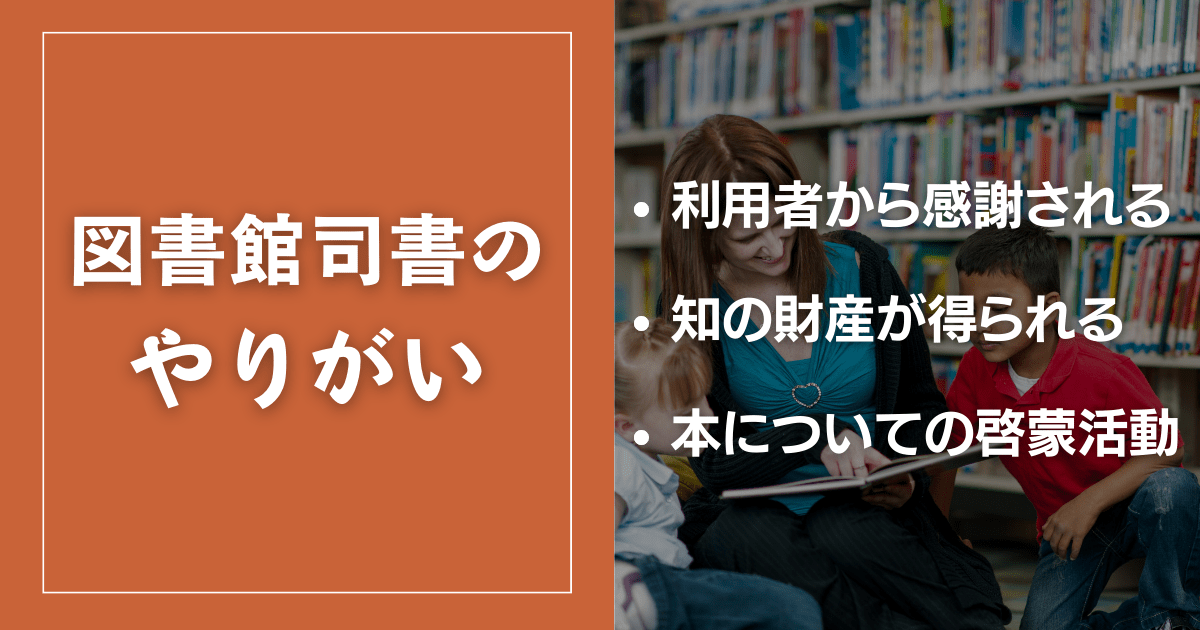
利用者から感謝される
タイトルや著者がわからない本を探している際、図書館の司書に本のことを尋ねて、その本がどの本なのかを教えてもらった経験はないでしょうか。
コンピュータによる検索システムができたといっても、検索システムでは書籍名の一部や、著者名の一部がわからないと検索ができません。
探していた本を見つけることができた利用者から、感謝をされる場面は多いはずです。
司書としての存在意義ややりがいを感じられる瞬間の1つでしょう。
知の財産が得られる
司書資格を有していたとしても、最初からあらゆる本についてなんでも知っているという方はいないでしょう。
日々の仕事の積み重ねが自分の力になっていくものです。長く働けば働くほど、その図書館で扱う本や資料に詳しくなります。
利用者の話を聞いて、どの分野のどのような本のことなのかを判断できる力は、まさに知の財産といえるのではないでしょうか。
本についての啓蒙活動
本が好きな図書館司書にとっては、利用者に本の魅力を知ってもらうのもうれしいことの1つでしょう。
図書館では読み聞かせや読書会、払い下げ図書の頒布会などさまざまなイベントがおこなわれています。
それらを企画・運営するのも司書の仕事です。
利用者の反応に直接触れる機会であり、大きなやりがいを感じられるでしょう。
司書の仕事で大変なこと
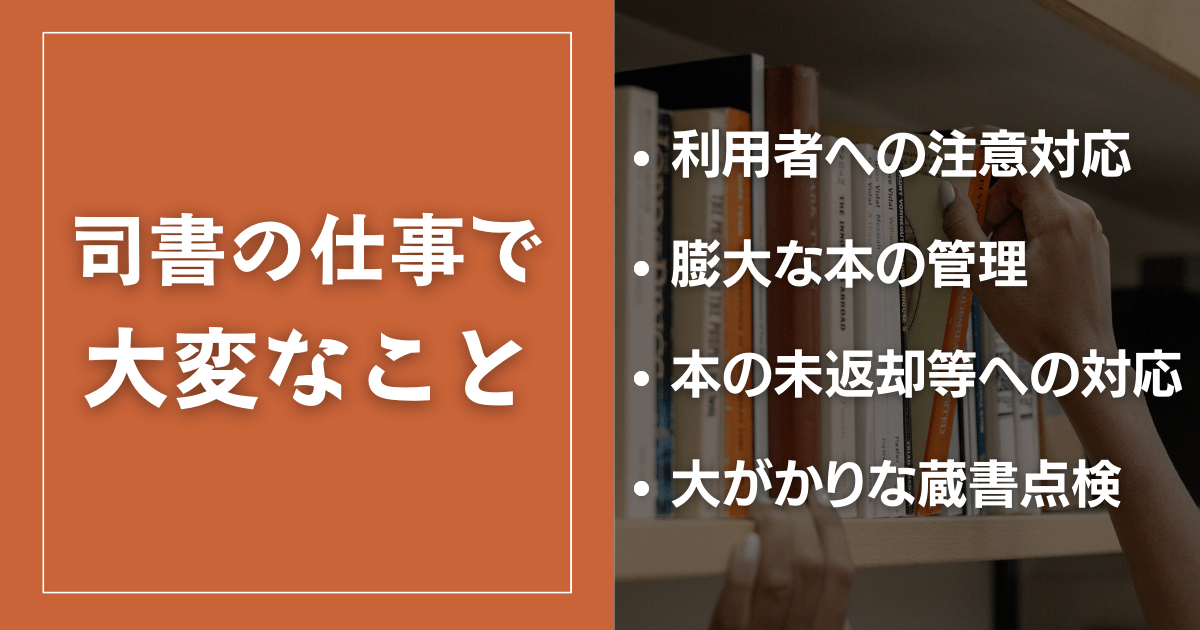
利用者への注意対応
図書館は公共の場です。
利用者同士、マナーを守ってもらうことで、図書館がより使いやすい環境になるといえるでしょう。
利用者の様子を見つつ、必要があれば注意をするのも司書の仕事の1つです。
粘り強さが大切
雑談で声が響いている、一人で座席をいくつも使っている、などがマナー違反の例として挙げられます。
また、貸出窓口で「なぜこの本が借りられないのか」というような、持ち出し禁止の本についてのクレームが入るかもしれません。
利用者に図書館のルールを理解していただくためにも、粘り強く説得していくことが大切だといえるでしょう。
膨大な本の管理
書籍の管理
利用者が必要な本をすぐに見つけられるよう、書籍を管理するのも司書の大切な仕事です。
書籍は分野ごとに分類コードで整理されており、購入・寄贈・他館からの受け入れなどで新たに受け入れた書籍については、専用システムにタイトル・著者名・出版社・ページ数、受け入れ日などの基本情報を登録します。そのうえで、バーコードや分類ラベルを貼付し、保護用のフィルムカバーを装着します。
また、新規書籍の登録だけでなく、利用者の登録や、貸出・返却といった日常的な業務にも図書館システムを使用して対応しています。
返却本のチェック・修繕作業
返却された書籍をチェックし、破れや汚れがある本は修繕してから書棚に戻します。
書籍が所定の書棚に入っているか確認し、整頓する作業もあります。
書籍の管理や返却・修繕作業は手作業でおこないます。地道で大変な業務といえるでしょう。
本の未返却への対応
一定の期日を過ぎても本の返却がない場合は返却の督促をおこないます。
いわば取り立ての仕事であり、気分よくできる仕事ではないかもしれませんが、図書館にとって本は財産です。
毅然とした態度で適切に返却を促しましょう。
大がかりな蔵書点検
図書館により頻度は異なりますが、定期的に蔵書点検と呼ばれる大がかりな書棚の整理や清掃を実施します。
利用者が本来あるべき場所と違う棚に本を戻していたり、無断で本を持ち出していたりすることもあるでしょう。
書籍データと書棚の照らし合わせをおこないながら、本を整理していきます。
職員総出の作業となり、一般的に蔵書点検の間は図書館を閉館します。
図書館司書の仕事に向いている人
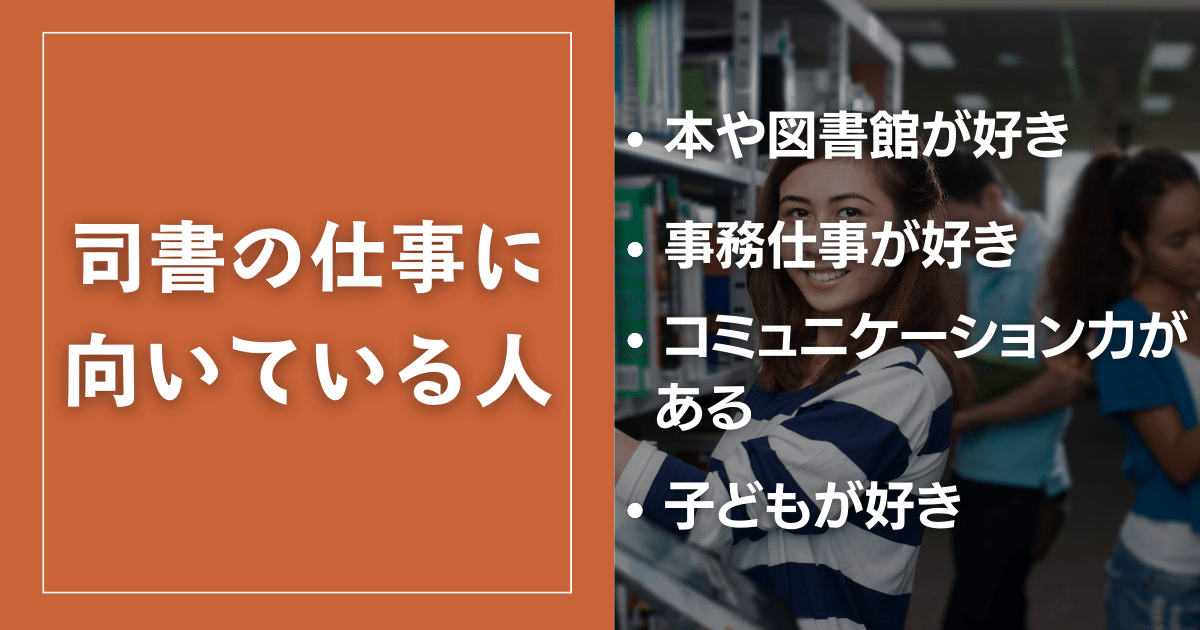
本や図書館が好きな人
図書館司書は勤務時間のほとんどを本に関する業務に費やしますので、本や図書館好きにはおすすめの職業です。
本の整理から新たに購入する書籍の選別に至るまで、図書館司書に任せられています。
そのため、幅広いジャンルの本に関する興味・関心の高さが求められるでしょう。
事務的な仕事をこつこつとこなせる人
図書館司書の仕事は事務作業がメインになります。
数えきれないほどの数がある蔵書を管理し、点検しなければなりません。
大量の本と向き合い、根気よく丁寧に作業をおこなえる人が図書館司書に向いているといえます。
コミュニケーションを取るのが好きな人
図書館司書は、人とのコミュニケーションが欠かせません。
図書館を訪れる利用者と円滑なやり取りをおこなう必要があります。
利用者の本の捜索の手助けや、イベントでの交流は、図書館司書の重要な仕事です。
業務を淡々とこなすだけでなく、思いやりをもって利用者とやり取りができる人が図書館司書の仕事には向いているでしょう。
子どもが好きな人
公共図書館や小学校の図書館では、児童向けの読み聞かせイベントを開催すること事があります。
子どもを対象としていますので、子どもが好きな方が向いています。
日々子どもとコミュニケーションをとり、成長を見守ることをやりがいに感じられる方も向いているでしょう。

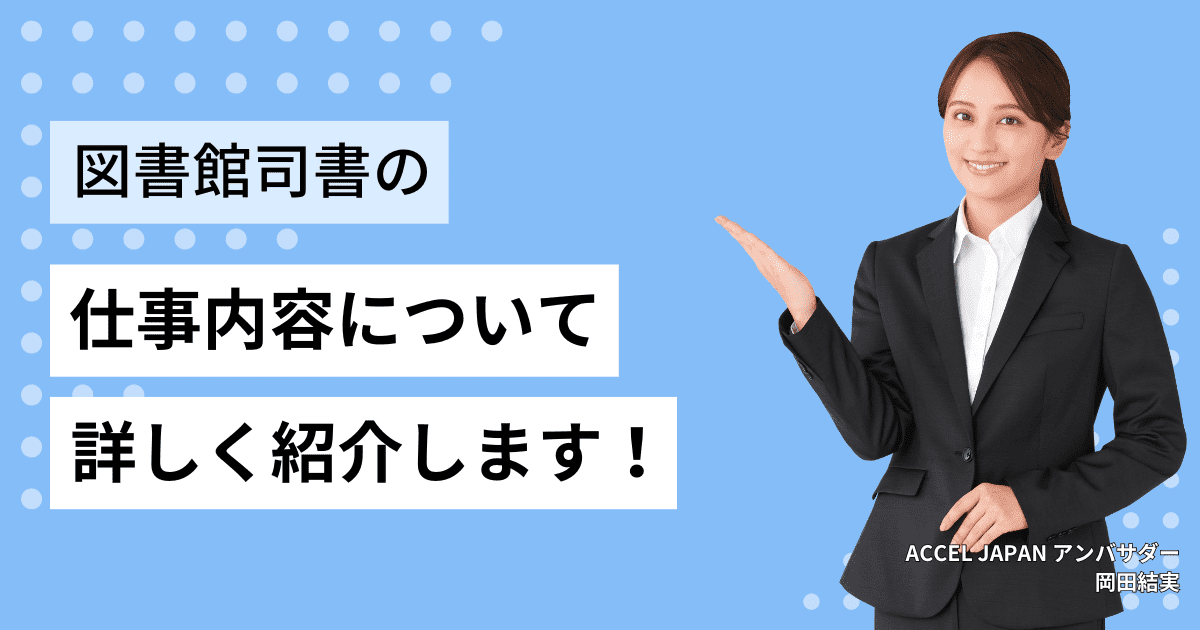


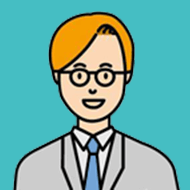



 失敗しにくい学び直しの始め方|資格を決める前の準備編
失敗しにくい学び直しの始め方|資格を決める前の準備編
 オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!
オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!
 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
 メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
 心理学で、自分と誰かの人生を整える。「心」の専門家として歩み始める第一歩
心理学で、自分と誰かの人生を整える。「心」の専門家として歩み始める第一歩





