社労士は独学で合格できる?

社会保険労務士(社労士)試験は、例年合格率が5%~7%の国会s核であり、数ある資格のなかでも難しい部類の試験です。
受験者の中にはもちろん「独学で合格した」という方もいます。しかしそういった方のほとんどが社労士事務所などでの実務経験があったり、予備知識を持っていたりするのです。
社労士試験の合格には約1,000時間以上の勉強時間が必要ともいわれています。勉強すべき範囲が広く、法改正があった際にもブラッシュアップしなければならないため、独学で長期間勉強のモチベーションを保つのが難しいこともあるでしょう。
試験を初めて受ける方の場合には、試験対策のための予備校に通ったり、通信講座を受講したりして合格を目指す方がおすすめです。
社労士試験を独学で目指すメリットとは
社労士試験への合格を独学で目指すメリットは以下の通りです。
- 自分のペースで学習を進められる
- 自分に合った参考書を選ぶことができる
- 学習費用を抑えることができる
社労士試験の受験者は、半数以上が会社員の方です。つまり働きながら勉強を進めている方がほとんどなのです。スクールに通うことでプロの手を借りながら試験対策に打ち込めますが、働きながら予備校に行くのは大変な方もいるでしょう。独学なら自分のペースで学習を進められるため、身体的な負担も軽くなります。
社労士試験の参考書は数多くあり、その中で自分が使いやすいものを選べるのも独学のメリットです。予備校や通信講座では決められたテキストを使用するため、自分で考えたり口コミを確認したりして選びたい方にとっては独学の方がよいでしょう。
社労士試験の対策講座は、受講費用が10万円~30万円かかるものがほとんどです。決して安くはない受講費用ですが、独学なら基本的には参考書のみで勉強を進められます。学習費用を抑えられる点も独学のメリットの1つでしょう。
独学で学習するデメリット
社労士試験を独学で目指そうと考えている方は、独学のデメリットも踏まえておくとよいでしょう。独学でのデメリットは以下が挙げられます。
- スケジュール管理や目標設定が難しい
- わからないところも自分で調べて解決しなければならない
独学では基本的に困ったときやわからないことが出てきたときにも、自分で1から調べなければなりません。学習のスケジュールや目標設定も自分自身でおこないます。
学習に慣れている方であれば問題ないかもしれません。しかし初めて学習する方にとってはハードルが高いでしょう。学習を始める前に、通信講座やスクールについて調べてみて、そのうえで学習方法を選択するのもおすすめですよ。
社労士試験に独学で合格するためのおすすめ勉強法
ここからは、社労士試験に独学で合格を目指すための「おすすめの勉強方法」を紹介します。
- 学習計画やスケジュールを立てる
- 入門書を一周する
- 演習問題を中心に反復学習する
(1)学習計画やスケジュールを立てる
社労士試験への合格に必要な学習時間の目安は「1,000時間以上」といわれています。働きながら学習を進めようとする場合、1日に確保できる学習時間を自分の場合はどのくらいか考えてみましょう。
例えば1日に2~3時間の学習時間を確保する場合、試験日から逆算すると約1年前に学習を始めなければなりません。仕事が休みの日に勉強時間を増やせそうな方は、1年よりも短い期間で試験に臨めるでしょう。
まずは自分のライフスタイルを振り返りながら、学習スケジュールを計画するのがおすすめです。
関連記事 社労士試験合格に必要な勉強時間は?最短合格のポイントも紹介します!
(2)入門書を一読する
社労士試験に初めて挑戦する方や、実務経験が多くない方はまず入門書を読み切りましょう。社労士試験は試験範囲が広いうえ、試験科目である10科目それぞれで合格基準点を獲得しなければなりません。
まずはベースとなる基本の知識を身に付けましょう。入門書は基本知識を身に付けるために適した内容のものがおすすめです。入門書をよむことで、社労士試験の法律科目に慣れることができ、試験で出題される法律の関係が理解できるようになるでしょう。
とくに、初学者の方が入門書を選ぶ際に、押さえておくべきポイントを紹介します。
- 法律用語や条文の解説がある
- 図やイラストなどがありビジュアルでわかりやすい
- 漫画形式など初めてでも読み進めやすい
また、社労士試験は法改正にも対応しなければなりません。毎年法改正があるため、勉強に使用する参考書も法改正に対応しているものを選びましょう。
(3)演習問題を中心に反復練習する
入門書で基礎知識を身に付けたら、演習問題を繰り返しおこないましょう。実際に問題を多く解いていくことで、現時点での自分の理解度を把握することができます。
問題を解き、わからないところや自信がないところを復習して、少しずつ知識を確かなものにしていく学習方法がおすすめです。
独学で演習問題をおこなう際には、以下のポイントに注意しましょう。
- テキストと同じシリーズの問題集を活用する
- インプットはテキストで、アウトプットは問題集でおこなう
- 5年分の過去問に取り組む
社労士試験は過去に出題された問題を、アレンジして出題されることが多くあります。そのため、過去問はマストで取り組んでおきましょう。
問題集を繰り返し解くことで、頻出問題の傾向がつかめるようになります。頻出問題は実際の試験でも出題される可能性が高いため、必ず正答が導き出せるように身に付けておきましょう。
学習に使用するテキストと問題集は、同じシリーズのものがおすすめです。同じシリーズなら、問題集でわからないところがあった場合にテキストで確認しやすくなります。
テキストや対策のための通信講座のなかには「頻出度」が記載されているものもあります。頻出度も参考にしながら対策をしていきましょう。
社労士試験を独学で合格するためのおすすめテキストは?
社会保険労務士(社労士)試験は、資格試験の中でもかなり難易度が高いです。そのため、詳しくわかりやすく解説された参考書を選ぶようにしましょう。
法律の初学者の方が、分厚くて難解なテキストを購入したとしても、勉強が長続きしない可能性もあります。
初学者の方の場合は、習慣的に読み進められて、かつ法律の知識が身につくようなテキストをお選びされることをおすすめいたします。
一方で、かなり学習が進んでいる方が、初学者の方に向けた参考書・テキストを繰り返し読み進めていても、合格率の向上には繋がりません。
上級者の場合は、実際の試験に触れることができる問題集を購入し、問題を解いていくという学習方法がよいでしょう。
テキストをお選びの際は、今のご自身の理解度のレベルなども考慮された上で、参考書を選ぶようにしましょう。
おすすめテキスト1:「みんなが欲しかった! 社労士の教科書」
社会保険労務士(社労士)試験を独学で学習する場合におすすすめのテキストが、初学者・独学者向けに開発された「みんなが欲しかった! 社労士の教科書 2023年度」です。
刊行しているのは、資格の学校TACで、社会保険労務士試験にも強いと評判があり、多くの方々から支持されている資格試験予備校です
「みんなが欲しかった!社労士の教科書2023年度」は、「働き方改革関連法」を含めた最新の法改正にも対応しています。この一冊だけ利用して学習しても、社会保険労務士試験の合格に必要な知識は身につくとされています。
書籍の特徴(おすすめポイント)は以下のとおりです。
- 社労士試験のスタートアップ講座なので、独学者だとしてもストレスなく知識をつけられる
- イラストが適宜利用されていて分かりやすくて、各科目がイメージしやすい
- 各CHAPTERの冒頭には、全体像が理解できるオリエンテーションが付いている
- 本文はカラフルでマスターすべきとところは本文に記載し、極力覚えた方がいい箇所はサイドにまとめられているため重要事項が一目瞭然
- 多彩なアイコンなどがあり瞬時にわかりやすい
- 〇×と穴埋めの2つの出題形式によるミニテストが、各科目Sectionの後にあり、Sectionごとでの理解度がわかる
- 労働関係科目と社会保険関係科目に分かれる、セパレートBOOK形式で持ち運びもしやすい
参考 Amazon みんなが欲しかった! 社労士の教科書 2023年度
おすすめテキスト2:「出る順社労士 必修基本書【2分冊合冊/セパレート式】」
社会保険労務士(社労士)試験の受験者から絶大な支持をされている資格試験予備校のLECです。
そのLECが社労士試験を独学で突破しようとする人向けに出版している社労士試験用のテキストが、受験生を最も楽に合格へ導く基本書「2023年版 出る順社労士 必修基本書【2分冊合冊/セパレート式】」。
独学で試験にチャレンジしている人から、使いやすさと学習効率のよさについて定評があります。
書籍の特徴(おすすめポイント)は以下のとおりです。
- 「労働編」「社会保険編」を分け2冊になるセパレート仕様のため、持ち運びにも便利
- 各法律の全体構造も含めて素早く理解できるように、図表を多く採用。学習すべきポイントが分かりやすい
- 過去30年分の過去問の主要出題箇所を分析し、おさえておきたいものを厳選して掲載
- 各科目の前に学び方を紹介、過去の出題や重要箇所の明示などの学習をラクにするための工夫がなされている
独学に自信がない方は講座の受講も検討しよう
社労士試験は合格率が5%~7%と非常に低く、試験範囲の広さもあり難易度の高い国家資格です。独学で合格する方は0ではありませんが、初学者の方にとっては、独学での一発合格はハードルが高く感じるでしょう。
それでも独学で挑戦したい方は、まず学習スケジュールを計画立ててみるのがおすすめです。計画した学習スケジュールが難しそうだと感じる場合には、対策講座や通信講座の受講も検討してみましょう。
対策講座では、プロの講師が生きた知識を教えてくれます。通信講座の場合には通学制のスクールに比べて、受講料を抑えられるのもポイントです。気になる方は資料請求をして比較してみてくださいね。

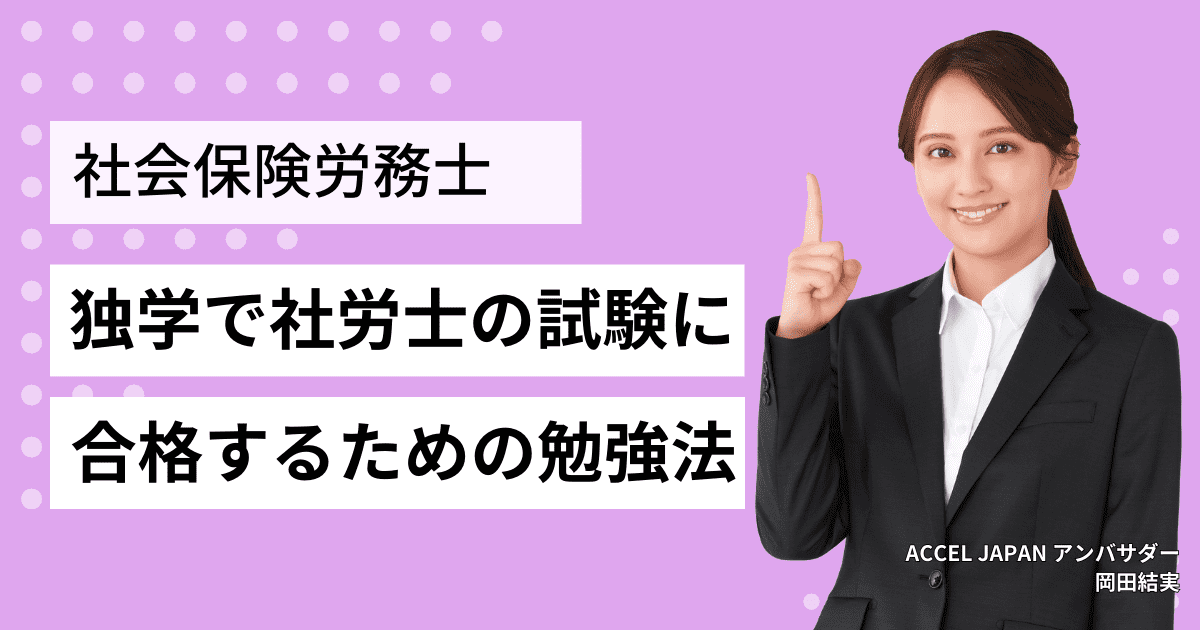






 40代・50代からでも大丈夫?キャリアコンサルタント資格の現実
40代・50代からでも大丈夫?キャリアコンサルタント資格の現実
 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
 メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
 失敗しにくい学び直しの始め方|資格を決める前の準備編
失敗しにくい学び直しの始め方|資格を決める前の準備編
 オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!
オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!





