社会保険労務士(社労士)の就職先

(1)社会保険労務士事務所
社会保険労務事務所では「労働社会保険」の各種手続き、相談などをおこないます。
具体例を挙げますと、人を雇用する際、『労働(雇用)契約書』という労働基準法に則った書類が必要となります。
また雇い入れた方に対して、健康保険や厚生年金、雇用保険、労災保険といった各種手続きがあります。
これらは各法に精通していなければなりません。
法改正もあり煩雑であるといえます。
そのため、多くの企業では専門家である社会保険労務士にこれらの仕事を任せています。
代表的ではありますが、求人募集が少ないのが難点であり、場合によってはすぐに就職できない可能性もあります。
そのため補助的な事務やパートタイムとしてキャリアを積むところからスタートされる方もいます。
(2)企業の人事・総務部
次によくある就職例としては、労務士事務所ではなく、労務士とは全然関係ない事業を行っている企業への就職です。
この場合は企業の人事や総務の一員として働きます。
俗に言う勤務労務士です。
企業の人事・総務部では、採用時の求人票作成、採用試験の実施、採用後の契約書や各種保険への加入手続きを、残業時間や有給休暇の取得状況の把握、産休・育休・介護休暇の手続き、従業員の健康管理、各種研修・教育の実施、職場環境の整備等その仕事内容は多岐にわたります。
人事や労務を社労士事務所に委託する企業も多数存在しますが、その場合、外注費が高くなってしまう可能性があります。ですが、社内で労務士を雇用することで、コンサルティング費を節約することができます。
また社内の社労士であれば、複雑な社内の労務問題も把握しているという点から、外部の労務士よりもさらに的確な提案が上がることも期待できるでしょう。
人事・総務の採用時に、労務士資格を持っている場合は優遇されることも少なくありませんのでチャンスも大きいといえます。
(3)コンサルティング会社
コンサルティング会社に就職することで、人事関係や労務関係についての相談やアドバイスを行うことができます。
雇用コストの見直しや雇用プランの設計などを行い、クライアント企業に利益をもたらす提案を行います。
コンサルティング会社で働くには、MBAや中小企業診断士の資格の方が有利とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、社会保険労務士(社労士)の就職先としても有利です。
企業の問題解決の中に労務管理といった分野もあります。
起業の際の各種手続きでも社労士の知識を必要とします。
社労士としては何か具体的な代行業務ではなく相談業務が中心となりますが、他の資格との組み合わせで、より力を発揮することができるでしょう。
コンサルティング会社では、業務を通じて会社経営について学ぶこともできます。独立時にコンサルティング会社で培ったスキルは多いに役立つことでしょう。
(4)独立開業
社会保険労務士(社労士)として数年間実務を積んだのちに独立開業する、というのも社会保険労務士のよくある事例です。
中には資格試験に合格後に独立される方も少なからずいらっしゃいます。
社会保険労務士の資格を得て、一番の魅力は自分の名前で独立開業できることかもしれません。
雇用される場合に比べて、自分で営業を行ったり、売上管理など、大変な面も沢山あります。
ですが、軌道に乗れば、勤務時によりも大幅に年収アップを望むこともできます。
企業との顧問料や就業規則の作成相談、助成金申請の書類作成など仕事内容に応じて、一定の相場に基づき料金を明示して仕事をおこないます。
企業と顧問契約を結んだ場合は、従業員何人で月額が決まるというかたちです。
一つの企業と契約することで、ある程度安定的な収入が見込めます。
実力次第でより多くの収入が見込めるのでやりがいにもつながります。
社会保険労務士(社労士)の転職先
(1)大企業の人事・経理・総務・厚生労働組合
一念発起して社会保険労務士(社労士)の資格を習得し、そのまま大手企業に就職するケースも多々あります。
大手企業には、人事課や総務課、経理課以外にも、労働組合(福利厚生課)という部署もあります。
中小企業では労働組合がなかったり、衛生管理者を置く義務のない所も多々あります。
加えて、中小企業では従業員数の少なさから各種保険手続きの書類作成も顧問契約の社会保険労務士事務所任せの場合が多いです。
ところが大企業の場合は人員が多いため、労働保険関連の書類の手続きも日常的に行われ、法令に基づく各種委員会の設置それに基づく書類の整備もあることから、社会保険労務士の需要が高いといえます。
過去に、人事や経理、総務などの実務経験がある方であれば、社会保険労務士の資格1つで、今の待遇よりも上の企業へ転職することが可能です。
(2)社労士事務所への転職
社会保険労務士(社労士)事務所への転職は、将来の独立開業を考えている方におすすめです。
業務としてはクライアント企業の労務問題のサポートと、コンサルタントして提案する業務の働き方があります。
事務所内で実際にどのような業務を行うのか経験を積むことができ、人脈というパイプづくりもできますので、独立後に役立つ可能性もあります。
また、少し特殊な事例にあたっても、業務の相談ができる環境も魅力的です。
ご自身のステップアップのために社労士資格を取得したものの、活かせていないという社労士の方で転職をご検討中の方にはおすすめの方法です。
ですが、就職同様、社労士事務所への転職は求人数としては少ないので、計画的に準備をしていく必要があります。
(3)経営コンサルティング会社への転職
経営コンサルティング会社も社労士が活躍できる場の一つです。
人事関係や労務関係についてのアドバイス・提案はもちろんのこと、地域再生中小企業創業助成金、雇用調整助成金などさまざまな助成金などの活用アドバイス、など幅広くクライアントにとって利益になることを提案する仕事になります。
また社会保険労務士(社労士)は、これらの活用のアドバイスだけでなく社労士の場合は申請書類の作成代行もできます。
経営士やMBAは相談業務はできても、書類の作成代行はできません。
経営士などの経営系の資格を持っていれば、もちろん活躍の場が広がります。
経営のスキルを身につけ、業務をおこないたい社労士の転職先として魅力です。
社会保険労務士(社労士)の現状のニーズ
政府の「働き方改革」の影響を受け、労働環境は目まぐるしく変化しています。
新たな助成金制度が生まれたりすることもあります。
法改正が行われるたびに対応していかなければならない企業の苦労は計り知れません。
また、人手不足解消から外国人労働者の雇い入れの問題もあります。
国内だけでなく、もっと広い視野を持たなければなりません。
このような状況下で労務支援のスペシャリストである社労士のニーズは高まってきています。
それと同時に社労士自体もまた、企業の労働環境を円滑にすべく、世の中の流れに注視し、自身のスキルアップを怠らないようにしなければなりません。
以上のようなことから、企業の内外を問わず、社労士は大切な存在であるといえるでしょう。
まとめ
社会保険労務士(社労士)は国家資格であり、それだけにスペシャリストとしてやりがいのある仕事です。
今回紹介したように社会保険労務士事務所やコンサルティング会社だけが就職先ではありません。
自分次第で活躍の仕方がたくさんあるのが社会保険労務士です。社会保険労務士の資格取得をご検討中の方はぜひ受験されることをおすすめいたします。

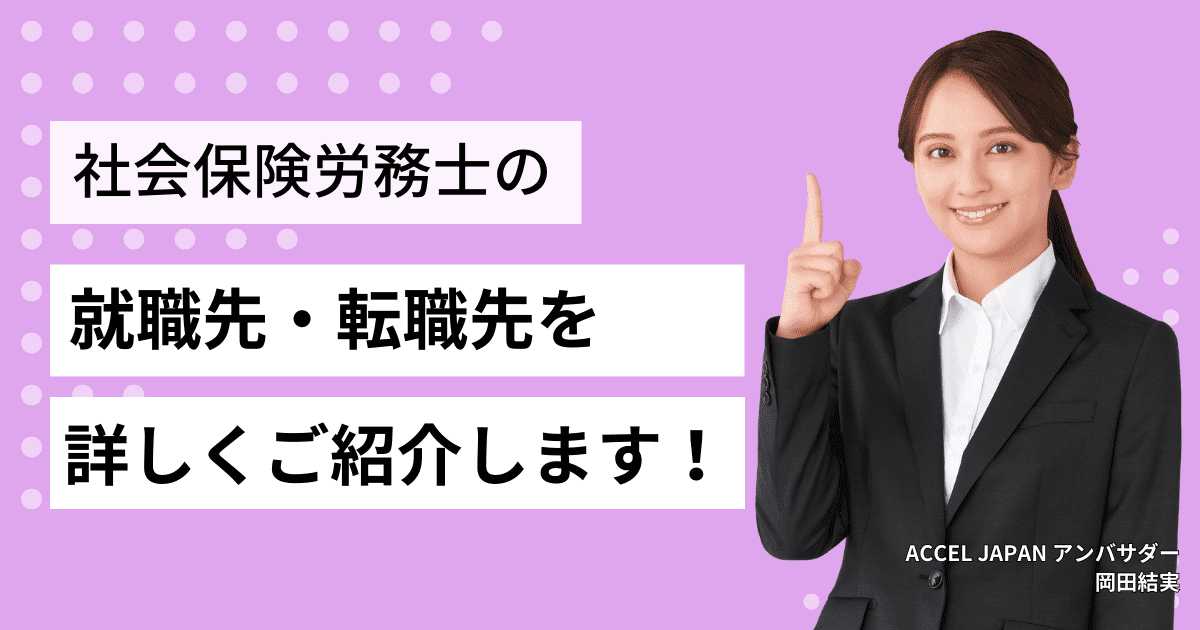






 40代・50代からでも大丈夫?キャリアコンサルタント資格の現実
40代・50代からでも大丈夫?キャリアコンサルタント資格の現実
 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
 メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
 失敗しにくい学び直しの始め方|資格を決める前の準備編
失敗しにくい学び直しの始め方|資格を決める前の準備編
 オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!
オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!





