社労士の独占業務とは?
社労士(社会保険労務士)は「士業」の1つとされ「学術研究、専門・技術サービス業」に分類される職業です。(総務省「日本標準産業分類」より)
ほかにも弁護士や司法書士、税理士などが士業とされており、それぞれの法律によって「独占業務」が定められています。
社労士の独占業務は、社会保険労務士法に基づき定められています。社労士の資格を有していない人がその独占業務をおこなうと、法律違反となるのです。
社労士|2つの独占業務

社労士は、社会保険労務士法の第27条(業務の制限)に基づき、「1号業務」「2号業務」とされる以下2つの業務を独占業務として定められています。
1号業務
行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類の作成(第2条第1項第1号)
2号業務
労働者名簿、賃金台帳、就業規則等の(行政機関への提出を目的に作成するわけではない)書類の作成(第2条第1項第2号)
どちらも「労働社会保険諸法令」に基づいた書類の作成です。社労士の資格を持っていない人は、依頼されても業務としておこなってはいけません。
1号業務
申請書の作成や提出代行、行政機関への事務代理などをおこないます。
企業が人材を雇用した場合に、雇用保険や社会保険の加入手続きが必要です。
しかし、各企業に必ず正確な知識を持ったスタッフがいるとは限りません。そのため、専門知識を有した社労士に依頼し、企業の人材における各種手続きを代行しておこなってもらうのです。
報酬があることを前提にこれらの業務を依頼する場合には、社労士の視覚を保有している人だけに依頼することになります。
2号業務
企業における就業規則や給与規則、労働者名簿、賃金台帳などの帳簿の作成が、2号業務にあたります。
企業には、人材が働くにあたって上記のような各種規則が必要です。最初に作成して終わりではなく、適宜内容を改定しなければならないこともあるでしょう。
しかし1号業務と同様に、正確に問題なく作成するためには、労働にまつわる法律に関する詳しい知識が必要です。それらの帳簿書類を適切に作成するため、社労士に依頼する必要があります。
賃金台帳は、すべての労働者に対して作成する必要があります。賃金(給料)が支払われるたびに記帳しなければならず、社員の労働状況や給与について記録する精度の高いスキルが求められます。
さらに、助成金などについて相談を受けることもあります。アドバイスや手続きの仕方をサポートし代行することも、社労士の2号業務の1つです。
社労士の独占業務ではない「3号業務」
3号業務は、社労士における独占業務には定められていません。
企業からの人材や労働に関する相談にのり、コンサルティングをおこなうことが3号業務にあたります。
人件費の削減や節税に対するアドバイスのほか、派遣社員やアルバと、パートといったさまざまな雇用形態での働き方指導、給与の相談などにのることもあるでしょう。
相談を受け、指導したり助言したりすることで企業の人材・労働に関する問題解決を図る、大切な業務です。
社労士の独占業務はなくなる?
社労士の業務は、企業が存在し人を雇用し続ける限りなくならない仕事です。独占業務は難関資格である社労士に合格し、勤務している人のみが携われるため、希少価値の高い職業ともいえます。
働き方の多様化により、企業が抱える人材や労働に関する悩みも幅広くなっています。それらの課題解決のためのプロとして、今後も社労士の独占業務がなくなることはないと考えられるでしょう。
そのほかにも、社労士は年金に関するエキスパートでもあります。勤務地で相談を受けることもあるため、アドバイスができるよう社労士が理解して必要のある知識は多岐にわたります。
法改正や制度変更などに関してもそうだにゃ、個人ビジネス向けのコンサルティング等もおこなうこともあるでしょう。
事業主に代わり帳簿の作成、総務部の仕事なども担うために、雇用のあり方についての知識が多く要求される仕事なのです。
高齢化社会や年金のあり方の変化により、今後は年金に関する仕事の代行業務なども増加していくと考えられるでしょう。
社労士の独占業務に関するよくある質問
社労士の独占業務に関して、よくある質問をピックアップしました。同じように疑問をお持ちの方は、ぜひ読んでみてください。
Q.無資格でも報酬を受けなければ独占業務をおこなってもいい?
A.残念ながら、報酬を受けない場合でも社労士の独占業務をおこなうことはできません。
「士業としておこなっている」とみなされ、社会保険労務士法に違反、罰せられることになります。
Q.税理士事務所に社会保険手続きを依頼したのは誤りでしょうか?
A.税理士はお金に関するプロであり、社労士同様に税理士にしかできない独占業務が存在します。社会保険に関する手続きは社労士の独占業務と定められているため、税理士への依頼は誤りとなります。
Q.就業規則を修正したいのですが相談しなくてもいいでしょうか?
A.就業規則の作成自体は、必ずしも社労士がおこなわないといけないわけではありません。しかし、社労士は人材・労働に関するプロであり、各企業からの依頼によって、企業の労働状況を詳しく理解しています。法改正にも対応できる正しい知識を持っているため、就業規則の修正の際には社労士に相談するのが望ましいでしょう。
まとめ
社労士(社会保険労務士)の独占業務は「1号業務」と「2号業務」があり、それらは無資格者が担うことができない業務です。
国家資格であり企業における人材・労働のプロとして、企業が抱える課題解決のためにその知識を活用します。
働き方の多様化や高齢化社会により、今後ますますの活躍が期待されるでしょう。

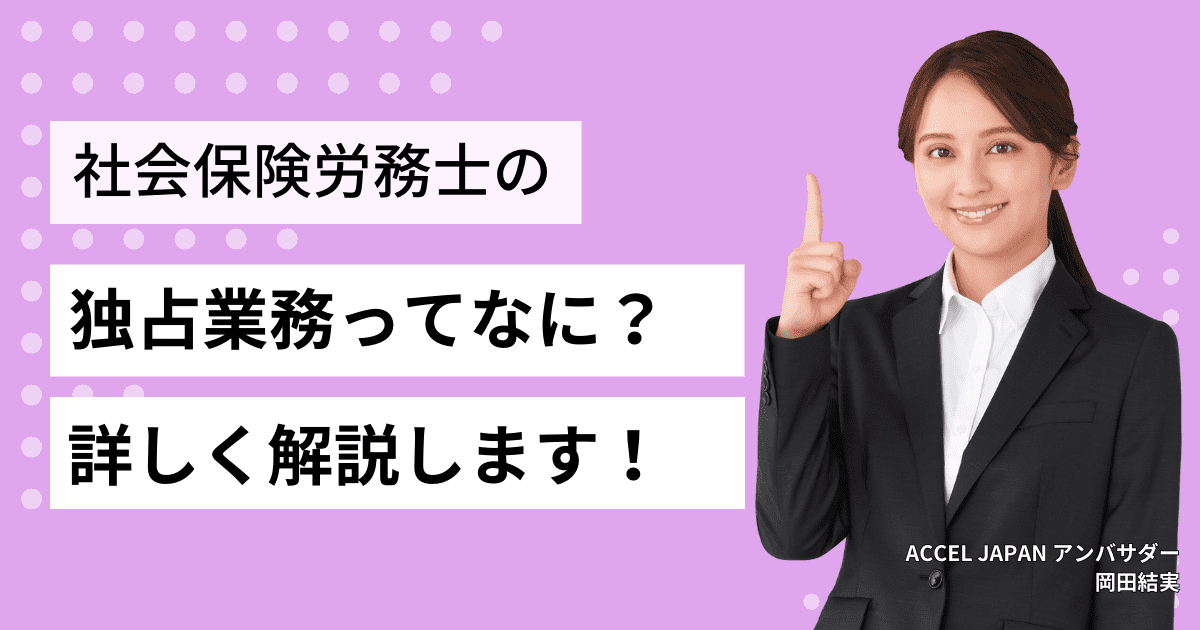






 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
 メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
 2025年12月15日掲載の新スクール&特集ページを大紹介!
2025年12月15日掲載の新スクール&特集ページを大紹介!
 来年を変えたいなら今!キャリアアップにつながる国家資格キャリアコンサルタント
来年を変えたいなら今!キャリアアップにつながる国家資格キャリアコンサルタント
 【1/6まで!5万円相当の講座が無料!】講座を申込むと新しくなった通信講座「翻訳入門」をプレゼント!
【1/6まで!5万円相当の講座が無料!】講座を申込むと新しくなった通信講座「翻訳入門」をプレゼント!





