社労士試験に合格後は社労士連合会への登録で社労士になれる

社労士試験に合格後、社労士として働く場合には「全国社会保険労務士連合会」の名簿へ登録が必要です。この登録を済ませないと「社労士試験に合格した者」という立場になり、社労士として独占業務をおこなうことができません。
試験に合格し、社労士として働きたい方は必ず登録をおこないましょう。
試験から登録までの流れ
- 社労士試験に合格する
- 社労士連合会の登録要件を満たしているか確認する
- 2年の実務経験がない場合は「事務指定講習」を受講し修了する
- 必要書類と登録費用を準備し、登録申請をおこなう
社労士は「都道府県ごと」の社労士会に入会します。開業する場合は開業する場所、勤務する事業所の場所もしくは居住地にある都道府県の社労保険労務士会の会員となります。
登録には2つの条件がある
社労士連合会に登録するには、社労士試験の合格を前提として、さらに以下の2つの条件があります。どちらかを満たすことで登録要件に達します。
- 労働社会保険諸法令に関する実務経験が2年以上ある
- 事務指定講習を修了している
それぞれ詳しく解説します。
労働社会保険諸法令に関する実務経験が2年以上ある
実務経験と認められるのは主に以下の業務経験です。
- 国または地方の公務員として労働や社会保険に関する法令の施行事務
- 企業や日本年金機構にておこなう労働社会保険諸法令の実施事務
- 国民年金事務組合での事務
- 企業や個人の従業者としておこなう労働社会保険諸法令に関する事務
- 労働組合の役員としての業務
- 企業の労務担当を役員としておこなう業務
- 社会保険労務士法人の補助
実務経験の内容が登録要件を満たしているか確認したい場合は、社労士の登録をおこなっている「全国社会保険労務士連合会」の事務局に問い合わせするのがおすすめです。
実務経験がない場合は事務指定講習を修了する
2年間の実務経験がない場合は、連合会が実施する「事務指定講習」を受講し、修了することで社労士の登録要件を満たすことができます。
これは、この講習を修了することで、2年間の実務経験と同等の経験をしていると認められるからです。
実務経験がない、期間が足りないという方は、指定講習の受講も検討してみてくださいね。
経験がなくても登録できる「事務指定講習」とは?
「事務指定講習」は、社労士試験に合格後、2年の実務経験がない方が受講します。「4か月の通信指導過程」と「4日間のeラーニング講習または面接指導過程」があり、以下の科目について学びます。
- 労働基準法及び労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
- 健康保険法
- 厚生年金保険法
- 国民年金法
- 年金裁定請求等の手続
通信指導過程
例年2月~5月の4か月の間に、通信教育方式で学習を進めます。一般的な通信講座のように教材を使用して自分で勉強し、期間内での課題提出が必須です。研究課題の報告には添削指導がおこなわれ、振り返りをしながら理解を深めることができるでしょう。
eラーニング講習または面接指導過程
eラーニングの場合はオンデマンド配信にて、1科目3時間の学習をおこないます。面接指導過程の場合は1科目3時間の講義を4日間受講します。
申し込みの時点でどちらの方式で学習をおこなうかの選択が必要です。
修了認定要件
通信指導過程、eラーニングまたは面接指導過程のすべての課程を修了し、課題の提出が完了していること。修了者には修了証が授与されます。
引用 全国社会保険労務士連合会「事務指定講習」
社労士名簿に登録しないとどうなる?
仮に「今すぐ社労士として活動するわけではない」場合は、社労士名簿に「登録しない」という手段も可能です。社労士試験後、すぐに登録申請しなくても問題ない理由は以下の通りです。
- 社労士試験の合格に有効期限はない
- 試験後の登録に申請期限がない
試験に合格後すぐに登録をしなかったとしても、合格資格や登録資格がなくなることはありません。社労士として働きたいと考えたタイミングで申請して問題はないものの、時間が経つにつれ勉強した知識はどうしても薄くなってしまう点には注意しましょう。
社会保険労務士(社労士)の登録には3パターンある
(1)開業型
社会保険労務士(社労士)の登録には「型」があり、登録後の働き方によって決まります。
開業型は文字通り、自分自身で社会保険労務士事務所を開く場合のことを指します。
企業内に社労士を置かない民間の中小企業を顧客先として顧問契約を結び、労務相談や手続き・申請関係の書類作成をするなどの仕事が中心です。
一人で事務所を開く場合以外に社会保険労務士法人として既に先輩社労士が開業している事務所に所属し、雇用されるというケースもあるかもしれません。
雇用されていても、社労士として名乗り仕事をする場合はこの開業型になります。
自分の実力次第で収入を増やすことができる点は開業型の魅力です。
収入が多くなることが見込まれるからこそ、登録料が高めに設定されているわけです。
(2)勤務型
勤務型は、社会保険労務士(社労士)事務所以外の一般の企業に所属し、労務士の仕事をするケースです。
医療保険や年金保険などの商品を扱う金融機関や保険会社といった企業で働いているイメージが強いかもしれません。
実際は、業種を問わず、従業員数の多い企業では人事部、総務部、法務部などに所属する企業内の社会保険労務士を置くケースがあります。
従業員が多ければ、健康保険法の加入、喪失、傷病手当金などの申請書類や労災関連の申請書類なども数多く処理していく必要があるためです。
また企業が何かの助成金を申請するケースなどもあり、大企業では特に必要とされます。
企業の給与規定に沿った収入のため、こちらは登録型よりも費用が低めに設定されています。
(3)その他
ここでご紹介する「その他」とは既に説明した「開業型」「勤務型」に該当しない方を指します。
社会保険労務士(社労士)試験には合格したが、それを仕事としないという場合は自宅を届け出ることで登録することができます。
法改正に対する情報などを得ることができるため、社労士の登録のメリットが全くないわけではありませんが、登録には勤務型の方とほぼ同じくらいの費用がかかります。
なかには、将来的に社労士の仕事をするかもしれないという考えから、登録を選ぶ方もいらっしゃると思いますが、先に述べた費用の部分も参考にしつつ、メリット・デメリットをよく考えたうえで登録されることをおすすめします。
まとめ
社労士として働くためには、全国社会保険労務士連合会への登録や、登録に必要な書類、費用があること、登録のパターンについて解説しました。
ご紹介のとおり、試験に合格後も登録、講習などが必要となるのは、国家資格として資格保持者の特別な仕事ができることの証であり、それに見合った報酬につながるものです。
独占業務を許される社労士だからこそ、正しい知識を有して業務に従事できるよう、日ごろからのスキルアップが大切といえます。

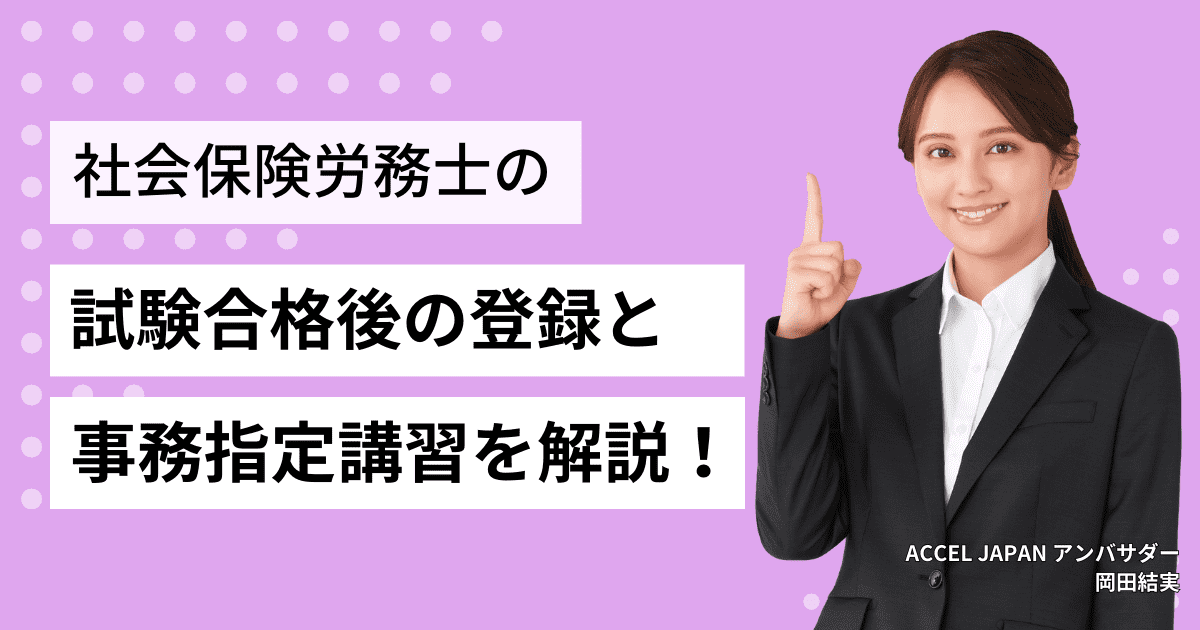






 40代・50代からでも大丈夫?キャリアコンサルタント資格の現実
40代・50代からでも大丈夫?キャリアコンサルタント資格の現実
 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
 メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
 失敗しにくい学び直しの始め方|資格を決める前の準備編
失敗しにくい学び直しの始め方|資格を決める前の準備編
 オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!
オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!





