社会保険労務士(社労士)として開業・独立する方法

社会保険労務士(社労士)試験に合格する
社会保険労務士(社労士)として独立・開業するには、まず国家試験に合格しなければなりません。
社会保険労務士の試験は年一回、例年8月の第4日曜日におこなわれます。
受験資格は、
・大学、短期大学、高等専門学校(5年生)を卒業した者
・行政書士資格を有する者
・司法試験1次試験合格者
・公務員として行政事務に3年以上従事した者
などの条件があります。
詳しくは関連記事の「高卒から社会保険労務士(社労士)を目指すには 3つの方法を紹介」をご覧ください。
社会保険労務士試験には受験資格が必要ですが、これは学歴、実務経験、国家試験合格など、全部で13項目のいずれかを満たしていれば良く、比較的幅広く設定されています。
試験の出題科目は労働関係科目や社会保険関係科目で、選択式と択一式の全問マークシート方式、足切り点も設定されています。
平均的な勉強時間は800~1,000時間、近年の合格率は2~9%と国家資格の中でも難関の試験のひとつです。
全国社会保険労務士連合会へ登録する
社会保険労務士(社労士)は国家試験の合格しても、すぐに社会保険労務士を名乗って独立したり、就職して仕事をすることは出来ません。
実際に社会保険労務士として仕事をするためには、全国社会保険労務士連合会の備える社労士名簿への登録が必要となります。
登録には、企業や社会保険労務士事務所などでの2年以上の実務経験、もしくは社会保険労務士連合会が主催する事務指定講習を修了していることのいずれかが条件となります。
実務経験が2年以上ない方は、事務指定講習の受講が必要になります。
実務経験がある人、または講習が終わった方は、全国社会保険労務士連合へ登録する必要がります。
社会保険労務士名簿に記載されれば、晴れて実務を行うことができます。
登録は、開業する場合はその事務所がある都道府県社会保険労務士会へ申請をし、社会保険労務士会から全国社会保険労務士連合会へ進達されます。
また社労士は登録を受けると同時に、この都道府県の社会保険労務士会の会員となります。
独立開業をする
社会保険労務士(社労士)は独立開業型の資格であり、全体の約7割は独立社労士といわれています。
また事務指定講習を修了すれば、未経験でも社会保険労務士として独立することが可能です。
独立に関しては、自分が開業する地域の税務署に「個人事業の開業届」を提出すれば完了です。
開業届は事業を始めてから1ヶ月以内に提出することが定められているので、開業を決断された場合は、1日でも早く提出するようにしましょう。
ですが、個人事業の開業届を提出したからといってすぐに独立開業するにはリスクもあるでしょう。
なかなか実務経験のない方に安心して仕事を任せられるということは少ないといえるでしょう。
独立をしたものの、仕事を得ることができずに廃業してしまうといったことにもなりかねません。
その場合には、勤務社労士として経験を積み重ね、知識やコンサルティングスキルを伸ばしつつ、独立開業後の人脈づくりをするという方法もおすすめです。
実務経験を積み、ある程度顧客の見込みが出来てからの独立・開業をされた方が、開業後の事務所の経営は安定するでしょう。
社会保険労務士(社労士)の開業・独立に必要なもの
社会保険労務士(社労士)の開業・独立は他業種に比べて必要となるものが少なく、低予算で開業できるという特徴があります。
必要なものといえば、事務所スペースとオフィス用品、ネット回線などですが、事務所は部屋を借りるとなると賃貸費用がかかるため、独立当初は自宅を事務所として構える人も少なくありません。
設備等に関してはデスク、パソコン、電話、FAX、プリンターなどがあります。
これらも新しく購入するよりも、今あるものを使い初期費用を抑える場合が多いです。
そのほか名刺や事務所案内なども作成しておくと、開業後の営業活動がスムーズになるでしょう。
開業・独立の手続としては、自分の納税地を管轄する税務署に「個人事業開業届」の届け出が必要になります。
開業届の提出期限は事業開始の事実があった日から1ヶ月以内と定められているため、開業後時間の合間を見つけて税務署窓口、もしくは送付などにより済ませるようにします。
社会保険労務士(社労士)の開業・独立の費用はどれくらい必要
社会保険労務士(社労士)として開業・独立をするために必要な費用は、まず全国社会保険労務士連合会への登録費用と社労士会への入会金が挙げられます。
●全国社会保険労務士連合会への登録免許税
・登録手数料:各30,000円(収入印紙もしくは納付証明書)
●各都道府県の社会保険労務士会への入会金:50,000円(東京都 開業の場合)
・実務経験がない場合:事務指定講習費用77,000円(税込)
上記のような費用が発生します。
このほかに社労士会は定期的な会費がかかり、東京都の場合ですと年間96,000円です。
自宅で開業する場合は別ですが、事務所を借りたり、自宅を改装したり備品を揃える費用としては事務所の賃料や敷金等、それぞれまとまった金額が必要となります。
また開業後の収入が安定しなかったときのために、数か月分の生活費や必要経費を用意しておく必要があります。
以上を含めると、開業・独立の費用と当面の活動費として150万から180万ほどは準備しておいた方が良いといえるでしょう。
社会保険労務士(社労士)の開業・独立のメリットとデメリット
社会保険労務士(社労士)の開業・独立のメリット
社会保険労務士(社労士)として開業・独立をする最大のメリットは、自分自身の裁量で働けることです。
顧客や仕事を自分で選ぶことができ、休日も顧客の予定を考慮しつつ、自分のタイミングでとれるなど個人のペースで働くことができます。
自分の好きな場所に職場を構えれば通勤によるストレスもありませんし、クライアントを選ぶこともできますので、かなり自由度が高いといえるのではないでしょうか。
実績や経験によってサラリーマンよりも高収入が望めるということもメリットの一つです。
他の独立系の職種と同じく、頑張れば頑張るほど収入につながり、成功すれば年収1,000万円を超えることも可能です。
会社勤めの場合、沢山のクライアントの仕事を抱えても給料以上増えることはありませんが、個人の場合はクライアントの数や報酬額がダイレクトに自分の売り上げになります。
また企業に勤めている場合と違い、顧客との関わりが親密になるため、顧客の課題を解決できる達成感を味わうことができ、仕事のやりがいも大きくなります。
その他にも定年がなく、体力を使わずに仕事ができるため、仕事をコントロールしながら長く働き続けることができるというメリットもあります。
社会保険労務士(社労士)の開業・独立のデメリット
社会保険労務士(社労士)が開業・独立するデメリットは、仕事を自分で獲得することができなければ収入が安定しないという点が挙げられます。
自ら営業をかけて仕事を獲得できるようなアクションを起こさない限り仕事を得ることは難しいかもしれません。
また税理士などと比べて顧客単価が低いため、安定した収入を得るためには、多くの顧問契約を結ぶ必要があるでしょう。
開業した社労士で高収入を得ている方もいますが、なかなか収入に結びつかず独立後数年で廃業というケースも少なくありません。
開業後は営業活動を行い、いかに多くの顧客を獲得できるかということが重要になってくるといえます。
また勤務社労士に比べて、開業した場合は本業以外の仕事が多くなります。
社労士としての業務だけではなく、経理や人材管理などの業務もこなさなくてはなりません。
それらの業務に時間をとられ、結局自分のペースでは働けなくなってしまえば、開業のメリットは薄れてしまうでしょう。
「自分で顧客を切り開く」という強い意志がないと、社労士として開業するのは難しいかもしれません。
まとめ
社会保険労務士(社労士)の開業・独立にはまず国家試験の合格、全国社会保険労務士連合会への登録、管轄する都道府県の社労士会への入会、実務経験または事務講習が必要となります。
開業にあたり必要なものとして、オフィスや備品などの準備に加え、当面の活動費用を用意しておくようにしましょう。
社労士は高収入を目指せメリットの多い職業ですが、開業当初は経営が安定しないことも考えられます。
開業・独立を成功させるためには、実務経験を積み自分の得意とする分野を磨きつつ、積極的に営業活動をすることが大切です。

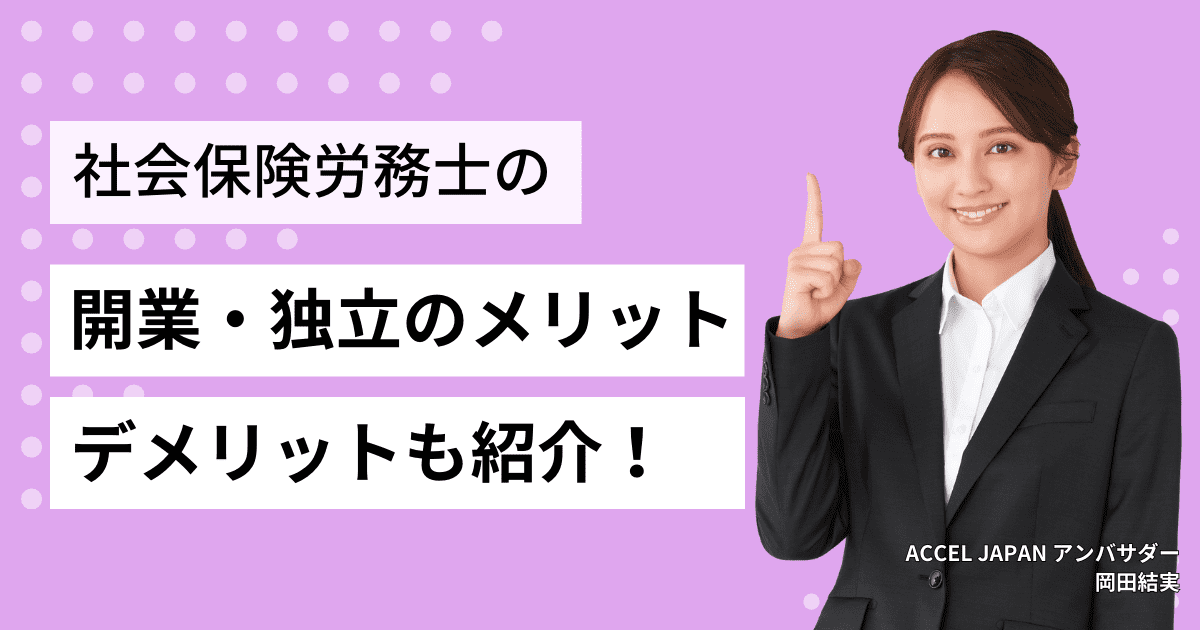






 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
 メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
 2025年12月15日掲載の新スクール&特集ページを大紹介!
2025年12月15日掲載の新スクール&特集ページを大紹介!
 来年を変えたいなら今!キャリアアップにつながる国家資格キャリアコンサルタント
来年を変えたいなら今!キャリアアップにつながる国家資格キャリアコンサルタント
 【1/6まで!5万円相当の講座が無料!】講座を申込むと新しくなった通信講座「翻訳入門」をプレゼント!
【1/6まで!5万円相当の講座が無料!】講座を申込むと新しくなった通信講座「翻訳入門」をプレゼント!





