アロマテラピーの資格・検定はたくさんの種類がある!
アロマテラピーにはたくさんの資格や検定が存在します。
認定する協会も複数あり、それぞれ学べる内容や活かせる場も異なります。
ここからは主なアロマテラピーの資格を認定している協会ごとに紹介します。
AEAJ(公益社団法人日本アロマ環境協会)
アロマテラピー検定
アロマテラピー検定は、AEAJ(公益社団法人日本アロマ環境協会)が認定するアロマテラピーの資格です。
アロマテラピーが家庭や趣味としてだけでなく、ビジネスでも使用されるようになるにつれて、正確な知識も求められるようになりました。
アロマテラピー検定は、そのような需要に対して応えるアロマの入門資格です。
アロマテラピーで必須の分野を学べる
アロマテラピー検定を通して基礎知識を習得すれば、より安全にアロマテラピーを楽しむことができるようになるでしょう。
この資格では体系的にアロマの初歩を学べるほか、様々な精油の知識等、アロマテラピーを行う上で必須ともいえる分野を学ぶことになります。
関連記事:
アロマテラピー検定とは?おすすめテキストや難易度など徹底解説
アロマテラピーアドバイザー
この資格を取得することで、精油の基本的な使用方法からアロマテラピー関連の法律まで、幅広い知識があることの証明になります。
アロマテラピーに関する仕事をしたいのであれば、是非取得しておきたい資格といえるでしょう。
アロマテラピーで必須の分野を学べる
アロマテラピーの仕事をする際、アロマテラピーアドバイザー(AEAJ)資格を持っていれば、お客様にアロマテラピーに関する正確な情報をご案内することができるでしょう。
また、アロマテラピーの精油がもたらす作用だけでなくお客様の状態に合わせて最適な商品を選択できるようになれば、今まで以上に活躍の場が広がる可能性があります。
関連記事:
アロマテラピーアドバイザー(AEAJ)とは?取得方法についても紹介!
アロマテラピーインストラクター
健康学やメンタルヘルスの知識がある証明に
この資格を取得することで、アロマテラピーに関するスペシャリストとして、人にアドバイスする力を身につけることができるでしょう。
アロマテラピーに用いる精油の知識はもちろん、健康学やメンタルヘルスの知識を備えた専門人材ということを証明できる資格といえます。
関連記事:
アロマテラピーインストラクター(AEAJ)とは?資格取得方法も紹介!
AEAJ認定アロマセラピスト
アロマの理論だけでなく実技やカルテ作成などの知識が必要な資格です。
受験条件の必須履修科目の中にはボディートリートメント50時間というものもあり、少々ハードルが高く感じるかもしれませんが、一般の方へのアロマトリートメント(アロママッサージ)が実践できる証明となります。
サロンへの就職や開業を目指す方は取得しておくとよいでしょう。
AEAJ認定ハンドセラピスト
安全にアロマを活用する知識を持ち、一般の方にアロマハンドトリートメントを提供できる能力を認定する資格です。
ボランティアや介護・福祉の領域での実践、自分の周りの人へのハンドトリートメント(ハンドマッサージ)を行うのに最適な資格です。基礎理論も学びますのでアロマの学び始めに挑戦してみてもよいでしょう。
サロン就職や開業を目指す方は、他の実技資格とあわせて取得するのがおすすめです。
日本アロマコーディネーター協会(JAA)
アロマコーディネーター
アロマの基礎知識を備えており、安全に生活に取り入れることができる証明となる資格です。日本アロマコーディネーター協会(JAA)が 認定する中で最も基本的な資格で、幅広く活かすことができます。
アロマショップ・サロンの開業、セミナーの開催など、アロマテラピーを普及するために活用でき、JAAからの活動支援も受けることができます。
NARD JAPAN ナード・アロマテラピー協会
アロマ・アドバイザー
NARD JAPAN(ナード・アロマテラピー協会)が認定する、基本的なアロマテラピー知識を習得し、 精油を安全かつ効果的に使用できることを証明する資格です。試験への合格後に申請を行うことでアロマ・アドバイザーとして認定を受けることができます。
受講するカリキュラムでは、基礎知識から心身の不調にアプローチする精油の化学的作用についてまで幅広く学習でき、アロマショップなどでの適切なアドバイスが可能になります。
アロマ・インストラクター
アロマテラピーの指導者として、より専門的な知識を学んだアロマ上級者であることを示す資格です。
アロマテラピーの専門家として、講師を目指す方に向けた受講内容で、アロマ・アドバイザーの学び以上に化学的な知識や解剖生理学に関しても身につけることができます。
アロマ・インストラクター資格を取得することでアロマ・アドバイザーのコースを指導する講師となるための申請も行うことができます。
IFA 国際アロマセラピスト連盟
IFA国際アロマセラピスト
国際アロマセラピスト連盟(IFA)が認定する、世界最高峰と名高いアロマテラピー資格です。
多くの症例を学ぶことで、セラピストとしての高い応用力が身につきます。アスリートのケアや心理学まで幅広く学ぶことができます。
AEAJのカリキュラムとも好相性で、本資格を目指す過程でAEAJ資格の取得も併せて目指すことが可能です。また、AEAJのアロマテラピーインストラクター資格などを取得していることでIFAのカリキュラムの一部免除が受けられる場合もあります。
IFPA 国際プロフェッショナルアロマセラピスト連盟
IFPA認定アロマセラピスト
国際プロフェッショナルアロマセラピスト連盟(IFPA)が認定する、アロマテラピーの国際資格です。IFPAはイギリス政府とも連携した、アロマに関して世界で最高水準の教育カリキュラムを提供する機関として知られています。
アロマテラピーの理論・実技の他、解剖生理学や病理学、ケーススタディが組み込まれたカリキュラムで、世界で活躍できるアロマセラピストを目指すことができます。
IFAと同様にAEAJの資格を取得している場合は、アップグレード制度などを利用し、不足したカリキュラムの履修のみで資格取得を目指せます。
関連記事:
「IFA」と「IFPA」の違いって?2つのアロマセラピー協会、アロマ資格についてご紹介!
アロマテラピーとは?
アロマテラピーとはどんな仕事・資格?
「アロマテラピー」とは、植物から抽出した天然の精油を用いて香り成分により心身の不調を改善し、リフレッシュさせる自然療法です。
香りで心身を癒す
その香りに親しみ、楽しみながら、より豊かなライフスタイルを提案したり、疲労やストレスの多い現代人を、香りによって心身共に癒す人のことを、「アロマセラピスト(アロマセラピスト)」や「アロマコーディネーター」と呼びます。
99年秋からスタートした「アロマテラピー検定」は、そんなアロマセラピストを目指されている方にとって入門編ともいえる資格です。
アロマテラピーを活かした活躍の場
主にアロマショップやアロマテラピーサロンに就職したり、インストラクターとして活躍することができるでしょう。
もちろん知識と経験があれば、独立開業も目指すこともできるでしょう。
香りで心身を癒す
最近では、香りがもたらす癒しの効果が、介護福祉の分野でも注目されており、ホームヘルパーや介護士の方が、+αの技術として、アロマテラピーを身につけるといったケースも目立ちます。
生活の中でのリフレッシュとして、個人や家族でも楽しめるので、プロにならなくても、趣味として活用できるスキルです。
アロマテラピーの仕事 こんな人が向いています
美と健康を増進させるためのものですから、愛情や思いやりのある方が求められます。
女性が自分自身の趣味や癒しのためにスクールに通い学習するというケースもあります。
避けるべき香りもあるので知識が不可欠
アロマテラピーで用いる香りには多種多様あり、リラクゼーションを高めるだけでなく、対象者の健康状態によっては避けるべき香りもあります。
従って、プロのアロマセラピストを目指すのであれば、香りについての深い知識は必要不可欠になります。
アロマテラピーの定義
公益社団法人 日本アロマ環境協会 Aroma Environment Association of Japan(AEAJ)では、アロマテラピーについて下記のように定義をしています。
アロマテラピーの定義
アロマテラピーは、植物から抽出した香り成分である「精油(エッセンシャルオイル)」を使って、美と健康に役立てていく自然療法です。
アロマテラピーの目的
●心と身体のリラックスやリフレッシュを促す
●心と身体の健康を保ち、豊かな毎日を過ごす
●心と身体のバランスを整え、本来の美しさを引き出す
※引用:
公益社団法人
日本アロマ環境協会 Aroma Environment Association of Japan(AEAJ)
「AEAJによるアロマテラピーの定義」
アロマテラピーの歴史
古くから治療や消毒用などで使われてきた
記録では、古代エジプト人がミイラをつくる際の防腐剤として乳香(フランキンセンス)や没薬(ミルラ)といった精油が使われていたことが判明しています。
儀式の際には香りが焚かれ、芳香の成分を病気や怪我の治療に使っていた形跡もみられました。
聖書や古い書物に記述されている
ヨーロッパでも、聖書の記述にアロマテラピーが登場します。
イエス・キリストが聖なる油を用いて人々を治療したとか、東方の三賢人がイエス誕生の際に捧げたというものです。
アロマテラピーの研究家によると、イエス・キリストが使用したものは現代でいう香油(ハーブ・植物の浸出油)だと推測されています。
また、医学の書物には、紀元前2000年ごろの中国や今から3000年以上前のインドでも、アロマテラピーが記述されているのが確認されています。
香料産業が発達した中世
中世に入ると本格的に香料産業が発達し、植物から精油を取り出す蒸留が流行します。
当時は錬金術の一種として用いられ、実験を通してさまざまな物質を作り出すことが目的でした。
現代でいうところの化学です。
17世紀のヨーロッパ
17世紀には最古の香水「オーアドミラブル」が発売され、ヨーロッパの貴族たちの間で非常に好まれました。
それと同時に、当時ヨーロッパで蔓延していた伝染病の殺菌作用目的としても精油は重宝されました。
特に香水文化が発達したフランス南部のプロヴァンス地方などは、香水の町として現代でも観光名所として有名です。
近世から現代に至るまで
近世に入ると、現代医学の発達によりアロマテラピーは民間療法として使われることが多くなります。
20世紀ではアロマテラピーという言葉が浸透し、芳香療法としてストレスの緩和や予防という重要な役割を担うようになりました。
日本での普及
日本でも万葉時代から果物や植物の香りを楽しむ文化があります。
ヨモギ湯、ユズ湯などは現代でも人気が高く、お香も当時から長く親しまれてきました。
アロマテラピーという文化が日本に普及したのは1990年代からです。
元々日本には香りを楽しむ文化があったという点と、バブル崩壊後、ストレス社会が問題になりつつあり、多くの人が癒しを求めていたことが日本でのアロマテラピー普及に大きな影響を与えたのかもしれません。
アロマテラピー・アロママッサージのやり方と効果
アロマテラピーの行い方、効果はさまざま!
アロマテラピーはオイル(精油)をどのように使用するかによって、さまざまな効果をもたらします。
メジャーなものでは以下のような使用方法があります。
アロママッサージ
アロマオイルを用いることによってマッサージの効果を高めます。
芳香浴
芳香浴とはアロマオイルの香り(芳香)を嗅ぐことによって、集中力を高めたり、入眠を促したりする効果を得る方法です。
湿布
肩こりや腰痛に悩んでいるなら、湿布がおすすめです。
関連記事:
アロマテラピー・アロママッサージのやり方と効果
アロマセラピスト 給料・年収分析
アロマセラピストの平均年収
アロマセラピストの年収は、全国平均で約250~270万円と言われています。
月収で言うと10万円台後半~20万円台前半の場合が多く、正社員であればボーナス支給があり、その他に手当や指名料・歩合給が付く場合も多いようです。その場合、より高い収入が見込めるでしょう。
アロマセラピストは勤務地や職場によっても給与水準が異なり、首都圏や京都、大阪、神戸などでは平均より高い場合が多くなっています。
また、管理職などに就くことができれば500万円~800万円の年収も目指せます。
関連記事:
アロマセラピストってどんな仕事?仕事内容や活躍の場、スケジュール事例も紹介!
アロマテラピーとアロマセラピーの違いは?【トピックス】
言葉の意味に違いはありません。
「アロマテラピー」はフランス語読みをしたもので、「アロマセラピー」は英語読みしたものです。
アルファベットの表記はどちらも「aromatherapy」になります。
日本ではセラピーやセラピストという言葉がよく使われていますので、アロマ+セラピーのアロマセラピーという言い方が定着しています。
医療行為としては認められていない
「セラピー」とは医療行為の「治療」という意味ですが、日本においてアロマセラピーは医療行為としては認められていないことは知っておく必要があるでしょう。
アロマセラピーを医療行為とするかしないかは国によっても異なってきます。
テラピーよりも「セラピー」が適している
フランスは「アロマテラピー」を医療行為として認められるいる一方、イギリスではエステなどのサービスとして「アロマセラピー」を行っています。
そのため、日本においてはアロマテラピーよりもアロマセラピーという言葉の方がよりマッチしていると言えるでしょう。
アロマテラピーが学べるおすすめスクール!
監修者プロフィール
AEAJ認定校「齋藤れいこアロマスタイルスクール」主宰。
日本プロフェッショナル講師協会認定講師。
【保有資格】
AEAJ認定 アロマテラピーインストラクター
JAMHA認定 メディカルハーブコーディネーター
一般社団法人EAPコンサルタント普及協会認定EAPコンサルタント
【主な経歴】
サクラビア成城 アロマテラピー講座講師
JTBトラベル &ホテルカレッジ アロマテラピー外部講師
日産自動車本社にて「働く人のためのアロマセミナー」開催
日本橋三越 真珠とアロマ香水のコラボ商品プロデュース
ほか
【齋藤れいこアロマスタイルスクール】のホームページはこちらから
試験データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資格・試験名 | AEAJ アロマテラピー検定 |
| 試験日 |
【第54回検定試験】 |
| 試験区分 | 民間資格 |
| 主催団体 | 公益社団法人 日本アロマ環境協会(AEAJ) アロマテラピー検定事務局 |
| 受験資格 | 特になし |
| 合格率 | 90%程度 |
| 出題内容・形式 | インターネット試験(選択解答方式)です。 【2級】 ・アロマテラピーの基本 ・きちんと知りたい、精油のこと ・アロマテラピーの安全性 ・アロマテラピーを実践する ・精油のプロフィール(対象11種類) (対象となる精油:スイートオレンジ、ゼラニウム、ティートリー、フランキンセンス、ペパーミント、ユーカリ、ラベンダー、レモン、ローズ(アブソリュート)、ローズオットー、ローズマリー) 出題数:55問 【1級】 ・アロマテラピーの基本 ・きちんと知りたい、精油のこと ・アロマテラピーの安全性 ・アロマテラピーを実践する ・アロマテラピーのメカニズム ・アロマテラピーとビューティ&ヘルスケア ・アロマテラピーの歴史をひもとく ・アロマテラピーに関係する法律 ・精油のプロフィール(対象30種類)※下記以外に2級の11種類も含む (対象となる精油:イランイラン、クラリセージ、グレープフルーツ、サイプレス、サンダルウッド、ジャーマンカモミール、ジャスミン(アブソリュート)、ジュニパーベリー、スイートマージョラム、ネロリ、パチュリ、ブラックペッパー、ベチバー、ベルガモット、ベンゾイン(レジノイド)、ミルラ、メリッサ、レモングラス、ローマンカモミール) 出題数:70問 |
| 検定料 | 2級 6,600円(税込) 1級 6,600円(税込) ※2級、1級同日に受験の場合、併願13,200円(税込) |
| 問い合わせ先 |
公益社団法人 日本アロマ環境協会(AEAJ) アロマテラピー検定事務局 http://www.aromakankyo.or.jp/inquiry/ 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前六丁目34番24号 AEAJグリーンテラス TEL:03-6384-2861(平日 10:00-16:00) |




 あなたの好きな香りを1Dayレッスンで見つけてみませんか?~アロマを使った癒しの技術を学ぶ~
あなたの好きな香りを1Dayレッスンで見つけてみませんか?~アロマを使った癒しの技術を学ぶ~
 感染症予防もアロマで!いい香りに包まれて気分もリフレッシュ
感染症予防もアロマで!いい香りに包まれて気分もリフレッシュ







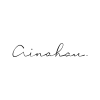




 キャリアコンサルタント7月試験はまだ先?実は「今」が最後の分かれ道です。
キャリアコンサルタント7月試験はまだ先?実は「今」が最後の分かれ道です。
 【3/1まで!】翻訳の通信講座について、じっくり検討できる「カウンセリング」受付中!
【3/1まで!】翻訳の通信講座について、じっくり検討できる「カウンセリング」受付中!
 介護・福祉分野に興味がある人が、最初に知っておきたいこと
介護・福祉分野に興味がある人が、最初に知っておきたいこと
 資格取得 春の新キャリア取得応援!受講料10%OFF!早期申し込み6万円分プレゼント特典付き!
資格取得 春の新キャリア取得応援!受講料10%OFF!早期申し込み6万円分プレゼント特典付き!
 オンライン心理学教室4月開講! 実践に強い資格が取れるカウンセラー育成スクールが5月にスタート!
オンライン心理学教室4月開講! 実践に強い資格が取れるカウンセラー育成スクールが5月にスタート!





