行政書士の試験は独学でも十分合格できる
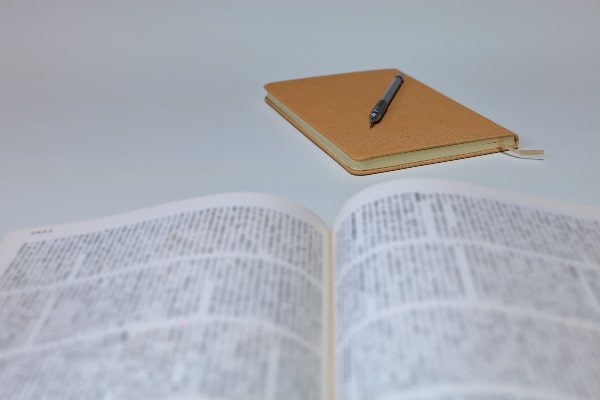
行政書士試験は、合格率が低いながらも受験資格がなく、年齢や職業にかかわらず誰でも受験することができる試験です。
実際に試験の受験者層も毎年10代以下~60代以上と、幅広い方が受験しています。全員がスクールや通信講座を受講しているわけではなく、独学での合格も十分に可能と考えられます。
行政書士に独学で合格するための勉強時間

行政書士試験の勉強を独学で進めるためには、勉強時間だけでなく学習するためのテキスト選びから試験までの勉強スケジュールの計画など、さまざまなことを考える必要があります。
独学での勉強時間の目安は約1,000時間
行政書士試験を独学で合格するための勉強時間は、約1,000時間程度が目安といわれています。
幅広い法律の知識が問われるため、初めて法律関係の勉強をする方の場合は、しっかりと知識が身に付くような時間数が必要です。
試験では法律に関する知識が問われる
行政書士の試験では、法律全般の知識が問われます。実際の行政書士の仕事は、主に行政への書類提出や作成、申請の代行、相談業務など法律全般に関わる内容です。
法律関係の手続きは一般の人にはわかりづらく、対応ができない人が正しい知識を持った行政書士に頼りたいというのは自然な感情でしょう。一般の人の生活問題を行政書士としてサポートするには、しっかりとした知識を身につける必要があります。
個人、法人問わずどのような顧客にも対応できるように、幅広い知識を身につけて試験に合格するには、1,000時間以上の勉強時間が必要と考えられます。
1日2時間の勉強で合格できた方もいる
行政書士の資格は、受験資格がないこともあり、他の法律系の資格よりも合格しやすいと考えられています。なかには1日2時間の勉強で合格を手にした方もいます。
1日2時間で合格した方は、短い時間で効率良く勉強を進めるために、通勤時間や昼休みに復習して音源教材も活用するといった勉強法を取り入れました。また、ひたすら教科書を読み込んで、何度も過去問題集を繰り返し解いたそうです。
そして、民法や行政法、一般知識など、試験問題で重要視される要点を押さえた学習方法をおこなった結果、見事合格に繋がりました。何度も繰り返すことこそが、最短合格のポイントともいえます。
試験に合格した方のなかには、独学だけでなくスクールや通信講座も活用し効率的に学習されている方もいます。独学だけでは不安な方は、学習に外部のサービスをうまく取り入れながら合格を目指していきましょう。
行政書士試験を独学で合格するためのおすすめ勉強法
ここからは、行政書士試験を独学で合格するためのおすすめの勉強方法をご紹介します。独学では自分で学習スケジュールを立てる必要があり、それが試験の結果を左右するポイントにもなります。
(1)試験日までの学習スケジュールを立てる
先述のとおり、行政書士試験に独学で臨むには約1,000時間の勉強時間が必要といわれています。自分のライフスタイルを振り返り、1日にとれる学習時間や週に何日勉強に充てられるかをあらかじめ考えておき、学習スケジュールを立てることが重要です。
たとえば一般的な行政書士試験の対策通信講座では、6ヶ月~12ヶ月の学習期間を設けていることがあります。通信講座では学習スケジュールをきちんと立てて講座を提供しているため、少なくとも半年は時間を確保することが望ましいと考えられます。また、働いている方の場合はさらに長い期間が必要になる可能性もあるでしょう。自分自身の生活の流れの中で1,000時間以上の学習を進めるためには、試験までにどのくらい前から勉強を始めるとよいかあらかじめ考えておきましょう。
行政書士試験の独学おすすめスケジュール例
受験年前年の11月中頃から12月中頃までの1ヶ月
- 基礎法学
法学の基礎となる内容。
行政書士試験の内容の、はじめに学ぶのがおすすめです。
受験年前年の12月中旬から試験年1月の1.5ヶ月
- 憲法
ほかの法規を学習する際に役立ちます。
試験年の2月から4月までの3ヶ月
- 民法
主要科目の一つであり、学習量が多いことをふまえてこの時期からの学習が良いでしょう。
日常生活で馴染みがあるので行政法より学習しやすいといえます。
試験年の5月から7月の3ヶ月
- 行政法
落としたくない主要科目の1つ。
この時期に学習を始めていければ、本試験までに学習をほぼ確実に終わらせることができるでしょう。
試験年の8月の1ヶ月
- 商法(会社法)
配点が比較的少ない科目。
万が一学習が追いつかない場合は重要ポイントだけ押さえておく方法もよいでしょう。
試験年の9月から10月中頃までの1.5ヶ月
- 一般常識
政治・経済・社会などの分野は比較的新しい話題も問われることもあります。
また、基本的には一般常識科目のみ法規ではなく、対策を取りやすい情報通信や個人情報保護、文章理解を重点的に学習するのがおすすめです。
試験年の10月下旬
- 模試
模試を受けてこの時点での実力を試し、試験本番までのチェックにしましょう。
試験年の10月中頃から試験日まで
- 総復習
テキストなどの暗記をおこなうとよいでしょう。
重要事項さえ覚えていれば応用にも活かすことができます。
試験年の11月の第2日曜日
- 試験本番
体調を整え、落ち着いて試験本番に臨みましょう。
関連記事 行政書士試験合格に向けてスケジュール、勉強時間などを動画でわかりやすく紹介!
業務でも重要な部分が頻出傾向にある
行政書士試験は6科目ありますが、その中でも出題されやすい傾向にある分野や項目があります。
例えば、行政事件訴訟法の条文や判例は問われることが多く、過去問をアレンジして出題されることが少なくありません。
効率的に勉強を進めることが重要な独学では、頻出の分野や項目を狙って繰り返し学習するのがおすすめです。頻出問題に特化した問題集もあるため、テキスト選びも大切です。
出題されやすい分野や項目は、行政書士として働き始めてから必要になる場面が多くあるからこそ、何回も出題されているとも考えられます。頻出問題を確実に解けるようになることで、行政書士になってから実務をおこなう際に役立つでしょう。
行政書士試験を独学で合格するためのおすすめテキストは?
BrushUP学び編集部が、行政書士試験を独学で合格するためにおすすめのテキストを2つ選びました。おすすめポイントをご紹介します。
おすすめテキスト1:うかる! 行政書士 入門ゼミ 2023年度版
行政書士試験の入門書(入門テキスト)として絶大な人気を誇るのが、『伊藤塾のうかる!行政書士シリーズ』です。伊藤塾は司法試験や公務員試験にも強いと有名で、独学用テキストの完成度の高さには定評があります。
その中でも入門テキストとされるのが「うかる!行政書士 入門ゼミ」です。
テキストの特徴
- 「行政書士試験とは何なのか」「各科目の全体像と体系」を容易にイメージすることができる
- 「法律の学習方法やすすめ方」「学習モデルプラン」「学習進度表」など、初学者が知りたい点が記載されている
- イラスト・図表・具体例があるので、法律科目だとしても理解しやすい
- 現役で活躍する行政書士の業務と一日のスケジュールが掲載されており、合格後の実務のイメージができる
- 伊藤塾の行政書士試験の総合テキストとリンクしていて、一緒に利用すると学習がスムーズに行く
伊藤塾の書籍の特徴は「とても分かりやすい」ということで、理解するのが難しい法律科目でも、普通の本のようにスラスラと読めると評判です。
大型書店チェーンの行政書士試験の入門書部門で、2012年11月から2018年8月まで6年連続売上No.1を記録した人気シリーズです。
シリーズ本での口コミでは、「初心者でもとても分かりやすいようになっている」「重要な論点をギュッと濃色している」などの声があります。
参考 Amazon うかる! 行政書士 入門ゼミ 2023年度版
おすすめテキスト2:行政書士過去問マスターDX
東京法経学院は、1961年に司法書士試験指導会として創立した、老舗の法律専門学校であり、長年培ってきた合格ノウハウを持っています。
過去問題集は過去5年間の本試験問題が対象で学習しやすい分量です。
テキストの特徴
- 過去問が法律別と科目別に分かれており、独学時にとても学習しやすく覚えやすい
- 多肢選択式・記述式は、過去13年分掲載されている
- 試験科目の法改正にも対応
- 分かりやすさを重視しているので、初学者でも知識を会得しやすい
『行政書士過去問マスターDX』は優れた過去問テキストですが、独学時、1回で覚えるのではなく2~3回繰り返し学習した方が「本試験で高得点を取る力」を身に付けることができるでしょう。
参考 Amazon 行政書士過去問マスターDX 2022年版
行政書士試験を独学で学習するメリットは?
コストを抑え、自分のペースで学習することができる
行政書士を独学で学習する大きなメリットとしては、費用を抑えることができるという点が挙げられます。
独学でかかる費用
合計で約45,000円の費用がかかります。
内訳としては下記の通りです。
独学費用の内訳
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| テキスト | 約5,000円(入門書や総合テキスト等) |
| 問題集 | 約18,000円(基本問題集・肢別問題集・一問一答問題集・40字記述式問題集など) |
| 行政書士試験六法費用 | 約4,000円(ミニマム六法だと約2,000円) |
| 模試費用 | 1回約4,000円(パックで申し込むと1回あたりの費用を安く抑えることができます) |
| 受験費用 | 10,400円(払い込み済みの受験料は自然災害等で試験が実施されなかった場合を除いて返還されないのでご注意ください) |
通信講座を利用する場合の費用が平均50,000~80,000円、受験料7,000円を足すと57,000~87,000円ほどといわれています。
ただし、模試や六法の有無は講座により異なりますので、別途費用が必要となる場合もあります。
通学講座の場合、費用の平均は約200,000円で受験料7,000円を足すと、約207,000円必要となります。
こちらも通信講座の場合と同様に、別途、模試代や六法購入費が必要となる場合があります。
他にも「会場での模試以外を除いて基本的に自分のペースで学習できること」「テキストなどがあれば好きな時間好きな場所で学習できること」などが行政書士試験を独学でチャレンジする場合のメリットとして挙げられます。
行政書士試験を独学で学習するデメリットは?
独学で学習する場合、スクールの通学・通信講座を受講した場合と比べて、行政書士試験を受けた際の合格率が劣ってしまう可能性があります。独学の場合にデメリットといわれる理由を解説します。
不明点が解消できなかったり、法改正などの最新情報を得ることができない可能性がある
行政書士試験を独学で学習している最中に不明点があった場合、インターネットで検索をしたり、新たにテキストを購入したりして調べる必要があります。
スクールの通学講座を受講された場合、講義後に講師に直接聞くことができたり、通信講座を受講する場合でも質問に回答をしてくれるといったサポートを利用することもできるでしょう。
独学で行政書士試験を学習する場合、最新情報を多くキャッチできない可能性があります。
例えば、2020年行政書士試験では、短期消滅時効の廃止などの債権法における改正点や遺言制度に関する見直しなどの相続法の改正点が出題される可能性があり、この点につき情報収集し対応する必要があるのです。
独学で費用を安く済ませようとして古いテキストを使い独学で学習される場合、最新情報に対応できないといったリスクもありますので要注意です。
通信講座であれ通学講座であれ、受講することで法改正などの最新情報を得ることができるようになるでしょう。
初心者が独学で行政書士試験に合格するのは厳しい?
これまでご紹介した通り、行政書士試験は法律に関する知識を幅広く問われる試験です。そのため、法律に関する勉強が初めての方や就業経験のない初心者の方が独学で合格を目指すには、難易度がかなり高くなるでしょう。
初心者が独学で行政書士試験に合格するのは厳しいといえますが、だからこそしっかりとした学習スケジュールを立てて、過去問を繰り返し解きながら理解を深めていくことで合格に近づけることができます。
試験に合格する以外で行政書士資格を取得できる方法とは?
(1)公務員として一定年数行政事務に携わっている
国家公務員や地方公務員として行政事務に一定年数従事していることも行政書士資格を得ることができる要件となっています。
最終学歴の高卒の方は17年、中卒の方は20年の実務経験を積むことで、行政書士の国家試験を受けずとも行政書士資格を取得することができます。
平成30年の日本行政書士連合会のアンケートでは登録資格者の15.5%が公務員行政事務からの登録者であり、さらにその内訳は定年退職後に行政書士として再出発する60歳前後の人が大半を占めているというデータもあります。
(2)行政書士資格を得る他資格に合格する
行政書士国家試験以外の他資格合格者にも自動的に行政書士資格が与えられることがあります。
この方法で行政書士になられた方は、日本行政書士連合会のアンケートによれば14.1%となっています。
試験に合格すると行政書士資格を与えられる国家資格は、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士の4つで、この中でも税理士からが13.4%と最も多くなっています。
他資格合格者が行政書士登録をしている場合は、税理士や会計士などもともとの取得資格の業務をメインで行っており、行政書士業務は関連する一部の業務に留まる場合が多いようです。
行政書士資格を得られる国家資格は、行政書士試験よりも難易度が高いため、はじめから行政書士を目指す方のルートとしてはあまり現実性がないかもしれません。
まとめ
ここまで独学で行政書士試験に合格するためのポイントを解説しました。独学は1人で勉強を進めるため、モチベーションを保つことも大変ですが、費用を安く済ませられ自分のペースで学習を進められるというメリットもあります。
学習スケジュールを立てながら試験日までに試験範囲を網羅できるよう、計画的に勉強を進めることが大切です。
また、初心者の方など行政書士の試験を独学だけで受験するのが不安な方は、スクールや通信講座と組み合わせて勉強するのもおすすめですよ。BrushUP学びでは、行政書士試験に合格するための対策講座や全国各地のスクールをご紹介しています。気になる方は資料請求で詳しい内容を確認してみてくださいね。

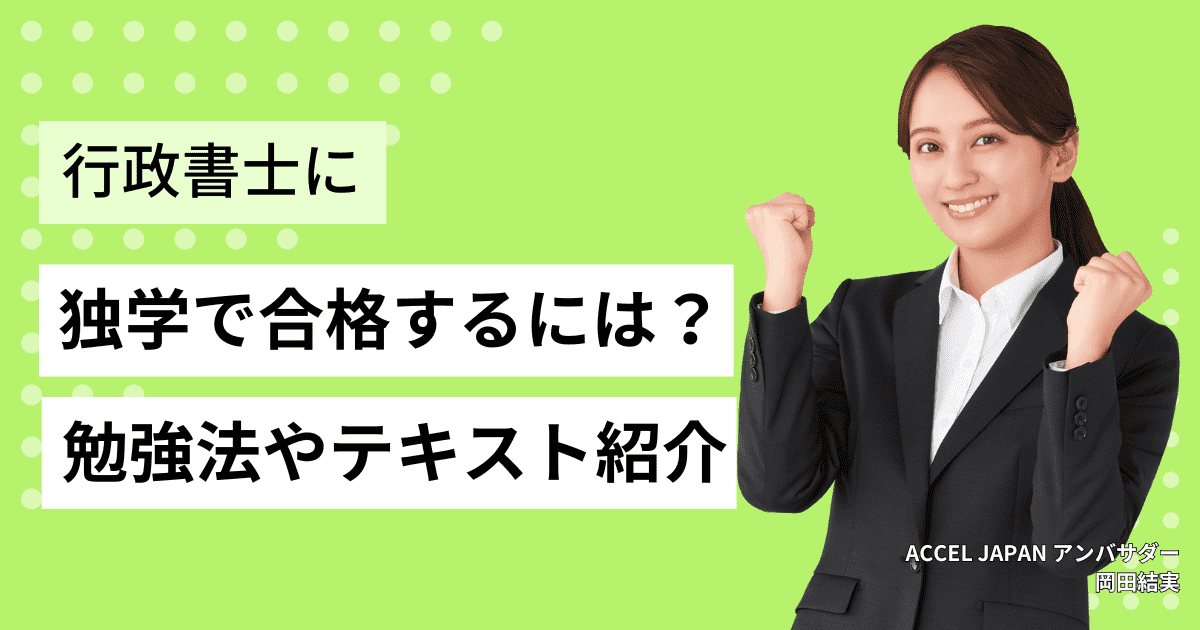




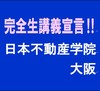


 40代・50代からでも大丈夫?キャリアコンサルタント資格の現実
40代・50代からでも大丈夫?キャリアコンサルタント資格の現実
 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
 メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
 失敗しにくい学び直しの始め方|資格を決める前の準備編
失敗しにくい学び直しの始め方|資格を決める前の準備編
 オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!
オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!





