行政書士試験の合格難易度はどのくらい?
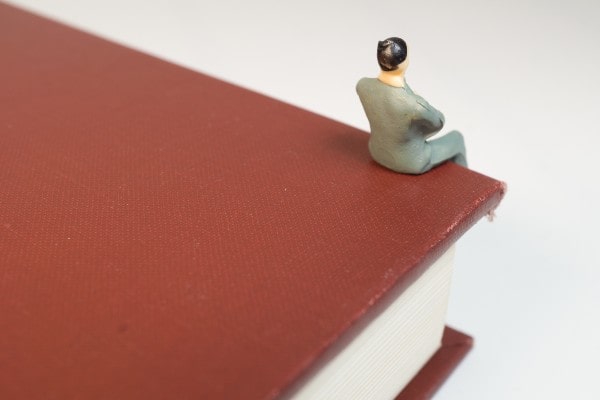
過去10年間の合格率の平均は11.24%と難易度は高い!
行政書士試験の過去10年間の合格率は以下のとおりです。
| 年度 | 合格率 |
|---|---|
| 平成24年度 | 9.2% |
| 平成25年度 | 10.1% |
| 平成26年度 | 8.3% |
| 平成27年度 | 13.1% |
| 平成28年度 | 10.0% |
| 平成29年度 | 15.7% |
| 平成30年度 | 12.7% |
| 令和元年度 | 11.5% |
| 令和2年度 | 10.7% |
| 令和3年度 | 11.2% |
行政書士試験は絶対評価の試験のため合格率に波があります。
平成24年度~令和3年度までの合格率の平均は、11.24%です。
傾向として合格率が上がったあとに下がっている状況なので、早めに学習をはじめておくとよいでしょう。
直近の令和3年度の受験状況をいえば、受験申込者61,869人、受験者47,870人、合格者5,353人、合格率11.2%です。
受験者は令和2年度よりおよそ15%増加しています。
特に女性受験者の増加率は21%以上とめざましく、女性からの注目が高まっている資格といえるでしょう。
行政書士試験は、「憲法」「行政法」「民法」「商法」「基礎法学」「一般知識」の6科目です。
科目数により難易度を考察する場合に注意したいのが、行政法という法律は存在しないということです。
行政書士試験での行政法は「行政に適用される法」のことで、行政作用法・行政手続法・行政事件訴訟法などのいろいろな法律か出題範囲となります。
また、主要科目の民法の条文数は1044条とかなりのボリュームがあり、対策するのに苦労されるかもしれません。
憲法は103条ですので、条文数を比較してみると、民法の学習の大変さが理解できるでしょう。
民法は択一で9問(一問4点)、記述で2問(一問20点満点)ですので、300点中180点以上得られれば合格できる行政書士試験において、捨て科目にすることはできません。
「平均合格率が約11%であること」「実際の科目数が多いこと」「主要科目の民法の条文数が多いこと」があるので、行政書士試験は難関資格だと評価できます。
行政書士試験と宅建(宅地建物取引士)試験に強く両資格ともに毎年多くの合格者を出している、資格の学校TACでは、資格の難易度評価をしています。
そこでの行政書士試験の評価は、5段階評価で上から二番目に難しい★4の評価です。
★4は難しい試験ではあるものの、継続的に努力すれば合格が十分手に届くというレベルです。
出典 一般財団法人行政書士試験研究センター
宅建(宅地建物取引士)試験の合格難易度はどのくらい?
過去10年間の合格率の平均は16.08%と難易度は高い!
宅建(宅地建物取引士)試験の合格率を以下で紹介します。
| 年度 | 合格率 |
|---|---|
| 平成25年度 | 15.3% |
| 平成26年度 | 17.5% |
| 平成27年度 | 15.4% |
| 平成28年度 | 15.4% |
| 平成29年度 | 15.6% |
| 平成30年度 | 15.6% |
| 令和元年度 | 17.0% |
| 令和2年度・10月実施分 | 17.6% |
| 令和2年度・12月実施分 | 13.1% |
| 令和3年度・10月実施分 | 17.9% |
| 令和3年度・12月実施分 | 15.6% |
| 令和4年度 | 17.0% |
宅建試験は、相対評価の試験のため試験合格率はある程度一定です。
平成25年度~令和4年度までの合格率の平均は、16.08%です。
合格率が一定だとしても、受かりにくい試験だということは変わらないので、早めの学習がおすすめです。
一番近い令和4年度の受験状況は、申込者283,856人、受験者226,048人、合格者38,525人、合格率17.0%です。
この10年間受験者数は増加傾向にあり、宅建士は需要と人気が年々高まっている資格の1つといえるでしょう。
宅建試験でおさえたい出題範囲について
宅建試験の受験科目は、「宅建業法」「民法など」「法令上の制限」「税・その他」で4科目扱いされるのが一般的です。
注意したいのは、民法などでは借地借家法や不動産登記法からも出題があり、法令上の制限においては国土利用計画法や都市計画法そして建築基準法なども出題範囲とされるため、実際の科目数はかなり多いということでしょう。
しかしながら、宅建試験は過去問と似たような問題が出題される傾向にあります(95%は過去問と似たような問題となっているようです)。
そのため、過去問をしっかり対策すると合格レベルまで到達することができるでしょう。
50問中20問出題される主要科目の宅建業法は、非常にわかりやすい法律であり、得点源にしやすいともいえます。
実質的な科目数は多いですが、「平均合格率が16%前後であること」「過去問対策により合格レベルまで到達できること」「主要科目の宅建業法が対策しやすいこと」という面では、行政書士の試験よりは合格を勝ち取りやすいといえるかもしれません。
行政書士試験と宅建試験の難易度評価をしている資格の学校TACでは、宅建試験の難易度は★3つとなっています。
5段階中真ん中の評価なので、努力をすれば合格を目指せる試験であるともいえます。
行政書士と宅建のダブルライセンスのメリットとは?
不動産に関わる書名作成の場面で活かすことができる!
行政書士の主な業務は、「官公署に提出する書類の作成やその代理」「権利義務に関する書類の作成やその代理」「事実証明に関する書類の作成やその代理」などです。
宅建士(宅地建物取引士)の主な業務となると、不動産取引時における「重要事項に関する説明」「重要事項説明書への記名と押印」「契約書(37条書面)の記名と押印」などです。
行政書士と宅建、2つの資格を持つと、それぞれの資格が扱う分野の仕事をもらうことができます。
例えば、飲食店の営業許可申請や農地転用の許認可などの際には、不動産取引が絡んでくることがありますが、この時にひとりでお客さまの悩みを解決できるのです。
ダブルライセンスで営業すると、他方の資格の知識が業務でいかされることがあります。
例えば、遺産相続の書類の作成や遺言書の作成の際に、宅建士の不動産の権利関係や契約に関する知識があると、より細かくお客さまに説明できるようになるのです。
宅建士として活躍する場合、宅建試験より難しいとされる行政書士試験に合格していると、知識的に間違いと判断されやすくなります。
両資格とも法律がメインの資格試験ですので、他方の資格を学習した際に身に付いた「法律の学習方法」を、もう一方の資格を学ぶ際にいかすことができます。
また、行政書士試験と宅建試験の共通科目に民法があります。
宅建試験で得た民法の知識は行政書士試験の受験の際に活かされます。
行政書士試験では民法は主要科目で、300点中76点の配点があります。
行政書士と宅建士のダブルライセンスを狙う際には、比較的難易度が低い宅建試験に受かってから行政書士試験に挑むという流れが一般的です。
ただし、興味があることの方が学習は進むので、行政書士業務をメインとしたい場合には行政書士試験を先に受験してもいいでしょう。
まとめ
当ページでは、以下のことを説明しました。
・行政書士試験の方が宅建試験より難易度が高いといえること
・行政書士と宅建のダブルライセンスは複数のメリットがあること
行政書士資格を取得すると、「一般生活やビジネスで役に立つ法的知識を得られること」「職場によっては資格手当が出る」というメリットがあります。
宅建資格を得ると、「独占業務を担当できるので不動産業界では資格手当がついたり、昇格できる可能性がある」「不動産の売買や仲介を行う場合、それぞれの事務所で5人に1人の割合で宅建士を在籍させることが必要となるので、有資格者は不動産業界で転職しやすいこと」「サラリーマン以外にも資格を使い独立開業するという選択股がうまれること」などのメリットがあります。
行政書士の資格取得をご検討されている方は、宅建(宅地建物取引士)の資格取得もご検討されてみてはいかがでしょうか。

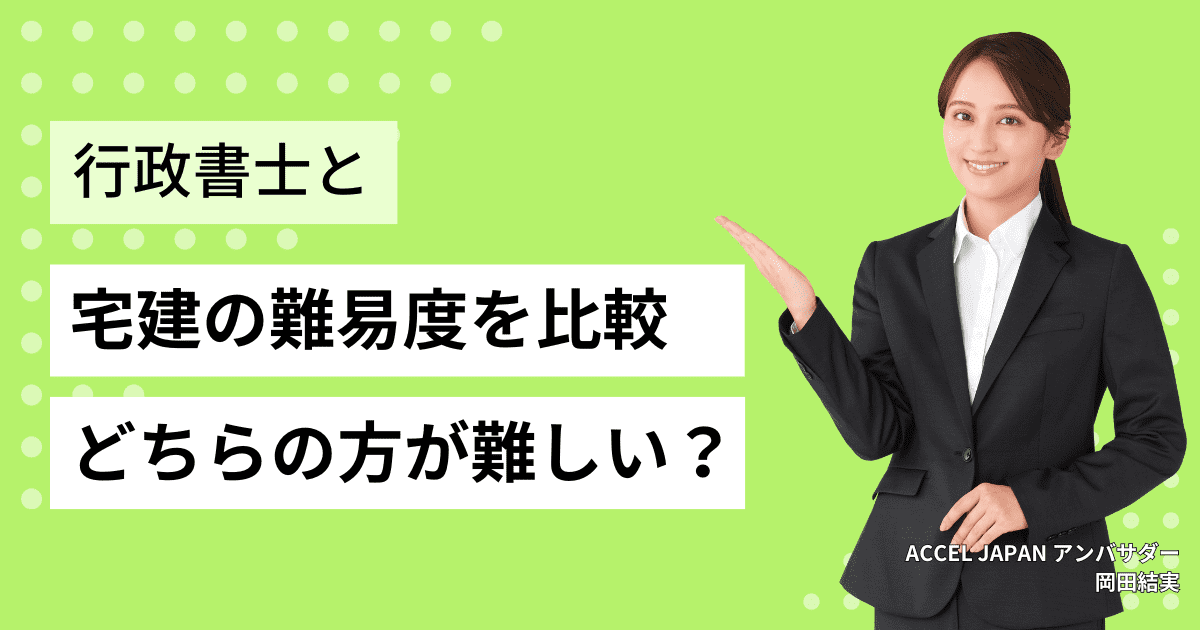




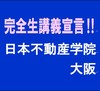


 2026年1月1日掲載の新スクール&特集ページを大紹介!
2026年1月1日掲載の新スクール&特集ページを大紹介!
 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
 メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】





