行政書士とはどんな資格?
行政書士とは、行政書士法によって定められている国家資格です。他者からの依頼を受け、以下のような手続きを代理でおこないます。
- 許認可等の申請書類の作成
- 申請書類の提出
- 遺言書等の権利義務や事実証明、契約書などの作成
- 行政不服申立ての手続き
上記のように書類の作成や官公署へ提出するのは、行政書士の国家資格を保有した人だけができる独占業務です。
資格の難易度は?
行政書士の合格率は例年10%~12%程度で推移しています。最新の2022年度に実施された試験では合格率が12.13%でした。
合格率だけで見ると難易度が高く感じますが、行政書士試験は受験資格がなく、誰でも受験することが可能です。実際に2022年度試験には最年少受験申し込み者が8歳、最年長受験申込者が98歳と、幅広い方が受験にチャレンジしていることがうかがえます。
行政書士の仕事を活かせる仕事は?
行政書士の資格は交通事故や相続関係など、個人や法人問わず幅広い業務があります。大きく「個人向け」と「法人向け」に分けて解説します。
個人向けの仕事内容
遺言屋相続関係の業務は以下が挙げられます。
- 遺言書の作成
- 遺産相続における遺産分割協議書の作成
- 相続人の確定調査
自動車登録関連の業務は以下が挙げられます。
- 自動車登録申請
- 自動車重量税申告
- 交通事故示談書
- 自賠責保険や任意保険金の請求
帰化許可の申請や国際業務などは以下が挙げられます。
- 日本国籍の取得を希望する人の帰化申請の手続き
- 在留資格の取得
- 永住許可
- 国際結婚の各種申請
市民法務の業務には以下が挙げられます。
- 内容証明書の作成
- クーリングオフ
- 契約書や示談書、協議書の作成
法人向けの仕事内容
法人関連の仕事には以下の業務が挙げられます。
- 株式会社や各種法人、組合等の設立手続き
- 飲食店や旅行店、建設業などの許認可申請
- 文化庁への著作権の登録申請
上記のほかにも、法人設立における事業運営の支援や設立後のサポートといったコンサルティング業務から、行政書士向けのセミナーや行政書士資格を取得したい人向けの講師として活躍している方もいます。
関連記事:
行政書士の仕事内容と需要・将来性
行政書士を取得するメリットとは?
行政書士の業務は個人向け、法人向け両方にあり、依頼人を幅広くサポートできる点が強みです。また独占業務においては行政書士資格を保有している人しかおこなうことができず、希少価値が高いといえるでしょう。
資格を取得することで就職や転職にも有利になるほか、独立して事務所を開業することも可能です。
オンラインを活用したサービスで将来性が高い
近年、Web会議システムを利用しオンラインにて相談を受けるという行政書士も増えてきています。「行政書士に相談する」というと敷居が高く感じる人もいるかもしれません。しかし身近になってきたオンラインツールを使用することで、事務所に訪問せずとも相談ができたり、遠方の行政書士を尋ねたりすることもできるでしょう。
幅広い業務を任せられ、さまざまなツールを活用しながら相談を受けられる行政書士は、将来性が高いといえます。
自宅で開業できる
行政書士は、多額な開業資金の必要もなく、自宅で開業することができます。
基本的には独立開業を前提とした資格なので、どこかに所属して働くよりも、自分で事務所を立ち上げて働くのが良いでしょう。
営業力が必要ですが、やればやった分だけ報酬になるというよさが独立開業にはあるといえます。
関連記事:
行政書士として開業・独立する方法やメリット・デメリットも紹介します!
転職や就職で有利になる
行政書士の資格を持っていることで基本的な法律知識があるとみなされ、企業の法務部や総務部に配属されれば知識を生かして働くことができます。資格を持っていない人と比較すると知識量に差がみられる可能性があるため、即戦力を求める企業が欲しい人材といえます。
行政書士としての求人は多くない
行政書士は独立、開業が一般的とされるため行政書士事務所や法人などで求人を見つけるには、タイミングもあるでしょう。
行政書士ではなく他の士業である、弁護士事務所や税理士事務所、会計事務所などへの就職・転職した際には、行政書士としての業務を任されることもあります。
関連記事:
行政書士の就職先・転職先について
行政書士の平均年収は?
行政書士の平均年収は公的に発表されているものはなく、民間が独自で調査した結果には差が見られます。約400万円~600万円が目安になるでしょう。
国税庁が公表している「令和4年分民間給与実態統計調査結果」によると、給与所得者の平均給与は458万円となっているため、行政書士は平均からやや平均以上の収入を得られる資格といえます。
申請料の高い業務は収入も多い
行政書士の業務は多岐にわたりますが、なかでも薬局開設許可は申請料が非常に高い業務です。その他にも産業廃棄物処理業許可申請や、知的資産経営報告書の作成、帰化許可申請といった業務も申請料が高く、行政書士の収入も高くなります。
数千万円や1億円以上の年収がある方も
一部、年収2,000万円~3,000万円以上を得ている行政書士もいるため、平均給与は全体的に引き上げられています。
中には、年収が1億円以上を超える方もいるようなので、行政書士の一般的な給与は、500万円以下になります。
人によって所得に大きな差がある仕事ですが、行政書士の所得は、日本人の平均給与と比べると高い水準であるといえるでしょう。
独立・フリーランスで収入アップも
行政書士として独立、開業する人は珍しくありません。独立することで幅広い業務から自分が携わりたい業務を選んで活動することができるでしょう。ただし独立して年収をアップさせるには、集客力やコミュニケーション能力も必須です。新規で顧客を獲得し、確かな信頼を築くことができれば、企業に就職するよりも高い年収を得ることも可能といえます。
関連記事:
行政書士の年収・給料について紹介します!
行政書士は最短4ヶ月で目指せる!
行政書士の対策講座の中には、4ヶ月で合格を目指すことを想定したカリキュラムもあります。一般的には行政書士の国家試験のための勉強期間は「6ヶ月~1年程度」といわれています。そのなかで最短で取得を目指すには、4ヶ月のように短期間での学習カリキュラムを受講するのも1つの手です。
保有する資格により試験が免除になる
国家試験を受ける他に、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士の資格を持っている方であれば、試験なしで日本行政書士会連合会に登録することで行政書士になることができます。
公務員として行政事務経験があれば試験免除
行政事務の仕事に公務員として17年(※最終学歴が中学校卒業の方は20年以上)携わった経験があれば、試験なしで行政書士になることができます。
しかし、ほとんどの方は国家試験への挑戦が必要となるでしょう。
関連記事:
行政書士試験合格に必要な勉強時間は?最短合格のポイントについても紹介します!
行政書士試験は11月!資格取得に向けたスケジュール例
行政書士の資格に合格するまでの勉強時間を、独学・通学の2パターンのモデルスケジュールをもとに動画で紹介します。
また、スクールを受講する場合の費用も紹介しています。
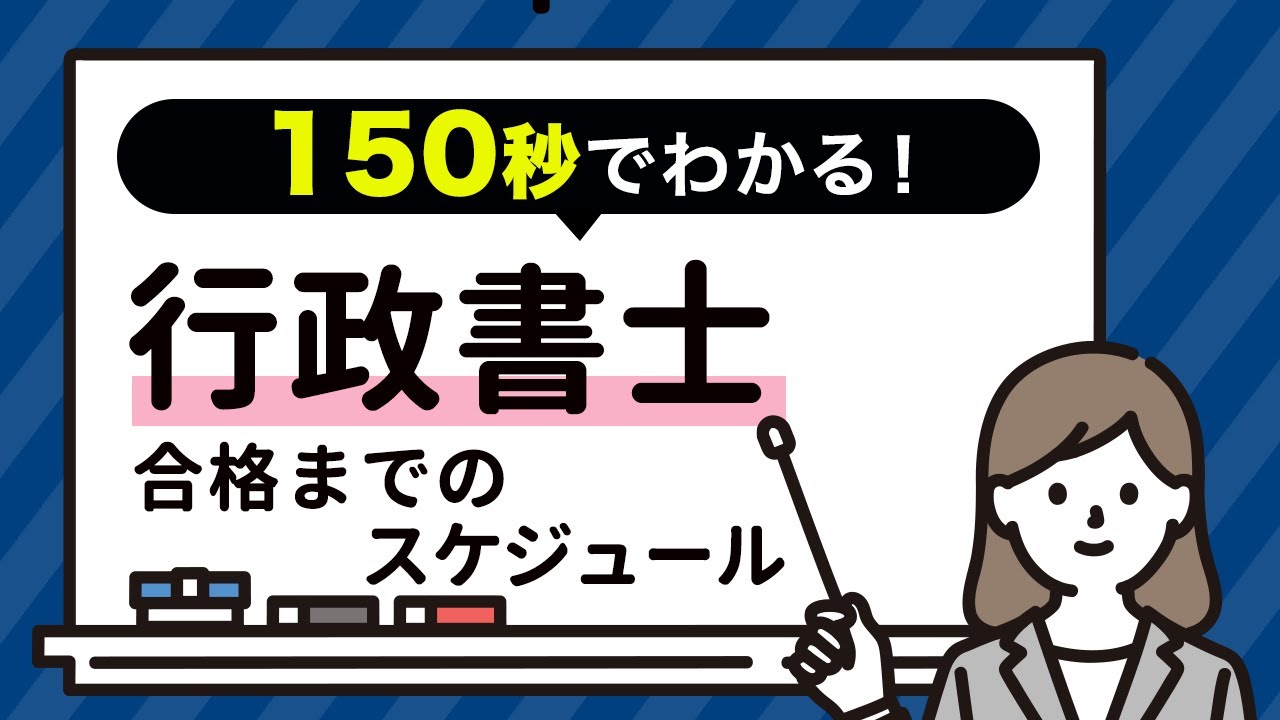
関連記事:
行政書士試験合格に向けてスケジュール、勉強時間などを動画でわかりやすく紹介
独学とスクールどちらが良い?
行政書士の出題範囲を網羅するためには、スクールでの学習がおすすめです。
行政書士試験は、行政法・民法・憲法の主要3科目をはじめとして民法・商法・基礎法学といった法令系の試験に加え、一般知識の出題もあり、出題範囲は広いといえます。
どういった順番で勉強を進めていくと良いのかというスケジューリングが合格のカギを握っています。スクールを選びの際にスケジュールもしっかりと教えてくれるかも確認しましょう。
問題演習に時間を多くとっている
問題演習は合格にとって大変重要ですが、スクールでは問題演習の時間も多くとってあることがほとんどです。
スクールの講座は通学コースと通信コースに分かれています。
講座にはCDが付いているものやスマートフォンに講義内容をダウンロードできるものもあります。
そういったものをうまく活用しながら効率的に勉強できるのも講座を受けるメリットといえるでしょう。
関連記事:
独学で行政書士試験に合格するための勉強法やおすすめのテキストも紹介します!
行政書士の通学講座と通信講座の違いは?
行政書士の通学講座と通信講座の一例として比較します。同時期に学習を始めても、様々な点で通学と通信は異なります。
講座を受講するメリット・デメリット
講座を受講するメリット・デメリットについては下記の通りです。
通学のメリット
- わからないことを質問しやすい
- 同じ目標をもつ仲間ができる
- 試験や業界、就業に関する情報が入手しやすい
通学のデメリット
- 決められた日程の範囲で通わなければならない
- 一定期間はスクールに通う必要がある
通信のメリット
- 自分で学習スケジュールを立てられるので、時間の融通がきく
- 自分のペースで学習できる
- 通学講座と比較して割安
通信のデメリット
- 自分でスケジュールを管理しなければならない
- 質問すると返事が来るまで時間がかかる場合がある
関連記事:
行政書士の通信講座を比較する!
行政書士の仕事内容は?
人に代わってさまざまな書類を作成する仕事
行政書士は、官公署などに提出する許可申請や認可申請などの書類作成および提出手続きの代行や、相談業務などを行う仕事です。
書類や手続きは煩雑なものが多いため、行政書士が代行することで、依頼主側の利益や権利を守り、行政側も処理が効率的に行えるようにすることが、行政書士の役割といえます。
仕事例1:田や畑を駐車場にしたい場合
田畑だった場所を駐車場にしたい場合、行政に許可を取る必要があります。
農業委員会などへの届出書類の提出も必要となるため、一般的には書類作成・提出を行政書士に依頼します。
仕事例2:お店を開業したい場合
新しくお店を開く際には、「飲食店営業許可申請」が必要ですが、これも書類作成・提出を行政書士がおこないます。
行政書士の仕事として増えているのが、外国人を日本に呼び寄せたい場合の配偶者ビザや就労ビザなどに関する「在留資格認定証明書」の交付申請手続きなどが近年増加しているようです。
行政書士のルーツ
行政書士のルーツをたどると、戦前までいた「代書人」という人に代わって手紙や書類などを書く人に行き当たります。
それが昭和26年施行の「行政書士法」という法律によって、行政書士という仕事になり、昭和58年からは国家試験になっています。
仕事の範囲
行政書士が扱う書類は、1万種類以上に及ぶといわれています。
実質的にはいくつか主要なものがあります。
以下のように、3つに分けて紹介していきましょう。
(1)官公庁に提出する書類
官公庁に提出する書類で、農地転用届・飲食店営業許可申請・建設業許可申請・風俗営業許可申請・産業廃棄物許可申請・車関係の書類などがあります。
(2)権利義務に関する書類
権利義務に関する書類で、遺産分割協議書・売買契約書・賃貸借契約書・示談書・始末書・定款などがあります。
(3)事実証明の書類
各種議事録・会計帳簿・実地調査に基づく各種図面類などがあります。
(4)その他の業務
行政書士は書類に関する相談業務も行っています。
また、成年後見人制度といい、認知症や知的障がい・精神障がいがある方などに代わって重要な契約や財産管理をする制度上の仕事も行うことができます。
関連記事:
行政書士の仕事内容と需要・将来性
行政書士の独占業務とは?
弁護士ができること
弁護士は、法律の専門家として法律事務の仕事をしますが、行政書士はその中の一部の仕事を担当していると考えて良いでしょう。
例えば、遺産相続に関して行政書士は遺言書や遺産分割協議書を作成することができますが、遺産相続に関して争いなどトラブルがある場合の法律相談は行うことができません。
司法書士ができること
司法書士は不動産登記など「登記」に関する書類を扱う仕事です。
行政書士が自治体などの「行政機関」に提出する書類を扱うのに対し、司法書士は「法務局」や「裁判所」に出す書類を扱っています。
行政書士が「街の法律家」といわれる理由
会社設立の申請手続きで、定款の作成や公証人役場に認証を受ける手続きは行政書士ができますが、法務局に対して会社設立の登記手続きをするのは司法書士しかできません。
このように、弁護士や司法書士の方ができることは多いですが、両者へ相談に行くのには敷居が高いといえます。
そのような時の相談先を知っているのが行政書士です。
そのため「街の法律家」ともいわれているようです。
関連記事:
行政書士と司法書士はどちらがおすすめ?ダブルライセンスについても紹介します!
行政書士に向いている人とは
事務処理能力が高い人
行政書士は書類を扱う仕事ですので、当然事務処理能力の高さは武器になります。
スピーディーに書類を作成しなくてはならず、行政機関を相手にする仕事のため書類の不備は許されません。
間違えてしまった場合、二度三度と行政機関に出向くことになります。
煩雑な書類が多い
行政書士が扱う書類は、添付書類が多いなど当然煩雑なものが多いです。
事務処理能力が高くなくては仕事をこなすのが難しいでしょう。
逆に、書類作成に関する細かいチェックなどが苦にならない方にはおすすめの仕事です。
コミュニケーション能力がある人
顧客は漠然とした悩みを持って相談に来ることも多いでしょう。
顧客の立場に立ったコンサルティングをするためには、信頼を得ることが必要です。
仕事が円滑になる
難解な法律用語を分かりやすく顧客に伝える姿勢やコミュニケーション能力は、行政機関の窓口で話しをするためにも必要な能力であるといえるでしょう。
人間関係を円滑になれば、仕事も円滑になりますし、顧客を獲得する上でも有利になる可能性があります。
弁護士・司法書士との繋がり
また、行政書士では対応できない仕事依頼に備えて、弁護士や司法書士などとのネットワークを構築しておくことも重要です。
営業力がある人
行政書士として仕事をするために、求人を探すのが難しい場合もあり、実務経験がないまま開業をするというケースも少なくありません。
そのような時に大切なのが営業力です。
人脈を作り、ホームページやSNSも活用する
同業の行政書士や弁護士・司法書士・税理士などから仕事が来ることも期待できる仕事ですので、人脈を作っておける方は行政書士に適しているでしょう。
また、ホームページやSNSなどで集客する方法も営業の手段として活用すると良いでしょう。
専門分野を持つことも重要で、営業がしやすくなりますし、勉強し続けることも容易になります。
臨機応変に行動できる人
行政書士が扱うことができる書類の数は1万種類以上といわれていますが、その中でも時代に合わせたニーズをくみ取って臨機応変に専門分野を開拓していけるかが、行政書士として仕事を成功させるカギとなるでしょう。
専門分野を開拓するには、まず自分がその分野が好きで関わりたいという思いが大事で、深く掘り下げて勉強する際にも重要です。
幅広い業務ができた方が良いケースもある
行政書士が少ない地域では専門分野を持つというよりも万遍なく色々な業務ができるようになり「街の法律家」として活躍する方が良い場合もあるでしょう。
その点から見ても、自分の置かれている状況によって臨機応変に行動できる人が行政書士には向いているといえるでしょう。
行政書士資格試験の概要
ここからは行政書士の試験概要について解説します。一般財団法人 行政書士試験研究センターが指定試験機関となり、行政書士の試験を運営しています。
試験日程
2024年11月12日(日)13時~16時
受験資格
受験資格はありません。誰でも受験することが可能です。
受験費用
10,400円
出題形式と配点
問題数は全部で60問、合計で300点満点の試験になっています。出題形式や配点は以下の通りです。
- 五肢択一式(1問4点):5つの選択肢の中から正しいものを1つ選ぶ形式
- 多岐選択式(1問8点):20ある選択肢の中から正しいものを4つ選ぶ形式
- 記述式(1問20点):40字程度で記述する形式
出題科目
科目は大きく分けて「法令」と「一般知識」の2つがあります。
| 項目 | 法令 | 一般知識 |
|---|---|---|
| 問題数(全60問) | 46問 | 14問 |
| 配点(全300点) | 244点 | 56点 |
| 科目 | ・基礎法学:2問 ・憲法:5問 ・民法:選択9問、記述2問 ・一般的法理論・統合:5問 ・行政手続法:3問 ・行政不服審査法:3問 ・行政事件訴訟法:選択3問、2問 ・国家賠償法・損失補償:2問 ・地方自治法:3問 ・商法:5問 |
・政治、経済、社会:7問 ・情報通信・個人情報保護:4問 ・文章理解:3問 |
合格率推移と合格基準点
行政書士国家試験の直近10年の合格率を調査しました。直近の試験でも合格率は12.13%と低く、難易度が高い試験といえるでしょう。
合格基準点
行政書士の試験の運営元である「一般社団法人 行政書士試験研究センター」のページによると、下記の通り合格基準が明確に定められています。
- 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、122点以上である者
- 行政書士の業務に関する一般知識等科目の得点が、24点以上である者
- 試験全体の得点が180点以上である者
行政書士と一緒に取りたいおすすめの資格
社会保険労務士
社会保険労務士とは、社会保険労務士法という法律に基づいた国家資格であり、「社会保険」「人事」「労務」の専門家です。
社会保険に関する書類の作成や申請、給付などの手続き、給与計算などの代行を行う仕事です。
行政書士×社会保険労務士
官公署への認可許可の書類や届出を作成し申請を行う行政書士とも関連が近く、会社の運営に関連する仕事を行える点は共通しているので、社会保険労務士の資格も併せて取得することで、活躍の幅をさらに広げられる可能性があります。
関連記事:
社会保険労務士になるには
司法書士
司法書士は、司法書士法に基づいた国家資格です。
主に財産や権利を守ることを目的とし、法律的なアドバイスを行ったり、相続関連や不動産、商業の登記申請などをおこないます。
行政書士×司法書士
行政書士の資格と併せて司法書士の資格も取得することで、相続での不動産登記も行うことができ、会社に関するものでは商号や法務局への提出することもできるようになるので、活躍の幅を広げることができるでしょう。
関連記事:
司法書士になるには
中小企業診断士
中小企業診断士は、中小企業の相談に乗り、経営課題への助言や診断を行う経営コンサルタントの国家資格です。
中小企業を対象とし、さまざまな角度から経営状況を診断した上で、アドバイス・助言などを行うため、「企業のお医者さん」ともいわれるような存在です。
行政書士×中小企業診断士
行政書士の資格と併せて、中小企業診断士の資格も取得することで、中小企業の経営を診断・助言・アドバイスを行うことができ、行政書士に認められている書類の作成や申請を行うこともできるため、活躍の幅を広げることができるでしょう。
関連記事:
中小企業診断士になるには






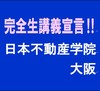


 資格取得 春の新キャリア取得応援!受講料10%OFF!早期申し込み6万円分プレゼント特典付き!
資格取得 春の新キャリア取得応援!受講料10%OFF!早期申し込み6万円分プレゼント特典付き!
 オンライン心理学教室4月開講! 実践に強い資格が取れるカウンセラー育成スクールが5月にスタート!
オンライン心理学教室4月開講! 実践に強い資格が取れるカウンセラー育成スクールが5月にスタート!
 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
 メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
 「日本語教師」の資格取得を目指すなら、38年超の実績を有するアークアカデミーで!
「日本語教師」の資格取得を目指すなら、38年超の実績を有するアークアカデミーで!





