行政書士と司法書士の年収比較

行政書士と司法書士は、どちらも「独占業務」をおこなうことができる国家資格です。資格の取得難易度が高く、資格取得者だけが実施できる独占業務を仕事にすることで、高い年収が見込めるでしょう。ここでは2つの資格に対しての年収を比較します。
司法書士の平均年収は971万円!
厚生労働省が発表している「令和4年賃金構造基本統計調査」をもとに算出されている司法書士の平均年収は971万円です。これは労働者の平均年収である311万円を大きく上回ります。
引用 厚生労働省「jobtag 司法書士」
行政書士の平均年収は579万円
対する行政書士の平均年収は579万円と、司法書士の平均年収と比較すると、行政書士が低く感じてしまうかもしれません。しかし労働者全体の平均年収と比べると行政書士の平均年収は200万円以上高くなっています。
引用 厚生労働省「jobtag 行政書士」
司法書士の方が年収が高い理由
司法書士の方が行政書士よりも年収が高くなる理由は、働く人数の違いによります。司法書士の資格難易度はとても高く、合格率は5%前後とされています。そのため司法書士として働いている人は少なく、全国でも25,000人ほどと希少価値の高い職業です。
行政書士の資格も取得難易度は高く、合格率が毎年10%前後です。ただし、現状司法書士よりも働く人が多く、全国でも約31万人いるとされています。
司法書士の方が低い競争率のなかで仕事を得られやすいことや、登記手続き、専門職御見人など案件が途切れにくいことも、司法書士の方が年収が高くなる理由の1つと考えられます。
独立開業でさらに年収アップが見込める
厚生労働省が発表している「職業情報提供サイト jobtag」によると、司法書士と行政書士の2つとも就業形態として「自営・フリーランス」を選んでいる方が圧倒的に多くなっています。
司法書士や行政書士で独立開業はめずらしくなく、開業前より年収がアップしたという方も多くいます。1つの勤務先で長く勤めていても自然と年収が上がっていくわけではない場合が多く、独立して自分自身で仕事を得る方が、収入に直接影響を与えると考えられます。
行政書士と司法書士の業務範囲の違い
ここからは行政書士と司法書士の具体的な業務について解説します。一般的には司法書士の方が行政書士よりも業務範囲が広いとされています。
行政書士の主な業務
行政書士の業務内容は、以下の項目での書類作成や代理、相談業務などが挙げられます。
官公署に提出する書類作成や代理、相談業務
行政書士が扱う官公署に提出する書類は、主に許認可などに関するものです。
官公署に提出する書類で扱えるものは、1万種類を超えます。
権利義務に関する書類作成や代理、相談業務
権利義務に関する書類とは、書類の中でも、権利の発生・変更・存続・消滅の効果の発生を目的とする「意思表示を内容」とするもの。
例えば、遺産分割協議書や各種契約書、内容証明などのことです。
事実証明に関する書類作成や代理、相談業務
事実証明に関する書類とは、文書の中でも、「社会生活に交渉を有する事項」を証明するに足りる書類のことで、例えば、議事録や会計帳簿、申述書などのことです。
その他の特定業務
例えば、地方入国管理局長に対して届け出を行った申請取次行政書士がおこなう、「出入国管理」や「難民認定法」に定められている申請に関して、申請書や資料などの提出、書類の提示などの業務があります。
司法書士の主な業務内容を紹介します。
司法書士の主な業務
- 登記や供託手続の代理
- 法務局に提出するさまざまな書類の作成
- 法務局長に対して行う登記や供託の審査請求手続の代理
- 裁判所や検察庁に対して提出する書類の作成、法務局に対して行う筆界特定手続書類の作成
- 上記に関する相談
- 認定司法書士は、簡易裁判所での訴額140万円以下の訴訟・裁判外和解・仲裁事件・民事調停などの代理とこれらに関する相談
- 5,600万円以下(対象土地の価格)の筆界特定手続の代理とこれに関する相談
行政書士と司法書士の試験難易度の違い
行政書士試験と司法書士試験を比較した場合、一般的に司法書士試験の方が難しい試験だとされています。その理由を解説します。
試験の難易度は司法書士の方が高い!その理由は
試験難易度が違う原因の一つに司法書士試験の科目数の多さが挙げられます。
科目数が多くなると、学習量が増えるので難易度が上がるということです。
難易度をイメージしやすくなるように、両資格の科目数を紹介します。
司法書士の試験は11科目
- 憲法
- 民法
- 商法(会社法含む)
- 刑法
- 不動産登記法
- 商業登記法
- 供託法
- 民事訴訟法
- 民事執行法
- 民事保全法
- 司法書士法
行政書士の試験は6科目
- 憲法
- 行政法
- 民法
- 商法(会社法含む)
- 基礎法学
- 一般知識
司法書士試験の方が行政書士試験より難しい理由は他には、取らなくてはいけない点数が高いということも挙げられます。
相対評価の試験である司法書士試験は、何点取れば合格と断言できませんが、例年の試験結果から、近年は得点率73%(280点中約206点)取れば合格が見えてくると考えられます。
行政書士試験は絶対評価の試験で、得点率6割以上(300点満点中180点以上)で合格です。得点率に関しては、司法書士試験の方が厳しいといえるでしょう。
試験の合格ライン
司法書士試験は相対評価のため断定的なことはいえませんが、司法書士試験に合格する場合、近年は最低でも午前択一71%以上、午後試験68%以上、記述43%以上の得点を得る必要があると考えられます。
行政書士試験は絶対評価の試験なので、例年基準が変更することはありません。足切りは法令等科目満点の50%以上、一般知識等科目満点の40%以上です。
試験合格率から考えても、司法書士試験の方が難しいといえます。
合格率の違い
司法書士試験の近年の合格率は、2019年は3.6%、2018年度が3.5%、2017年度だと3.3%です。
行政書士試験は、2019年だと11.5%、2018年が12.7%、2017年は15.7%となっています。
以上をふまえると、行政書士試験より司法書士試験の方が難しいといえるでしょう。
行政書士資格を取得するメリット
難易度が高い資格試験の方を必ずしも取得した方がいいとはいえません。
行政書士資格を取得するメリットは、司法書士試験より比較的簡単ではありながらも、仕事の仕方によっては司法書士と同等の収入を得られる可能性があることです。
勉強時間についても、司法書士資格を取得するには、1,200~3,500時間、行政書士資格を取得するなら400~800時間必要だとされており、司法書士よりも短時間で合格を目指すことができます。
もちろん、司法書士資格を取得するメリットもあります。
勤務でも独立でも、平均的な数字で考えたら年収が高いことに加えて、行政書士と比較して、求人数が多い傾向があり、独立開業も成功しやすいです。
行政書士と司法書士、どちらの業務が合っているか、また、どちらのメリットを選びたいのかにより、取得する資格を選ぶことをおすすめします。
ダブルライセンスとして行政書士と司法書士を取得するメリットは?
なかには行政書士と司法書士の両方の資格を取得する「ダブルライセンス」で活躍している方もいます。それぞれの業務ができるようになり、業務の範囲が広がります。
仕事の依頼が増えたり、信用度も上がる!
例えば、離婚協議書と財産分与の名義変更登記、遺産分割協議書と相続登記、許認可と会社設立登記などをセットで依頼を受けられるようになります。
依頼可能な業務範囲が広くなると、それはアピールポイントとなり、めんどうなことを一か所で任せたいと考える方の心を掴め、依頼されやすくなるでしょう。
また、信用度もアップします。
行政書士試験も司法書士試験もどちらも難しい試験ですので、一つの資格保持者より、2つの資格を持っている方が優秀な先生だと判断されやすくなるということです。
依頼料も高額になることが多く、収入アップにつながるでしょう。
共通した内容があるためW取得しやすい
さらに、一方の資格試験に合格後、試験科目で共通なものもあるため、行政書士試験か司法書士試験の学習にすんなりと入っていけるメリットもあります。
民法・商法(会社法含む)・憲法は、共通科目です。出題の仕方も、択一式は共通です。
通信講座を運営しているスクールなどによっては、他資格を受験していたり合格している場合、別資格の講座を受ける際に割引となるケースもあります。
行政書士資格と司法書士資格とのダブルライセンスを目指す場合、一方の資格取得の際に得られた知識を最大限いかすために、一つの資格に合格したあとすぐに、他方の資格の学習に入ることをおすすめします。
時間が経過してしまうと、知識を忘れてしまったり、法改正などによる変更が生じる可能性があるためです。
まとめ
この記事では、以下のことをお伝えしました。
●「業務に対する適性」「資格のメリット」を考慮し、行政書士資格と司法書士資格、どちらを取得した方が良いのか判断するのがよいこと
●「ワンストップサービスを行いやすい」「信用が上がる」などのメリットがあるので、できるなら行政書士資格と司法書士資格のダブルライセンスで営業した方が良いこと
行政書士資格と司法書士資格は国家資格であり社会的にも信頼されている資格です。
先生といわれることになる行政書士と司法書士は、人生経験豊富で貫録があるほうが信頼されやすくなるので、30代や40代以降でも独立開業は十分できます。
「司法書士」の資格の詳細や試験データについては、下記リンクよりご確認いただけます。
【司法書士】の資格の詳細やQ&A、試験データはこちらから

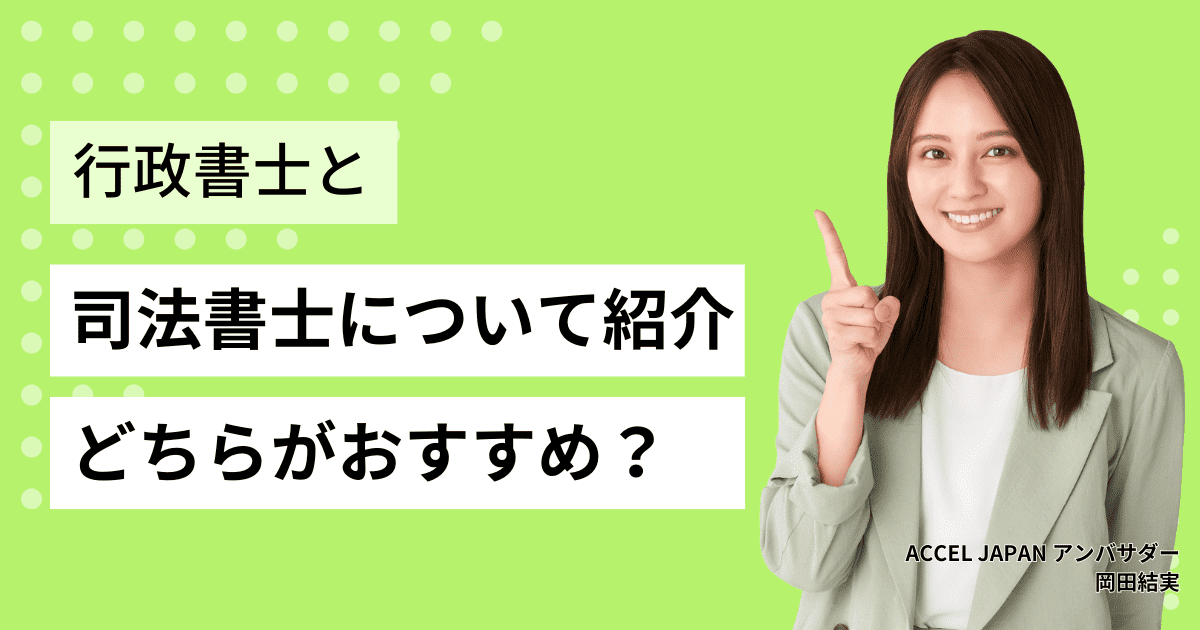




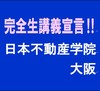


 世界で最も取得されているNASMパーソナルトレーナーライセンスで、トレーナーになろう!!
世界で最も取得されているNASMパーソナルトレーナーライセンスで、トレーナーになろう!!
 受講料10%OFF!6万円分プレゼント特典付き!年末年始学習応援キャンペーン実施中(1月開催/全国)
受講料10%OFF!6万円分プレゼント特典付き!年末年始学習応援キャンペーン実施中(1月開催/全国)
 動き出す人は、もう準備している。国家資格で差がつく1年へ!
動き出す人は、もう準備している。国家資格で差がつく1年へ!
 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定





