社会福祉士が目指せるおすすめスクール
高卒でも社会福祉士になれる!

社会福祉士は大学卒業者が目指す資格という印象が強いかもしれませんが、高卒でも一定の条件を満たせば受験資格を得られます。
主なルートは、福祉系の短大や専門学校に進学して必要な科目を履修する方法、または介護職などで実務経験を積み、その後に養成施設で学ぶ方法の2つです。
2025年度からは制度改正により、実習時間が180時間から240時間に拡大され、複数の施設で実習をおこなうことが必須となりました。この点も踏まえた準備が求められます。
高卒であっても、自分に合ったルートを選び、計画的に学習を進めていけば、社会福祉士を目指すことは十分に可能です。
高卒者が社会福祉士を目指す6つの受験資格ルート
社会福祉士国家試験には多様な受験資格が用意されており、高卒からでも挑戦できるように複数のルートが整備されています。以下では6つの代表的なルートを解説します。
1.福祉系大学(4年制)に進学するルート
一般的な方法は、福祉系の大学に進学し、指定科目を履修して卒業するルートです。この場合、卒業と同時に社会福祉士国家試験の受験資格が得られるため、学習から資格取得までの流れが明確でわかりやすいのが特徴です。
大学では、福祉理論やソーシャルワーク実習(※2025年度の制度改正により「相談援助」から名称変更)が体系的に組み込まれており、240時間以上の実習を複数の施設でおこなうことが必須となっています。これにより、知識と実践力の両方をバランスよく身につけやすく、基礎力の定着にもつながります。
学費や4年間の在学期間は必要ですが、計画的に学習を進めれば、最も確実に受験資格を取得できるルートの1つといえるでしょう。
2.福祉系短期大学・専門学校に進学するルート
短期大学や専門学校に進学し、必要な科目を履修・卒業することで、社会福祉士国家試験の受験資格を得られます。
学習期間は2〜3年と大学より短く、学費も比較的抑えられるため、できるだけ早く受験資格を取得して福祉の現場で働きたい人に適したルートです。
2025年度の制度改正により、カリキュラムには「ソーシャルワーク(旧・相談援助)」が含まれ、実習は240時間以上かつ複数施設での実施が必須となりました。
この変更により、短期間でも現場経験をしっかり積みながら、実践的に学べる環境が整っています。
ただし、大学と比べると学習範囲がやや限定されるため、卒業後も継続的に学び、最新の制度や知識を積極的に取り入れていく姿勢が求められます。
3.一般大学卒業後に養成施設を経由するルート
福祉系以外の大学を卒業した人でも、社会福祉士一般養成施設で1年間学ぶことで、国家試験の受験資格を得られます。
このルートは、すでに大学を卒業している社会人がキャリアチェンジとして福祉分野を目指す際によく選ばれています。
一般養成施設では、大学で身につけた基礎学力や学習習慣を活かしながら、福祉に必要な専門知識と実践力を短期間で集中的に学ぶことが可能です。
2025年度の制度改正により、カリキュラムには「ソーシャルワーク(旧・相談援助)」が含まれ、実習は240時間以上、かつ複数の施設での実施が必須となりました。
これにより、知識だけでなく、現場での対応力もバランスよく養える環境が整っています。
4.社会福祉士一般養成施設を利用するルート
高卒者でも、相談援助業務に4年以上(かつ540日以上)従事した実務経験があれば、社会福祉士一般養成施設に入学できます。
そこで1年間学ぶことで、社会福祉士国家試験の受験資格を得ることが可能です。
このルートの大きな特徴は、介護職や福祉現場で培った実務経験を基盤に、社会福祉士に求められる専門知識や理論を体系的に学べる点にあります。
2025年度の制度改正により、カリキュラムには「ソーシャルワーク(旧・相談援助)」が組み込まれ、実習は240時間以上、かつ複数の施設でおこなうことが必須となりました。
これにより、実務経験を理論的に補完しながら、より高度な支援スキルを身につけられる学習環境が整っています。
5.相談援助の実務経験を積むルート
特定の相談援助業務に4年以上(かつ通算540日以上)従事することで、社会福祉士国家試験の受験資格を得ることも可能です。対象となる業務には、福祉事務所での相談員、社会福祉施設での生活相談員、児童相談所や医療機関でのソーシャルワーク業務などが含まれます。ただし、すべての福祉関連業務が対象となるわけではなく、厚生労働省が定める職種や業務内容に該当している必要があります。
このルートの大きなメリットは、働きながら資格取得を目指せる点です。実務経験を通じて現場の課題や支援の流れを体感できるため、その後の学習や試験対策にも大いに役立ちます。
ただし、経験年数や勤務日数には厳密な条件があるため、事前に最新の受験資格要件をしっかり確認しておくことが重要です。
6.特定職種(5種類)での実務経験を積むルート
介護福祉士や精神保健福祉士、看護師・准看護師、作業療法士、理学療法士などが対象となります。これら厚生労働省が定める特定の職種で一定期間の実務経験を積むことで、社会福祉士国家試験の受験資格を得られます。
このルートは、すでに関連資格を取得している人がキャリアアップとして社会福祉士を目指す際におすすめです。現場で培った専門知識やスキルを活かしながら、より広範な相談援助業務に対応できるようになる点が大きなメリットです。
高卒者におすすめの社会福祉士の受験資格最短取得ルート
高卒から社会福祉士を目指す際には、自分の学歴や実務経験の有無に応じて最短で受験資格を得られるルートを選ぶことが重要です。ここでは状況別に最短ルートを整理します。
実務経験なしの場合
実務経験がない場合は、福祉系の短期大学や専門学校に進学するのが、比較的短期間で社会福祉士国家試験の受験資格を得られるルートです。
2〜3年間の学習で必要な科目を修了すれば、卒業と同時に受験資格を取得できます。
大学進学に比べて在学期間が短いため、できるだけ早く資格を取得して福祉の現場で働きたい人に適した方法といえるでしょう。
さらに、2025年度の制度改正により、カリキュラムには「ソーシャルワーク(旧・相談援助)」が組み込まれ、実習は240時間以上、かつ複数施設での実施が必須となりました。
これにより、短期間でも実践的な経験を積みながら学べる環境が整っています。
実務経験ありの場合
相談援助業務に4年以上(かつ通算540日以上)従事した実務経験がある人は、社会福祉士一般養成施設で1年間学ぶことで、社会福祉士国家試験の受験資格を得ることができます。介護現場であっても、生活相談員など相談援助に該当する業務経験が必要です。
このルートの利点は、現場で培った経験を基盤に理論や専門知識を学べるため、学習内容を実際の支援に結びつけて理解しやすい点にあります。
さらに、2025年度の制度改正により、養成課程では「ソーシャルワーク(旧・相談援助)」を中心に240時間以上の実習を複数の施設でおこなうことが必須となりました。
これにより、実務経験者が現場スキルを理論的に補強し、より高度な支援力を身につけられる環境が整っています。
働きながら学ぶ場合
働きながら社会福祉士を目指す場合、通信制大学を利用するルートが有力な選択肢となります。通信制大学で指定科目を履修し、卒業することで社会福祉士国家試験の受験資格を得られます。
通学制と比べて学費を抑えられるケースが多く、在職中でも学習を進められるため、収入を維持しながら資格取得を目指せる点が大きな利点です。ただし、自己管理が不可欠であり、計画的に学習を継続する工夫が求められます。
さらに、2025年度の制度改正により、カリキュラムには「ソーシャルワーク(旧・相談援助)」が必修として組み込まれ、実習は240時間以上、かつ複数施設での実施が義務づけられました。仕事と両立しながらこの実習要件を満たす必要があるため、事前にスケジュールを立てて時間を確保することが重要です。
学歴別最短ルート早見表
高卒から社会福祉士を目指す場合、学歴や実務経験の有無によって最短ルートは異なります。効率よく受験資格を得るには、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。以下に代表的な学歴・経験別の最短ルートを整理しました。
| 学歴・経験 | 最短ルート | 期間目安 | 特徴 |
| 高卒・実務経験なし | 福祉系短大・専門学校 | 2年~3年 | 指定科目を修了すれば、卒業と同時に受験資格を取得 |
| 高卒・実務経験あり | 一般養成施設 | 実務4年以上+1年 | 現場経験を基盤に、1年間の学習で受験資格を取得 |
| 働きながら学習 | 通信制大学 | 4年 | 収入を維持しつつ、指定科目を履修して受験資格を取得 |
| 一般大学卒業者 | 一般養成施設 | 1年 | 学士取得後、1年間の学習で受験資格を取得 |
2025年度の制度改正により、カリキュラムには「ソーシャルワーク(旧・相談援助)」が必修科目として組み込まれ、実習は240時間以上、かつ複数の施設でおこなうことが義務化されました。
これにより、どのルートを選んでも実践的な経験を積みながら学べる体制が整っています。
自分のライフスタイルやこれまでの経験に応じて最適なルートを選べば、計画的に資格取得を進めることが可能です。
社会福祉士の受験資格における「実務経験」とは?
社会福祉士国家試験の受験資格は、大学や養成施設を修了する方法だけでなく、「実務経験」によって得ることもできます。ただし、対象となる業務や施設は厚生労働省によって明確に定められており、すべての福祉関連の仕事が認められるわけではありません。
ここでは、実務経験が認められるケースと認められないケース、さらに介護士やヘルパーとして働く人が注意すべきポイントを整理します。
実務経験が認められるケース
福祉事務所や社会福祉施設、児童相談所、障害者支援施設などでおこなうソーシャルワーク(旧・相談援助業務)は、社会福祉士国家試験の受験資格要件として認められています。
これらの職務で4年以上、かつ通算540日以上の経験を積むことで、社会福祉士一般養成施設や短期養成施設に入学する資格を得られます。その後、1年間の課程を修了すれば、国家試験の受験資格が与えられる仕組みです。
一方、身体介護が中心の介護職や一般的な事務業務は対象外です。自分の業務内容が受験資格に含まれるかどうかは、事前に確認しておくことが欠かせません。
実務経験が認められないケース
身体介護や清掃、調理補助といった直接援助のみをおこなう業務は、社会福祉士国家試験の受験資格要件として認められません。利用者支援に関わっていても、ソーシャルワーク(旧・相談援助)の要素が含まれていなければ対象外となります。
たとえば、介護施設で介護職員として入浴介助や排せつ介助など、身体介護のみを担当している場合です。この場合、勤務先が福祉施設であっても受験資格の実務要件は満たされません。
そのため、福祉施設で働いている人であっても、自身の職務内容が資格要件に含まれるかどうかを事前に確認しておくことが重要です。
介護士・ヘルパー経験者の注意すべき点
介護士や訪問ヘルパーとして働いていても、業務内容が介助中心であれば、社会福祉士国家試験の受験資格に必要な実務経験としては認められません。ソーシャルワーク(旧・相談援助業務)として扱われるためには、ケアマネジメントや利用者・家族への相談対応など、厚生労働省が定める「相談援助業務」に該当する職務である必要があります。
そのため、介護職からキャリアを積んで社会福祉士を目指す場合は、生活相談員やケアマネジャー(介護支援専門員)といった相談援助業務を含む役職に就くことが重要です。
高卒から社会福祉士を目指すメリット
高卒から社会福祉士を目指すことで、資格取得後には多くのメリットが得られます。収入やキャリアの安定、社会的評価の向上に加え、仕事のやりがいにも直結する点が大きな魅力です。以下では、代表的なメリットを具体的に整理します。
安定した収入とキャリアを得られるチャンスが広がる
社会福祉士の資格を取得すると、求人の選択肢が広がり、キャリアの安定性も高まります。福祉の現場では資格保持者が優遇される傾向があり、昇進や役職登用の条件として資格が求められることも少なくありません。
たとえば、介護職として現場からキャリアを始めた場合でも、社会福祉士の資格を持つことで生活相談員などの相談援助業務に携わる可能性が高まり、キャリアの幅を大きく広げられます。
さらに、厚生労働省の調査によると、社会福祉士の平均月収は介護職員よりも高く(令和6年度調査で数万円程度の差)、処遇改善にもつながりやすいとされています。
学歴のハンデを補い社会的評価を高められる
高卒という学歴に不安を感じている方でも、国家資格である社会福祉士を取得すれば専門性を証明でき、十分に評価されやすくなります。資格は専門知識と技能を客観的に示すものであり、学歴に左右されず強みを発揮できる要素です。
特に福祉業界では「実務能力」と「資格」が重視されるため、学歴のハンデを補い、信頼を得る手段として大きな効果を持ちます。実際、社会福祉士の資格を採用条件や昇進要件に設定している求人も多く、履歴書や面接での強力なアピール材料になります。
介護職・福祉職からのキャリアアップにつながる
介護や支援の現場で働く方にとって、社会福祉士の資格はキャリアアップを実現するための大切なステップです。
資格を取得すれば、日常的なケア業務にとどまらず、相談支援や地域との連携や行政との協働など、より専門性が高く責任ある業務に携わる機会が増えます。
その結果、仕事の幅が広がり、将来的には生活相談員や地域包括支援センターの職員、施設の管理職といった役職やリーダー職を目指す道も開かれます。
社会福祉士の資格取得は、現場経験を土台にキャリアの選択肢を広げる有効な手段といえるでしょう。
専門資格を得て自信とやりがいを持てる
社会福祉士は国家資格であり、その取得過程では福祉制度・心理学・医療・法律・ソーシャルワーク技術など幅広い知識を学ぶとともに、実習を通じて実践力を身につけられます。
試験に合格することは、長期間の努力が成果として形になる達成感につながり、大きな自信を得る契機にもなります。
資格を持つことで、利用者や家族から専門家として信頼されやすくなり、相談援助や支援計画の策定や地域包括ケアへの参画など、責任ある業務に携わることが可能です。
その結果、「専門職として社会に貢献している」という実感を持ちながら働ける点が、大きな魅力といえるでしょう。
長期的に安定した職場で働ける可能性が高まる
福祉分野は少子高齢化が進む日本社会において、今後も需要が高まり続ける分野です。
社会福祉士の資格を持つことで病院や行政機関、社会福祉施設、地域包括支援センターなど、幅広い職場で活躍できる可能性が広がります。
厚生労働省の調査でも、福祉人材の不足は深刻な課題とされており、有資格者の需要は今後も安定的に続くと見込まれています。
そのため、社会福祉士の資格は長期的に仕事を続けるうえで大きな強みとなり、安定したキャリア形成に直結するのです。
高卒から社会福祉士を目指すデメリット
高卒から社会福祉士を目指す道には多くのメリットがありますが、その一方で乗り越えるべき課題も存在します。
ただし、これらのデメリットもあらかじめ理解し、適切な対策を取れば大きな障害にはなりません。以下で詳しく解説します。
基礎学力や専門知識の習得が必要になる
社会福祉士国家試験では福祉制度や心理学や法律、医学、社会学、現代社会など、20科目以上にわたる幅広い分野が出題されます。
そのため、高卒から挑戦する場合は、まず基礎学力をしっかり固めることが欠かせません。
特に法律や制度の分野は専門用語が多く、独学では理解が難しいこともあるため、わかりやすいテキストや通信講座を活用すると効果的です。
さらに、過去問題集を繰り返し解くことで出題傾向をつかみやすくなります。
計画的に学習を進めて少しずつ知識を積み重ねていけば、試験へのハードルを下げ、合格の可能性を高めることができます。
学費や通信講座など費用の負担が大きい
大学や専門学校に進学する場合、学費は進学先によって大きく異なります。国公立では数十万〜100万円台、私立では数百万円に及ぶこともあります。通信講座を利用する場合でも、受講料や教材費といった費用は必要です。
ただし、こうした負担を軽減できる制度も整っています。
| 制度名 | 対象 | 給付内容 | 備考 |
| 教育訓練給付金制度 | 厚生労働省が指定する講座を受講した場合 | 受講料の20%(上限あり) | 一般的な教育訓練講座が対象 |
| 専門実践教育訓練給付金 | 専門性の高い指定講座を受講した場合 | 受講料の最大50% | より専門的・実践的な講座が対象 |
上記に加えて、奨学金制度を活用すれば、在学中の学費を分割して負担することも可能です。
資格取得までに年数がかかる
最短ルートを選んだとしても、社会福祉士の受験資格を得るには数年単位の学習期間が必要です。
| ルート | 必要期間 | 条件・特徴 |
| 福祉系大学 | 4年 | 卒業と同時に受験資格を取得 |
| 短大・専門学校 | 2~3年 | 指定科目を修了すれば受験資格を取得 |
| 実務経験+一般養成施設 | 実務4年以上+1年 | 相談援助業務に4年以上(かつ540日以上)従事後、一般養成施設で1年間学習 |
| 一般大学卒業+一般養成施設 | 1年 | 大学卒業後、一般養成施設で1年間学習 |
短期間での資格取得を希望する方にとっては長く感じられるかもしれませんが、いずれのルートでも計画的に学習を積み重ねていけば、着実に資格取得へと近づけます。
働きながら学ぶ場合は両立が難しい
社会人として働きながら学習を続ける場合、最大の課題は勉強時間の確保です。残業や家庭の事情によって、計画どおりに学習を進められないことも少なくありません。
こうした状況では、通勤時間や休憩時間に利用できるスマートフォンアプリや音声教材、自分のペースで進められる通信講座を活用するのが効果的です。
また、週末にまとまった時間を確保する、あるいは毎日30分だけでも継続するなど、自分の生活リズムに合わせた工夫も大切です。
効率的な学習方法を取り入れることで、仕事と学習の両立を無理なく続けやすくなります。
途中で挫折してしまうリスクがある
社会福祉士を目指す学習は長期にわたるため、途中でモチベーションが下がるリスクがあります。ですが、同じ目標を持つ仲間と交流したり(SNSの勉強コミュニティや通信講座の受講生同士など)、合格までの中間目標を細かく設定したりすることで、学習を継続しやすくなります。
さらに、過去問を1年分解き終える、模試で一定の得点を取るといった小さな達成感を積み重ねることも効果的です。こうした工夫を取り入れることで、挫折を防ぎ、最後まで学習を続けやすくなります。
よくある質問
最後によくある質問について紹介します。
高校生でも社会福祉士の資格は取れますか?
高校を卒業した直後に、すぐに社会福祉士国家試験を受けることはできません。受験資格を得るには、福祉系大学(4年)、短期大学や専門学校(2〜3年)、あるいは相談援助業務に4年以上(かつ540日以上)従事したうえで養成施設に1年間通うなど、定められたルートを経る必要があります。
社会福祉士は通信講座で取得できますか?
社会福祉士そのものを通信講座だけで取得することはできません。国家試験の受験資格を得るためには、大学や養成施設での履修や、一定の実務経験が必要だからです。
ただし、通信制大学や通信教育課程を活用して必要科目を履修・卒業すれば、受験資格を得ることは可能です。
まとめ:高卒から社会福祉士を目指すあなたへ
高卒から社会福祉士を目指す道は決して平坦ではありませんが、制度上には明確なルートが用意されており、計画的に努力を重ねれば十分に達成可能です。
一方で、学習や費用の負担、資格取得までにかかる時間といった課題は避けられません。しかし、通信制大学や柔軟な学習スタイルを取り入れたり、教育訓練給付金や奨学金などの支援制度を活用したりすることで、負担を軽減することは可能です。
大切なのは、自分に合ったルートを早めに見極め、計画的に学習を継続することです。行動を起こすことで、将来の可能性を広げる確かな一歩となるでしょう。

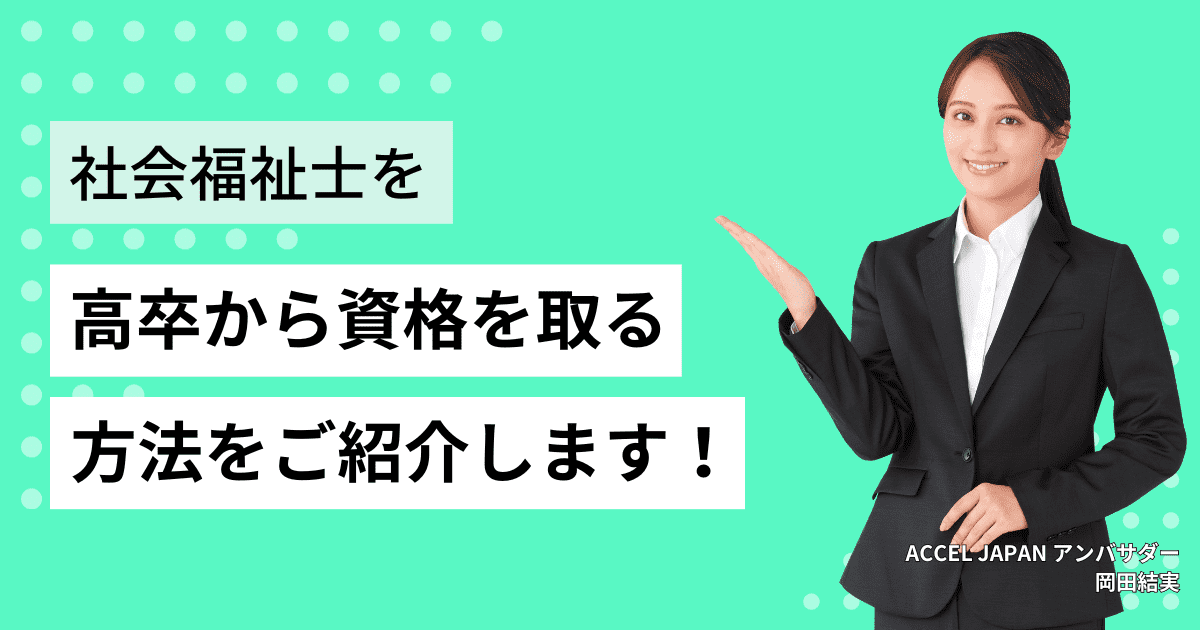


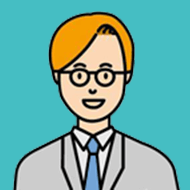
 児童福祉司が国家資格に!?厚生労働省が検討
児童福祉司が国家資格に!?厚生労働省が検討
 児童養護福祉士資格が新設!3月より認定講座開講
児童養護福祉士資格が新設!3月より認定講座開講











 オンライン心理学教室4月開講! 実践に強い資格が取れるカウンセラー育成スクールが5月にスタート!
オンライン心理学教室4月開講! 実践に強い資格が取れるカウンセラー育成スクールが5月にスタート!
 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
 メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
 「日本語教師」の資格取得を目指すなら、38年超の実績を有するアークアカデミーで!
「日本語教師」の資格取得を目指すなら、38年超の実績を有するアークアカデミーで!
 心理学で、自分と誰かの人生を整える。「心」の専門家として歩み始める第一歩
心理学で、自分と誰かの人生を整える。「心」の専門家として歩み始める第一歩





