社会福祉士が目指せるおすすめスクール
社会福祉士国家試験とは?
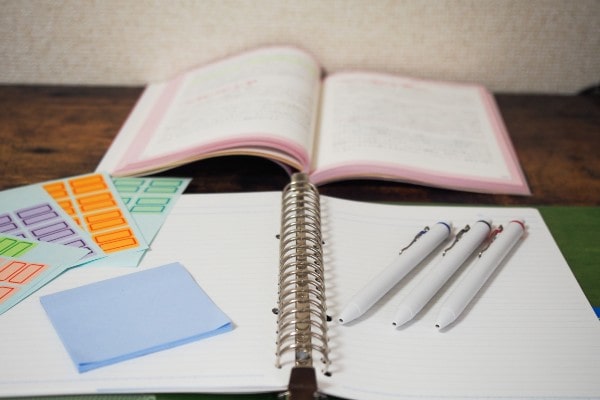
社会福祉士国家試験は、福祉分野で専門職として活動するために不可欠な国家資格を取得する試験です。受験する意義は、専門的な知識と技能を証明し、現場での信頼を高めながらキャリアの幅を広げられる点にあります。
特に高齢化が進む日本社会では、社会福祉士の需要が年々増加しています。厚生労働省の統計によれば、登録者数は累計25万人を超えており、それに伴って福祉の現場での活躍の場も一層広がっているのです。
この試験の大きな特徴は法律や医学、心理学、社会学など幅広い分野から出題されることです。「共通科目11」「専門科目8」の計19科目で構成され、制度改正や社会状況を反映した問題が出題されます。
社会福祉士国家試験の合格率を高める勉強法7選
ここでは、社会福祉士国家試験の対策として、予備校や通信講座で推奨され、さらに多くの合格者が実際に取り入れている代表的な勉強法を7つ紹介します。
1.社会福祉士試験日から逆算して計画的なスケジュールを作成する
合格に必要な学習時間は、受験者の基礎知識や学習環境によって異なりますが、予備校や通信講座ではおおむね300〜500時間が目安とされています。
限られた時間を有効に使うためには、試験日から逆算して学習計画を立てることが効果的です。ゴールを明確に設定すれば、日々の学習に迷いが生じにくく、進捗の把握もしやすくなります。
具体的な流れとしては、まず試験日までの残り日数を確認し、学習期間を大きく3つに分けます。初期は基礎固め、中期は過去問演習と苦手分野の克服、終盤は模試と総復習に充てるのが一般的です。
さらに1週間単位、1日単位まで計画を細分化すれば、多少の遅れがあっても柔軟に調整できます。
2.社会福祉士国家試験の過去問を徹底活用する
社会福祉士試験の合格率を高めるには、過去問の活用が非常に効果的です。過去問は出題傾向や頻出分野を把握するのに最適な教材であり、効率よく学習範囲を絞り込めます。
参考書を漫然と読み進めるよりも、過去問演習を繰り返すことで、合格に直結する知識を効率的に身につけられるでしょう。
予備校や合格者の体験談でも、直近5年分ほどの過去問を繰り返し解く方法が推奨されています。1周目は理解が不十分でも問題ありませんが、解説を丁寧に読み込み、間違えた問題には付箋を貼るなどして弱点を「見える化」すると効果的です。
2周目は苦手分野を重点的に解き直し、3周目には知識の定着度を確認すると、着実に得点力を伸ばせます。
3.インプットとアウトプットを繰り返して知識を定着させる
試験勉強では、知識を覚える「インプット」と、問題を解いて使う「アウトプット」をバランスよく繰り返すことが、学習効率を高めるポイントです。インプットだけでは知識が曖昧になりやすく、アウトプットだけでは基礎理解が不足する恐れがあります。
たとえば、新しい単元を学んだら、その日のうちに小テストや一問一答形式でアウトプットすると効果的です。
さらに翌日や数日後に解き直せば、記憶が定着しやすくなります。また、参考書を読みながら要点を自分でまとめたり、図表に整理したりするのもアウトプットの一つであり、理解を深めるのに有効です。
4.苦手分野を重点的に復習し全科目対策を行う
社会福祉士国家試験の合格基準は、総得点の60%以上を取ることに加え、各科目群で1点以上を得点することが条件です。
つまり、特定の科目群を全く学習せずに0点となれば、不合格になる可能性があります。そのため、全科目をまんべんなく学習しつつ、弱点分野を重点的に復習することが欠かせません。
具体的には、過去問や模試で正答率が低かった科目を一覧化し、復習スケジュールに組み込むのが効果的です。
たとえば「社会保障制度」や「心理学概論」など苦手意識のある科目は、短時間でも毎日触れることで知識の定着につながります。さらに、苦手科目を得意科目の直後に学習すると、心理的な負担を軽減しながら継続しやすくなります。
5.模擬試験を受けて本番に備える
模擬試験は、本番に近い環境で実力を測る有効な方法の一つです。受験直前に模試を受ければ、得点の確認だけでなく、時間配分や集中力の維持方法も身につけられます。
模試を受けた後は、結果に一喜一憂するのではなく、間違えた問題や時間の使い方を分析することが大切です。たとえば、序盤に時間をかけすぎて後半を焦って解いた場合は、次回以降の解答順を工夫する必要があります。
また、模試の結果を学習計画に反映させ、苦手分野を直前期に集中的に復習すれば、効率よく得点力を高められるでしょう。さらに、模試を一度だけでなく複数回受験すると、本番までに改善の成果を実感しやすくなります。
6.スキマ時間を有効活用して学習時間を増やす
忙しい社会人にとって、まとまった時間を確保するのは難しいため、スキマ時間を活用することが学習時間を増やす鍵となります。
通勤や休憩の合間を上手に使えば、多くの人が1日あたり30分〜1時間ほどを勉強に充てられます。
具体的には、スマートフォンアプリで一問一答に取り組む、音声教材を聞き流す、暗記カードを持ち歩いて復習するなどの方法が効果的です。
さらに、学習ログをアプリや手帳に記録して「これだけ学習できた」と可視化すると、達成感を得られ、モチベーションの維持にもつながります。
7.通信講座や対策講座を活用して効率を上げる
独学では情報収集や教材選びに時間がかかることがありますが、通信講座や対策講座を利用すれば学習効率を高めやすくなります。
専門家が出題傾向を分析してカリキュラムを組んでいるため、学習の優先順位をつけやすく、効率的に合格を目指せるでしょう。
たとえば、2025年度の制度改正(実習時間の240時間化や新科目「地域福祉と包括支援体制」の追加など)にも対応した最新のテキストや動画解説、添削課題を利用すれば、独学では得にくい情報や指導を受けられます。
さらに、質問サポートのある講座なら疑問点をすぐに解決でき、独学で感じやすい不安を軽減できる点も大きなメリットです。
社会福祉士国家試験の勉強を独学でするメリット・デメリット
社会福祉士国家試験は、独学でも合格できる資格です。ただし、独学を選ぶ際にはメリットとデメリットを正しく理解し、自分の状況に合った学習方法を見極めることが重要です。ここでは、独学で試験勉強を進める場合のメリットとデメリットを紹介します。
独学でする3つのメリット
社会福祉士国家試験を独学で勉強するメリットを3つ紹介します。
費用を大幅に抑えられる
独学の大きなメリットは、受験準備にかかる費用を大幅に抑えられる点です。
通信講座を利用すると7〜10万円前後、専門学校や養成課程に通うと20〜40万円程度かかるのが一般的ですが、独学なら必要最低限の参考書や過去問題集を購入する程度で済みます。たとえば中央法規や成美堂出版の教材をそろえても、1〜2万円程度に収まるケースが多いでしょう。
その分、経済的な負担を軽減しながら学習を継続でき、合格後に必要となる資格更新や研修の費用に回すことも可能です。
費用を抑えつつ、自分に合った効率的な学習法を確立できれば、費用対効果の高い方法として資格取得を実現できます。
自分のペースで学習できる
独学の強みは、時間や場所に縛られず、自分のライフスタイルに合わせて学習を進められる点です。
特に仕事や家庭と両立しながら学ぶ社会人にとって、自由度の高さは大きなメリットです。
たとえば、平日は通勤時間にアプリで学習し、休日はまとまった時間を使って過去問演習を進めるなど、自分に合ったスケジュールを組めます。
誰かのペースに合わせる必要がないため、自分にとって効率的な学習スタイルを作りやすく、途中で学習が滞った場合も柔軟に調整できます。ただし、その反面、強い自己管理力が求められる点には注意が必要です。
自己管理能力・情報収集力が身につく
独学では、教材の選択からスケジュール管理までを自分で担うため、自然と自己管理能力や情報収集力が鍛えられます。これらのスキルは資格取得後にも仕事で活かしやすい強みとなるでしょう。
たとえば、法改正の情報を厚生労働省の公式サイトで定期的に確認する習慣を持てば、実務に直結する最新知識を得られます。また、計画的に学習を進めた経験は、福祉現場での業務管理や利用者支援計画の立案にも応用可能です。
独学で培った自己管理力や情報収集力は、試験対策にとどまらず、将来のキャリア形成にも役立つ実践的なスキルとなります。
独学でする3つのデメリット
続いて、社会福祉士国家試験を独学で勉強するデメリットを3つ紹介します。
スケジュール管理が難しい
独学は自由度が高い反面、計画的に進めないと学習が中断したり遅れが生じたりする点がデメリットです。特に働きながら学ぶ場合、仕事の繁忙期や家庭の事情で勉強が後回しになることも少なくありません。
この課題を克服するには、試験日から逆算して学習計画を立て、1日ごとの目標を小さく設定するのが有効です。さらに、スマートフォンアプリや手帳に学習記録を残せば進捗を可視化でき、達成感を得ながらモチベーションを維持しやすくなります。
最新情報や改正内容を入手しづらい
社会福祉士試験は制度改正や法律の変更を反映して出題されるため、古い教材だけで学習を続けると不利になる恐れがあります。
独学では最新情報を自分で収集する必要があり、その分、時間や労力がかかる点が負担になりやすいのも事実です。
この問題を避けるには、厚生労働省や社会福祉振興・試験センターの公式発表を定期的に確認し、必ず受験年度に対応した参考書や過去問を使用することが欠かせません。
一次情報と合わせて参照することで、独学でも最新の出題傾向を反映した学習が可能になります。
疑問点をすぐに解決できない
独学では、理解できない部分が出ても質問できる相手がいないため、学習が停滞するリスクがあります。特に法律や統計の問題は専門用語が多く、一人で調べるのに時間がかかりがちです。
これを防ぐには、複数の教材を併用して説明を比較したり、オンライン掲示板やSNSで情報交換をしたりする方法があります。近年ではAI学習ツールや通信教育の単科受講を利用し、必要なときだけサポートを受ける選択肢もあります。
疑問を放置せず、解決する工夫を取り入れることで、独学の弱点を補えるでしょう。
社会福祉士国家試験の勉強を独学が向いている人・向いていない人
社会福祉士国家試験は独学でも合格できますが、人によって向き不向きがあります。自分の性格や生活環境に合わせて学習方法を選ぶことで、効率的に勉強を進めやすくなります。
独学が向いているのは、自己管理が得意で学習計画を立てて実行できるタイプです。毎日の勉強を習慣化できる人や、スケジュールを柔軟に調整できる人は成果を出しやすい傾向があります。
一方、独学が不向きなのは、学習のペースを自己管理するのが苦手なタイプです。計画を立てても継続が難しい人や、一人で勉強していると不安を感じやすい人は、通信講座や対策講座を利用した方が効果的です。
社会福祉士国家試験の主な特徴
社会福祉士国家試験には、他の資格試験にはない独特の特徴があります。ここでは、社会福祉士国家試験の特徴について詳しく紹介します。
幅広い出題範囲(全19科目)
社会福祉士試験は法律、心理学、医学、社会学など福祉にかかわる幅広い分野から出題されます。
共通科目11科目と専門科目8科目の計19科目に及ぶ学習範囲は受験生にとって大きな負担ですが、全体像を把握し、優先順位をつけることが効率的に得点を伸ばすための鍵となります。
具体的には、「社会保障」「権利擁護」「ソーシャルワーク(旧:相談援助)」といった頻出科目を重点的に学習しつつ、出題数の少ない科目も基礎だけは押さえておくことが大切です。
得点配分を理解したうえで学習計画を立てれば、合格基準点を満たしやすくなります。
出題形式と試験時間の配分
社会福祉士国家試験はマークシート方式で実施され、午前と午後にわかれて長時間行われます。出題数は150問(午前75問・午後75問)で、各150分、合計300分の試験時間が設定されています。
そのため、正確に解答する力だけでなく、時間内に全問を解き切るための配分力も重要です。
学習段階から制限時間を意識し、過去問を本番と同じ条件で解く練習を重ねておくと、当日も落ち着いて取り組めます。
試験形式に慣れておくことは、知識の確認だけでなく実践力を養ううえでも有効です。
合格基準と科目別最低得点制度
合格基準は、総得点の60%以上を満たすことに加え、各科目群で1点以上を得点することが条件です。
これは、特定の科目群が極端に弱い場合は不合格になる仕組みであり、複数分野をまんべんなく学習する必要があることを示しています。
そのため、得意科目だけで突破を狙うのは危険です。苦手分野も最低限は得点できるようにし、全科目をバランスよく学習することが不可欠です。
問題の多様性と事例問題の比率
社会福祉士国家試験では、暗記型の問題だけでなく、全体の3〜4割が事例をもとに解答する形式で構成されています。
これにより、知識の理解度や応用力が試されます。単に用語を覚えるだけでなく、実際の相談援助や福祉現場をイメージしながら学習することが効果的です。
事例問題への対策としては、過去問を繰り返し解くだけでなく、テキストの解説を実務に置き換えて考える習慣を持つと理解が深まります。
さらに、厚生労働省が発表する制度改正や最新の福祉施策を踏まえて学習すれば、事例問題への対応力を一層高められます。
福祉全体を俯瞰できる内容と実務との関連性
社会福祉士国家試験は、単なる暗記ではなく、福祉全体の知識を体系的に理解し、実務に応用できるかを確認する試験です。
出題内容には福祉制度の仕組みや相談援助の過程などが含まれ、現場での実務と密接にかかわっています。そのため、受験者の判断力や応用力を評価することが狙いとなっています。
たとえば、利用者支援における相談援助の進め方や、制度利用の具体的な流れに関する設問は、現場の業務をそのまま反映したものです。こうした学習を通じて、資格取得後に求められる実践力を磨ける点も、この試験ならではの特徴といえるでしょう。
社会福祉士国家試験の勉強に役立つ参考書やツールの選び方
社会福祉士国家試験に合格するためには、正しい教材選びが学習効率を大きく左右します。ここでは、勉強に役立つ参考書やツールの選び方を紹介します。
テキスト・問題集の選び方
学習の基盤となるテキストは、必ず最新年度版を選ぶのが望ましいです。社会福祉士国家試験は法改正や制度変更が反映されるため、古いテキストでは内容が最新に対応していない可能性があります。
代表的な教材としては、中央法規やみらいのテキストシリーズがあり、体系的に整理されていて初学者にも理解しやすい構成です。
問題集は必ず過去問に対応したものを選びましょう。特に直近5年分を収録したものは、出題傾向を把握するのに有効です。
また、解説が詳しいかどうかも重要なポイントです。理解できなかった問題をその場で確認・整理できれば、知識の定着につながります。
短期集中向け教材の選び方
限られた時間で効率的に合格を目指すには、要点を凝縮した教材が役立ちます。
たとえば「一問一答形式」の問題集や「要点まとめ本」は短時間で繰り返し学習できるため、忙しい社会人をはじめ効率よく学びたい受験者におすすめです。
さらに、カラー図解やチャート形式で整理された教材は視覚的に理解しやすく、記憶の定着を促す工夫も施されています。
学習時間が限られているときこそ、重点を絞った教材を選ぶことで、出題範囲の広さに振り回されず得点力を伸ばしやすいでしょう。
アプリ・音声教材の選び方
近年、受験生の間ではスマートフォンアプリや音声教材を活用する学習法が広がっています。
アプリは一問一答や模擬試験形式に対応しており、移動中や休憩時間のわずかな時間でも学習できるのが利点です。中でも学習記録が残るタイプは、進捗の把握や計画的な学習に役立ちます。
一方、音声教材は目を使わずに学習できるため、家事や通勤中でも知識を取り入れられます。繰り返し耳にすることで記憶に定着しやすく、特に暗記科目で効果を発揮しやすい方法です。
このように、アプリや音声教材を補助的に取り入れることで、日常生活の中に自然と学習時間を組みやすくなります。
社会福祉士の勉強方法に関するよくある質問
最後に社会福祉士の勉強方法に関するよくある質問を紹介します。
社会福祉士国家試験の過去問は何年分やるべきですか?
社会福祉士国家試験の過去問は、直近5年分を重点的に取り組むのがおすすめです。出題傾向や頻出分野を把握するには、複数年度を通して分析することが効果的だからです。
さらに余裕があれば10年分まで解いておくと、出題形式や内容の変化も確認でき、より安心して本番に臨めます。
社会福祉士を独学で勉強するにはどれくらいの期間がかかりますか?
独学の場合、学習期間は基礎知識や生活環境によって変わりますが、多くの合格者は半年〜1年を目安に勉強しています。
必要な学習時間はおおよそ300〜500時間とされており、毎日2時間勉強すれば半年ほどで到達可能です。ただし、仕事や家庭と両立する社会人は学習時間が限られるため、1年前から計画的に準備を始めると安心です。
社会福祉士は働きながら勉強できますか?
社会福祉士試験は働きながらでも十分に合格を目指せます。ただし、日々の勉強時間を確保しにくいのが現実です。
そのため、通勤時間や休憩時間といったスキマ時間の活用、学習アプリの利用、週末の集中学習など効率的な工夫を取り入れることが、合格への近道となります。
まとめ:社会福祉士の勉強方法を理解して国家試験を一発合格しよう
社会福祉士国家試験は、出題範囲の広さや制度改正の影響もあり、難易度が高い国家資格の一つです。しかし、効率的な学習法を実践すれば、独学でも十分に合格を目指せます。
合格率を高めるには、試験日から逆算して学習計画を立て、過去問演習を中心に知識を定着させることが欠かせません。さらに、苦手分野の克服や模試での実践練習、スキマ時間の活用を組み合わせることで、安定した得点力を養いやすくなります。
加えて、自分に合った教材や学習ツールを選ぶことも重要です。独学に不安がある場合や、より効率を高めたい場合には、通信講座や対策講座を取り入れるのも有効な方法です。

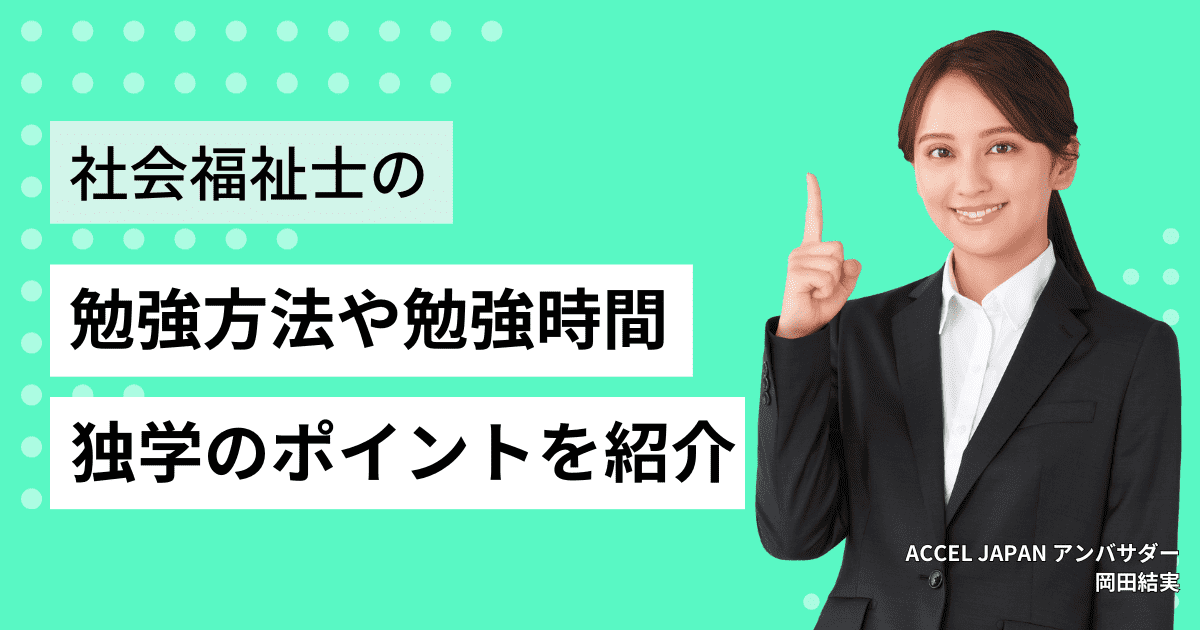


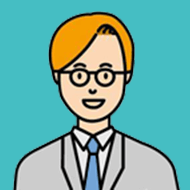
 児童福祉司が国家資格に!?厚生労働省が検討
児童福祉司が国家資格に!?厚生労働省が検討
 児童養護福祉士資格が新設!3月より認定講座開講
児童養護福祉士資格が新設!3月より認定講座開講










 オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!
オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!
 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
 メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
 心理学で、自分と誰かの人生を整える。「心」の専門家として歩み始める第一歩
心理学で、自分と誰かの人生を整える。「心」の専門家として歩み始める第一歩
 【期間限定:3/14まで】学習スタート応援キャンペーン実施中!
【期間限定:3/14まで】学習スタート応援キャンペーン実施中!





