社会福祉士が目指せるおすすめスクール
社会福祉士とは?資格の全体像を解説

社会福祉士は、福祉分野の専門職として、困難を抱える人々の生活を支える国家資格です。社会福祉士および介護福祉士法に基づき、相談援助の専門家として法的に位置づけられています。
- 行政機関(福祉事務所)
- 医療機関(医療ソーシャルワーカー)
- 地域包括支援センター、福祉施設など
多様な現場で活躍しています。こうした配置の広がりは、専門性の向上につながるとともに、資格保有者が社会的信頼を得てキャリアを築く大きな後押しとなっています。
社会福祉士の役割と国家資格としての意義
社会福祉士の役割は生活困窮者や高齢者や障害者、児童、家族など、社会的支援を必要とする人々に対して適切な相談援助を行うことです。
- 生活保護制度の申請支援
- 介護や医療との連携
- 障害福祉サービスの利用調整
- 児童福祉や地域包括支援センターでの相談対応
- 精神保健分野での支援など
幅広い課題に取り組みます。
この資格が国家資格として制度化されている背景には、社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、相談援助に必要な知識・技術・倫理を備えた専門職を育成し、その専門性を法的に担保する狙いがあります。
そのため、社会福祉士は単なる支援者ではありません。法律や制度を正しく理解し、成年後見制度の活用や虐待防止支援などを通じて、利用者の権利を守りながら生活改善を支える専門職として位置づけられています。
「受験資格」が必要な背景と目的
社会福祉士に受験資格が設けられているのは、相談援助の専門職として必要な知識と実務経験を確実に担保するためです。
もし誰でも受験できる制度であれば、専門教育や現場経験のない人が資格を取得し、利用者の生活や権利に深刻な影響を及ぼす危険性があります。
社会福祉士の受験資格をルート別に紹介
社会福祉士の受験資格には、学歴や職歴に応じて複数の取得ルートがあります。ここでは代表的な3つのルートを取り上げ、それぞれの特徴を整理します。
一般養成施設ルート:一般大学卒などの社会人向けルート
一般大学や短期大学を卒業した人が社会福祉士を目指す際、代表的な方法の一つが「一般養成施設ルート」です。指定された一般養成施設に1年以上通い、必要な科目を修了することで国家試験の受験資格を得られます。
このルートの強みは、福祉系学部を卒業していなくても挑戦できる点にあります。特に社会人経験を積んだ後にキャリアチェンジを考える人にとって、幅広く利用されているルートです。
一方で、学費や通学時間の確保が課題となるため、厚生労働省が指定する夜間課程や通信制課程を活用し、自分に合った柔軟な学習方法を選ぶことが重要です。
福祉系大学等ルート:指定科目を履修すればそのまま受験可能
福祉系の大学・短期大学・専門学校を卒業する場合、在学中に指定科目を履修すれば、卒業と同時に社会福祉士国家試験の受験資格を得られます。このため、数あるルートの中でも最短で資格取得につながる方法といえます。
福祉分野に早い段階から進むと決めている学生にとっては、体系的に学びながら受験資格を得られる点が大きなメリットです。さらに、多くの大学では国家試験対策講座や実習支援が整備されており、資格取得までを一貫してサポートする環境が整っています。
ただし、福祉系以外の学部や学科を選んだ場合にはこのルートを利用できないため、進学時点での専攻選択がその後の受験資格の有無を左右します。
「短期養成施設ルート:必要科目+短期養成+実務経験
福祉系の学部を卒業した人や、精神保健福祉士などの関連資格を持つ人が短期間で受験資格を得られるのが「短期養成施設ルート」です。このルートは、大学や専門学校で社会福祉士国家試験に必要な科目の一部をすでに修了していることが前提となり、さらに相談援助業務で一定期間(例:1年以上)の実務経験が必要です。
その上で、短期養成施設に通い、6か月から1年程度(施設により異なる)のカリキュラムを履修すれば、国家試験の受験資格を取得できます。現場経験と専門的な学びを組み合わせることで、実務で培ったスキルを資格取得に直接つなげられるのが大きな特徴です。
【条件別】社会福祉士受験資格の最短ルート一覧
社会福祉士を目指す際、最短ルートは学歴や保有資格によって大きく異なります。ここでは代表的なケースごとに最短ルートを整理し、余分な時間や費用をかけずに資格取得を目指すための道筋を紹介します。
福祉系4年制大学卒業(または卒業見込み)の場合
福祉系大学で指定科目を履修して卒業すれば、追加の学習や実務経験を経ずに、そのまま社会福祉士国家試験の受験資格を得られます。このルートは、最も基本的かつ代表的な方法であり、学生生活の中で必要な知識と実習を体系的に習得できる点が大きな強みです。
特に進路を早い段階で定めている人にとっては、卒業と同時に受験資格を取得できるため、追加学習なしで試験に挑める明確な道筋となります。
ただし、指定科目の履修が不足している場合は追加履修が必要になるため、大学ごとのカリキュラムを確認し、在学中から計画的に履修を進めておくことが重要です。
福祉系短期大学・専門学校卒業の場合
福祉系短期大学や専門学校を卒業した場合、カリキュラムによっては卒業と同時に社会福祉士国家試験の受験資格を得られることもあります。
ただし多くの場合は、卒業後に相談援助業務で一定期間(例:1〜数年)の実務経験を積むことが条件となるため、現場経験を前提にキャリアを設計する必要があります。
このルートの利点は、短大や専門学校を卒業した時点で早く社会に出て働きながら資格取得を目指せる点です。
一方で、必要な実務経験の年数は課程や就職先によって異なるため、社会福祉士受験資格に該当する相談援助業務に従事できる職場を選ぶことが重要となります。
一般大学(非福祉系)卒業の場合
福祉系以外の大学を卒業した人は、一般養成施設に1年以上通学するルートが基本です。この課程を修了すれば、社会福祉士国家試験の受験資格を得られるため、非福祉系出身者でも資格取得に挑戦できます。
特に社会人経験を経てから福祉職へ転じたい人にとっては、このルートが広く利用されています。
ただし、学費(年間数十万円〜100万円程度)や通学時間の確保が課題となることが多いため、通信制や夜間課程を設けている養成施設を選べば、働きながら学ぶことも可能です。
高卒・中卒+相談援助実務経験がある場合
高卒や中卒の人でも、福祉分野での相談援助業務を一定期間経験すれば、社会福祉士国家試験の受験資格を得られます。
- 高卒者:相談援助業務で通算5年以上の実務経験
- 中卒者:相談援助業務で通算8年以上の実務経験
また、介護福祉士や児童指導員など、厚生労働省が定める特定職種で5年以上の実務経験を積む場合も対象となります。
このルートの強みは、学歴に関わらず現場経験を重ねることで資格取得を目指せる点です。
一方で、必要な年数が長いため、対象となる職種に継続して従事するなど、計画的にキャリアを積むことが不可欠です。
他資格保有者(介護福祉士・保育士・看護師など)の場合
すでに介護福祉士や保育士、看護師などの国家資格を持っている場合は、「短期養成施設ルート」を利用して短期間で社会福祉士国家試験の受験資格を得られる場合があります。
これらの資格保持者は、修得済みの専門知識や実務経験が評価され、必要な指定科目や実務経験の一部が免除されます。そのうえで、短期養成施設に通い、6か月〜1年程度のカリキュラムを修了すれば受験資格を取得可能です。
この仕組みの特徴は、介護・医療・児童福祉といった分野で培ったスキルを、社会福祉士としての専門性に結び付けられる点にあります。結果として、多職種連携の場で果たせる役割が広がり、キャリアの幅を一層広げやすいルートとなっています。
働きながら資格取得を目指す社会人の場合
社会人が働きながら社会福祉士を目指す場合は、通信制や夜間課程を設けている一般養成施設を利用する方法が広く選ばれています。これにより、仕事を続けながら学習できるため、収入を維持しつつ資格取得に挑戦することが可能です。
ただし、学習時間の確保やモチベーションの維持は大きな課題となるため、計画的な学習スケジュールを立てることが欠かせません。特に相談援助業務などの実務経験を同時に積める環境にある場合は、学習と実務を並行して進められるため、国家試験受験資格の要件を早期に満たしやすい点で有利です。
社会福祉士の受験資格における実務経験とは?
社会福祉士の受験資格で重要な要素のひとつが「実務経験」です。ここでは、実務経験として認められる分野と職種、認められない職種、そして誤解されやすい職種の具体例を整理して紹介します。
実務経験として認められる分野と職種一覧
社会福祉士の受験資格における実務経験は、福祉制度に基づいた相談援助業務に従事する職種に限られます。これは、利用者の生活課題を把握し、行政制度や福祉サービスを適切に調整する役割が求められるためです。
以下に、実務経験として認められる分野と職種の一例を紹介します。
| 分野 | 認められる職種・業務例 |
| 生活保護分野 | 福祉事務所のケースワーカー、生活保護担当相談員 |
| 高齢者福祉 | 地域包括支援センター職員、介護保険相談員、生活相談員 |
| 障害福祉 | 障害者支援施設の相談員、就労支援センター職員 |
| 児童福祉 | 児童相談所の相談員、児童家庭支援センター職員 |
| 地域福祉・行政機関 | 社会福祉協議会の相談員、自治体福祉課の相談援助職 |
このように、制度を基盤とした相談援助業務に従事する職種が実務経験として認められます。
一方で、介護職員やホームヘルパーなど、日常生活における身体介助や家事援助を中心とする職種は「相談援助業務」に含まれないため、受験資格には直結しません。
認められない職種・誤解されやすい職種の具体例
一方で、福祉分野に従事していても、社会福祉士国家試験の受験資格に必要な実務経験として認められない職種もあります。これは、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく「相談援助業務」に該当しないためであり、主に直接的な生活支援や事務業務に限定される点が理由です。
| 認められない職種分類 | 具体的な職種・内容例 | 認められない理由 |
| 介護・支援スタッフ系 | 特別養護老人ホームの介護職員、訪問介護員(ホームヘルパー) | 相談援助ではなく、生活介助が中心のため |
| ボランティア・非正規活動 | 地域ボランティア、アルバイト、インターンシップ | 業務が一時的かつ制度に基づいた援助ではないため |
| 事務・管理系 | 福祉施設の事務員、施設長、管理職 | 相談援助業務を直接行わないため |
| その他誤解されやすい業務 | 送迎担当、調理スタッフ | 生活支援に限定され、相談業務を含まないため |
このように、利用者と関わる仕事であっても、相談援助業務として厚生労働省の基準に該当しなければ受験資格には含まれません。誤解を避けるためには、勤務先が発行する勤務証明書に「相談援助業務」である旨が明記されているかを必ず確認することが重要です。
せっかく積み重ねた勤務経験が資格要件に反映されない事態を防ぐためにも、事前のチェックは欠かせません。
2025年2月導入の社会福祉士国家試験の改正ポイント
2025年2月に実施される第37回社会福祉士国家試験から、試験制度に大きな変更が導入されます。ここでは、その改正ポイントについて詳しく解説します。
「相談援助」から「ソーシャルワーク」へ名称変更
従来の試験科目であった「相談援助」は、2025年以降の新カリキュラムで正式に「ソーシャルワーク」へと名称が改められました。これは、社会福祉士の職能や教育内容を再構築することを目的とした見直しの一環です。
この変更の背景には、相談業務にとどまらず、地域や制度との連携を含め、生活全体にわたる支援能力を幅広く身につける必要があるという認識があります。
| 区分 | 従来 | 新カリキュラム | 主な変更点 |
| 演習科目 | 「相談援助演習」(時間数:不明確/一括科目) | 「ソーシャルワーク演習(共通)」30時間「ソーシャルワーク演習(専門)」120時間 | ・科目名を「ソーシャルワーク演習」に改称・共通と専門に分割・時間数を明確化(計150時間) |
| 実習科目 | 「相談援助実習」180時間以上実習先:1か所以上 | 「ソーシャルワーク実習」240時間以上実習先:2か所以上 | ・科目名を「ソーシャルワーク実習」に改称・時間数を180→240時間に拡充・実習先を1か所以上→2か所以上に拡大 |
これらの見直しは、講義・演習・実習を通じてソーシャルワークの機能を体系的に習得できる「学習循環」の構築を重視したものです。
「地域福祉と包括支援体制」科目が新設
新たに「地域福祉と包括支援体制」という科目が追加されます。これは、厚生労働省が推進する地域包括ケアシステムの理念や、多職種連携の重要性を背景に導入されたものです。
超高齢社会においては、医療・介護・福祉を切れ目なく統合的に提供できる人材が求められています。そのため、この科目では以下の内容が学習対象となります。
- 地域包括ケアシステムの構築と運営の仕組み
- 地域福祉計画や包括支援センターの役割
- 医療・介護・福祉の連携体制と情報共有の方法
- 多職種チームアプローチによる支援の実際
このように「地域福祉と包括支援体制」は、制度や地域資源を活用しながら、住民の生活を包括的に支える力を養うことを目的とした科目です。
実習内容・時間数・実習先の変更点
実習についても見直しが行われ、従来以上に内容の質が重視されるようになりました。これまでの「相談援助実習」は、新カリキュラムでは「ソーシャルワーク実習」と改称され、実習時間は180時間から240時間へと拡充されています。さらに、実習先は2か所以上での経験が必須となり、多様な現場で学ぶことが求められるようになりました。
社会福祉士国家試験の概要と出題科目
社会福祉士国家試験は、福祉分野の専門職として必要な知識と実践力を備えているかを確認するために実施されています。ここでは、試験の日時や科目、会場、受験料、申し込み方法といった基本情報を整理し、全体像を示します。
試験の日時と試験科目
社会福祉士国家試験は、例年2月上旬の土日2日間にわたって実施されます。
- 1日目は共通科目群(基礎知識・法律・人間理解など)
- 2日目は専門科目群(相談援助や事例問題)
このような構成で、午前・午後を通じて幅広い知識と実践力が問われます。
出題範囲は福祉の基礎から専門領域まで多岐にわたり、2025年度以降はカリキュラム改正に伴い新たな科目も追加されています。
| 時間帯 | 出題内容の特徴 | 主な科目 |
| 午前(基礎科目) | 福祉の基礎知識・法律・社会制度 | 人間と社会、心理学、社会学、法律、医療・保健、福祉サービス など |
| 午後(専門科目) | 相談援助・事例問題中心 | ソーシャルワーク(旧・相談援助)、相談援助演習、相談援助実習、地域福祉と包括支援体制(新設) |
このように、1日目は幅広い基礎知識を網羅する内容、2日目は相談援助を中心とした実践的な出題となります。特に2025年以降は「ソーシャルワーク」や「地域福祉と包括支援体制」といった科目が新たに加わったため、従来の学習計画を見直し、地域包括ケアや多職種連携を含む幅広いテーマを意識した対策が求められます。
試験会場
社会福祉士国家試験の会場は、全国各地に設けられ、主要都市を中心に配置されています。例年、東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・仙台といった大都市に加え、全国でおよそ20会場前後です。
試験会場は毎年、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが発行する「受験の手引き」で公表され、例年8月下旬〜9月頃に公開されます。受験希望者は必ず確認し、希望する会場を選択する必要があります。
特に地方から受験する場合は、会場までの交通手段や宿泊場所の確保を含め、早めに計画を立てておくことが重要です。
受験手数料
社会福祉士国家試験の受験手数料は毎年変動するため、必ず最新の「受験案内」で確認する必要があります。2025年度(第38回試験)の実績は以下のとおりです。
- 社会福祉士のみ受験:19,370円
- 社会福祉士と精神保健福祉士を同時受験(共通科目免除):16,840円
- 科目免除を受ける場合:16,230円
これらはあくまで参考額であり、正確な金額は最新の「受験案内」や公益財団法人社会福祉振興・試験センターの公式資料をご確認ください。
受験申し込みと受付期間
社会福祉士国家試験の受験申し込みは、例年8月下旬から9月中旬にかけて受け付けられます。提出方法は原則として郵送で、願書に加えて以下のような受験資格を証明する書類が必要です。
- 卒業証明書(大学・短大・専門学校など)
- 成績証明書(指定科目履修の確認用)
- 実務経験証明書(相談援助業務従事者の場合)
受付期間を過ぎると、その年度の受験はできず、翌年度以降に改めて出願しなければなりません。したがって、必要書類は早めに準備し、確実に提出することが重要です。
社会福祉士に向いている人の特徴と活かせる強み
社会福祉士は、生活上の課題を抱える人々に寄り添い、解決に向けて支援する専門職です。そのため、資格取得を目指す人は、求められる資質や能力を理解し、自身の適性を見極めることが重要です。これは将来のキャリア形成にもつながります。求められる主な資質は次の通りです。
- コミュニケーション能力
- 共感力や思いやり
- 課題解決力や調整力
これらの資質を身につけることで、社会福祉士としての専門性が高まり、実務現場での信頼を得るとともに、キャリアの発展にも大きく寄与します。
社会福祉士の資格取得に向けた学習計画の立て方
社会福祉士国家試験は科目数が多く、基礎から専門まで幅広い知識を問われるため、計画的な学習が欠かせません。特に仕事や学業と両立しながら勉強する人にとっては、効率的な学習計画を立てることが合格への近道となります。
無計画に取り組むと、学習範囲が偏り、重要科目を取りこぼすリスクが高まります。そこで有効なのが、受験日から逆算して段階的に学習を進める方法です。
このように計画的に学習を進めることで、知識をバランスよく習得でき、限られた時間の中でも合格に必要な力を着実に身につけられます。
| 時期 | 学習の目標 | 主な取り組み内容 |
| 4月~6月 | 全体像の理解と基礎知識のインプット | 教科書・参考書を用いた通読、重要用語の整理、簡単な問題演習。特に「共通科目群(人間と社会、心理学、社会学、法律、医療・保健など)」の基礎固めを行う。 |
| 7月~9月 | 出題傾向を把握し応用力を高める | 過去問演習、弱点分野の補強、記述問題への対応。2025年から新設された「ソーシャルワーク」「地域福祉と包括支援体制」にも重点を置く。 |
| 10月~12月 | 実践的な得点力を身につける | 模擬試験を受験し時間配分を確認。法律・制度の改正点を厚生労働省資料等でチェックし、出題可能性の高い最新トピックを整理する。 |
| 1月~試験直前 | 知識の最終確認と弱点克服 | 直前チェックリスト作成、重要ポイントの暗記、頻出テーマの総復習。加えて、睡眠・食事・体調管理を整え、試験当日の生活リズムに慣らす。 |
このように、学習計画を段階的に進めれば、無理なく知識を積み上げられ、試験本番で実力を発揮しやすくなります。特に社会人受験生は時間の制約が大きいため、スキマ時間の活用や効率的な復習法の導入が合格への大きなカギとなります。
社会福祉士の受験資格に関するよくある質問
最後に社会福祉士の受験資格に関するよくある質問に回答します。
社会福祉士の試験は誰でも受けられますか?
社会福祉士国家試験は、誰でも自由に受験できるわけではありません。受験資格として、大学や短期大学で指定科目を履修するか、養成施設を修了するか、あるいは福祉分野で一定の実務経験を積む必要があります。
大学に行かなくても社会福祉士になれますか?
大学に進学していなくても、受験資格を得られるルートはあります。ただし「短期養成施設ルート」は、福祉系大学や短大で一部の指定科目を履修済みの人、または精神保健福祉士などの関連資格を持つ人が対象です。そのため、高卒者が直接このルートを利用することはできません。
社会福祉士の受験資格取得後の有効期限はいつまでですか?
社会福祉士の受験資格に有効期限はなく、一度取得すれば生涯にわたって有効です。何年経過しても受験できます。ただし、国家試験は毎年1回(例年2月上旬)に実施されるため、受験する際は毎回「受験案内」に従って出願手続きを行う必要があります。
社会福祉士の受験資格は自分の最短ルートで取得しよう
社会福祉士を目指すうえで、最初の大きな関門となるのが受験資格の確認です。学歴や職歴、保有資格によって取得ルートが異なるため、自分にとって最適な方法を見極めることが大切です。福祉系大学を卒業すれば比較的スムーズに受験資格を得られますが、一般大学出身者や社会人であっても、養成施設での学習や実務経験を積むことで挑戦できます。
受験資格の取得はゴールではなくスタートラインです。資格を取得した後に、どのようにキャリアを築くかが本当の課題となります。無理のない計画を立て、自分の状況に合ったルートを選び着実に進むことが、社会福祉士として成功するための第一歩となります。

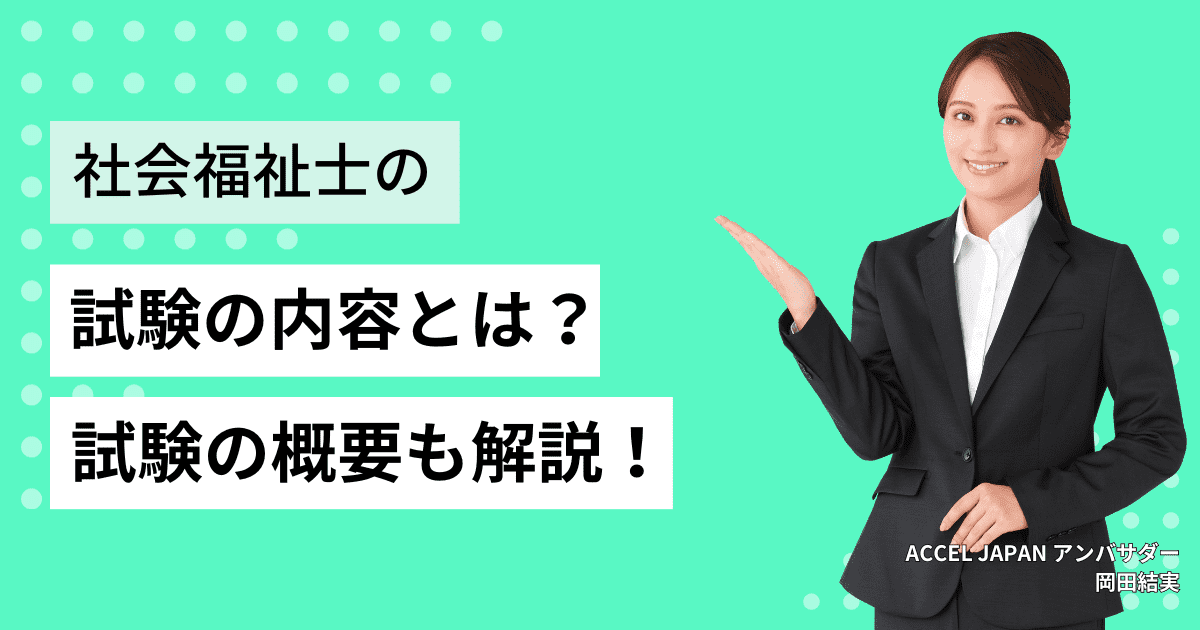


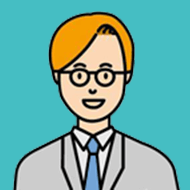
 児童福祉司が国家資格に!?厚生労働省が検討
児童福祉司が国家資格に!?厚生労働省が検討
 児童養護福祉士資格が新設!3月より認定講座開講
児童養護福祉士資格が新設!3月より認定講座開講













 心理学で、自分と誰かの人生を整える。「心」の専門家として歩み始める第一歩
心理学で、自分と誰かの人生を整える。「心」の専門家として歩み始める第一歩
 【期間限定:3/14まで】学習スタート応援キャンペーン実施中!
【期間限定:3/14まで】学習スタート応援キャンペーン実施中!
 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
 キャリアコンサルタント資格はどんな人に向いている?活かせるタイプ別解説
キャリアコンサルタント資格はどんな人に向いている?活かせるタイプ別解説
 メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】





