登録販売者とは

薬剤師以外で医薬品の販売ができる唯一の資格
登録販売者は、2009年6月に誕生した医薬品を販売できる資格です。
医薬品を取り扱うドラッグストアなどの店舗では、薬剤師または登録販売者がいなければ薬を販売することができません。
登録販売者資格を保有していると、市販薬と呼ばれる一般用医薬品(OTC医薬品 ※)のうち、第2類・第3類医薬品を販売することができます。
(※)OTC医薬品:一般用医薬品のこと。カウンター越しに医薬品の販売をおこなうことから「Over The Counter」の頭文字をとり「OTC」と呼ぶ。
登録販売者が扱える医薬品は市販薬の90%以上
登録販売者が取り扱うことのできる「第2類医薬品」「第3類医薬品」は市販薬の90%以上を占めます。
医薬品販売店舗で業務に携わるには、十分に活躍できる資格といえるでしょう。
登録販売者になるには?

登録販売者試験に合格し、販売従事登録をおこなう
登録販売者になるには、都道府県で実施される登録販売者試験に合格する必要があります。
登録販売者は国家資格に準じた資格ですが、未経験でも受験でき、比較的ハードルが低いというのが特徴です。
なお、試験合格後、勤務先の店舗がある都道府県に販売従事登録申請をおこなうことで登録販売者としての業務がスタートできます。
関連記事 販売従事登録について詳しく解説
単独で医薬品を販売するには管理者要件(実務経験)を満たす必要がある
登録販売者試験は実務経験なしで受けることができ、試験に合格すると資格の取得が可能になります。
しかし、登録販売者が単独で医薬品を販売するには、以下いずれかの要件を満たす必要があります。
- 直近5年間に2年以上かつ1,920時間以上の実務経験がある
- 直近5年間に1年以上かつ1,920時間以上の実務経験があり、外部研修(継続研修)の受講と、店舗または区域の管理および法令遵守に関する追加的な研修を受講している
- 過去に店舗管理者(区域管理者)として就業した経験があり、通算1年以上かつ1,920時間以上の実務経験がある
実務経験の要件が2023年4月1日に緩和!
登録販売者の実務経験要件は、2023年4月1日より緩和されました。
以前は「直近5年間に2年以上かつ1,920時間以上の実務経験」が対象でした。
しかし、ドラッグストア等で働く登録販売者の人手不足の影響で、規定の研修を受けることなどを条件に、1年の経験でも実務経験として認められることになったのです。
参考 厚生労働省/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和5年3月31日)
実務経験を満たさない間は「研修中」の見習い登録販売者
実務経験を満たさない間は、「研修中」の見習い登録販売者としての扱いになります(名札に研修中の旨を明記)。
研修中はひとりで医薬品を販売することはできず、薬剤師または店舗管理者や実務経験を満たしている正規の登録販売者の指導のもと、医薬品販売の業務に携わります。
なお、登録販売者の実務経験の規定は細かく複雑なため、詳しくは関連記事をご覧ください。
関連記事 登録販売者の実務経験なしの場合、どこで何時間経験を積めばよい?
店舗管理者になるためにも実務経験を積もう!
実務経験を満たすと店舗管理者になれる
店舗管理者は、薬局やドラッグストアなど、一般用医薬品を取り扱いしている店舗の責任者のことで、1店舗につき1人の配置が義務づけられています。
登録販売者の実務経験要件を満たすと店舗管理者になることができ、選任された場合は、店舗責任者として、店舗環境の整備や従業員の監督などをおこないます。
ドラッグストア等の店長が店舗管理者であるケースが多く、実務経験を積んでおくとキャリアアップにつながる可能性が高くなるといえるでしょう。
年収もアップしますので、実務経験を積んでおくことが推奨されます。
関連記事 店舗管理者になるための要件とは?
登録販売者試験に合格するには?
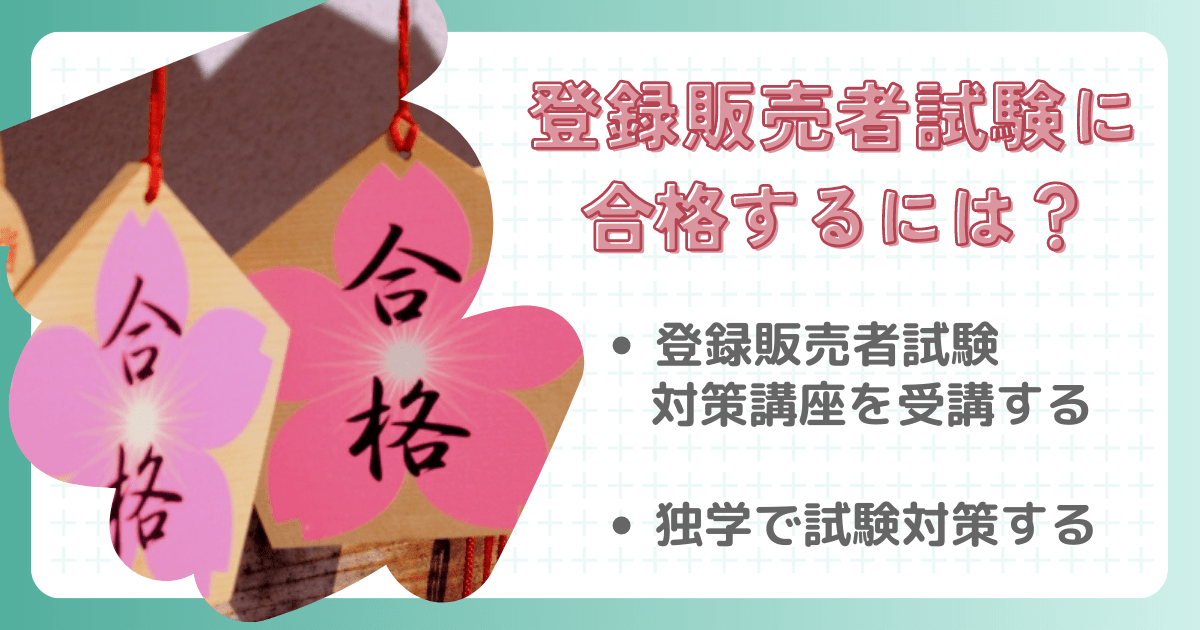
登録販売者試験に合格するには、まず、以下のいずれかの方法で試験勉強をおこないます。
- 登録販売者試験対策講座(通学・通信)を受講し、試験対策する
- 市販のテキストなどを用いて、独学で試験対策する
いずれも3ヶ月~半年程度が標準的な学習期間となります。
登録販売者試験は、独学でも合格が目指せる資格ではありますが、学習方法や学習スケジュールの管理はすべて自分でおこなわなければならないデメリットがあります。
確実に合格したければ、登録販売者試験講座の受講が推奨されるでしょう。
関連記事
登録販売者の試験対策ができるeラーニング講座(通信講座)を比較!
登録販売者試験に独学で合格するには?
登録販売者の年収・給料について

正社員で働く登録販売者の平均年収
登録販売者の給料ですが、平均年収は380万円程度といわれています。
1つの目安として、ドラッグストアに正社員として就職した場合、初年度の年収は300万円前後です。
そして店長クラスになると、400万円を超えてきます。
日本の年収の中央値が350万円程度、年収分布のボリュームゾーンが300~400万円(※)ですので、登録販売者の年収はちょうどその範囲に属する額であるといえます。
なお、勤務先によっては資格手当や役職手当などが充実しているケースもあります。
実績によっては、一般社員であっても年収が400万円以上となる場合があるでしょう。
なお、登録販売者の資格手当は、5千円~1万円程度を支給する勤務先が多いようです。
(※)転職サービスdoda統計データによる。同データによると、日本は年収400万円未満の層が56.5%を占める(300~400万円の層は32.7%)。
パートで働く登録販売者の平均時給
登録販売者としてパート勤務する場合、地域によって差がありますが、平均で1,100~1,400円程度の時給となります。
日本の最低賃金の平均(全国加重平均額)が961円ですので、好待遇とまではいえないものの、無資格者より時給アップが見込める仕事です。
パートであっても昇給制度のある勤務先が多くありますので、勤務を続ければ、着実に収入を上げていくことができるでしょう。
また、パート登録販売者として働くメリットとして、短時間で勤務する等、自分のペースで働けるため、Wワークや家事・育児との両立がしやすいことが挙げられます。
登録販売者という資格が生まれた背景
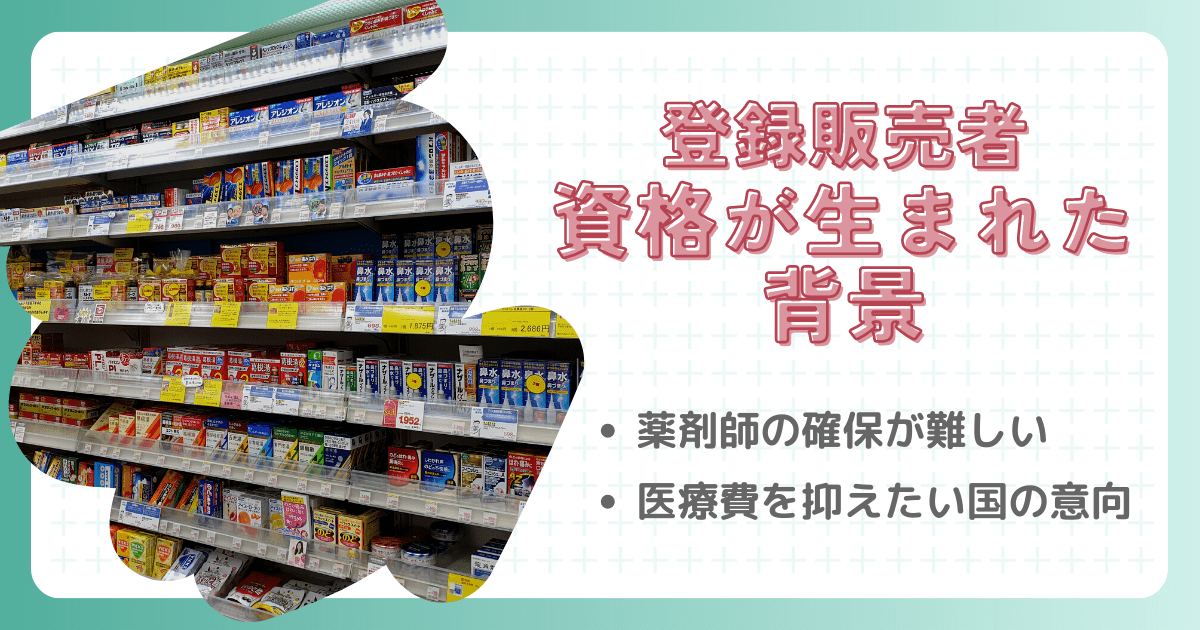
薬剤師の確保が難しい
登録販売者資格の創設以前は、薬剤師または登録販売者の前身ともいえる薬種商(薬種商販売業。登録販売者創設により廃止。)の資格保有者が医薬品の販売をおこなっていました。
薬種商は薬剤師に比べ資格保有者が少なく、医薬品の販売は主に薬剤師が担っていたという経緯があります。
そして、1990年代以降、ドラッグストアのチェーン展開が広まり、全国各地にドラッグストアが出店されました。
その分、ドラッグストアでは多くの薬剤師を雇用する必要が出てきたのです。
しかしながら、ドラッグストアで働きたいという薬剤師は少ない傾向にあり、現在においても薬剤師の確保がとても難しいという実情があります。
参考文献 国税庁/医薬品販売に係る規制緩和等について(平成16年5月開催 第17回酒類販売業等に関する懇談会説明資料)
医療費を抑えたい国の意向
また、国内では高齢化や医療技術の高度化などの影響により、医療費が年々膨らみ続け、社会保障費の負担がますます大きなものとなってきました。
国としてもセルフメディケーション(※)を推進し、国民に市販薬の購入を促したい意向が強まります。
そのような背景のなか、市販薬を取り扱える資格として新たに誕生したのが登録販売者なのです。
登録販売者は、薬剤師の次に頼りになる薬の専門家として期待されている資格といえるでしょう。
(※)セルフメディケーション:自分で健康管理をおこない、軽度な身体の不調は自分で対処するという考え。
登録販売者は薬剤師や調剤事務とどう違う?

登録販売者と薬剤師の違い
対応可能な医薬品の範囲が異なる
登録販売者と薬剤師のいちばんの違いは、対応できる医薬品の範囲が異なることです。
以下の表に、登録販売者と薬剤師それぞれが取り扱い可能な医薬品の範囲と、資格の区分についてまとめました。
| 項目 | 登録販売者 | 薬剤師 |
|---|---|---|
| 取り扱いできる医薬品 | 第2類医薬品・第3類医薬品 | 要指導医薬品・第1類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品 (医療用医薬品含むすべての医薬品の取り扱いが可能) |
| 薬の調剤 | 不可 | 可能 |
| 資格区分 | 国家資格に準ずる公的な資格 (都道府県知事認定) |
国家資格 |
ドラッグストアなどで販売される一般用医薬品は、使用・服用方法や副作用の程度などに応じて「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」に分類されます。
登録販売者は、このうちの「第2類医薬品」「第3類医薬品」の取り扱いが可能です。
薬剤師は、「第2類医薬品」「第3類医薬品」に加え、登録販売者が扱えない「要指導医薬品」「第1類医薬品」の取り扱いができるほか、医師の処方箋に基づいた薬の調剤や「医療用医薬品」の販売もおこなうことができます。
国家資格である薬剤師は難易度の高い資格
薬剤師は難易度の高い国家資格であり、資格を取得するには6年制薬学部のある大学を卒業し、国家試験に合格しなければなりません。
数ヶ月程度の試験勉強で合格が目指せる登録販売者とは、習得する知識量が全く異なることがわかります。
そのため、薬剤師は扱える医薬品の幅が広く、重要な業務を担えるのです。
参考 薬剤師国家試験について
登録販売者と調剤事務の違い
その他、薬に関連する仕事には、「調剤事務」があります。
調剤事務は、調剤薬局において薬剤師の調剤補助をおこなう仕事です。
主に受付や会計業務、薬歴管理や薬品の在庫管理、調剤報酬を計算するレセプト業務を担います。
調剤事務にも資格がありますが、国家資格や公的資格は存在せず、さまざまな機関により認定される民間資格が発行されています。
なお近年、登録販売者が調剤事務の資格も取得し、調剤薬局で働くというケースも目立つようになりました。
参考 調剤薬局事務について
登録販売者試験を受けるのに受験資格は必要?
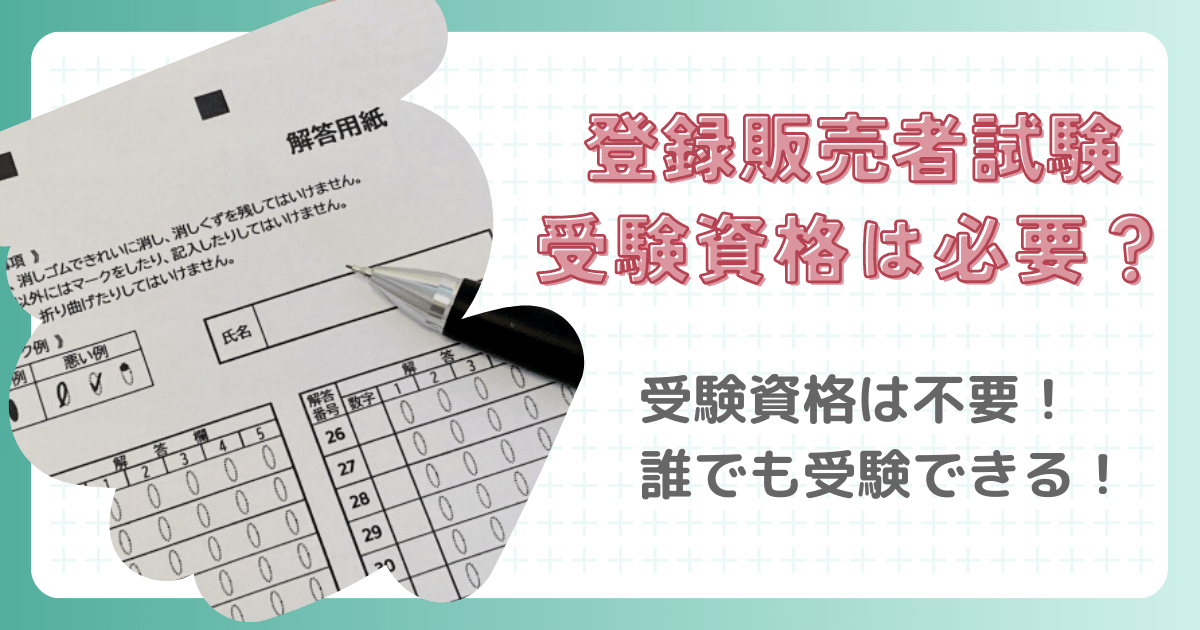
受験資格が不要で、誰でも受験できる試験!
登録販売者の資格は、2009年に誕生した資格です。
以前は登録販売者試験の受験資格として、試験を受ける前に実務経験が必要でしたが、2015年4月の薬事法改正により受験資格が撤廃され、どなたでも受けられる試験となりました。
なお、年齢・性別・学歴の制限もありません。
以下に試験概要を簡単に紹介しましょう。
- 試験実施:各都道府県で年1回
- 合格率:30~60%程度
- 検定料:13,000円~18,000円程度(受験する都道府県による)
- 試験形式:筆記試験(マークシート方式)
関連記事 登録販売者試験について詳しくはこちら
参考文献 厚生労働省/登録販売者試験実施要領
登録販売者に求められること
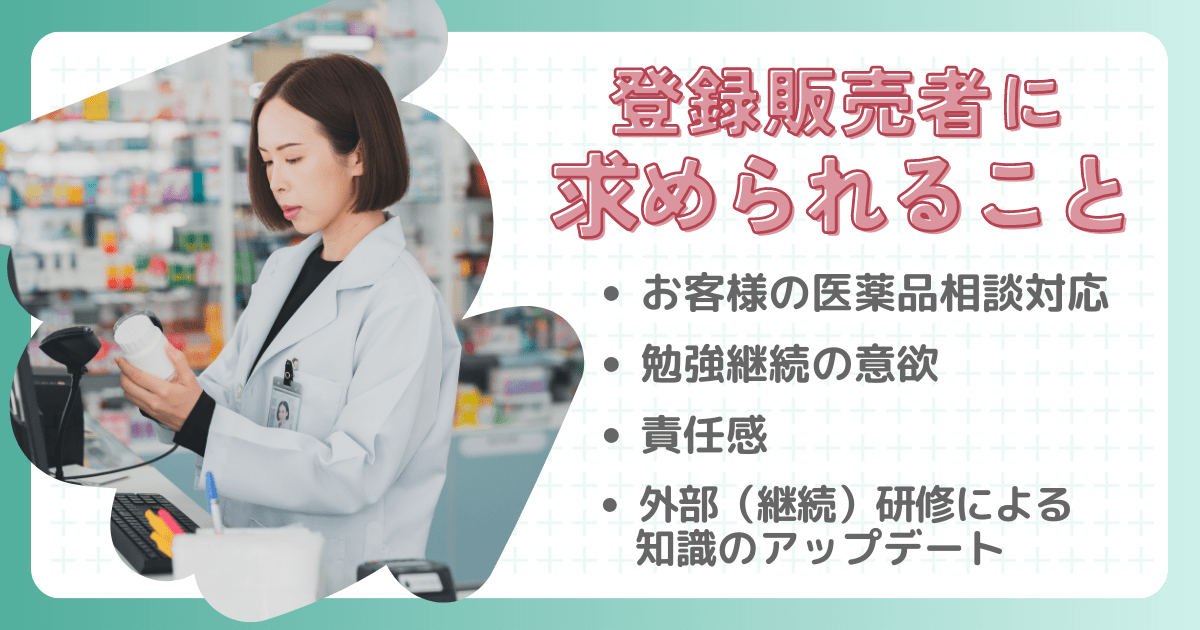
登録販売者は、かぜ薬・解熱鎮痛剤・胃腸薬・便秘薬・ビタミン剤など、あらゆる市販薬を取り扱います。
胃腸薬1つとっても種類は数多く、食前に飲むのか食後に飲むのかなど服用方法もさまざま。一般のお客様はどの薬を選ぶべきか自分で判断することは非常に難しく、その選択をサポートするのが登録販売者です。
お客様の相談対応は登録販売者の義務
医薬品は薬の区分によって、医薬品についての説明が義務づけられています。
登録販売者がおこなう医薬品の説明は努力義務の範囲になりますが、お客様から相談があった場合の対応は義務づけられていますので、必ず応じなければなりません。
| 医薬品の種類 | 対応できる資格 | お客様への説明 | お客様からの相談への対応 | |
|---|---|---|---|---|
| 要指導医薬品 ※ | 薬剤師 | 対面にて、書面での情報提供義務あり | 義務 | |
| 一般用医薬品 | 第1類医薬品 (ロキソニンS、ガスター10など) |
書面での情報提供義務あり | ||
| 第2類医薬品 | 薬剤師 登録販売者 |
努力義務 | ||
| 第3類医薬品 | 規定なし | |||
※要指導医薬品:スイッチOTC医薬品、ダイレクトOTC医薬品、毒薬・劇薬が該当
要指導医薬品と第1類医薬品は情報提供義務があることから、薬剤師が在駐している時しか販売ができません。そのため、鍵のついたガラスケース内など、一般客の手が届かない場所で薬を管理します。
ドラッグストアなどで、一般客も手に取れるようにオープンに陳列されている医薬品は、基本的に第2類・第3類の医薬品となります。
参考 厚生労働省/要指導医薬品について(令和5年3月 第2回 医薬品の販売制度に関する検討会説明資料)
登録販売者に必要なマインド
登録販売者は、お客様から話を伺い、症状に合った医薬品を選び、薬についての情報提供をするのが仕事です。
医薬品に対する興味はもちろんのこと、勉強し続ける意欲やコミュニケーション能力、誠実な人柄などが求められます。
対応の間違いがお客様にとって大きな損害になる可能性がありますので、お客様に正しい説明をするための知識と責任感が必要でしょう。
医薬品知識アップデートのための研修(外部研修)も義務づけられている
また、登録販売者は最新知識のアップデートが義務づけられており、厚生労働省が認定する機関が実施する「外部研修(継続研修)」を受講しなければなりません。
関連記事 登録販売者の外部研修(継続研修)について
登録販売者の仕事内容や勤務時間について

登録販売者の仕事は医薬品販売に関連する内容が中心
登録販売者は医薬品を販売、アドバイスするための資格ですので、医薬品の販売、薬の相談受付、薬の情報提供が中心の仕事となります。
それらに付随した業務である、医薬品やヘルスケア商品の発注・管理、品出し、売場作りなども含まれてくるでしょう。
勤務先によっては医薬品以外の仕事も対応する
薬を販売する小規模ドラッグストアなどの小型店舗や、薬剤師が常駐している薬局・ドラッグストアなどでは、登録販売者が医薬品以外の仕事にも対応するケースが多くあります。
理由としては、小型店舗であれば、従業員数が少なく、どのスタッフも店内全般の業務に対応しなければならないこと、薬剤師が常駐しているところであれば、薬剤師がメインとして医薬品担当を務め、登録販売者は薬剤師不在時の補佐としての役割になることが挙げられます。
登録販売者の勤務時間
登録販売者の勤務時間は、勤務先によって大きな差があります。
例えば、登録販売者が多く就業するドラッグストアであれば、店舗の営業時間が午前から夜間までの長時間となりますので、それぞれの従業員の勤務時間をスライドさせるシフト制の勤務であることがほとんどでしょう。
一方、ドラッグストアは残業時間が少なめの傾向で、正社員の登録販売者であれば月10~20時間程度、パートの登録販売者であればほぼなしであることが多いようです。
参考:キャリコネ「小売業界の企業 残業時間ランキング」
登録販売者の就職先と働き方

登録販売者の就職先は医薬品を販売する店舗・薬局が中心
登録販売者の実務経験が積める先は決まっている
登録販売者の就職先は、ドラッグストアや調剤薬局など、医薬品を販売する場所が中心となります。
なお、登録販売者が単独で医薬品を販売するためには、規定の実務経験を満たす必要があります。
実務経験が積める先は「調剤薬局」「店舗販売業(ドラッグストア等)」「配置販売業(置き薬の営業)」の3つに限られているため、ドラッグストアをはじめとする店舗や薬局での就職が中心となるのです。
登録販売者の知識が活かせる就職先はほかにもある
登録販売者の実務経験は積めませんが、登録販売者の知識が活かせる就職先はほかにもあります。
健康や美容に関連する職種が多く、登録販売者の薬やビタミンなどの知識を活かした仕事ができるでしょう。
代表的なものを以下に紹介します。
- 製薬会社の営業(MR)
- ビューティーアドバイザー(美容部員)
- エステティシャン
- 健康食品会社などのカスタマーサポート
関連記事 登録販売者の知識が活かせる就職先について詳しくはこちら
いろいろな働き方が選べる
登録販売者はあらゆる雇用形態での募集があり、正社員や契約社員、パートなど、ワークライフバランスに合わせた働き方ができるのが特徴です。
登録販売者は主婦も多い
登録販売者の資格が活かせる場所は、都心や地方問わず、住まいの近隣で見つけやすいこともポイントです。
雇用形態を選べば、家庭との両立がしやすい環境ですので、登録販売者には主婦が多いのも特徴といえるでしょう。
例えば、子どもが小さなうちはパートで、手が離れてからはフルタイムでという働き方の選択もできますので、特に子育て中の方におすすめの資格です。
登録販売者の資格を取得するメリット
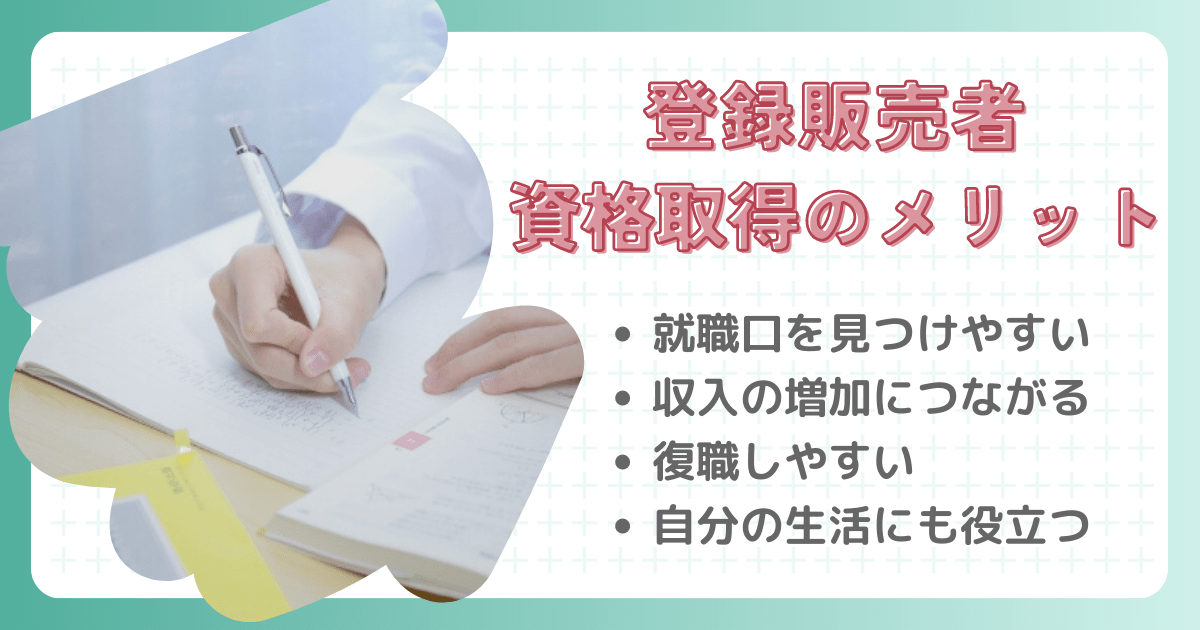
登録販売者の資格を取得するメリットは複数あります。
- 就・転職に有利
- 収入アップ
- 復職しやすい
- ライフスタイルに合わせて働ける
- 自分や家族の健康を守れる など
登録販売者の活躍の場は、ドラッグストア、薬局をはじめ、コンビニエンスストア、大型スーパーマーケット、ホームセンター、家電量販店など多彩です。
全国どこの都道府県にいても就職口が見つけやすく、転居などで職場を変えた場合でも経験を活かして働けます。
また、登録販売者の資格を保有していると、資格手当や時給アップなど収入の増加につながります。
登録販売者の資格自体に有効期限はないため、資格取得後に更新の必要もありません。
出産・育児後などに復職しやすい資格を探している方にもおすすめです。
自分の生活にも役立つ
登録販売者の知識は、自分が市販薬を買うときにも役立ち、症状に合った薬を選べるようになります。
家族の健康維持にも活かせる資格というのもメリットの1つといえるでしょう。
登録販売者の資格を取る最短ルートは?
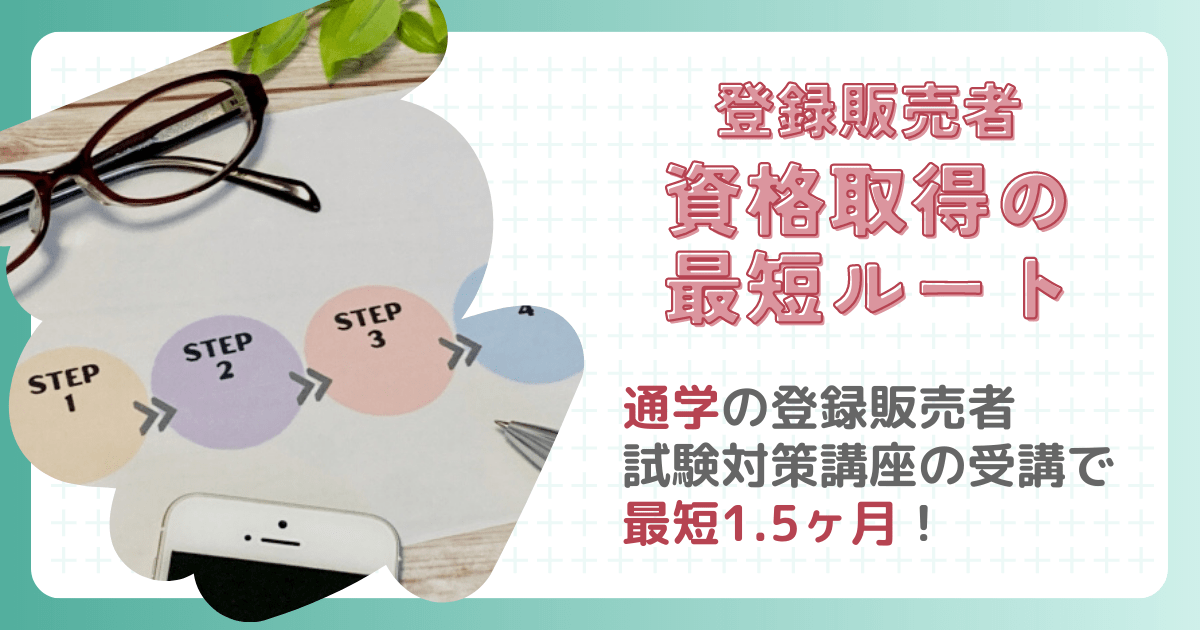
最短1.5ヶ月で合格が目指せる!
登録販売者の試験対策ができる通学講座では、最短1.5ヶ月という学習期間のコースが開講されています。
試験前までに修了できる適切なコースを受講することで、最短での合格が目指せるでしょう。
【注意点】都道府県によりますが、登録販売者試験の申込受付は試験日の3~4ヶ月前となりますのでご注意ください。
登録販売者に向いている人とは
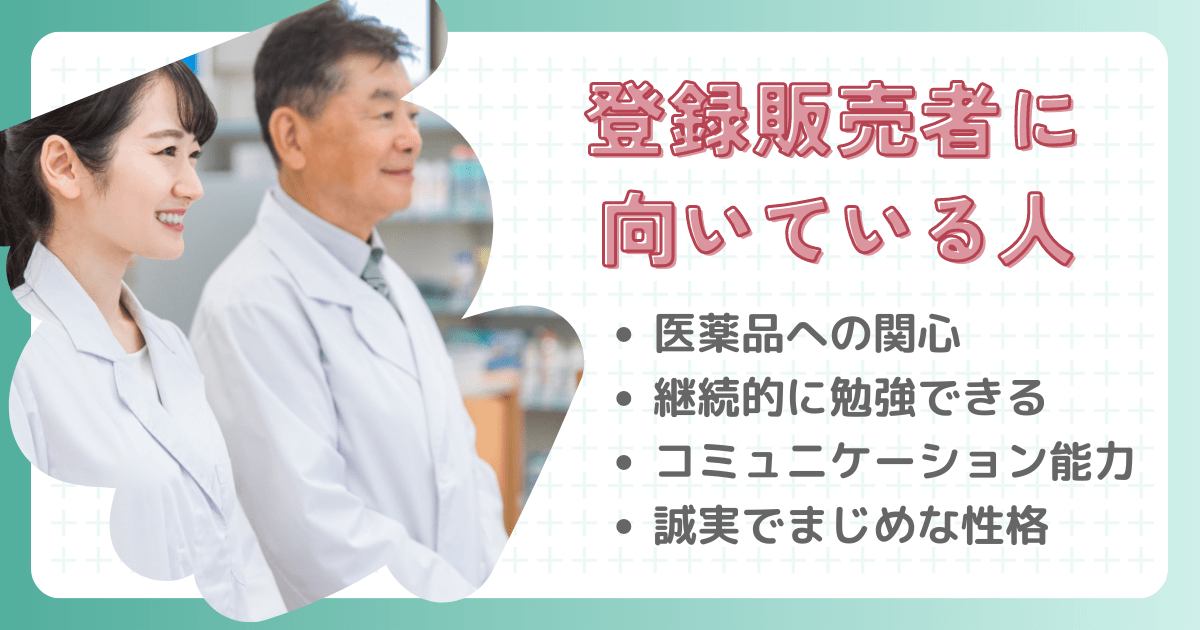
医薬品に対する関心
登録販売者は、医薬品を扱う仕事です。
医薬品に関心がなければ、仕事に対して面白さややりがいを感じられないことになるでしょう。
医薬品への興味は、登録販売者を目指す上で大事な要素であるといえます。
継続的に勉強ができる
医薬品は法制度の改訂が多い分野であり、登録販売者として知っておくべき情報や、お客様に伝えるべき情報が変更になることがあります。
また、製薬メーカーから新しい医薬品が次々と登場するため、医薬品についての知識のアップデートが欠かせません。
資格を取ったら終わりというわけではないため、継続的な勉強ができる人が向いているといえるでしょう。
コミュニケーション能力がある
登録販売者は、お客様から薬についての相談を受ける場面が多々あります。
お客様の症状や生活習慣などを聞き取るなど、コミュニケーションを取らなければ、適切に薬のアドバイスをすることができません。
また、店舗や薬局にいるほかのスタッフと連携した仕事をすることもあります。
登録販売者は、デスクワークなどの職種以上に、周囲とのコミュニケーションが重視されます。
コミュニケーション能力の高い方は、登録販売者に適した人材です。
誠実でまじめな性格である
医薬品の販売でいちばん注意しなければならないことは、お客様の症状に適さない薬を販売したり、誤った情報を提供したりすることです。
お客様の話を聞かない雑な接客は、医薬品による事故も引き起こしかねず、お客様の信頼を損なう結果となります。
誠実でまじめな性格、かつミスを起こさないような慎重さを兼ね備えた方は、登録販売者に向いているでしょう。
登録販売者のやりがいについて
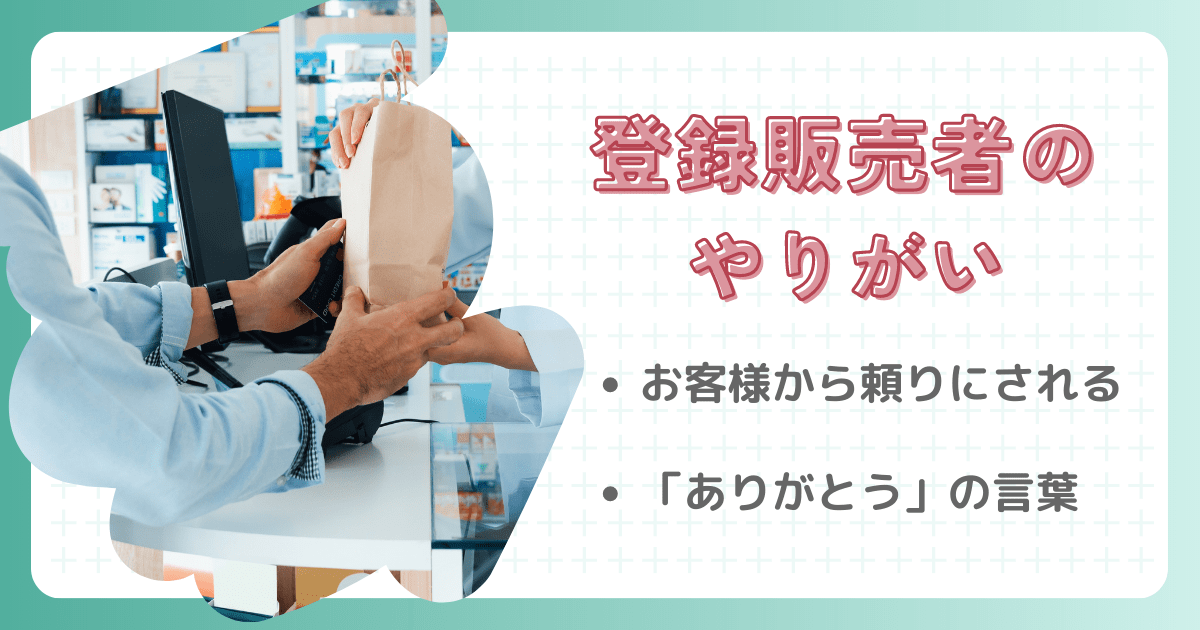
お客様から頼りにされる仕事
病院を受診するほどでもない不調の場合、ドラッグストアなどで手に入る一般用医薬品は、私たちにとってなくてはならない存在です。
その医薬品のアドバイザーである登録販売者は、お客様から頼りにされ、大きなやりがいを持てる仕事といえるでしょう。
人の健康にかかわる責任の重さもありますが、お客様からの相談にのったり、医薬品を選ぶうえでのアドバイスをしたり、医薬品の専門知識を活かした対応ができるのは、無資格者にはない登録販売者ならではの特権です。
「ありがとう」の言葉が大きなやりがい
医薬品の説明や相談対応に感謝されたり、接客したお客様が後日来店して薬が効いたことにお礼の言葉をくれたりする場面もあります。
お客様と直接対話する仕事なので、「ありがとう」の言葉は大きなやりがいと充実感につながるでしょう。
関連記事 登録販売者の仕事はつらい?楽しい?
登録販売者は将来性のある仕事
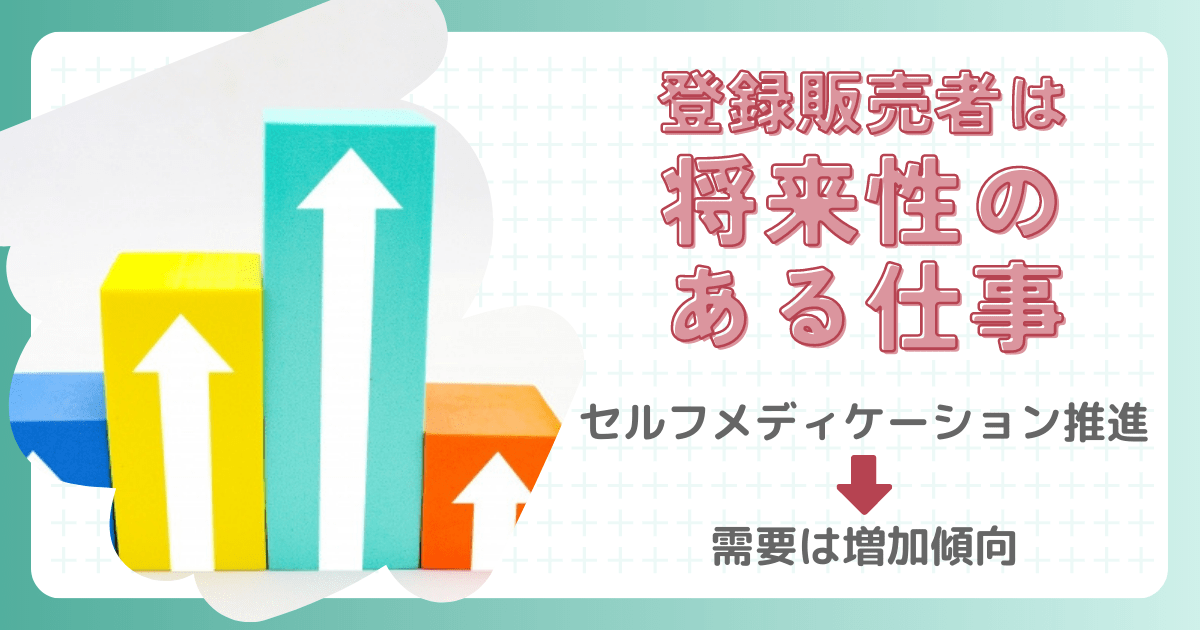
セルフメディケーションの影響で登録販売者の需要が増加傾向
セルフメディケーションについて
WHO(世界保健機関)では、セルフメディケーションを「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な心身の不調は自分で手当てすること」定義しています。
具体的には、自分自身の健康管理や疾病予防のほか、軽度な怪我や病気をしたときに自身で医薬品を選び使用することが挙げられます。
セルフメディケーション税制による消費者の変化
セルフメディケーション推進の一環として、一定の条件のもとで所得控除を受けることができる「セルフメディケーション税制」も始まりました。
健康への考え方や取り組みが変わるなか、薬の取捨選択も自分でできるようになりたいという方が増えてきています。
医薬品販売の需要はますます高まっていくことでしょう。安全性の確保にも従来以上に目を向けなくてはいけません。
参考 厚生労働省/セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
登録販売者は消費者ニーズに欠かせない存在
そこで求められるのが、医薬品の知識を備えた登録販売者の存在です。
法制度の整備・改正により、薬剤師しか取り扱えなかった医薬品の多くが、登録販売者でも扱えるようになりました。
また、医薬品を扱える店の規制が緩和され、スーパーやコンビニエンスストアなどでも販売できることもあり、登録販売者は消費者の医薬品ニーズに欠かせない存在となっています。
消費者が誤った知識によって医薬品を使用したり、間違った摂取をしたりしないようにリスク管理を担うのが登録販売者の重要な仕事といえるでしょう。
登録販売者を目指せるおすすめ通信講座
監修者プロフィール
埼玉県生まれ。
登録販売者受験対策・薬膳・漢方医学教育の日本統合医療学園にて教務部長を務める。
また、各種専門学校非常勤講師、社会人スクール、相談専門の漢方薬局等を兼任し、全国の大学・製薬メーカー等の企業にて登録販売者の育成を行う。
日本統合医療学園では、登録販売者制度が始まった翌年より試験対策に携わり、合格率は驚異の100%を誇る。そのなかで培った経験とノウハウを、多くの受験者の方々に伝え、医薬関係者のボトムアップに向けて奮闘中。
【登録販売者★石川達也】YouTubeチャンネル
試験対策動画【再生回数250万回】以上!の専門家、石川達也先生がわかりやすく解説!
>> 【登録販売者★石川達也】YouTubeチャンネルはこちらから
試験データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資格・試験名 | 登録販売者 |
| 試験区分 | 公的資格 |
| 主催団体 | 各都道府県 |
| 受験資格 | 特になし |
| 合格率 | 30~60%程度 |
| 出題内容・形式 | 筆記試験(多肢選択式)で実施。 ▽試験項目及び問題数 1 医薬品に共通する特性と基本的な知識 20問 2 人体の働きと医薬品 20問 3 薬事に関する法規と制度 20問 4 主な医薬品とその作用 40問 5 医薬品の適正使用と安全対策 20問 |
| 検定料 | 東京都:13,600円 (都道府県により異なります) |
| 問い合わせ先 |
各都道府県にお問い合わせ下さい。 ※東京都の場合 東京都福祉保健局健康安全部薬務課 登録販売者試験担当 TEL:03-5320-4522(9:00~12:00、13:00~17:00) (土日祝日を除く) http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/tourokushiken/ |


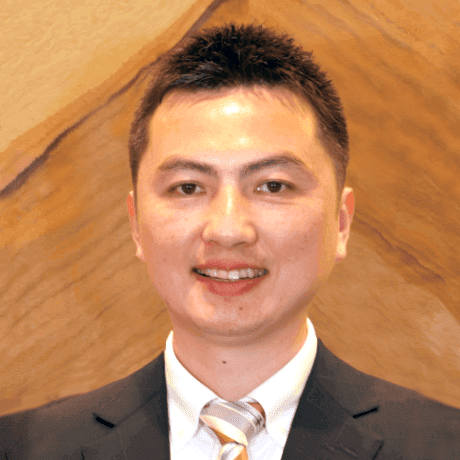
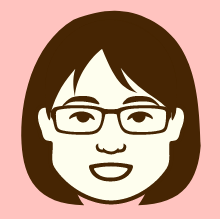

 「登録販売者」未経験から合格する方法は?
「登録販売者」未経験から合格する方法は?














 「日本語教師」の資格取得を目指すなら、38年超の実績を有するアークアカデミーで!
「日本語教師」の資格取得を目指すなら、38年超の実績を有するアークアカデミーで!
 心理学で、自分と誰かの人生を整える。「心」の専門家として歩み始める第一歩
心理学で、自分と誰かの人生を整える。「心」の専門家として歩み始める第一歩
 世界で最も取得されているNASMパーソナルトレーナーライセンスで、トレーナーになろう!!
世界で最も取得されているNASMパーソナルトレーナーライセンスで、トレーナーになろう!!
 2026年2月1日掲載の新スクール&特集ページを大紹介!
2026年2月1日掲載の新スクール&特集ページを大紹介!
 人気のZUMBAインストラクターになろう!動画orライブ配信トレーニングが選べる&今だけ50%OFF!
人気のZUMBAインストラクターになろう!動画orライブ配信トレーニングが選べる&今だけ50%OFF!





