医療事務とは
医療事務とは、受付業務・診療報酬請求(レセプト業務)・クラーク業務の3つの業務をメインに行う仕事です。
日常的に行う業務としては病院やクリニックの受付です。医療機関の顔として来院された患者に初診・再診の受付を行い、医師の診察が終われば会計を担当します。
また、レセプト業務は、月末から翌月の10日までに行う作業です。
レセプト業務は、市区町村などの健康保険の保険者に診療報酬を請求する仕事で、医療施設の収入になる重要な仕事です。
クラーク業務は、医療スタッフと患者のやり取りを円滑にする業務です。カルテの代行入力や入院手続きを行います。
一般事務との大きな違いは、カルテの取り扱いやレセプト業務など、医療にかかわる専門的な業務の多さです。
医療事務の仕事が女性からの人気が高い理由
医療事務は、女性に人気の仕事として知られています。その大きな理由として、女性特有のライフスタイルが変化しても働きやすい点が挙げられるでしょう。
結婚・出産・子育てといった人生のイベントが多い女性は、どうしても働き方を変えざるを得ない時があります。
医療事務には様々な雇用形態があり、子どもが小さいうちはパートやアルバイトで時短勤務し、子育てが落ち着いたら正社員や派遣社員としてフルタイムで働く選択が可能です。
このような多様な働き方が選べるのは、女性にとって大きなメリットと言えるでしょう。
ほかにも、女性からの人気が高い理由はいくつかあります。
仕事の残業が少ない
医療事務は、企業における事務処理のような業務がメインなので、ルーチンワークが多く、残業の少ない仕事として人気です。
ただし、絶対に残業がないわけではありません。次のような時期には残業が発生することもあります。
- 月末月初
- 繁忙期
- 患者が多かった時
月末月初は前月分のレセプトのデータをまとめて請求する業務が発生します。そのため、患者数の多い大規模な病院では残業が発生することもあります。
また、インフルエンザのような感染症が流行している繁忙期や患者が多い日は、事務処理数が増えるため、残業しないと翌日の業務に影響が出てしまうでしょう。
しかし、こういった時期以外の残業は基本的に少なく、負担が軽い仕事として知られています。「なるべく残業を避けたい」「子どもの時間を大切にしたい」などの要望がある方も働きやすいでしょう。
ブランクがあっても復帰しやすい
医療事務は、ブランクがあっても職場復帰しやすい仕事です。
経験が重視されるため、出産や子育てで退職せざるを得なかった人でも、再度求人に応募すれば採用される可能性が高くなります。
特に、医療事務の資格があれば、経験と資格をアピールできるため、就職や転職活動が非常に有利になるでしょう。
また、医療事務は人手不足で、求人数も多い傾向にあります。
日本は高齢化の影響で医療の需要が増え、医療事務の不足も予想されています。求人が増えることはあっても減ることはありません。
ブランクがあってもチャレンジしやすい仕事と言えるでしょう。
子育てしやすい環境で家庭との両立もしやすい
医療事務は、自分のライフスタイルに合わせて働き方を変えることが可能です。
子育て中の人でも働きやすい、4~5時間勤務のパートやアルバイトの求人も多くあります。
医療事務のように、「妊娠・出産後は子育てをしながら時短のパートやアルバイトで働き、子どもが大きくなったらまた正社員に戻る」という働き方ができる仕事はあまり多くありません。
加えて職場によっては託児所が完備されている、出産・育児休暇を利用できるところもあります。
医療事務は女性が家事や子育てなど、家庭と両立しながら安心して働くことが可能な仕事と言えるでしょう。
全国どこでも仕事を探せる
病院やクリニックなどの医療施設は日本全国どこにでもあります。
仮に夫が転勤になり、一緒についていくことになったとしても、医療事務の仕事ならどんな場所でも探すことができます。経験や資格があれば、条件の良い就職・転職活動が可能でしょう。
また、医療事務の平均年収は250~350万円と言われています。
日本の女性の平均月収が280万円と言われているので、医療事務の仕事をした場合、平均または平均以上の年収が得られる可能性が高くなります。
関連記事 医療事務の給料はいくら?勤務形態別の年収相場や安いと言われる理由
関連記事 男性でも医療事務はできる?男性医療事務の需要や待遇について
医療事務の仕事内容
医療事務のメイン業務は次の3つです。
これらの業務では、カルテの読み方や診療報酬の計算などの知識が求められるため、一般事務よりも専門性の高い事務職と言えるでしょう。
受付業務
1つめは受付業務です。窓口で受付をおこなう医療機関では、医療事務が「病院の顔」としての役割を持ちます。
来院した患者から保険証や診察券を預かり、必要に応じて問診票に記入してもらうなどの業務を行います。
初診であれば診察券やカルテの発行を行い、再診であればカルテを探して医師に症状が伝わるようにします。
初診料や受診料を伝えるのも窓口の仕事です。
患者さんとの接点が多くあるため、マナーやコミュニケーション能力が求められます。
レセプト業務
医療事務の仕事内容で、特に重要なのが2つめのレセプト業務です。
レセプトとは「診療報酬請求」のことです。
医療保険制度が充実している日本では、患者側の診療費の負担は1~3割で、残りの診療費は病院側から保険団体に請求します。
診療費請求のためには、医師が書いたカルテを見ながら、保険診療で定められた診療行為を点数にして計算し、請求書を作成します。
レセプトは毎月10日までに提出しなければならず、月末から月初は非常に忙しくなります。
保健制度は定期的に変わり、診療報酬点数も2年ごとに改正されるため、医療事務は常に知識のアップデートが必要な仕事です。
レセプト業務を実施しなければ、医師がいくら診療をしても病院の経営が成り立ちません。医療事務は病院経営にとって欠かすことができないポジションで、非常に重要な立場となるのです。
関連記事 レセプト業務とは?資格は必要?未経験でもできる?仕事内容や流れを解説
クラーク業務
3つめは、医師や看護師の秘書としての仕事である「クラーク業務」です。
医療事務は医師や看護師などの医療スタッフと、患者さんとの懸け橋として働く機会が多くあります。
これを「クラーク」業務と呼び、規模の大きな病院では「外来クラーク」と「病棟クラーク」の仕事を医療事務が受け持ちます。
クラークの仕事には、カルテやレントゲンの準備から、入院・退院手続きなども含まれます。
当然、患者や家族から質問されることも多くあるので、ある程度の医療知識を持つことが必要です。
また、同時に医師や看護師とのコミュニケーションも必要です。クラーク業務を行う医療事務には専門的な知識と、高いコミュニケーション能力が求められると言えるでしょう。
関連記事 医療事務になるには?未経験からなるための方法を紹介!
医療事務として働くメリット・デメリット
医療事務として働くメリットとして、次のようなものがあります。
- ライフスタイルが変化しても雇用形態を変えて働ける
- 全国のどこでも働ける
- 医療機関は景気に左右されないので安定職
- 未経験でも働けるチャンスがある
- レセプト業務やクラーク業務は専門性が高くやりがいがある
- 患者や医療スタッフに感謝の言葉がもらえる
- 社会貢献ができる
一方で、次のようなデメリットも理解しておきましょう。
- レセプト作成やカルテのデータ入力の業務が大変
- 医療制度や診療報酬の改定があるので学び続ける必要がある
- 高いコミュニケーション能力が求められる
- 平均年収は250~350万円で日本の平均年収より低い
医療事務は決して楽な仕事ではありません。しかし、大変さを上回る多くのメリットがあるからこそ人気のある仕事といえます。
「将来は安定した仕事に就きたい」「地域や人に貢献できる仕事がしたい」「医療従事者として働きたい」などの要望がある方は、ぜひ医療事務を目指してみてはいかがでしょうか。
関連記事 医療事務のやりがいを感じるシーン4選!仕事の魅力や楽しいことも紹介
医療事務に向いている人とは
医療事務の仕事に向いているのは、次のような人です。
人とのコミュニケーションが好きな人
人とのコミュニケーションが好きな方は、医療事務の仕事に向いていると言えるでしょう。
医療事務は医師や看護師、検査技師など、さまざまな関係者と連携しながら進めるお仕事です。
コミュニケーション能力がすぐれていれば、ほかの医療事務スタッフとも良好な関係を築くことができます。業務で病院・クリニック中がバタバタしているときにも、うまく連携して業務を進めることができるでしょう。
また、医療事務は、子どもから老人まで幅広い年齢層の人と接する機会があります。
コミュニケーション能力があり、どんな人とも気軽に明るく話せるという人であれば、患者からどんな状態か聞き取りやすくなります。医療スタッフに伝えて診療がスムーズになるでしょう。
一人ひとりの業務量が膨大な小さな病院では、コミュニケーション能力は欠かせないほど重要なスキルです。自信がある方は、医療事務にチャレンジしてみると良いでしょう。
思いやりがあるやさしい人
医療事務は、さまざまな立場で仕事をするスタッフたちの「調整役」という側面もあります。
働く方たちを気遣いながら仕事を進められる思いやりのある方は、病院やクリニックから重宝されるでしょう。
高い事務処理能力も大切ですが、重要なのはチームとして円滑に業務を進めることです。
また、怪我や病気をかかえて来院する患者の中には、不安な気持ちを抱えている方もいます。医療事務は、そういった方に寄り添えるやさしさも求められます。
たとえば、患者からの質問や不満を伝えられた時に、根気強く丁寧に聞き取り、正確に説明できれば、患者も安心して診療を受けられます。
笑顔や朗らかな態度も、患者に安心感を与えるでしょう。
受付で「お体の調子はいかがですか?」「今日はあたたかいですね」などの思いやりのある会話が、病院への愛着や信頼につながっていくはずです。
細かい仕事が苦にならない人
医療事務の仕事は、医療費の計算・パソコンへのデータ入力・カルテや伝票の整理など、細かな業務の連続です。
レセプト業務は、レセプトコンピュータ(レセコン)に正確に入力しないと診療報酬が支払われません。カルテのデータ入力も患者の健康に関わることです。情報の誤入力を防ぐ必要性があるため、高い正確性が要求されます。
パソコン作業・計算・文字を書くことなどが苦にならない人は向いているといえるでしょう。
また、几帳面で細かいところにまで気がまわるという人も、チェックで不備を見つけたり、患者の様子に気を配ったりと、医療事務の現場で力を発揮できる可能性があります。
整理整頓が得意な人
医療事務の仕事は、きれい好きで整理整頓が得意という人にも向いています。
カルテや伝票は個人情報が記載されているので、どこに置いたかわからなくなったなどのミスがないよう、慎重な管理が求められます。
きれい好きで整理整頓が得意な方であれば、資料をうまく管理し、業務もスムーズに進められるでしょう。そのような方は病院やクリニックでも重宝されます。
日頃から整理整頓を意識して行動している方は、医療事務の現場で活躍できる可能性が高いでしょう。
関連記事 男性でも医療事務はできる?
関連記事 医療事務になるには?未経験からなるための方法を紹介!
【平均はどのくらい?】医療事務の給料・年収・ボーナス事情
医療事務の平均年収は、250~350万円です。
しかし、これは正規雇用も非正規雇用も含めた平均なので、実際には大きな開きがあります。
たとえば、正社員であればボーナスが支給され、社会保険も完備されている職場も多いでしょう。年齢とともに役職がついたり手当がついたりすると収入が上がるので、長年勤務している人は平均年収を上回る場合もあります。
一方で、パートやアルバイトなどの非正規雇用は基本的にボーナスがなく、時給は1,000円前後です。時短で働いている人も多いので、平均すると医療事務の年収は低くなってしまうのです。
医療事務の給料は、地域や医療施設の規模によっても差があります。
地域による給料の違い
勤務する地域や職場によって、医療事務は給与水準が大きく異なります。
首都圏エリアや京阪神では、平均年収よりも高い水準ですが、地方都市になると平均年収以下になる場合がほとんどです。
たとえば、正社員で比較した場合、関東は平均年収324万円、派遣の時給は1,325円ですが、九州・沖縄は277万円、時給は1,126円と大きな差があります。
このように首都圏の賃金は高く、地方は低い傾向にあります。もし高い給料を求めている場合は、首都圏の病院やクリニックへ就職を目指してみると良いでしょう。
職場による給料の違い
医療事務の給与水準は、職場によって異なります。
勤務先としては、クリニック・診療所・総合病院・大学病院・一般企業が一般的です。
個人の病院や開業医の例
個人の病院や開業医の場合、給与水準は決して高くありません。
年収で言うと約200万円台が目安です。
また、個人経営や数人規模のクリニックなどでは、ボーナスや各種手当・社会保険などが支給されない職場もあります。
総合病院・大学病院、大企業の例
総合病院では250~300万円前後、大学病院や大企業では300万円以上の年収が見込める可能性があります。
基本的に、医療施設の規模が大きくなるほど年収は高くなる傾向にあります。
年収を充実させたい方は、働きながら資格取得を目指したり、スキルを増やしたりしながらキャリアアップを目指してみましょう。
関連記事 医療事務の給料相場は?安いと言われる理由や給与アップの方法をご紹介
医療事務を目指せるおすすめスクール
医療事務の資格の概要
医療事務は、診療報酬明細書の作成やカルテのデータ入力など、一般事務と比べると特殊な業務の多い仕事です。働き始めると、医療制度をはじめとした医療に関する様々な専門知識が求められます。
資格は不要とされている医療事務ですが、このような専門的な知識やスキルがあることを証明する民間資格が多数あります。
医療事務の資格には様々な種類があるので、病院・クリニック・歯科・調剤薬局・健診センターなど、働く場所の特色に合わせて選ぶことが可能です。
「未経験で医療事務を始めるのは不安」「医療事務の知識を学びなおしたい」という人は、医療事務の資格を取得すると良いでしょう。
医療事務資格の特長
- 1最短1ヶ月で学べる通信講座も多く、働いている方や主婦の方でも短期間で資格の取得が可能です
- 2未経験・ブランクありでも大丈夫実務経験がなくても必要な知識を学べば就転職がしやすくなります
- 3高齢化により需要が増加中高齢化に伴い、医療費の請求業務などができる医療事務資格保有者の需要が増加
医療事務の資格はすべて民間資格で、約20種類以上あります。
「民間資格なら取得の意味がないのでは?」という人もいるでしょう。
しかし、医療事務の仕事は専門性が高く、働き始めてから医療事務の資格を取得して学びなおす人もいます。初心者であれば、なおさら資格があった方が良いでしょう。
また、高齢化が進む日本では、今後ますます医療事務の需要が高まります。医療事務の資格があれば未経験やブランクがある状態でも就職や転職で有利です。
では、数ある資格の中からどれを選べばよいのでしょう。
医療事務の資格は難易度や受験条件が異なり、通信講座を受講すれば1ヶ月程度で取得できるものもあれば、合格率30%程度の取得が難しいものもあります。
「短期間で取れる資格が欲しい」「キャリアアップできる資格が欲しい」など、自分が目指す職場や目的によって選び方が変わってきます。
医療事務の資格を取るには?
医療事務の資格を取得するには、通学講座や通信講座、独学など、いずれかの方法で知識を習得し、試験などを受けて証明証・認定証をもらうのが一般的です。
テキストや試験対策の本が市販されているため、自分で学習するのが得意な人は独学で医療事務資格の取得を目指すことも可能です。
しかし、おすすめなのは通学講座や通信講座です。
医療事務の業務内容は専門性が高く、試験内容には実技も含まれます。疑問や不明点が生じた時に、通学講座や通信講座なら講師に質問できますが、独学は自分で解決しなければなりません。
通学講座や通信講座では、試験対策として出題ポイントが教えてもらえるのも大きなメリットです。
できるだけ効率的に合格したいという人は通学講座や通信講座で学ぶのが良いでしょう。
医療事務の資格取得に向けたスケジュール例
ここでは、医療事務の資格を取得するまでのスケジュールを動画でご紹介しています。2つの講座・資格を例にしていますので、参考にしてみてください。
また、通信・通学を受講する場合の費用も紹介しています。
オプションの資格でスキルアップ
医療事務の資格の中には、医療機関でのパソコン操作のスキルを証明するものや、レセプトチェックに特化したものなどがあります。
自分が目指す現場の状況に合わせて、医療事務の資格にプラスして取得すると、さらにスキルアップが期待できるでしょう。
また、介護施設や歯科医院などの別の知識が必要な職場への就職を目指す場合は、プラスアルファの講座を受講した方が良いこともあります。
医療事務コンピュータ・電子カルテ講座
カルテは手書きだった昔と違って、ほとんどの医療機関で電子カルテを導入しています。
カルテのデータ入力をする時に使われるソフトは、メーカーによって操作の違いはありますが、医療事務は受付で電子カルテのデータを扱うので、基本的な操作を学んでおいて損はないでしょう。
カルテ情報のデータ入力をするときに使われる医事会計システムは、メーカーによって操作の違いはありますが、今や多くの医療機関で使われていますので、基本的な操作を学んでおくことは決して無駄にはならないでしょう。
レセプトチェック講座
診療報酬明細書(レセプト)の内容に間違いがないかチェックできるように学べる講座もあります。
レセプトの確認には単なる計算能力だけでなく、診療報酬制度を理解していることが求められます。
「なぜこのような計算になるのか」をわかったうえで実務に望めるのは大きな強みと言えるでしょう。
調剤薬局事務講座、介護事務講座、歯科医療事務講座
職場の特性に合わせた事務の知識を身につけられる講座もあります。
調剤薬局で事務をするなら調剤特有の算定方法や薬の知識が求められる場合があるでしょう。また、介護施設で事務をするなら介護の知識が、歯科で働くなら歯の基礎知識が必要です。
医療事務として行う仕事は共通していますが、系統によってサポート内容や学ぶ分野が異なります。
将来就職したい職場のイメージが固まっている方は、このような講座を受けてみるのもおすすめです。
医療事務資格の種類一覧
医療事務の資格は協会や団体が主催している民間資格です。2023年時点で数多くの資格が存在します。
その中でも「診療報酬請求事務能力認定試験」・「医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®)」・「医療事務管理士技能認定試験」は認知度が高く人気のある資格です。
しかし、 基本的にはどの資格を取得しても医療事務の基礎を学んだことの証明になります。
実務には医療事務の基礎知識だけでなく、医療費等の計算や医療コンピュータのスキルも求められるため、セット講座やW資格取得を目指す講座もあります。
| 資格名 | 特長 |
|---|---|
| 診療報酬請求事務能力認定試験 | 合格率:30%前後 主催:公益財団法人日本医療保険事務協会 |
| 医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®) | 合格率:70%~80% 主催:日本医療教育財団 |
| 医療事務管理士技能認定試験 | 合格率:医科が50%前後、歯科が70%前後 主催:JSMA 技能認定振興協会 |
| 医科2級医療事務実務能力認定試験 | 合格率:60%~80% 主催:全国医療福祉教育協会 |
| 医療事務検定試験 | 合格率:90%前後 主催:日本医療事務協会 |
診療報酬請求事務能力認定試験
診療報酬請求事務能力認定試験は医療事務資格で唯一、厚生労働省が認定した試験で、最も難易度の高い資格です。
医療機関からの認知度・信頼度が高く、職場によっては資格手当の出る場合もあります。
そのため、一度他の医療事務資格を取った後に取得を目指して受験する人や、実務に就いてから受験する人もいます。
年2回試験が実施されています。試験内容は制度や法規などを含む学科問題とレセプトを作成する実技問題で、他の医療事務資格検定試験よりレベルは高い傾向です。
関連記事 診療報酬請求事務能力認定試験の内容は?合格率や難易度について
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®)
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®)は1974年から試験が実施されている歴史の長い資格です。
試験は毎月行われており、受験のしやすさから多くの人が受験しています。合格率は70%~80%を推移しており、難易度は高くありません。
患者待遇や医療事務知識を問われる学科と、診療報酬請求事務の実技からなる試験です。
医療事務系の資格の中では最大規模の試験として高い認知度を誇り、対策講座も通学・通信講座で多数あります。
2024年7月からIBT方式の試験へ移行
2024年7月の試験からペーパー試験から、インターネットを通じてご自宅やスクールのパソコンで試験を受ける事ができるIBT方式の試験に移行することとなりました。
※2024年6月までは、今まで通り紙による試験が実施されます。
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®)の詳細や、IBT方式の詳細、主な変更点につきましては以下ページでご紹介しています。
関連記事 医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®)とは?難易度や合格率は?
医療事務管理士技能認定試験
医療事務管理士技能認定試験は、医療保険制度などの法規や、保険請求事務の知識などについて問われる学科と、レセプト作成・点検の実技試験があります。
医科は毎月、歯科は奇数月に試験が実施されており、何度もチャレンジしやすい資格と言えるでしょう。
日本初の医療事務の資格として知られており、医療関係者にも高い信頼を得ています。医療事務の総合的な知識が習得できる人気の資格です。
関連記事 医療事務管理士技能認定試験とは?独学でも合格できる?難易度は?
医科2級医療事務実務能力認定試験
医科2級医療事務実務能力認定試験は診療報酬明細書作成技能のほか、診療報酬に関する知識や医療関連法規に関する知識を客観的に判断します。
精度の高い請求実務能力をアピールするなら、最適の資格です。
試験は3月、6月、11月の年3回実施されており、一般受験と団体受験があります。一般受験は在宅、団体受験は認定機関が試験会場です。
医療事務検定試験
医療事務検定試験は、日本医療事務協会が認定する医療事務講座の修了が受験条件の資格です。
通信コースと通学コースがあり、どちらも自宅で受験できます。
通学コースは年6回、通信コースは毎月試験が実施されており、費用は掛かりますが合格率90%程度で効率的な資格の取得が可能です。
基本的な医療事務の知識とスキルを証明したい人におすすめです。
医療事務の資格を合格するまでに必要な期間
当然ですが、医療事務の資格の取得までにかかる時間は、就職したい職場や勉強方法により大きく変わってきます。
医療事務には医科・歯科・調剤と3種類があり、それぞれ働く場所が異なります。病院やクリニックで働きたいなら医科ですが、デンタルクリニックなら歯科の勉強が必要です。
薬局で事務をしたいなら調剤の知識が求められるでしょう。
医療事務の資格も医科・歯科・調剤で分かれており、合格率や試験内容に違いがあります。
また、医療事務の資格は難易度に幅があります。合格率80%の資格なら200時間、合格率30%の診療報酬請求事務能力認定試験は600時間の勉強時間が目安です。
勉強法としては、次のような選択肢があります。
- 通信講座
- 通学講座
- 専門学校
- 短期大学
専門学校や短期大学は1~2年在学し、医療事務の資格を取得します。
通信講座や通学講座は資格取得に特化したコースが用意されており、受講期間に幅があります。たとえば、代表的な医療事務資格の医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®)の合格に必要な期間は3~6ヶ月です。
通信講座・通学講座の場合
通信講座や通学講座は、講座受講者の資格取得に特化してカリキュラムが組まれていることもあり、比較的短期間での取得が目指せます。
最短1ヶ月から半年程度を見積もっておくと良いでしょう。
専門学校・短期大学の場合
専門学校や短期大学は資格以外のビジネススキルや臨床医学などの学習も含まれており、卒業要件を満たすためには1年から2年必要となります。
社会人ではなく、学生がこれから医療系の仕事を目指したい、という時に選択肢に入る方法です。
在学中のどのタイミングで資格取得を目指せるかは学校のスケジュールによって変わります。
独学の場合
独学の場合は、スケジュールも学習方法も自身で設定できますので、資格試験に合格するまでの期間は人それぞれです。
人によっては独学の勉強方法が合わず、合格まで時間がかかる人や、通信講座・通学講座に切り替える人もいます。
医療事務における資格の取り方の手順
医療事務の資格の取り方をまとめました。
上記のような手順で進めていただければ失敗がありません。後悔したくない方は、ぜひ参考にしてください。
(1)取得を目指す資格を決める
医療事務の資格は膨大な数があります。将来のキャリアで後悔しないためにも、まず自分がどの資格を取得したいのかを決める必要があります。
未経験の人なら、知名度が高く医療業界からの信頼が高い「医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®)」や、「医療事務認定実務者®」が最適です。
すでに就業中の方は、業務の生産性向上に繋がる資格、給料アップの可能性がある資格を選ぶと良いでしょう。
就職・転職活動中なら、キャリアアップを目指せる資格や募集要項に記載されている資格を選ぶなど、状況に合わせて選ぶのがおすすめです。
たとえば、「診療報酬請求事務能力認定試験」や「医療事務管理士技能認定試験」は資格手当やキャリアアップにつながりやすい資格です。
とはいえ、取りたい資格が決まっても、資格の合格を目指せる通信講座やスクールを探すのは大変ですよね。
BrushUP学びであれば、医療事務講座・スクールの資料を一括で請求できます。費用や教材をまとめて比較したい方は、ぜひ活用してください。
(2)試験日・申し込み期日を調べる
目標とする資格を決めた後は、主催している団体の公式サイトなどで試験日と申し込み期日を調べましょう。
年に数回のみ実施される試験もあれば、毎月試験が実施される資格もあります。試験勉強は試験日から逆算してスケジュールを組むので、日程の把握は必須です。
通信講座や通学講座を利用する場合も、試験日に合ったスケジュール・カリキュラムの講座に申し込む必要があります。
(3)受験申込書・受験費用を用意する
スケジュールの確認を済ませたあとは、受験申込書と受験費用を用意しましょう。
受験申込に必要な書類は主催団体の公式サイトの指示に従って手続きを済ませてください。書類郵送・ネット申込・講座で申込用紙提出など、主催団体や資格ごとに異なるので注意が必要です。
受験料も、振り込みやクレジットなどで期日までに支払いを済ませます。
不明な点がある場合は、必ずメールや電話で問い合わせ、確実に受験できるようにしましょう。
(4)試験本番に挑む
以上の準備を終えたあとは、いよいよ試験本番です。
受験要綱を確認のうえ、試験に挑みましょう。試験会場への移動、筆記用具の用意など、万全の体制を整えることが大事です。
基本的に医療事務の資格試験は、資料やテキストの持ち込みが許可されているので、忘れずに持参しましょう。
(5)合格発表・合格証を待つ
受験が終了したあとは、合格発表を待つのみです。
およそ試験後1ヶ月以内に結果通知が届きます。合格証が資格取得の証になりますので、大切に保管しましょう。
関連記事 医療事務の資格取得までを3分の動画でわかりやすく紹介!
働きながら医療事務資格を取るにはどうすればいい?
仕事をしている人は勉強時間の確保が難しく、医療事務の資格が取れるか不安な人もいるでしょう。
そのような人には、医療事務の資格取得を目的とした通学講座と通信講座の利用がおすすめです。
独学は自分でスケジュールを立てて勉強します。しかし、働いていると残業があったり、仕事で疲れたりで、スケジュール通りに進まないものです。
通学講座は学校に通うので予定に組み込んでしまえば、働きながらでも合格を目指せます。また、通信講座は自主性が必要ですが、隙間時間に勉強できるのが魅力です。
仕事との両立は通信講座がオススメ
通信講座は、試験合格のために講座が作られているので、無駄がありません。勉強が効率的に進められ、仕事とメリハリがつけやすいのでおすすめです。
Webを視聴するタイプの通信講座なら、バスや電車内などスマートフォンやタブレットでどこでも受講できます。
たとえば、ニチイの医療事務講座(医科)通信コースは、Webで受講や質問ができます。
また、テキストさえあればどこでも勉強が進められるので、持ち歩いて仕事の休憩時間や空き時間に予習・復習をすることも可能です。
通信講座の平均的な受講期間は3~6ヶ月程度ですが、学習ペースに応じて1年くらいまでは延ばすことができる講座もあります。
仕事によっては繁忙期のある人や、急な残業がある人など、仕事が忙しい人でも無理なく対応できる勉強方法といえるでしょう。
通学講座も工夫次第で仕事と両立できる
通学講座も、やり方次第で仕事との両立が可能です。
たとえば、平日に仕事をしている人であれば、土日に集中して学べるコースを選ぶという方法があります。1回の授業時間数は約4時間と比較的長くはなりますが、少ない通学日数で勉強を進められるので効率的です。
また、通学講座によっては夜間コースがあり、仕事帰りに学校に通えます。毎週決まった曜日に授業に通うだけなら、意外と負担にならないでしょう。
ニチイの医療事務講座を例にとると、午前・午後・夜間・土・日など豊富なクラスが用意されています。
講座によっては、振り替え受講システムが利用できるところもあります。「急に残業が発生してしまった」といった状況でも一定期間内に受講しなおすことができるので、受講料をムダにしてしまうこともありません。
通学講座は対面で講師に教えてもらえるので質問がしやすかったり、仲間がいるのでモチベーションが維持しやすかったりといったメリットもあります。
より知識を高めるならプラスアルファの講座受講も検討しよう
医療事務の資格に合格してから、さらに深い知識を求めて、取得した資格とは異なる医療事務講座を受講される方もいます。
具体的には、次のような例があります。
- 医療事務コンピュータ・電子カルテ講座
- レセプトチェック講座
- メディカルマナー講座
これらは、医療事務の基礎的な知識をより深く専門的に学ぶための講座です。
医療事務として働き始めると日々忙しく、専門分野をじっくり突き詰めて学ぶ機会はなかなかありません。
未経験者の場合は、そういったことを踏まえて、就職活動の時期をずらしてプラスアルファの講座を受講しておけば、採用時の強力なアドバンテージになるでしょう。
また、すでに医療事務として働いている人にも、スキルアップの良い機会になります。転職を考えている人なら経験と資格は強力な武器になるでしょう。
関連記事 医療事務になるために勉強するべきことまとめ|独学でも合格できる?勉強のコツ
医療事務講座の受講から就職までの流れ
医療事務講座を受講してから就職するまでの流れは、次のようになります。
- (1)資料請求する
- (2)講座に申し込む
- (3)講座を受講する
- (4)受験し、合格を目指す
- (5)就職・転職活動をする
通学講座も通信講座も、就職サポートがついている場合があります。
中には、就職先を紹介してもらえたり、アドバイザーに悩み相談ができたりと手厚いサポートを売りにしている講座もあるので、比較検討してみましょう。
通学講座の受講の流れ
(1)資料請求をする
インターネットや学校に置いてあるチラシなどから通学講座を探し、気になったものは資料請求をしましょう。
講座によっては自分に適した講座やスケジュールの提案を一緒に送付してくれることもあり、受講のイメージがわきやすくなります。
BrushUP学びは、医療事務の通学講座の一括資料請求が可能です。
2~3分の手続きで、さまざまな医療事務講座・スクールの情報がまとめて手に入りますので、ぜひご活用ください。
(2)無料説明会や体験受講に参加する
受講したい講座がある程度しぼれてきたら、無料説明会や体験受講に参加してみましょう。
医療事務という仕事やカリキュラムについて詳細に解説してもらえます。
(3)講座を申し込む
受講したい講座が決まったら、申し込みをします。
受講料は5~10万円と幅があります。資格の種類や学校によって異なるので、事前によく調べましょう。
受講料については、厚生労働省指定の「一般教育訓練給付制度」や「母子家庭等自立支援教育訓練給付金制度」などで補助を得られる可能性もあります。
自分が対象になるのかどうかを確認して、申請してみましょう。
(4)コースを選び受講する
授業は週1~2回が多いようです。
1日4時間の受講で集中的に勉強するコース、平日の午前または午後のみに受講するコース、土日のみの受講コースなど、自分のライフスタイルに合わせてコースを選択することができます。
(5)受験して合格をする
すべてのカリキュラムを修了したら、別途受験料を支払い資格試験を受験します。
合格すれば、晴れて資格認定となります。
(6)就職・転職活動をする
資格を取得したら、就職・転職活動を開始します。求人雑誌や求人サイトで自分の条件に合ったものを探します。
通信講座の受講の流れ
(1)資料請求する
通学講座と同様、インターネットなどで通信講座を探し、資料請求をしましょう。
わからないことが出てきたときのフォロー体制、就職サポートの充実度など、詳細をチェックしておくと安心です。
BrushUP学びの一括資料請求では、サポートが充実した通信講座を多数掲載しています。
(2)講座に申し込む
どの講座にするか決まったら、講座に申し込みをします。通学講座に比べると通信講座は比較的安価で、15,000~50,000円が目安です。
(3)講座を受講しレポートを提出し課題を終える
通信講座はオンラインまたはDVDなどを視聴しながら授業を進めるスタイルです。
通信講座によっては、メール・オンライン・電話で講師に質問ができます。質問できる体制かどうかは、事前に調べておきましょう。
3~4回のレポート提出のあと、修了課題が出され、これをクリアすると、すべてのカリキュラムが修了となります。
受講開始から資格取得までの期間は、約半年が目安です。
(4)在宅で受験し、合格を目指す
修了後は、在宅もしくは指定の会場にて資格試験を受験します。
資格試験では教材の持ち込みが可能ですので、しっかり持ち込むものを準備した上で試験に望みましょう。合格すると、資格認定となります。
(5)就職・転職活動をする
資格を取得したら、できるだけ早く就職・転職活動を開始しましょう。医療事務の知識は新しいほど評価されます。
就職サポートを利用して好条件で就職を目指す
通学講座も通信講座も、就職サポートがついている場合があります。
資格を主催している団体の関連企業や、希望に応じた就職先の紹介をしてくれるので、自分で求人を探すより効率的です。初めて医療事務の職を目指す人にとっては、非常に心強いサポートと言えるでしょう。
さらにサポートが手厚い所だと、アドバイザーが就業初日に同行してくれたり、就業後のスキルアップや悩み相談にも応じてもらえたりする場合もあります。
自分のキャリアプランを長い目で考え、必要なサポートが受けられる講座を選ぶようにしましょう。
監修者プロフィール
東京三洋電気株式会社エレクトロニクス事業部マイコン応用センター退社後、レセプト専用コンピュータ(医科・調剤)販売会社入社。インストラクターに転身。
その後、一時中断をはさみ、2009年から医療事務講師を務める。
現在は横浜医療情報専門学校、神田外語学院(医薬通訳を学ぶ学生対象)の非常勤講師、医科診療報酬検定試験の作問委員、レセプト点検に携わっている。
【保有資格】
・診療情報管理士
・診療報酬請求事務能力認定試験(医科)
・在宅診療報酬管理士
・調剤事務管理士
・介護事務管理士
・医師事務作業補助者基礎知識研修終了証明書(日本病院会)
【代表著書】 「初級者のための診療報酬完全マスタードリル」 医学通信社ほか
試験データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資格・試験名 | 医療事務管理士技能認定試験 |
| 試験日 |
【インターネット試験】 【2025年6月 在宅試験】 【2025年7月 在宅試験】 【2025年8月 在宅試験】 |
| 試験区分 | 民間資格 |
| 主催団体 | JSMA技能認定振興協会 |
| 受験資格 | 特になし |
| 合格率 | 50%前後 |
| 出題内容・形式 | ▽学科・・・マークシート形式10問 1.法規(医療保険制度・公費負担医療制度等についての知識) 2.保険請求事務(診療報酬点数の算定・診療報酬明細書の作成・医療用語等の知識) 3.医学一般(臓器・生理機能・傷病等についての知識) ▽実技・・・3問 1.レセプト点検問題(1問) 2.レセプト作成(外来・入院 各1問) |
| 検定料 | 7,500円(税込)(学科・実技) |
| 問い合わせ先 |
JSMA技能認定振興協会 https://www.ginou.co.jp/qualifications/iryojimu.html 〒108-8210 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟 12F TEL:03-4363-4518 (平日11:00~15:00) |
医療事務を目指す上でよくある質問
- Q.医療事務の資格はいらないって本当?
- A.
医療事務の仕事は資格がなくても就業できます。
しかし、医療事務の資格は取得することで多くのメリットが得られるため、特別な理由がない限り、資格取得を目指すと良いでしょう。
たとえば、時給が高くなったり、資格手当が出たりと給与面で優遇される場合があります。昇進できる可能性もあるため、将来的なキャリアアップを目指すなら、資格はあった方が良いでしょう。
また、資格勉強で医療事務に必要な専門的な知識を学べるため、資格がない人より働くときに精神的な余裕が持てる点で有利です。
- Q.医療事務の資格試験の合格率と難易度は?
- A.
医療事務試験には多くの種類がありますが、難易度と合格率はそれぞれ異なります。
代表的な資格である「医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®)」「医療事務管理士技能検定試験」「医科2級医療事務実務能力認定試験」などの資格は、合格率約50~70%です。
通信講座や通学講座を利用した人であれば十分合格が目指せる資格と言えるでしょう。
一方で、「診療報酬請求事務能力認定試験」のような合格率30%前後の難易度の高い資格もあります。
- Q.医療事務の資格でおすすめなのはどれ?
- A.
医療事務の資格は働きたい場所に合わせて取得するのが良いでしょう。
クリニックや診療所、病院、介護施設など、職場によって求められる能力・知識が異なるからです。
医療事務の業務全般のスキルをアピールするなら「医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®)」がおすすめです。
スキルアップや給与アップを目指す人は、資格手当が出ることの多い「診療報酬請求事務能力認定試験」の取得を目指すと良いでしょう。
- Q.医療事務の仕事は大変なの?
- A.
医療事務の仕事は覚えること、やることが膨大で、楽な仕事とは言えません。
窓口として患者と接する機会が多い分、クレームや医師・看護師に対する苦情を言われることもあります。
関連記事 医療事務はきつい・つらいって本当?先輩スタッフの声からわかる仕事の大変さ
しかし、大変だからこそ、やりがいもあるのが医療事務の仕事です。
レセプト業務やカルテのデータ入力などは専門性が高く、働き続けるうちに成長を実感できるでしょう。
また受付を通して、患者に感謝や喜びを伝えられることもあります。「誰かの助けになっている」という実感は、人生の充実感につながります。子どもにも自慢できる仕事と言えるでしょう。
向上心のある人や社会貢献したい人にとって、医療事務は理想の仕事と言えるでしょう。

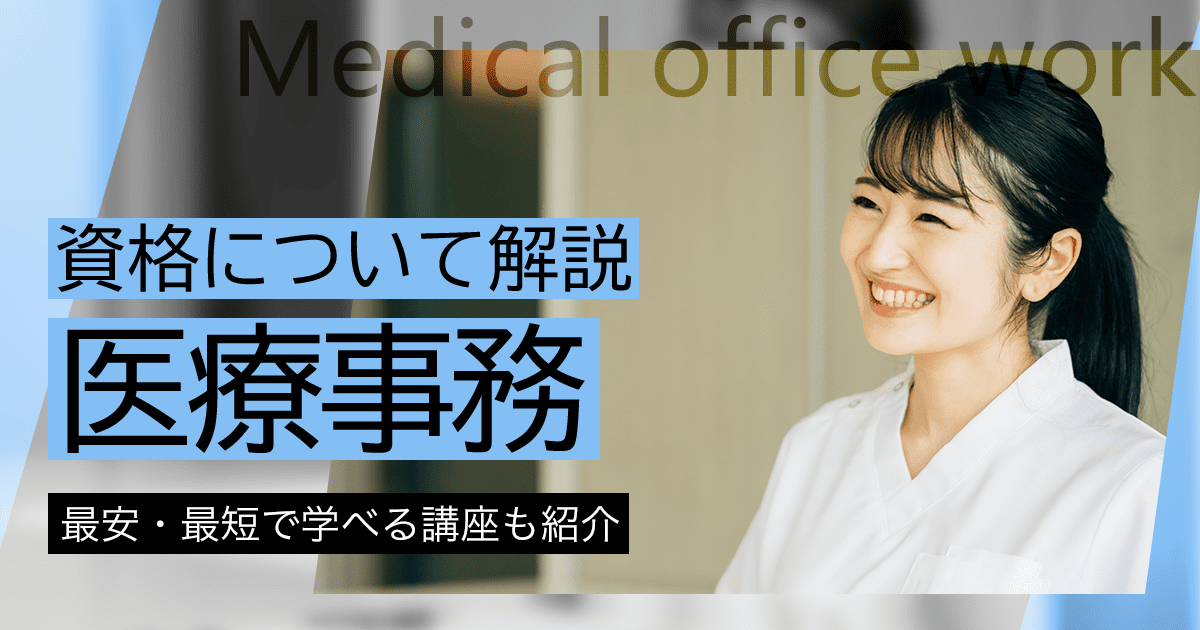
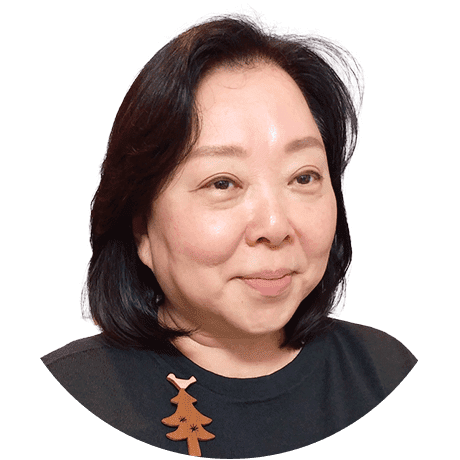

 【3/31まで!受講料割引キャンペーン】実績ある医療事務講座で、安定して働ける医療事務職を目指そう!
【3/31まで!受講料割引キャンペーン】実績ある医療事務講座で、安定して働ける医療事務職を目指そう!
 30代女性の転職に有利なおすすめ資格~モデルケースに学ぶPart.2 ~
30代女性の転職に有利なおすすめ資格~モデルケースに学ぶPart.2 ~
 「医療事務」「調剤事務」「介護事務」事務系資格のお仕事の違いと魅力は?
「医療事務」「調剤事務」「介護事務」事務系資格のお仕事の違いと魅力は?
 資格取得で未経験でも就業を目指せる!医療関連のお仕事を紹介します
資格取得で未経験でも就業を目指せる!医療関連のお仕事を紹介します










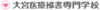











 学びとキャリアのヒント集 ぷらキャリ記事一覧
学びとキャリアのヒント集 ぷらキャリ記事一覧
 腸もみセラピストに聞く「腸もみとの出会い」「腸もみに期待できる効果」とは??
腸もみセラピストに聞く「腸もみとの出会い」「腸もみに期待できる効果」とは??
 キャリアコンサルタント7月試験はまだ先?実は「今」が最後の分かれ道です。
キャリアコンサルタント7月試験はまだ先?実は「今」が最後の分かれ道です。
 【3/1まで!】翻訳の通信講座について、じっくり検討できる「カウンセリング」受付中!
【3/1まで!】翻訳の通信講座について、じっくり検討できる「カウンセリング」受付中!
 介護・福祉分野に興味がある人が、最初に知っておきたいこと
介護・福祉分野に興味がある人が、最初に知っておきたいこと





