医療事務の資格取得は独学でも可能!

診療報酬請求業務やカルテ入力など専門性の高い仕事が中心の医療事務は、「独学では合格が難しいのでは?」と感じる方も少なくないでしょう。
しかし実際には、医療事務の資格試験の多くは合格率50~80%と比較的やさしく、資料やテキストの持ち込みが認められる試験も多くあります。
自分に合ったテキストを選べば、未経験からでも独学で合格することは十分可能です。
ただし、次のような方には講座利用がおすすめです。
- 確実に合格を目指したい
- 短期で合格したい
- ダラダラ勉強を続けたくない
- 不合格になって受験料を無駄にしたくない
独学にも講座にもそれぞれメリット・デメリットがあります。
お金をかけたくないからという理由だけで独学を選ぶと、思うように学習が進まず後悔したり、途中で挫折してしまうこともあります。
着実に合格を目指したい場合は講座を利用するのもひとつの手段です。
独学は何から始めればいい?医療事務の勉強手順

医療事務の資格を独学で取ろうと決めても、「まず何から始めればいいの?」と迷う人は多いでしょう。
医療事務資格を目指す具体的な流れは次の3ステップになります。
- 受験する医療事務の資格を決める
- 合格までのスケジュールを立てる
- 試験合格を目指し、必要な知識を身につける
受験する医療事務の資格を決める
医療事務の資格には2つの区分があります。
- 医科
- 歯科
医療事務といえば一般的には「医科」です。特に診療科にこだわりがないなら、「医科」の資格を選ぶと良いでしょう。
もし働きたい場所がデンタルクリニックなら、「歯科」、調剤薬局なら「調剤」と目的によって資格の選び方が変わります。
また、医療事務の資格は数多く、基本的なスキルを証明する難易度の低いものから、難しいレベルのものまでさまざまです。
もし、とりたい資格が明確ではない場合は、メディカルクラーク®の資格がオススメです。
医療業界での認知度も高く、比較的取得しやすい資格のため、医療事務を目指す方に人気があります。
関連記事 医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®)とは?難易度や合格率、給料事情もまとめました
関連記事 【おすすめ10選】医療事務の資格を取るならどれがいい?取得する難易度別でまとめました
合格までのスケジュールを立てる
独学は自分のペース都合に合わせて勉強できますが、忙しくてつい勉強を後回しにしてしまったり、ダラダラしてしまったりということもあるでしょう。
医療事務の資格を目指すなら、受験日から逆算して毎日の学習時間を確保することが大切です。
毎日少しずつでもインプットとアウトプットを繰り返して、知識をしっかり定着させましょう。
学習のポイントは次の通りです。
- 日々の学習時間を確保する
- テキストで知識をインプットする
- 問題集でアウトプットを繰り返す
参考までに、通信講座を利用して資格取得を目指す場合、標準学習期間は以下のようになります。
| 資格名 | 受講期間 |
|---|---|
| 医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®) | 3~6ヶ月 |
| 医科 医療事務管理士®技能認定試験 | 5ヶ月 |
| 医療保険士 | 6ヶ月 |
独学は自分のペースで進められる反面、計画どおりに勉強が進まないこともあります。
できれば講座で学ぶ場合よりも、1~2ヶ月ほど余裕を持ったスケジュールを立てるのがおすすめです。
試験合格を目指し、必要な知識を身につける
医療事務の業務は、窓口対応・カルテ整理・会計・診療報酬請求(レセプト作成)など多岐にわたります。
また、医療事務の資格試験では、パソコンスキルを問われる場合もあります。
試験に合格するには、次のような知識やスキルの習得が必要です。
- レセプト業務に関連する知識
- 事務処理能力やパソコン操作のスキル
- 窓口対応に関するスキル
関連記事 医療事務になるには?仕事内容・なるための方法を紹介!
レセプト業務に関連する知識
独学で医療事務資格を目指す場合、最も難しいのはレセプト業務に関する知識を習得することでしょう。
日本の保険診療では、患者が支払うのは1~3割で、残りの7~9割は健康保険組合や共済組合、市区町村が負担します。
患者負担分はその都度請求できますが、残りの保険負担分は一括で請求する必要があります。
この一括請求の作業がレセプト業務です。
医療事務資格の試験では、レセプトの作成や点検について出題されます。
そのため、診療報酬点数表やカルテの読み方など、専門的な知識が不可欠です。
事務処理能力とパソコンスキル
医療事務の資格には、「医療事務OA実務能力認定試験」や「医事コンピュータ能力技能検定試験」など、パソコンスキルを証明するものもあります。
医療現場のIT化が進み、カルテやレセプトの作成も大抵の場合パソコンでおこなわれます。
基本的なパソコン操作は必須です。
さらに、医療事務では事務処理能力も重要です。
書類整理やデータ入力では、正確さとスピードが求められます。
窓口対応に関するスキル
医療事務は、窓口業務などで患者やスタッフと接する機会が多い仕事です。
医療事務の資格試験でも、マナーや接遇スキルが問われる問題があります。
たとえば、「患者から質問された時にどう対応するのか」を問う内容などです。
ポイントは以下の通りです。
- 患者の質問に正確に答えられる
- 待ち時間が長くなりそうな場合は座ってもらうなどの配慮ができる
- 丁寧な言葉遣いで接する
- 相手の気持ちに寄り添い、基本的なマナーを守る
さらに、患者の質問に正確に答えるために、保険制度や診療報酬制度などの専門知識が必要になる場合もあります。
医療事務の勉強方法(独学・通学講座・通信講座)とメリット・デメリット
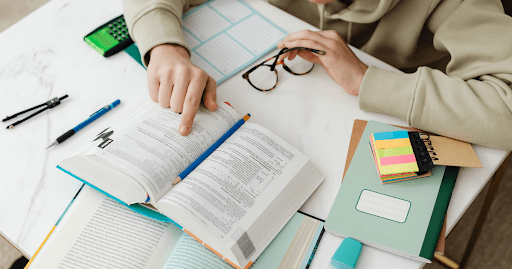
医療事務の資格を目指す方法としては、以下の3つがあげられます。
- 市販のテキストを購入して独学で学ぶ
- 通学講座を受講する
- 通信講座を利用する
それぞれメリット・デメリットがあり、人によって合う勉強方法は異なります。
独学で学ぶ
独学には、次のようなメリット・デメリットがあります。
■独学のメリット
- 費用が抑えられる
- 手軽に始められる
- 自分のペースで勉強できる
■独学のデメリット
- モチベーションの維持が難しい
- わからない点を解決するのに時間がかかる
- 合格まで時間がかかることがある
独学のメリット
独学の最大のメリットは、費用を抑えられる点です。
テキスト代と受験料のみで合格を目指すことができ、お金をかけずに資格を取得したい人には向いている勉強方法と言えます。
また、手軽に始められるのも特徴です。
市販のテキストを購入すればすぐに学習をスタートでき、勉強期間も自分で自由に設定できます。
さらに、仕事や育児などで決まった勉強時間を確保しづらい人でも、自分のライフスタイルに合わせて無理なく学習できるのも独学ならではの利点といえるでしょう。
独学のデメリット
一方で、独学は自分でスケジュールを立てて学習を進める必要があります。
一人でコツコツ勉強するのが苦手な人は、モチベーションを維持できず、なかなか勉強が進まないこともあるでしょう。
また、不明点や疑問点があっても自力で解決しなければならず、理解するまでに時間がかかってしまうことも。
市販のテキストは種類が多いため、自分に合ったものや試験対策に適した教材を選べないと、合格が難しくなることもあります。
特に社会人は仕事で忙しく、勉強時間の確保が困難です。
資格を目指すと決めてから気づけば数年経っていたというケースも少なくありません。
自己管理が得意でない人には、独学での合格は難しいと言えるでしょう。
通学講座を受講する
■通学講座のメリット
- カリキュラムにそって効率的に学べる
- 学習スケジュールを管理してくれる
- わからない点をプロの講師に質問できる
- 仲間と一緒に学べるのでモチベーションを維持しやすい
- 就職サポートを受けられる講座がある
■通学講座のデメリット
- 受講料や交通費などのお金がかかる
- 受講時間が決まっている
- 通える範囲に学校がない場合がある
スクールや通学講座のメリット
通学講座では、医療事務の資格取得を目的としたカリキュラムにそって効率的に学習を進められます。
過去の出題傾向や最新の情報を反映したテキストを使用でき、短期間で合格したい人におすすめの勉強方法です。
また、プロの講師にすぐ質問できる環境なのも大きなメリットです。
わからない点が出てもすぐに解決できるのでストレスが少なく、独学より理解が深まりやすいでしょう。
さらに、同じ目的を持った仲間と一緒に学べるため、一人で勉強するよりもモチベーションを維持しやすくなります。
講座によっては就職相談、求人の紹介など就職サポートが受けられる場合もあり、資格取得後に就転職を考えている方におすすめです。
スクールや通学講座のデメリット
一方で、費用の負担が大きい点は通学講座のデメリットといえるでしょう。
通学講座の費用はおよそ6万円台が目安で、独学で勉強を始める場合に比べると出費が大きくなります。
受講する日程や時間が決まっているため、時間の自由度が低いのも難点です。
また、教室まで通う必要があり、忙しい人には負担になるかもしれません。
学校によっては土日や夜間に学べるコース、短期で資格取得を目指せるコースが用意されている場合もあります。
授業を欠席した際に振替受講ができる講座もあるため、事前に確認しておけば自分のスケジュールに合わせて学ぶことも可能です。
ただし、教室のあるエリアはある程度限られており、お住まいの地域によっては通学できる範囲に教室がない場合もあるでしょう。
一部の講座では教室でおこなっている授業をライブ配信しています。
近くに教室がない方はこういったオンライン受講を利用するのもひとつの手段です。
通信講座を利用する
自分のペースで、なおかつ効率よく学べる医療事務の通信講座も人気があります。
通信講座には以下のようなメリット・デメリットがあります。
■通信講座のメリット
- 通学講座より費用が安い
- 自分のペースで学べる
- メールやオンラインで講師に質問できる
- 就職サポートを受けられる講座がある
■通信講座のデメリット
- 自己管理が必要
- モチベーション維持が難しい
- 通信機器が必要な場合がある
通信講座のメリット
通信講座の費用は3~4万円台が目安で、通学講座に比べて費用を抑えられます。
カリキュラムも通学講座と遜色なく、効率的に学習できる点がメリットです。
受講スタイルはテキストや動画が中心で、自分のライフスタイルに合わせて勉強を進められます。
また、添削課題は解説やアドバイス付きで返却されるため、自分の弱点を把握しやすくなります。
メールやオンラインで講師に質問できる講座も多く、学習上でわからない点があってもすぐに解決できます。
さらに、通信講座の中には求人の紹介や就職相談などの就職サポートが受けられるものもあります。
独学に不安を感じる人や、通学講座ほど費用をかけられない方、教室に通う時間の余裕がない方、就職サポートを受けたい方には通信講座がおすすめです。
通信講座のデメリット
メリットの多い通信講座ですが、いくつかデメリットもあります。
通信講座は独学ほど自己管理が必要ではなく、テキストやカリキュラムは講座側が用意してくれます。
スケジュールどおりに受講すれば、高い確率で試験に合格できるでしょう。
しかし、自宅で学べる気軽さから勉強を後回しにしてしまい、受講期間が過ぎてしまうケースもあります。
一人で学習する環境は独学に似ているため、モチベーションを維持しづらい点もデメリットです。
また、Web通信講座ではスマホ、タブレット、パソコンなどの通信機器が必要です。
医療事務を目指せるおすすめスクール
独学で医療事務の資格取得を目指す場合の難易度は?
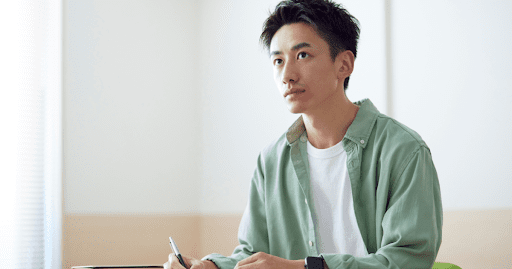
医療事務は資格の種類によって難易度が異なります。
合格率が高い資格は試験対策がしやすく、比較的、難易度が低いといえるでしょう。
代表的な医療事務資格を3つ比較すると、その差がはっきりと分かります。
| 資格名 | 受験日 | 合格率 |
|---|---|---|
| 医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®) | 土日を中心にほぼ毎週 | 60~70% |
| 医科 医療事務管理士®技能認定試験 | いつでも受験可能 (※インターネット試験の場合) |
50% |
| 診療報酬請求事務能力認定試験 | 年2回 | 30% |
また、試験日が多く設定されている資格は受験のチャンスが増えるため挑戦しやすく、合格の可能性も高まります。
ただし、合格率が高い=必ずしも試験が簡単というわけではありません。
たとえば「医療事務検定試験」は合格率が90%と非常に高いですが、基本的に主催団体の講座を受講した人が受験しています。
講座でしっかり対策を行っているからこそ、高い合格率につながっているのです。
独学で医療事務の資格取得を目指す場合は、受験資格などもしっかり確認しておきましょう。
関連記事 医療事務の資格試験の合格率は?自分にあった医療事務の資格を取ろう!
医療事務試験の短期合格を目指すなら講座・スクールの利用がおすすめ
短期間で資格取得を目指すなら、講座・スクールの利用が効果的です。
試験に合わせたカリキュラムやテキストが用意されており、効率的に学ぶことができます。
以下に医療事務の代表的な講座・スクールを紹介します。
▼通学講座
| 講座名(スクール名) | 目指せる資格 |
|---|---|
| 医療事務講座 (医科)通学コース (ニチイ) | メディカル クラーク(R) (医療事務技能審査試験) |
| 医療事務講座通学コース (日本医療事務協会) | 医療事務検定試験 |
▼通信講座
| 講座名(スクール名) | 目指せる資格 |
|---|---|
| 医療事務講座(医科)通信コース (ニチイ) | メディカル クラーク(R) (医療事務技能審査試験) |
| 医療事務講座通信コース (日本医療事務協会) | 医療事務検定試験 |
| 【通信】医療事務講座 eラーニングコース (ヒューマンアカデミー) | 医療事務認定実務者(R) |
| 医療事務講座[6C] (生涯学習のユーキャン) | 医療事務認定実務者(R) |
医療事務の独学勉強でよくある質問

医療事務の資格取得を独学で目指す際によくある質問について、Q&A形式でまとめました。
- 医療事務で一番難しい資格試験はどれ?
- 独学におすすめのテキストは?
- 合格を目指すには1日何時間勉強すればいいの?
- そもそも医療事務の資格取得に意味はあるの?
医療事務で一番難しい資格試験はどれ?
数ある医療事務資格の中で最難関とされるのは、合格率約30%の診療報酬請求事務能力認定試験です。
診療報酬請求業務(レセプト作成)のスキルを問う試験で、医療に関する法規や保険制度など幅広い範囲から出題されます。2023年の合格ラインは学科が70点以上、実技が85点以上と高く設定されています。また、試験の実施は年2回しかありません。
難易度は高めですが、資格手当の対象になったり、就職・転職活動で有利になったりと、持っているとさまざまなメリットのある資格です。
関連記事 診療報酬請求事務能力認定試験の内容は?合格率や難易度について
※診療報酬請求事務能力認定試験は、2025年12月をもって終了予定です。
独学におすすめのテキストは?
医療事務のテキストや問題集は書店やオンラインで購入することができます。
資格によっては公式テキストや推奨書籍を紹介している場合がありますので、まずは試験団体のHPをチェックするといいでしょう。
資格に対応した通学講座や通信講座のテキストを活用するのも効果的です。
試験に合わせて作られているため、資格取得に向けて効率的に学習を進められます。
講座によっては受講しなくても問題集などを購入できる場合があるので、確認してみるとよいでしょう。
合格を目指すには1日何時間勉強すればいいの?
医療事務の資格取得を目指すにあたって、必要な勉強時間は資格の種類などによって異なります。
初心者から合格を目指す場合、合格率が80%以上の比較的やさしい資格で、学習時間の目安はおよそ200時間です。
1日1時間ずつ勉強を続けた場合で、合格までには約6〜7か月かかる計算になります。
平日は30分、休日は2〜3時間など、自分の生活リズムに合わせて計画を立てるのもおすすめです。
試験日から逆算して1日の学習時間を決めるとよいでしょう。
忙しい日でも、5分、10分と短い時間で構いません。スキマ時間をうまく使い、勉強を日課にすることが合格への近道です。
短期間で合格を狙う場合は、通信講座を活用して効率的に学ぶのもおすすめです。
関連記事 医療事務の資格試験の合格率は?自分にあった医療事務の資格を取ろう!
そもそも医療事務の資格取得に意味はあるの?
「医療事務の資格を取得しても意味がない」といわれることがあります。
実際に、資格を取っても就職や転職で苦労したり、現場であまり役立たなかったと感じる人がいるのも事実です。
しかし、資格を持っていることは努力や学習意欲の証明となり、無資格・未経験の人よりも書類選考や面接で有利になる可能性があります。
さらに、医療事務の知識や専門用語は共通しているため、まったく知識がない状態よりも仕事を始めやすく、スムーズに業務に入れるでしょう。学んで損をすることはありません。
関連記事 医療事務の資格は意味がない・いらないと言われる理由は?取得のメリット・デメリットまとめ
まとめ

医療事務の資格は独学でも取得可能です。
基本的な学習手順を押さえれば自宅学習でも十分合格を目指せます。
ただし、試験によって難易度は異なり、効率よく短期合格を狙うなら講座やスクールの活用も有効です。
自分の目的や状況に合わせて学習方法を選びましょう。


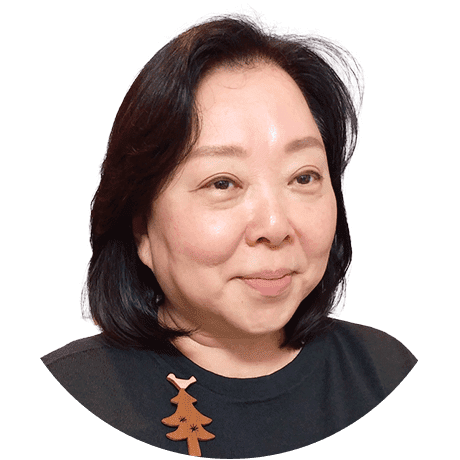


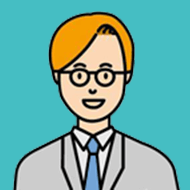
 【3/31まで!受講料割引キャンペーン】実績ある医療事務講座で、安定して働ける医療事務職を目指そう!
【3/31まで!受講料割引キャンペーン】実績ある医療事務講座で、安定して働ける医療事務職を目指そう!
 30代女性の転職に有利なおすすめ資格~モデルケースに学ぶPart.2 ~
30代女性の転職に有利なおすすめ資格~モデルケースに学ぶPart.2 ~
 「医療事務」「調剤事務」「介護事務」事務系資格のお仕事の違いと魅力は?
「医療事務」「調剤事務」「介護事務」事務系資格のお仕事の違いと魅力は?
 資格取得で未経験でも就業を目指せる!医療関連のお仕事を紹介します
資格取得で未経験でも就業を目指せる!医療関連のお仕事を紹介します








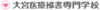











 受講料10%OFF!6万円分プレゼント特典付き!年末年始学習応援キャンペーン実施中(1月開催/全国)
受講料10%OFF!6万円分プレゼント特典付き!年末年始学習応援キャンペーン実施中(1月開催/全国)
 動き出す人は、もう準備している。国家資格で差がつく1年へ!
動き出す人は、もう準備している。国家資格で差がつく1年へ!
 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
 人気のZUMBAインストラクターになろう!動画orライブ配信トレーニングが選べる&今だけ50%OFF!
人気のZUMBAインストラクターになろう!動画orライブ配信トレーニングが選べる&今だけ50%OFF!
 メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】





