レセプト業務とは?

診療費を計算し診療報酬明細書を作成する
レセプトはドイツ語で、つづりはRezept、英語ではreceiptにあたります。
レシートと言われれば想像しやすいのではないでしょうか。
レシートが購入した商品やサービスの明細を表すのに対し、レセプトは診療行為などを記載した明細書です。
まず診療行為を終えた患者のカルテにある診療内容から、項目別に点数に置き換えて診療費を計算します。
患者の自己負担分については窓口で請求し、その後、医療機関が保険者に請求するための診療報酬明細書(レセプト)を作成します。
医療機関の収入に直結する、非常に重要な業務です。
国民皆保険制度
現在日本では、国民皆保険制度が採られており、患者は通常、健康保険組合、共済組合、市町村などが発行した被保険者証をを提出して診療を受けます。
この際、患者が窓口で支払うお金は医療機関が診療行為の対価として受け取る診療報酬の最大3割になっており、残り7割以上は、健康保険組合や共済組合、市町村などの保険者が負担するしくみになっています。
レセプト業務は医療機関が健康保険組合や市区町村などの保険者に残り7割の部分を保険者に請求する仕事です。
診療報酬が払われる仕組み
レセプト業務には診療報酬が大きく関わるわけですが、その診療報酬がどのような仕組みで支払われているのか見ていきましょう。
保険診療の場合
診療報酬のうち3割を患者、残り7割の部分を健康組合、共済組合、市町村などの保険者に請求しています。
患者への請求は窓口で行うことができますが、残り7割、健康組合や共済組合、市町村への請求をその都度行うことは困難なので、残り7割については1ヶ月ごとにまとめて請求する仕組みになっています。
審査支払機関に診療報酬を請求する
また、請求する際ですが、医療機関が直接、保険者に請求するわけではありません。
医療機関と保険者の間に「国民健康保険団体連合会」「社会保険診療報酬支払基金」という、審査支払機関があり、そこに診療報酬の請求をするしくみになっています。
この時、提出しなければいけない書類が「診療報酬請求書」「診療報酬明細書(レセプト)」です。
診療報酬請求書はその名の通り請求書になり、レセプトは、患者の被保険者証の情報や医療機関名、傷病名、診療行為の内容や処方した薬などが記載されています。
不備がなければ各保険者に診療報酬を請求
その後、審査支払機関の方で、提出された診療報酬請求書とレセプトを審査し、請求内容に不備がなければ健康保険組合、共済組合、市区町村に診療報酬を請求します。
審査支払機関からの請求を受けて、健康保険組合、共済組合、市区町村は審査支払機関を通して医療機関に診療報酬を支払うかたちになります。
書類の不備に注意
請求内容に不備があれば、審査が通らないことや報酬が少なくなってしまうこともあり、医療機関の収入に大きな問題が発生します。
提出した書類の内容の間違いが悪質だと判断された場合には、不正請求とみなされて刑事罰の対象になることもありますので、責任の重い仕事といえるでしょう。
レセプト業務の流れ
レセプト業務の内容、流れを確認する前にあらかじめ知っておくべきポイントがあります。
1つ目はレセプトの提出期限です。
レセプトの期限は翌月10日まで
医療機関が審査支払機関へ提出する診療報酬請求書とレセプトは、診療行為をおこなった翌月の10日までと定められています。
そのため、レセプト業務は月末から翌月初めにかけて集中的におこなうのが一般的です。
次に、レセプトの作成方法と提出方法についてです。
レセプトの作成・提出方法
レセプトは、主に以下の4ついずれかの方法で作成・提出されています。
- 手書きで作成して、郵送で提出する
- レセプトコンピューター(レセコン)で作成し、プリントアウトして提出する
- レセコンで作成して、そのデータを保存した記録媒体を提出する
- レセコンで作成して、そのデータをオンライン上で審査支払機関に送信する方法
STEP1:診療内容をレセプトコンピューター(レセコン)に入力
レセプトコンピュータに診療内容を入力します。
この作業は毎日の窓口会計業務と共ともに実施します。
診療内容ごとにレセコンにコード入力することで、診療報酬点数が自動的に計算される仕組みになっています。
通常、外来患者は来院するたびに、入院患者の場合は、医療機関によって違いがありますが、退院までにまとめて入力することが多いです。
STEP2:レセプトの作成(出力)
STEP2からは審査支払機関への提出期限に合わせて作業が行われます。
各患者ごとに、1ヶ月間の診療内容と診療報酬を記録したレセプトの作成をします。
STEP1で入力した診療内容は自動で集計・計算されます。
日々の入力作業でミスがあるとレセプト請求にも誤りが出てしまうので注意が必要です。
STEP3:レセプトの点検・確認作業
発行したレセプに不備や誤りがないかを点検・確認します。レセプト提出前に行う重要な作業です。
日々注意して診療内容を入力していても、人間の作業である以上、ミスが完全に防げるわけではありません。
カルテの内容を見誤ったり、レセコンへの誤入力がないかを確認する作業が必要になります。
この作業が適切に実施されていない場合、審査支払機関への請求が通らず、医療機関の収入に大きく影響します。
STEP4:医師によるレセプトの確認
万が一、レセプトに記録されている診療行為、処方薬、傷病名に整合性が取れていない場合は医師による確認が必要です。
医師により不整合な点が確認された場合は、レセプトを修正し、再度医師に確認を受けます。
STEP5:審査支払機関に提出
診療行為を行った翌月1日~10日までに、作成した診療報酬請求書とレセプトを審査支払機関に提出します。
ここで、記載内容に不備や誤りが見つかると、提出した書類の返戻もしくは診療報酬点数の減点が行われ、再提出が必要になりますので注意しましょう。
レセプト業務は未経験者には難しい?
全くの未経験には難しい
レセプト業務は専門知識や用語の理解が必要で、病院の診療報酬などお金に関わる重要な仕事です。
そのため、全くの未経験ではすぐに業務をこなすのは難しいでしょう。
まずは日々の業務に慣れることから始めます。
勉強は必要
最初は窓口業務に慣れ、レセコンへの入力を覚えながら経験を積む必要があります。
未経験でも採用されることはありますが、レセプト作成や点検の業務は基礎知識がない場合、すぐには任せてもらえません。
レセプト業務を正確に、スムーズにおこなえるようにするには、勉強は欠かせません。
医療事務を目指せるおすすめスクール
レセプト業務には資格が必要
レセプト業務には正しい知識が必要
レセプト業務は医療機関の経営を支える重要な仕事です。
作成や確認には専門的な知識や経験が必要とされます。
レセプト業務に就くのに資格は必須ではありませんが、正しい知識を身につけるための講座や資格も用意されています。
資格取得を通じて必要な知識を身につければ、自信を持ってレセプト業務に取り組めるようになるでしょう。
レセプト業務に関連する、代表的な医療事務資格を3つご紹介します。
上から順番に難易度が高くなっています。
レセプトに関連する医療事務資格
- 医療事務管理士
- 医療事務実務能力認定試験
- 医療事務技能審査試験
医療事務管理士
医療事務管理士は技能認定振興協会(JSMA)が認定する資格です。
実技試験と学科試験があり、実技では診療報酬明細書(レセプト)点検や作成について出題されます。
試験はインターネット試験(IBT方式)か、ペーパー試験(マークシート方式)のいずれかを選択可能。
どちらも在宅で試験を受けられます。
インターネット試験はいつでも都合のよい時間に受験が可能。
ペーパー試験については月1回の実施となります。
合格率は50%程度と、医療事務の資格のなかではやや難易度が高いといえます。
関連記事 医療事務管理士技能認定試験とは?独学でも合格できる?難易度は?
医科2級 医療事務実務能力認定試験
医科2級医療事務実務能力認定試験は、全国医療福祉教育協会が主催する試験です。
試験には学科問題と実技問題があります。
学科試験はマークシート方式、実技では診療報酬明細書作成の問題が2問出題され、実際のレセプト作成力が問われます。
試験は年3回。個人で受験する場合は在宅受験となり、試験団体から送付される問題用紙・解答用紙を使用して試験を受けます。
合格率はおおむね60%~80%となっており、知識をしっかり身につければ合格は十分可能です。
医療事務技能審査試験(メディカル クラーク®)
医療事務技能審査試験は一般財団法人 日本医療教育財団が主催する試験です。
試験に合格するとメディカル クラーク®の称号が与えられます。
試験はインターネットで受験できるIBT方式で、在宅での受験が可能。
診療報酬明細書の作成や基本診療料および特掲診療料の項目ごとの計算などについて出題されます。
試験は土日を中心にほぼ毎週実施されており、合格率は60~70%ほどです。
関連記事 医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®)とは?難易度や合格率、給料事情もまとめました
関連記事 【おすすめ10選】医療事務の資格を取るならどれがいい?取得する難易度別でまとめました
レセプト業務でスキルアップするには
(1)資格取得や研修・講座を受講する
専門的な知識を体系的に学ぶには、資格取得や講座の受講が効果的です。
基礎から実務に役立つ知識まで幅広く学べるため、理解が深まり、自信を持ってレセプト業務に取り組めるようになります。
資格があれば就職や転職時にも有利に働くでしょう。
(2)多くの経験を積む
レセプト業務は知識だけでなく、実際の現場での経験が大きな力になります。
日々の入力や点検作業を通じて、少しずつ正確さやスピードが身につきます。
業務の中で多くの症例やケースに触れることで応用力が鍛えられ、自然とスキルアップにつながります。
(3)大きな病院へ転職
小規模なクリニックや診療所では、経験できる業務や扱う症例に限りがあります。
より多くのケースや複雑なレセプト業務を経験するには、複数の診療科を持つ大きな病院で働くことが効果的です。
扱う病名や処方薬の種類も増えるため、幅広い知識を身につけられ、実践的なスキルを磨けます。
資格取得や研修で学びを積み重ね、小規模医療機関から大規模病院へ転職することは、スキルアップだけでなくキャリアアップにもつながります。
まとめ
レセプト業務は、医療機関の収入を支える重要な仕事です。
レセプトコンピューター(レセコン)により一部は自動化されていますが、業務を正確に遂行するには専門的な知識が欠かせません。
レセプト関連の資格も複数あるので、自分の状況や将来の目標に合わせて選んで学習するとよいでしょう。
毎月発生する業務だからこそ、知識を身につけて自信を持って取り組みたいものですね。
レセプト業務を学べる、医療事務講座も多く開講されています。
興味のある方は、無料で資料請求も可能ですので、ぜひ検討してみてください。
監修者プロフィール
東京三洋電気株式会社エレクトロニクス事業部マイコン応用センター退社後、レセプト専用コンピュータ(医科・調剤)販売会社入社。インストラクターに転身。
その後、一時中断をはさみ、2009年から医療事務講師を務める。・・・ [続きを読む]


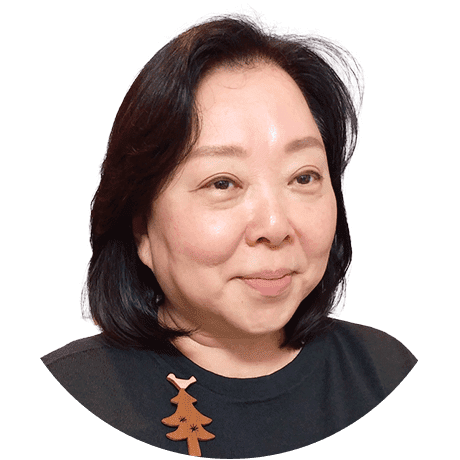


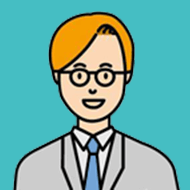
 【3/31まで!受講料割引キャンペーン】実績ある医療事務講座で、安定して働ける医療事務職を目指そう!
【3/31まで!受講料割引キャンペーン】実績ある医療事務講座で、安定して働ける医療事務職を目指そう!
 30代女性の転職に有利なおすすめ資格~モデルケースに学ぶPart.2 ~
30代女性の転職に有利なおすすめ資格~モデルケースに学ぶPart.2 ~
 「医療事務」「調剤事務」「介護事務」事務系資格のお仕事の違いと魅力は?
「医療事務」「調剤事務」「介護事務」事務系資格のお仕事の違いと魅力は?
 資格取得で未経験でも就業を目指せる!医療関連のお仕事を紹介します
資格取得で未経験でも就業を目指せる!医療関連のお仕事を紹介します








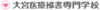











 2026年2月1日掲載の新スクール&特集ページを大紹介!
2026年2月1日掲載の新スクール&特集ページを大紹介!
 人気のZUMBAインストラクターになろう!動画orライブ配信トレーニングが選べる&今だけ50%OFF!
人気のZUMBAインストラクターになろう!動画orライブ配信トレーニングが選べる&今だけ50%OFF!
 メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
 40代・50代からでも大丈夫?キャリアコンサルタント資格の現実
40代・50代からでも大丈夫?キャリアコンサルタント資格の現実
 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定





