社会福祉士が目指せるおすすめスクール
社会福祉士を通信で目指せるの?

社会福祉士は、高齢者や障害者、生活困窮者などが抱える課題に対して相談を受け、社会参加や日常生活の支援を行う国家資格です。
従来は福祉系大学などの通学課程を修了するのが一般的な受験ルートでしたが、現在では通信課程を通じて受験資格を得ることも可能になっています。
- 通信制大学
- 社会福祉士一般養成施設(通信課程)
- 短期養成施設(通信課程)
どのルートを選ぶかは、学歴や実務経験によって異なります。特に、仕事を続けながら資格取得を目指す社会人や、近隣に福祉系大学がない地域に住む方にとって、通信課程は柔軟に学べる実用的な方法といえるでしょう。
通信課程で社会福祉士を目指す3つのルート
通信課程から社会福祉士を目指す方法には大きく分けて3つのルートがあります。自分の学歴や実務経験に応じて最適な道が異なるため、まずはルートの違いを理解することが重要です。
通信制大学に入学して資格を取得するルート
社会福祉士を通信制大学で目指す場合は、厚生労働省が指定する「指定科目」を履修し、卒業することで国家試験の受験資格を得られます。
指定科目には以下のような内容が含まれています。
- ソーシャルワーク(旧・相談援助)
- 社会保障論
- 心理学
- 医学的知識
- 福祉行財政など
これらを通じて、福祉の基礎から実践まで体系的に学べるカリキュラムが用意されています。
このルートは、高校卒業後に大学卒業資格(学士)を取得しつつ、社会福祉士を目指したい人に適しています。大学での学びを通じて、福祉制度や相談援助技術といった基礎力を計画的に習得しやすい点が大きな特徴です。
一般養成施設(通信課程)を利用するルート
すでに一般大学や短期大学を卒業している人は、社会福祉士一般養成施設(通信課程)を利用することで、国家試験の受験資格を得られます。
このルートでは、厚生労働省が指定する専門科目(例:ソーシャルワーク、社会福祉原論、社会保障、心理学、医学的知識、福祉行財政など)を追加履修しながら学習を進めます。
修了までの期間は1年半〜2年程度が一般的で、比較的短期間で受験資格を取得できる点が大きな特徴です。
短期養成施設(通信課程)を利用するルート
すでに介護福祉士や精神保健福祉士といった国家資格を持っている人は、社会福祉士短期養成施設(通信課程)を利用することで、効率的に国家試験の受験資格を取得できます。
このルートは、既存の資格取得時に習得済みとみなされる科目を除外し、不足分のみを履修する仕組みとなっており、通常は6か月〜1年程度で修了できるのが大きな特徴です。
通信課程の特徴と学び方
通信課程で社会福祉士を目指す場合、学習の基本は自宅での独習です。ここでは、通信課程の特徴と学び方に関して解説します。
レポート課題の内容と提出方法
通信課程での学習では、各科目ごとにレポート課題の提出が求められます。課題は、教科書や指定図書で学んだ理論を整理し、それを具体的な事例や現場の状況に当てはめて考察する形式が中心です。
たとえば「ソーシャルワークの基本原則を踏まえた高齢者支援のあり方」や「地域福祉と包括支援体制の連携に関する事例分析」といったテーマが出題されます。
レポートの提出方法は大学や養成施設によって異なりますが、現在はオンライン(Web提出フォームや専用ポータル)が主流で、一部では郵送提出にも対応しています。
スクーリング(対面授業)の頻度と形式
通信課程においても、演習や実技をともなう学習内容は、原則としてスクーリング(対面授業)で補われます。
スクーリングの実施回数や日程は大学や養成施設によって異なり、年に2回程度の集中開催から、月1回ペースで十数回行われるものまでさまざまです。
形式としては、土日や夏期・冬期の連続休暇を活用した2〜4日間の集中講義が多く、働きながら学ぶ社会人でも参加しやすいように工夫されています。
具体的には、開催曜日や地域の選択肢を増やしたり、事前学習資料を提供したりする配慮がなされています。
実習の有無と免除条件
社会福祉士の通信課程では、相談援助実習の履修がすべての学生に原則必須となっています。
2025年度からのカリキュラム改正により、すべての養成ルートで「240時間以上」「2か所以上の実習施設での実施」が義務づけられ、従来のような実習免除や短縮措置は原則廃止されました。
実習では、利用者支援の現場に入り、面接場面の観察や相談記録の作成、支援計画の立案・評価といった一連の援助プロセスを体験します。
さらに、実習指導者との振り返りや実習日誌の作成も課されるため、理論だけでは得られない「実践力」と「専門職としての倫理観」を養う貴重な機会となります。
学習スケジュールと両立の工夫
通信課程は、時間や場所を選ばず自分のペースで学習を進められる自由度の高さが魅力です。しかしその一方で、仕事や家庭との両立が大きな課題になることもあります。特に社会人の場合、日々の業務や家庭の予定に追われ、学習時間を確保するのが難しくなるケースは少なくありません。
学習を継続するためには、毎日決まった時間に短時間でも勉強を取り入れる「学習習慣の定着」が効果的です。たとえば、通勤時間にスマートフォンで講義動画や教材PDFを確認し、週末に数時間まとめてレポート作成に取り組むといった工夫は現実的な方法です。
通信制の学費・費用を徹底比較
社会福祉士を通信で目指す際に多くの人が気にするのが学費です。大学や養成施設によって費用には大きな差があるため、事前に相場や利用できる補助制度を把握しておくことが重要です。
ここからは、通信制で学ぶ際に必要となる学費や関連費用について、詳しく解説していきます。
通信制大学の学費相場
通信制大学に入学して社会福祉士の受験資格を得る場合、年間の学費はおおむね20万〜40万円程度が一般的です。これに入学金(約2万〜3万円)や教材費、スクーリング費、実習費などが加わり、卒業までに必要な総額は100万〜160万円ほどとなります。
通学制大学(4年間で約300万〜400万円)と比べると、通信制は大幅に費用を抑えられる点が大きな魅力です。
一般・短期養成施設の費用相場
すでに大学や短期大学を卒業している人は、社会福祉士国家試験の受験資格を得るために、一般養成施設または短期養成施設を利用できます。
いずれも通信課程を設けているところが多く、自宅学習を中心に進めながら資格取得を目指せるのが特徴です。
一般養成施設(通信課程)の場合、標準的な修了期間は1年半〜2年程度で、学費の目安は60万〜90万円前後(入学金・教材費・スクーリング費・実習費を含む)です。
一方、介護福祉士や精神保健福祉士といった国家資格をすでに取得している人を対象とする短期養成施設では、修了期間は半年〜1年程度と短く、学費も30万〜60万円前後と比較的低く抑えられています。
教育訓練給付金などの補助制度
社会人が通信課程を利用して社会福祉士資格の取得を目指す場合、教育訓練給付制度などの公的支援を活用すれば、学費の負担を大きく軽減できます。
この制度は厚生労働省が所管する雇用保険の給付制度で、講座が認定を受けていれば以下のような支援を受けられます。
| 制度名 | 対象 | 給付内容 | 備考 |
| 教育訓練給付金制度 | 厚生労働省が指定する講座を受講した場合 | 受講料の20%(上限あり) | 一般的な教育訓練講座が対象 |
| 専門実践教育訓練給付金 | 専門性の高い指定講座を受講した場合 | 受講料の最大50% | より専門的・実践的な講座が対象 |
社会福祉士の通信課程の中には、この「専門実践教育訓練給付金」の対象に認定されているものもあり、条件を満たせば100万円以上の支援を受けられるケースもあります。
また、地方自治体が実施する職業訓練支援給付金や、各大学・養成施設が独自に設ける学費分納制度・奨学金制度・減免制度といった補助制度を併用できる場合もあります。
【一覧表】通信制大学・養成施設の学費比較
社会福祉士を通信課程で目指す際に最も気になるのが「学費と学習期間」です。通信制は自宅で学べる自由度の高さが魅力ですが、大学や養成施設によって費用の幅が大きく、さらに
スクーリングや実習にともなう追加費用がかかることもあります。そのため、総額の見積もりと補助制度の確認が欠かせません。
以下に、主な3つの学習ルートと費用・特徴をまとめました。
| 学習ルート | 期間の目安 | 費用相場 | 特徴 |
| 通信制大学 | 約4年 | 100万~160万 | 学位取得と同時に受験資格を得られる |
| 一般養成施設(通信) | 1年半~2年 | 60万~90万 | 大卒者向け、短期間で効率的に受験資格を取得 |
| 短期養成施設(通信) | 半年~1年 | 30万~60万 | 他資格保持者向け、最短ルートで受験資格を取得 |
通信制大学は「学位取得と同時に受験資格を得たい人」に最適です。一般養成施設は「すでに大学を卒業しており、短期間で効率よく受験資格を得たい人」に向いています。
短期養成施設は「介護福祉士や精神保健福祉士などの資格を持つ実務経験者が、最短で受験資格を取得したい場合」に適しています。
自分の学歴・職歴・ライフスタイル・学習目的を踏まえ、「期間・費用・補助制度・最終目標」のバランスから最適なルートを選ぶことが大切です。
社会福祉士の資格取得でおすすめの通信講座
通信課程を選ぶ際は、学習サポートや実績、学費などを比較して選ぶことが重要です。ここでは代表的な通信講座を4つ紹介します。
1.専門学校高崎福祉医療カレッジ
高崎福祉医療カレッジは、社会人や働きながら社会福祉士資格の取得を目指す人に対応した通信課程を設けており、個別フォロー体制の手厚さが特徴です。
学費はおおむね60万〜70万円前後で、一般養成施設(通信課程)の相場範囲に収まります。
ただし、入学金・教材費・スクーリング費・実習費などが別途かかる場合があるため、事前に総額を確認しておくことが重要です。
スクーリングは主に関東エリアで実施され、土日や短期集中形式が多いため、社会人でも参加しやすい日程が組まれています。
受講生からは「質問への対応が迅速で学習を継続しやすい」といった声も寄せられており、学習支援体制の評価が高い点も大きな魅力です。
2.資格の大原(通信課程)
資格の大原は、社会福祉士国家試験の対策に特化した予備校であり、受験資格を得るための養成施設とは異なります。
対象となるのは、すでに受験資格を持ち、合格を目指して効率的に学習したい人です。
学費は講座の内容(通学・通信の組み合わせ、模擬試験や教材パックの有無など)によって異なりますが、おおむね60万円前後で、資格予備校としては平均的な水準です。
全国に校舎があるため、スクーリングや模試を受講しやすく、地方在住者でも利用しやすい点が大きなメリットといえます。
3.日本福祉大学通信教育部
日本福祉大学は、福祉分野で長い教育実績を持つ通信制大学の一つで、社会人や地方在住者から広く利用されています。
年間の授業料はおおむね20万〜30万円程度です。4年間の学習を通じて学士(学位)と社会福祉士国家試験の受験資格を同時に取得できます。
入学金・スクーリング費・実習費などを含めると、総額は100万〜160万円ほどとなり、通学制大学と比べると費用を抑えて学べるのが魅力です。
スクーリングは全国各地で実施され、平日・土日、集中講義など多様な日程が用意されているため、仕事や家庭と両立しやすい点も大きな特徴です。
4.佛教大学通信教育課程
佛教大学は、長年にわたり通信教育課程を運営してきた実績があり、福祉分野の指定科目が豊富に開講されている点で高い評価を得ています。
年間の授業料はおおむね20万円前後と比較的安価で、入学金・教材費・スクーリング費・実習費を含めた総額は100万〜150万円程度が一般的です。通学制大学に比べて費用を抑えながら学べる点が大きな魅力です。
スクーリングは京都を中心に、東京や大阪などの主要都市で開催されており、集中形式や土日開講も用意されています。そのため、地方在住の受講者でも参加しやすい体制が整っています。
通信課程で社会福祉士を目指すメリット
通信課程を利用する大きな魅力は、時間や場所に縛られず柔軟に学習できる点です。特に社会人や家庭を持つ人にとって、働きながら資格取得を目指せる仕組みは大きな利点となります。ここでは具体的なメリットを5つ紹介します。
働きながら資格取得を目指せる
通信課程は在宅学習を基本としているため、フルタイムで働きながらでも学習を続けることが可能です。日々の業務で得た実務経験を学習内容と結びつけることで理解が深まり、福祉分野でのキャリア形成やスキルアップにもつながります。
また、多くの受講生が社会人であることから、スクーリングやオンライン学習コミュニティを通じて同じ立場の仲間と交流できるのも大きな魅力です。こうした学び合いは学習意欲の維持にも効果的に働きます。
勤務形態や生活スタイルに合わせて学習計画を立てやすい点は、大きなメリットです。
ただし2025年度以降は、相談援助実習が「240時間以上」「複数施設で必須」となったため、仕事や家庭との両立にはいっそうの計画性が求められます。
学費が比較的安い
通信課程の大きなメリットの一つは、通学制の大学や専門学校と比べて学費を大幅に抑えられる点です。
| 学習ルート | 期間 | 費用相場 | 特徴 |
| 通信制大学 | 約4年 | 100万〜160万円 | 学位取得と同時に受験資格を得られる |
| 一般養成施設(通信課程) | 1年半〜2年 | 60万〜90万円 | 大卒者向け。短期間で効率的に学べる |
| 通学制大学 | 約4年 | 300万〜400万円 | 費用が高めだが、通学型で学習環境が整っている |
| 専門学校 | 約2〜3年 | 200万~300万 | 実践的な学習が多いが、費用負担は大きい |
さらに、日本学生支援機構の奨学金制度や、大学・養成施設が独自に設ける学費分納・免除制度を活用すれば、経済的な理由で進学をためらっていた人にとっても現実的な選択肢となります。
地域を選ばず学習できる
通信課程は、インターネットや郵送を活用して学習を進められるため、都市部に通学することなく資格取得を目指せるのが大きな特徴です。
地方在住者や海外在住者でも、教材やオンライン講義を通じて学習の機会を得やすい環境が整っています。
スクーリングは一部必須です。しかし、多くの大学や養成施設では主要都市での集中開催や、土日・連休を利用した短期日程を採用しており、社会人でも参加しやすい形式になっています。
さらに近年では、オンラインスクーリング(ライブ配信・オンデマンド)を併用する学校も増えており、より柔軟な受講方法を選べるようになっています。
実習免除や単位認定で短縮できる場合がある
介護福祉士や精神保健福祉士などの資格を持つ場合、これまでは相談援助実習の一部免除や履修済み科目の単位認定が認められるケースがありました。
ところが、2025年度からの制度改正により、すべての養成課程で「相談援助実習240時間以上・複数施設での実施」が必須となり、原則として免除は廃止されました。
ただし、すでに他の国家資格を有する人は、短期養成施設(通信課程)を利用することで学習期間を半年〜1年程度に短縮できます。
このルートでは、介護福祉士や精神保健福祉士として培った知識や経験を前提にカリキュラムが設計されており、履修科目を抑えながら効率的に社会福祉士国家試験の受験資格を取得できます。
自分のペースで学べる
通信課程の大きな特徴は、自分で学習スケジュールを調整できる点です。
生活リズムや体調に合わせて進められるため、仕事や家庭の事情で学習時間が不規則になりやすい人でも、通勤時間や週末の空き時間を活用し、少しずつ学習を積み重ねられます。
自宅学習を中心に柔軟に取り組めることは、無理なく継続するための支えとなり、長期的な学習計画でも負担を抑えやすいという利点があります。
ただし、スクーリングや相談援助実習については大学や養成施設が指定する日程・会場での参加が必須です。
通信課程で社会福祉士を目指すデメリット
通信課程には多くのメリットがありますが、一方で注意すべき課題も存在します。特に自己管理の難しさや学習環境の制約は受講者が直面しやすい問題です。ここでは代表的なデメリットを5つ取り上げ、解決策とあわせて解説します。
レポート課題や学習量が多く負担が大きい
通信課程では、各科目ごとに複数のレポート課題が課されます。内容は、教科書や指定図書で学んだ理論を整理し、具体的な事例に当てはめて考察する形式が中心です。
これに加えて科目修得試験やスクーリングがあり、さらに2025年度以降は「相談援助実習240時間以上・複数施設での実施」が必須となったため、従来よりも学習負担はいっそう大きくなっています。
そのため、仕事や家庭と両立しながら学習を続けるには計画性が欠かせません。負担を軽減するためには、週単位で学習計画を立てるのが効果的です。
スクーリングや実習が避けられない場合がある
通信課程といっても、すべてを在宅で完結できるわけではありません。
対面授業であるスクーリングや、2025年度以降は必須となった相談援助実習(240時間以上・複数施設での実施)が組み込まれており、学習者にとって大きな負担となる部分です。
特に実習は長期間にわたり、勤務や家庭との調整が欠かせません。
- 土日や長期休暇を活用した集中スクーリング
- 主要都市での開催
- オンライン併用型の導入など
多くの大学や養成施設では、受講生が参加しやすいように工夫されています。
孤独になりやすくモチベーション維持が難しい
通信課程は自宅学習が中心となるため、仲間や教員との交流が限られ、孤独感を覚えることがあります。その結果、学習意欲が下がり、途中で学習を中断してしまうリスクも否定できません。
この課題を解消するには、まずスクーリングでの対面交流を大切にし、同じ目標を持つ仲間と関係を築くことが有効です。
多くの大学や養成施設が、オンラインフォーラムや学習管理システムを導入しており、質問や情報交換を通じて孤立感を軽減できる仕組みが整いつつあります。
また、学外でもSNSや勉強会といった自主的なコミュニティに参加することで、進捗を共有し合い、互いに励ましながら学習意欲を維持・向上させることができます。
就職・転職で年齢や実務経験が壁になる場合がある
社会福祉士の資格を取得しても、採用時には年齢や実務経験の有無が重視されることが多く、特に未経験者の場合は「資格だけでは即戦力とみなされにくい」という現実があります。実際の相談援助の現場では、資格に加えて実務経験や対人援助スキルが求められるためです。
ただし、近年は福祉分野の人材不足もあり、年齢よりもやる気や適性を評価して未経験者を採用するケースも増えています。
- 学習中から関連分野でのアルバイト
- 非常勤勤務
- 介護職
- 相談員補助
- 地域活動やボランティアなど
これらに取り組んでおくと、履歴書に実務経験を加えられ、資格の価値をさらに高めることができます。
学費以外の隠れコストがかかる
通信課程の学費は、通学制大学や専門学校に比べて年間20万〜40万円程度(総額100万〜160万円程度)と比較的安価です。ただし、実際にはこれに加えて以下のような付帯費用が発生します。
| スクーリング関連費用 | 交通費・宿泊費・食費 |
| 実習関連費用 | 実習地までの交通費、滞在費、生活費 |
| 教材費 | 教科書や指定図書の購入費用 |
| 通信・設備費 | 必要なパソコン・ネット環境 |
これらの費用を事前に見込んでおかないと、予算を超えてしまうことがあります。
負担を抑えるためには、教育訓練給付金(20〜70%支給)の活用、日本学生支援機構の奨学金制度、さらには大学独自の学費分納・減免制度を利用するのが効果的です。
よくある質問
最後に社会福祉士を通信で取得することに関してのよくある質問を紹介します。
社会福祉士は独学で取れますか?
独学だけでは取得できません。受験資格を得るには、大学や養成施設で厚生労働省が指定する科目を修了する必要があります。
さらに、2025年度以降は相談援助実習(240時間以上・複数施設必須)が必修となるため、必ず養成課程を経なければなりません。。
社会福祉士は働きながら勉強できますか?
通信課程を利用すれば、多くの社会人が仕事と学習を両立しています。レポートや試験を自宅で進められる仕組みが整っており、スクーリングも土日や集中形式で実施される場合が多いため、勤務の合間に学習を組み込みやすい環境です。
社会福祉士は何か月で取得できますか?
必要な期間は学歴や保有資格によって異なります。目安は以下のとおりです。
- 通信制大学:約4年(学士取得+受験資格取得)
- 一般養成施設(通信課程):1年半〜2年(大学・短大卒業者向け)
- 短期養成施設(通信課程):6か月〜1年(介護福祉士・精神保健福祉士などの資格保持者向け)
いずれのルートでも、2025年度以降は相談援助実習が必須となるため、従来より時間的・経済的な負担は増えています。
まとめ:あなたに最適な社会福祉士通信ルートを選ぼう
社会福祉士を通信で目指す方法は複数あり、学歴・保有資格・生活環境によって最適なルートは異なります。
通信課程には「働きながら学べる自由度」という大きな利点がある一方で、レポート課題の多さやスクーリング・実習の調整といった負担も避けられません。特に2025年度からは、相談援助実習が240時間以上・複数施設で必須となり、時間的・経済的な負担は従来よりも大きくなっています。
重要なのは、自分の状況に合った学習スタイルを見極め、資金計画と学習計画を立てて無理なく継続することです。これらを整えることで、社会福祉士資格取得への道は着実に開かれていきます。

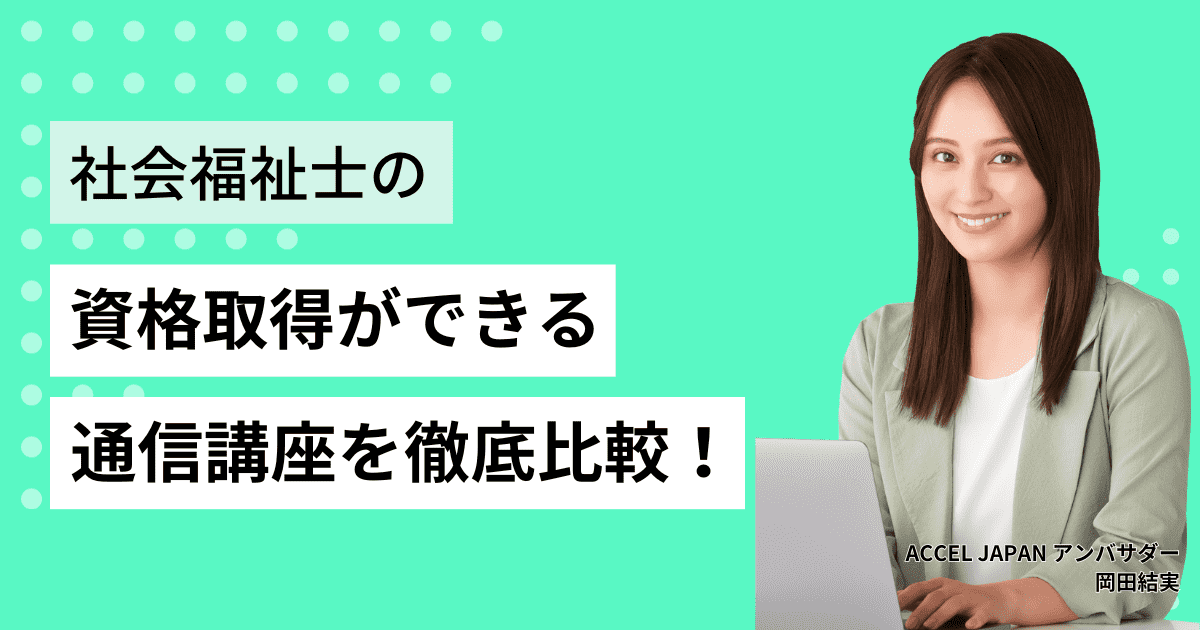


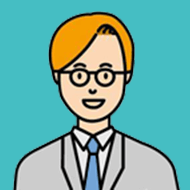
 児童福祉司が国家資格に!?厚生労働省が検討
児童福祉司が国家資格に!?厚生労働省が検討
 児童養護福祉士資格が新設!3月より認定講座開講
児童養護福祉士資格が新設!3月より認定講座開講




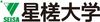





 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
 メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
 ぷらキャリって何?
ぷらキャリって何?
 短期集中は不安?それでも選ばれる理由があります!キャリアコンサルタント最短コースのリアル
短期集中は不安?それでも選ばれる理由があります!キャリアコンサルタント最短コースのリアル
 学びとキャリアのヒント集 ぷらキャリ記事一覧
学びとキャリアのヒント集 ぷらキャリ記事一覧





