心理カウンセラーとはどんな仕事?
心理カウンセラーとは、カウンセリングなどを行い、悩みを抱えた人の問題解決をサポートする仕事です。心や対人関係などの悩みに対応するため、臨床心理に関する専門知識が必要になります。
ストレス社会と言われる現代では心理カウンセラーの重要性は増しており、さまざまな場所で活躍しています。
ストレス社会と言われる現代では心理カウンセラーの重要性は増しており、さまざまな場所で活躍しています。
病院・クリニックなどの医療機関で働く
精神科医の指示のもと、利用者にカウンセリングを行い、問題解決や症状の緩和を支援します。
学校で働く
学校現場で子ども達や保護者、教師の悩みに対応し、問題解決を支援します。
企業で働く
企業の従業員に対して、仕事の悩みにのったり、健康をサポートしたりします。
福祉施設で働く
児童相談所や女性相談センターなどの福祉施設で、相談対応や支援を行います。
独立で働く
フリーランスや開業する方以外にも、副業として心理カウンセラーを始める方もいます。
病院で働く心理カウンセラー(臨床心理士)のある日のイメージをご紹介します。
- 8:00
- 今日1日の予定を確認。
最初にカウンセリングする方の準備をする。 - 8:10
- 外来で病院に来た方のカウンセリングや心理検査を行う。
- 12:00
- お昼休憩:同僚とおしゃべりしながら昼食
- 13:00
- 入院中の患者に対し、心理教育を行う。
同じ病気に悩む人達と一緒に、症状や治療方法、再発予防などを伝え、病気の対処法を身につけさせる。薬剤師や作業療法士とチームで取り組む。 - 15:30
- 入院中の患者のカウンセリングや心理検査を行う。
- 17:00
- 明日の予定を確認して、1日の仕事が終了。
心理カウンセラーの給料と働ける年齢
働く場所によって異なりますが、平均年収と就業形態をご紹介します。
- 平均年収
- 360万円~440万円
- 就業形態
- 正社員:50.8%
パートタイマー:29.2%
自営・フリーランス:27.7%
参考 職業情報提供サイトjob tag/求人ボックス
job tagのデータは、カウンセラー(医療福祉分野)が属する職業分類の統計情報です。
病院や企業などに所属する場合は、職場ごとで定年年齢が設けられていますが、自営業やフリーランスで働く場合は、年齢の制限なく働くことが可能です。
職場別!心理カウンセラーの仕事内容
医療現場
病院やクリニックでは、精神科医の指示のもと、患者にカウンセリングを行い、症状の緩和をサポートします。心理カウンセラーの代表的な資格の「臨床心理士」は、次のような専門業務を行います。
臨床心理査定
クライアントに対して、さまざまな心理テストや観察面接を行います。そして、クライアント独自の特徴や問題点を明らかにしたり、どのようにサポートするのがよいか検討したりします。他の専門家と一緒に検討することもあります。
臨床心理面接
クライアントに対してカウンセリングを行います。クライアントと人間関係を築く中で、共感や理解、納得といった心情が産まれる心的空間となります。クライアントによっては、精神分析や遊戯療法、集団心理療法など臨床心理学的技法を用いて心のサポートを行います。
臨床心理的地域援助
悩みを抱えている人だけにアプローチするのではなく、その人の周辺環境(地域住民や学校、職場など)にも心の健康をサポートする活動を行います。個人のプライバシーを守りながら情報を整理したり環境を調整したりします。また、一般的な心の健康の発展のためにも、講演や啓蒙活動を行います。
調査・研究
人々の心のサポートを行うため、知識やスキルの向上は大切です。そのため、基礎となる臨床心理的調査や研究活動が行われます。
学校現場
学校現場で、子ども達や教職員、保護者に対して相談・支援を行う人をスクールカウンセラーといいます。不登校やいじめの問題など、子ども達に寄り添い、心のケアや立ち直りを促します。
スクールカウンセラーが行う仕事内容の一部をご紹介します。
カウンセリング
スクールカウンセラーの代表的な業務で、子ども達の相談に応じます。面接が必要と判断された子どもや保護者に対しては、担任や担当教員と協力しながら面接を組み立てていく努力をします。また、長期の治療面接が必要となるケースもあり、外部の相談機関に依頼することもあります。
コンサルテーション
ものごとの見方や関わり方などを検討して、適切なアドバイスを行います。例えば、不登校に関する相談では、不登校への理解の仕方を示し、対応の仕方やフリースクールの是非などを伝えます。
カンファレンス
事例に対して関係者が情報共有を行い、その事例の解決に向けて役割分担や連携などを話し合います。学校内の生徒指導委員会や教育相談委員会などもカンファレンスの1つです。
これらの仕事の他にも、教職員や保護者に向けた研修を行ったり、問題が発生する前に予防的対応に努めたりします。
企業や職場
働く人達が抱える悩みをサポートするため、職場でカウンセリングを行う心理カウンセラーを産業カウンセラーといいます。産業カウンセラーが行う仕事内容の一部をご紹介します。
メンタルヘルスへの対策
従業員に対する個別のカウンセリングを行ったり、管理・監督者へメンタルヘルス研修を行ったりします。従業員に過度なストレスがかからないようにする予防方法や、ストレスのコントロール方法などを助言します。
人間関係開発へのサポート
予防開発的対策として、成長を促す人間関係の育成をサポートします。経営政策への参加意識やコミュニケーションスキル、自己開示などを指導します。また、よりよい職場環境を作るための職場づくりなど組織開発のプログラムを行います。
このような従業員のメンタルヘルスをサポートする仕事の他に、働く人のキャリアの選択や開発をサポートするキャリアカウンセラーという仕事もあります。就職や転職の悩みから、子育てと仕事との両立に関する悩みなどに対して、よりよいキャリアを描けるよう支援します。規模が大きい企業の中には、職場にキャリアカウンセラーを配置しているところも増えつつあります。
福祉
福祉施設でも、心理カウンセラーは活躍しています。例えば、18歳未満の子どもに関する相談を行う児童相談所では、虐待や非行などさまざまな悩みに対応します。
児童相談所の支援内容の一部をご紹介します。
助言指導
子どもに関する相談に対して、アドバイスや指示、情報提供を行います。必要な場合は、外部の専門機関を紹介して、他機関の援助につなぎます。相談内容は虐待相談だけでなく、障害、非行、不登校、しつけなど多岐に渡ります。
継続的な援助
必要に応じて、専門職員が一定期間援助を行います。その中で、カウンセリングやペアレントトレーニング、遊びを通じた治療プログラムなどを行う場合もあります。
児童関連の施設以外にも、身体・知的障害施設などの障害関連、DV相談支援センターなどの女性関連、特別養護老人ホームなどの老人福祉施設でも心理カウンセラーが活躍しています。
その他
上記でご紹介した場所以外にも、さまざまな場所で心理カウンセラーは活躍しています。
精神保健福祉センター
精神保健福祉センターとは、地域住民のこころの健康の向上や、社会復帰を目指す支援を行う機関で、各都道府県への設置が定められています。地域住民を対象に、心の問題を抱えている人やその家族からの相談に対応します。
民間のカウンセリング
民間の相談室を開いているところもあります。近年では、ビデオ通話や電話でカウンセリングをしたり、メールやチャットでやり取りしたりと、対面してカウンセリングを受ける以外の方法も行われています。
個人のカウンセリング
自宅のスペースを使ってカウンセリングを始めたり、電話やオンラインで相談を受けつけたりして、個人で心理カウンセラーの仕事を行う人もいます。また、近年ではスキルマーケットで副業を始める人もいます。自分のスキルや経験をサービスとして販売するスキルマーケットでは、「1分100円から相談にのります」というようにカウンセリングのサービスを提供している人もいます。
広がる働き方
民間のカウンセリングやスキルマーケットのように、電話やオンラインでカウンセリングを実施しているところもあります。カウンセリングというと対面のイメージがありますが、オンラインでの実施になり、在宅で働くことも可能となりました。
また、心理カウンセラー自体は、正社員の他に契約社員や業務委託、契約社員、独立、副業とさまざまな働き方があります。
心理カウンセラーになるには?
心理カウンセラーになること自体に、必須となる資格はありません。特に資格を持っていなくても心理カウンセラーを名乗ることはできます。しかし、実際に活躍している心理カウンセラーは、「臨床心理士」や「公認心理師」などの資格を持っている割合が高いです。
また、客観的にスキルを証明できる資格は、カウンセリングを受けるクライアントにとっても、カウンセラーを選ぶ際の指標となります。無資格者よりも資格を持っているカウンセラーの方が、専門知識やスキルがあると判断されて信頼されやすいです。
そのため、これから心理カウンセラーを目指す方は、心理学やカウンセリングスキルを身につけるためにも、資格の取得が最初のステップとなります。
心理カウンセラーの代表的な資格
代表的な資格
心理学に関する資格は、国家資格から民間資格までさまざまです。尚、職場によっては、「臨床心理士」や「公認心理師」などの特定の資格を採用条件に掲げていることもあります。取得難易度やご自身が働きたい職場などを踏まえて、どのような資格を取得したいか考えてみてください。
今回は心理カウンセラーに関する資格の中から7つご紹介します。
臨床心理士
心の問題に取り組む心理の専門職を証明する資格です。日本臨床心理士資格認定協会が認定する資格で、試験に合格すると取得できます。
試験を受けるためには、受験資格を満たさなければいけません。基本的には、大学院を修了していることが条件となります。
●主な受験資格
・指定大学院(1種・2種)を修了して、所定の条件を満たしている。
・臨床心理士養成に関する専門職大学院を修了している。 など
公認心理師
公認心理士とは、心の支援を必要とする人に対して、相談やサポートを行う仕事です。国家資格であり、資格を持っている者だけが「公認心理師」や「心理師」の文字を用いた名称を名乗ることができます。
国家試験に合格すると資格を取得できますが、受験資格が定められており、基本的には大学や大学院を修了していることが条件となります。
●主な受験資格
・大学と大学院でそれぞれ主務大臣指定の科目を修め、課程を修了している。
・大学で主務大臣指定の科目を修め、卒業後2年以上の実務経験を積んでいる。 など
認定心理士
日本心理学会が、大学で心理学の基礎知識や技術を習得した者に対して認定する資格です。心理学の専門家として働くのに必要な、最小限のスキルを習得していることを証明します。試験はなく、大学を卒業した者が資格の申請を行うことで取得できます。
JADP認定メンタル心理カウンセラー®
日本能力開発推進協会(JADP)が認定する資格で、医療や福祉などの場でカウンセリングを行う能力があることを証明します。認定教育機関が行う講座でカリキュラムを修了し、資格試験に合格することで取得できます。
産業カウンセラー
日本産業カウンセラー協会が認定する資格です。試験に合格することで取得できます。
●主な受験資格
・産業カウンセラーの養成講座を修了している。
・大学院で指定の課程を修了し、必要な科目単位を取得している。
・規定の実務経験があり、大学院で指定の課程を修了し、必要な科目単位を取得している。
・大学を卒業し、指定の単位を取得している。
チャイルドカウンセラー
日本能力開発推進協会が認定する資格で、学校内の問題対応に必要なスキルを持っているカウンセラーであることを証明します。認定教育機関などが行う教育訓練で、カリキュラムを修了して、試験に合格すると、資格を取得できます。
高齢者ケアストレスカウンセラー
職業技能振興会が認定する資格で、高齢者の心のケアを学べます。資格試験に合格することで取得できます。受験資格は18歳以上であることと、職業技能振興会が認定する「ケアストレスカウンセラー」の資格を持っていることです。(「ケアストレスカウンセラー」は18歳以上なら誰でも受験可能)
| 資格 | 主な取得方法 | 難易度 |
|---|---|---|
| 臨床心理士 | 大学院を修了後、試験に合格する。 | 上級者向け |
| 公認心理師 | 大学・大学院を修了後、試験に合格する。 | 上級者向け |
| 認定心理士 | 大学で科目を履修する。 | 上級者向け |
| JADP認定メンタル心理カウンセラー® | 講座修了後、試験に合格する。 | 初心者向け |
| 産業カウンセラー | 養成講座を修了後、試験に合格する。 | 初心者向け |
| チャイルドカウンセラー | 講座修了後、試験に合格する。 | 初心者向け |
| 高齢者ケアストレスカウンセラー | 試験に合格する。 | 初心者向け |
資格取得後の流れは?
●病院や学校、企業などに所属する場合
それぞれの求人情報に申し込みます。職場によっては特定の資格取得を応募条件にしているところもあります。例えばスクールカウンセラーは、「臨床心理士」の資格を条件にしているところが多いです。就きたい仕事に応じて、どのような資格が求められるのか、事前に調べましょう。
●独立する場合
オフィスを借りたり、自宅を用いたりして開業する人もいます。スキルマーケットでカウンセリングサービスを販売することも可能です。
心理カウンセラーに向いている人は?
人の話を聞くのが好きな人
心理カウンセラーは、クライアントに質問をして話を引き出したり、相談内容を分析したりしながら相談に応じます。カウンセリングには傾聴のスキルが求められるため、人の話を聞くのが好きな人は、心理カウンセラーに向いていると言えます。
心理学に興味があって勉強熱心な人
クライアントが抱えるさまざまな悩みに対応するために、臨床心理に関する専門知識やカウンセリングのスキルは常にアップデートすることが大切です。心理学に興味があって勉強熱心な人は、心理カウンセラーとして働くようになった後も自己研鑽を続けられると考えられます。
チームで協力することが得意な人
心理カウンセラーの仕事は、クライアントと一対一の関係のイメージがあるかもしれません。しかし、関係機関などと連携してクライアントの問題解決をサポートすることがあり、チームワークが大切になります。
物事を客観的に見ることができる人
心理カウンセラーの仕事は、クライアントの悩みを聴くだけではありません。カウンセリングの結果を整理したり、クライアントの状況を分析したりして今後の方針を検討します。そのため、物事を客観的に見る力は、心理カウンセラーの仕事の上で大切になります。
心理カウンセラーの今後の需要は?
現代社会では、カウンセリングの重要性が増しています。
厚生労働省の「自殺対策白書」では、先進国(日本・アメリカ・フランス・カナダ・ドイツ・イギリス・イタリア)の中で、日本は自殺死亡率(総数)が高いということが示されています。
参考 自殺対策白書|厚生労働省
政府は地域の自殺対策として、自治体の実情に応じて交付金を活用しています。その中には、対面相談事業、電話・SNS相談事業といった、カウンセリングに関わる事業が挙げられています。
また、文部科学省の「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」では、小学校・中学校で不登校児童が増加傾向にあることが指摘されています。そのため、課題の早期発見やサポートを担うスクールカウンセラーの配置充実が進められてきました。
このように、子どもから大人まで、悩みを相談できるカウンセラーの存在は重要になってきています。
カウンセリングが自分にできるか不安...そんなときは?
心理カウンセラーに興味がある方の中には、大変な仕事というイメージから、「自分にできるかな」と不安に思う方もいると思います。
そのような方は、ボランティアやインターンシップ、アルバイトを活用して経験を積むということも1つの方法です。例えば、無料で相談できる「いのちの電話」は、ボランティアの相談員によって構成され、約1年半の養成研修を修了した人が相談員として活躍しています。
「心理カウンセラーとして働きたい」と考える方は、自分にできることから始めてみてはいかがでしょうか。
まとめ
心理カウンセラーの仕事内容のイメージはついたでしょうか。「心理学について今から学べるかな」と不安な方もいるかもしれません。しかし、民間のスクールや通信講座で学べる資格もあるため、すでに社会人の方でも資格を取得することが可能です。心理カウンセラーの仕事に興味を持った方は、ぜひ、資格取得にも挑戦してみてください。
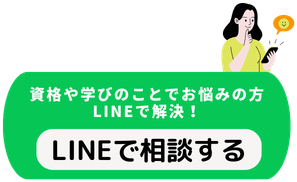
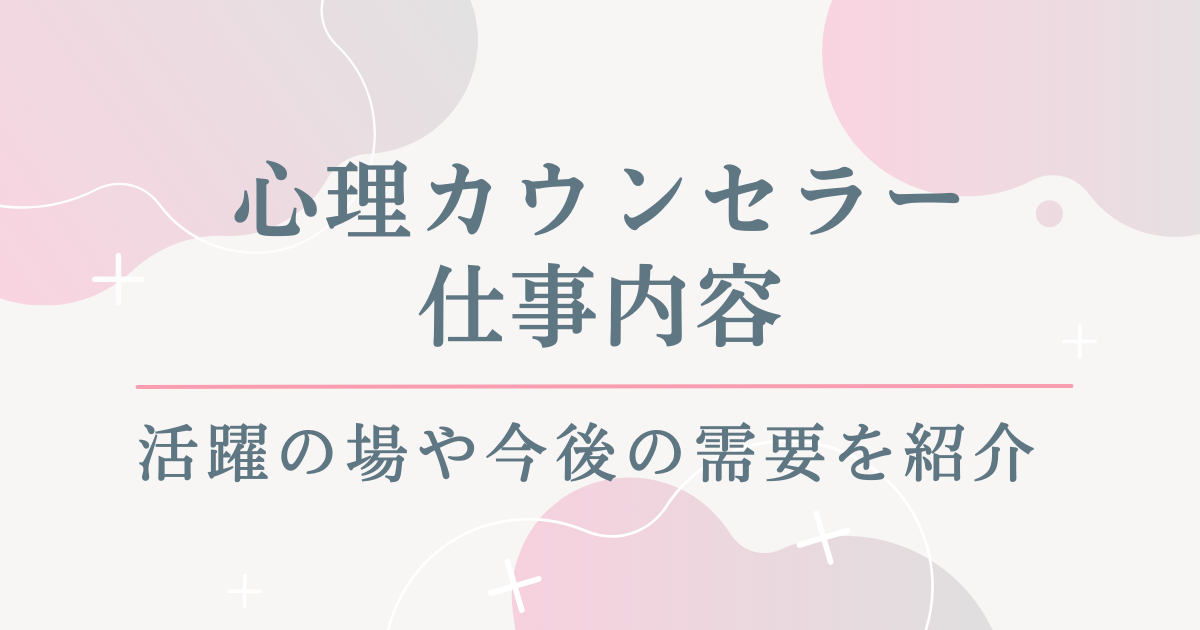


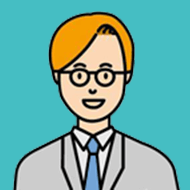
 オンライン心理学教室4月開講! 実践に強い資格が取れるカウンセラー育成スクールが5月にスタート!
オンライン心理学教室4月開講! 実践に強い資格が取れるカウンセラー育成スクールが5月にスタート!
 メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
 心理学で、自分と誰かの人生を整える。「心」の専門家として歩み始める第一歩
心理学で、自分と誰かの人生を整える。「心」の専門家として歩み始める第一歩
 周りから頼られ、相談される人になる! 性格診断『エゴグラム』から導くタイプ別対話術
周りから頼られ、相談される人になる! 性格診断『エゴグラム』から導くタイプ別対話術




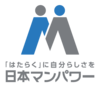



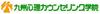







 「キャリア」の語源を知っていますか?【4月コースは豪華特典】で一生モノの国家資格!
「キャリア」の語源を知っていますか?【4月コースは豪華特典】で一生モノの国家資格!
 2026年3月1日掲載の新スクール&特集ページを大紹介!
2026年3月1日掲載の新スクール&特集ページを大紹介!
 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
 人気のZUMBAインストラクターになろう!動画orライブ配信トレーニングが選べる&今だけ50%OFF!
人気のZUMBAインストラクターになろう!動画orライブ配信トレーニングが選べる&今だけ50%OFF!





