独学でキャリアコンサルタント試験を受けるための条件とは?
独学で受験するためには実務経験が必要
キャリアコンサルタント試験を独学で受験するためには、キャリアコンサルティングの実務経験が3年以上必要です。まずは、厚生労働省が定めるキャリアコンサルタント試験の受験資格をご確認ください。
・厚生労働大臣が認定する講習の課程を修了した者(講習カリキュラムは別表に記載)
・労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上のいずれかに関する相談に関し3年以上の経験(4を参照)を有する者
・技能検定キャリアコンサルティング職種の学科試験又は実技試験に合格した者
・上記の項目と同等以上の能力を有する者
上記のいずれかの条件を満たすことで、キャリアコンサルタント試験の受験が可能となります。
関連記事:
キャリアコンサルタントの受験資格とは?未経験でも取得できる!
この条件の中で独学での受験が可能な方は、2番目から4番目に該当する方となります。2番目の、「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上のいずれかに関する相談に関し3年以上の経験を有する者」というのは、企業や大学などで3年以上、キャリアコンサルティングに携わった実務経験を持つ方、という意味です。
3番目の「技能検定キャリアコンサルティング職種の学科試験又は実技試験に合格した者」とは、国家検定であるキャリアコンサルティング技能検定に合格した方という意味であり、この検定を受験するためにも3年以上の実務経験が必要です。
独学で受験する人は少ない
独学でキャリアコンサルタント試験を受験する方は非常に少なく、受験者の1割程度です。
2023年11月実施の第24回キャリアコンサルタント試験(学科試験)では、独学での受験である実務経験をもって受験資格を得た人の割合は10.40%でした。
学科試験の受験資格別 受験者数割合
| 受験資格 | 受験者数 | 受験者数割合 |
|---|---|---|
| 養成講習修了者 | 3,822 | 89.55% |
| 実務経験者 | 444 | 10.40% |
| 技能検定の合格者 | 2 | 0.00% |
出典 第24回キャリアコンサルタント試験の概要(pdf)|厚生労働省
また、同試験の実技試験では、独学での受験である実務経験をもって受験資格を得た人の割合は10.27%でした。
実技試験の受験資格別 受験者数割合
| 受験資格 | 受験者数 | 受験者数割合 |
|---|---|---|
| 養成講習修了者 | 4,507 | 89.00% |
| 実務経験者 | 520 | 10.27% |
| 技能検定の合格者 | 37 | 0.73% |
またBrushUP学び内でキャリアコンサルタント関連の講座への資料請求は毎年14,000件以上あり、毎年一定の人が講座を受講しています。
| 年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 資格請求数 | 14,119 | 16,487 | 14,478 | 14,455 |
※BrushUP学び内における2020年から2023年までのキャリアカウンセラー関連の資格請求数
これらのことからキャリアコンサルタント試験を受験する方のほとんどが、独学ではなく講習を受けていることが分かります。
キャリアコンサルタント試験を独学で受ける場合の合格率
独学でキャリアコンサルタント試験に合格することは可能です。しかし、独学で受験する方の合格率は、養成講習を修了した方の合格率よりも低い傾向があります。
厚生労働省が公表している2023年11月実施の第24回キャリアコンサルタント試験のデータからは、以下のような数字が読みとれます。
第24回 キャリアコンサルタント学科試験データ
| 受験資格 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 養成講習修了者 | 3,822人 | 2,086人 | 54.58% |
| 実務経験者 | 444人 | 158人 | 35.59% |
第24回 キャリアコンサルタント実技試験データ
| 受験資格 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 養成講習修了者 | 4,507人 | 3,049人 | 67.65% |
| 実務経験者 | 520人 | 247人 | 47.5% |
学科試験、実技試験ともに、独学者(実務経験者)の合格率は養成講習修了者よりも下回っていることが分かります。
キャリアコンサルタント資格の独学で合格するためのステップ
ここからは、キャリアコンサルタントの資格を独学で合格するための方法をステップ別に紹介します。
上記のステップを踏むことで、時間やお金をかけずに、効率的にキャリアコンサルタントの資格取得を目指せます。
目標の設定
まず、合格を目指す試験の範囲や難易度を把握し、それに基づいて明確な目標を設定します。
次に、必要な勉強時間やスケジュールを考慮することが大切です。適切な目標を設定することで、学習のモチベーションを維持できます。その結果、効果的な学習計画を立てることが可能です。
具体的な目標設定の例として、以下のようにまとめるとよいでしょう。
| 目標の内容 | 期間 |
|---|---|
| 毎週10時間以上の学習時間を確保する | 毎週 |
| キャリアコンサルティング理論の基礎を修得する | 2ヶ月以内 |
| 模擬カウンセリングを10回以上実施する | 3ヶ月後まで |
| 模擬試験で80%以上の正答率を達成する | 6ヶ月後 |
| キャリアコンサルタントの資格を取得する | 1年以内 |
このように具体的な数値目標を立てることで、達成度を測りやすくなります。
しょう。
教材の選定
信頼性の高い参考書やオンラインコースを選ぶことが重要です。特に、過去問題集を活用して試験の傾向や出題形式を把握することが有効です。基本的な知識を学ぶためには、「キャリアコンサルティング概論」のような包括的な教科書を使用しましょう。
次に、「キャリア理論ハンドブック」といった専門的な参考書を用いて、知識を深めることが必要です。実践力を養うためには、「ケーススタディ集」や「模擬面接演習DVD」などの教材が役立ちます。
試験対策は「模擬試験問題集」を使って、実際の試験形式に慣れるようにしましょう。オンライン学習教材やアプリなどは、隙間時間を有効に活用するためのよい方法です。
学習計画の作成
日々の学習計画を立て、週ごとや日ごとの学習目標を設定することが大切です。進捗状況を着実に確認しながら、目標達成までの期間を考慮しましょう。
具体的な学習計画作成を例として紹介します。
| 月数 | 期間 |
|---|---|
| 1ヶ月目~2ヶ月目 | 基礎知識の習得 |
| 3ヶ月目~5ヶ月目 | 応用知識と実践スキルの向上 |
| 6ヶ月目 | 総復習と模擬試験 |
これにより、各月の目標が明確になり、学習計画がより具体的になります。
次に、週単位の詳細な計画を作成しましょう。
平日は1日2時間、週末は1日4時間の学習時間を確保し、具体的な時間配分を決定します。さらに、各学習で扱うテーマや教材を明確にし、定期的な復習と自己評価の時間も取り入れることが重要です。
知識の習得
定期的に学習を進め、理解度を確認することが重要です。
理解が難しい部分は復習を行い、問題集や模擬試験を活用して理解を深めます。例えば、キャリア発達理論や職業選択理論といった基礎的な理論の学習が挙げられます。次に、労働市場の動向や雇用関連法規など、実務に直結する知識を習得しましょう。
カウンセリング技法やアセスメントツールの使用方法など、実践的なスキルに関する知識も深めます。これらの学習には、テキストの精読に加え、要点のノート作成、関連する事例の研究、オンライン講座の受講など多角的なアプローチを取ることが効果的です。
実践的な学習
理論だけでなく、実務経験や実践的なスキルも身につけることも大切です。
事例集やロールプレイを活用して、実務的な問題に対処する能力を養います。例えば、家族や友人を相手にロールプレイを行い、基本的なカウンセリングスキルを練習します。これは、現実の場面でのスキル適用をシミュレーションするよい機会です。
次に、オンラインの模擬カウンセリングに参加することで、より現実的な環境での経験ができます。これにより、異なるシチュエーションでの対応力を高められます。
自分のカウンセリングセッションを録画して振り返り、改善点を分析することも効果的です。自己評価と継続的な改善が可能になります。
持続と徹底
継続的な努力も大切です。モチベーションを維持しながら、コツコツと学習を続けていきます。試験直前には過去問や模擬試験を解き、実践的な対策を行いましょう。
具体的な方法として、まず、日々の学習ルーチンを確立し、毎日決まった時間に学習を取り入れることで、学習を習慣化できます。次に、学習の進捗を定期的に記録し、目標との差異を分析してください。分析により、自分の学習状況を把握し、必要な調整を行えます。
また、モチベーションを維持するために、小さな達成を自己褒美で祝う習慣を作るとよいでしょう。これにより、学習意欲を保ちながら、楽しみを持って学び続けられます。
キャリアコンサルタントを独学で取得する際の勉強時間
キャリアコンサルタント試験を独学で受験する際の勉強時間の目安は、厚生労働省のキャリアコンサルタントになりたい方へを参考にした場合、150時間とされています。
各スクールの養成講習を受講した場合の平均学習時間は、以下のとおりです。
| スクール名 | 平均学習時間 |
|---|---|
| JAICO | 153時間 |
| LEC東京リーガルマインド | 155時間 |
| 資格の大原 | 160時間 |
独学の場合、苦手分野の克服や自信を持って試験に臨むためには、さらに時間をかける必要があります。
完全未経験から始める場合は、おおよそ200〜300時間を目安にすると良いかもしれません。実技試験対策は独学では難しいため、スクールの単科講座やYouTubeのロールプレイ動画を活用するのがおすすめです。
キャリアコンサルタントの資格を独学で取得する3つのメリット
資格取得にかかる費用が節約できる
独学で学習するメリットの1つは、資格取得にかかる費用が節約できることです。
キャリアコンサルタントの養成講習を受講するとなると、受講料だけでも30万円から40万円程度の費用が必要となります。
一方、独学であれば、テキスト代や受験費用(学科:8,900円、実技:29,900円)、名簿への登録料(登録免許税:9,000円、登録手数料:8,000円)だけで済むため、費用がグッと抑えられるでしょう。
勉強する時間や場所の制約がない
独学のもう一つのメリットが、時間や場所を問わず勉強できる点です。独学を希望する方の中には仕事で忙しく、養成講習に通う時間がないという方も多いでしょう。独学であれば、スクールのように時間で拘束されることがないため、休日や深夜など、都合のよい時間に勉強に取り組めます。また、通勤電車の中やカフェ、図書館など、自分の集中しやすい環境で勉強することも自由です。
自分に合う教材で学習を進められる
キャリアコンサルタントを独学で学ぶ方法では、自分のペースや学習スタイルに合わせて教材を選べます。市販の参考書やオンライン講座、過去問題集など、多様な教材の中から自分に最適なものを選ぶ自由があり、学習効率を最大化することが可能です。
例えば、視覚的学習が得意な人は図解や図表が豊富な教材を選ぶと効果的です。また、聴覚的学習者は講義音声や対話形式の解説CDなどのオーディオ教材を利用すると理解が深まります。読み書きによる学習を好む人には、詳細な解説と練習問題が豊富なワークブック形式の教材がおすすめです。
このように、自分の学習スタイルに合った教材を選択することで、独学でも効率的にキャリアコンサルタントの知識を身につけられます。
キャリアコンサルタントの資格を独学で取得する3つのデメリット
キャリアコンサルタントの資格を独学で取得することには、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、独学で資格取得を目指す際に直面する可能性のある3つのデメリットについて詳しく紹介します。
独学での合格率は低い傾向にある
キャリアコンサルタント試験を独学で受ける場合、実務経験者の合格率は養成講習修了者に比べて低い傾向があります。これは、独学では体系的な学習がしにくいためです。
まず、試験範囲が非常に広く、科目数も多いため、独学では何から手をつければよいのか迷うことが多いです。その結果、計画的に勉強を進めるのが難しくなり、効率的な学習ができないことがあります。
また、独学では最新の試験傾向や出題ポイントを把握するのが難しいです。養成講座では、過去の試験分析に基づいた的確な情報が提供され、重要な項目を見落とすことなく学習が進められますが、独学ではそれを自力で収集し、分析しなければならないため、情報の偏りや不足が発生する可能性があります。
このように、独学では計画的でバランスの取れた学習が難しく、合格率が低くなるリスクがあります。
実技試験対策が難しい
キャリアコンサルタントの試験には実技試験(面接試験と論述試験)があります。面接試験のロールプレイと、口頭試問が独学で受験する人にとって難関です。
ロールプレイでは、クライアントに寄り添った臨機応変な対応が求められますが、独学だと実践経験とフィードバックを受ける機会が少ないため、柔軟に対応するのが難しい傾向にあります。
また、実務経験がある人でも、自分の「悪いクセ」に気づかずに試験に臨むこともあるため、合格するためにはキャリアコンサルタント理論に基づいた対策が必要です。
口頭試問では、受験者の理論的な理解や実務における応用力が試されます。独学での準備では、細かい部分まで深掘りされる質問に対応するための練習が不足しがちです。そのため、実務経験がある人でも、自分の「悪いクセ」に気づかずに試験に臨むことがあり、合格にはキャリアコンサルタント理論に基づいた対策が必要です。
学習効率が下がる可能性がある
キャリアコンサルタントの学習は、独学だと効率が低下する可能性があります。
【学習効率が下がる主な理由】
- 学習内容の構造化が難しい
- 質問や疑問を即座に解決できない
- 学習ペースの管理が難しい
養成講座ではカリキュラムが体系化されています。しかし、独学では自分で学習内容を組み立てなくてはいけません。その際、どこから学習するべきかが難しく、混乱してしまいます。
また、養成講座では講師に直接質問できますが、独学では疑問が解決できないまま進むことも多いため、知識の理解が不完全になります。さらに、独学では計画通りに進めるのが難しく、詰め込み学習やペースダウンが起こる可能性が高いです。
孤独感を抱きながら、1人で勉強に立ち向かう必要があるため、安定した学習リズムの維持が難しい傾向です。

キャリアコンサルタントの受験資格を独学で取得できない場合はスクールを利用する
ここからは、キャリアコンサルタント資格取得のためのスクールをいくつか紹介します。
キャリアコンサルタントを独学で取得した方の体験談
ここでは、キャリアコンサルタントを独学で取得した方の体験談を紹介します。
(私は独学受験してしまったので、若干後悔しています。独学のせいで特定の領域に偏った学習をしてしまったので、満遍なく学びたい人はキャリアコンサルタント養成講座受講がおすすめです。)
引用:X
国家資格キャリアコンサルタント受けます。スクーリングは時間かかるし高いから独学でいきます。独学は難しいらしいけど。
まずは腕試しで学科にトライ。理論とか知らない事もあるけど、現役の人事の職制ですから。
結果はいきなり合格圏内。学科は大丈夫かな。あとは論述と面接。面接が難関だね。
引用:X
独学で合格するのは難しいといった体験談が多くあります。
このようにキャリアコンサルタントの資格は独学で取得可能ですが、難しく感じる人もいます。合格率を高めたいのであれば、次の項目で紹介するスクールを利用しましょう。
キャリアコンサルタントの独学に関するQ&A
キャリアコンサルタント資格の独学に関して、多くの方が疑問や不安を抱えています。ここでは、よくある質問とその回答を紹介し、独学で資格取得を目指す方々の参考になる情報を提供します。
キャリアコンサルタントのおすすめの勉強方法は?
キャリアコンサルタントの試験に独学で臨む場合、以下の勉強方法がおすすめです。
- テキストによる基礎知識の習得
- 音声教材の活用
- 実践的なロールプレイング
- オンライン学習コミュニティへの参加
- 模擬試験の活用
一つの勉強方法に固執するのではなく、すべて試したうえで自分にぴったりな方法を複数組み合わせてみましょう。
電車で移動する際は音声教材、家で勉強に集中できる際はテキストなど、うまく活用することで、キャリアコンサルタント試験に向けた効率的な学習が可能となり、合格への道が開けます。
キャリアコンサルタントの試験対策アプリは何がある?
キャリアコンサルタント試験対策に役立つアプリとして、「キャリアコンサルタント試験対策アプリ」があります。
本アプリでは、過去問や模擬試験問題を解く練習が可能です。移動中や隙間時間を有効に使い、効率的に学習を進められます。
まとめ
キャリアコンサルタント試験を独学で受験するには、メリット・デメリット両方が存在します。両方を把握しながら自分の環境や性格に合った勉強方法を見極めて合格を目指しましょう。

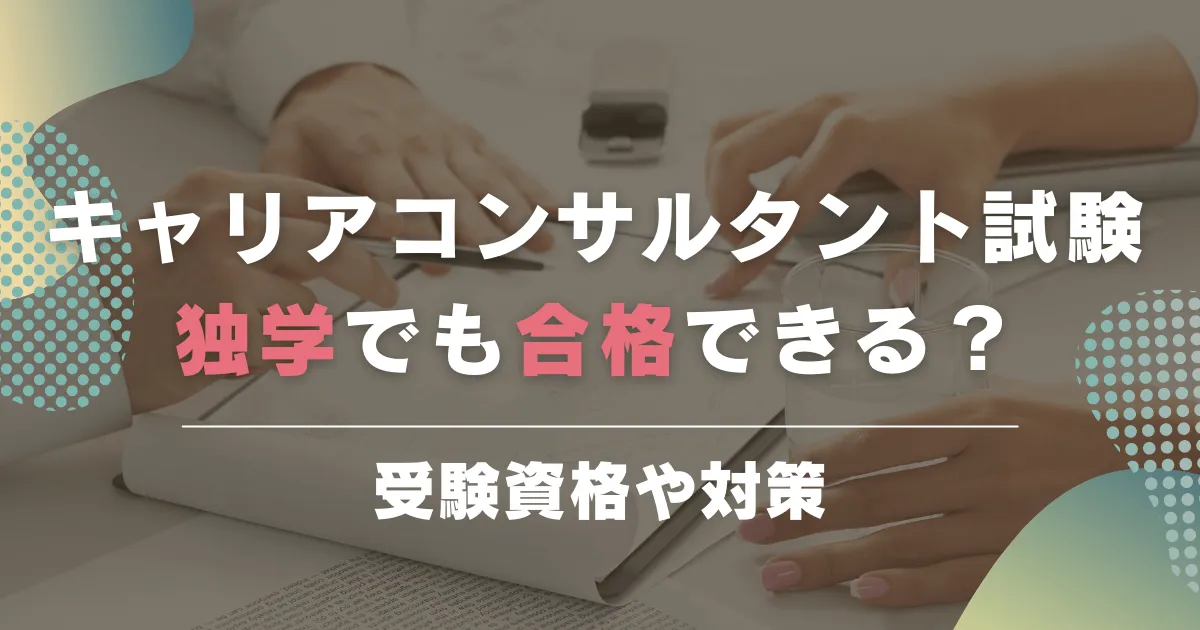







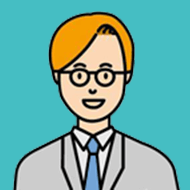
 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
 キャリアコンサルタント資格はどんな人に向いている?活かせるタイプ別解説
キャリアコンサルタント資格はどんな人に向いている?活かせるタイプ別解説
 仕事・育児と両立しながら国家資格取得を目指す【キャリアコンサルタント養成講座】
仕事・育児と両立しながら国家資格取得を目指す【キャリアコンサルタント養成講座】
 キャリアコンサルタントの資格の活かし方― 「独立して成功をつかむ秘訣」(11月/オンライン)
キャリアコンサルタントの資格の活かし方― 「独立して成功をつかむ秘訣」(11月/オンライン)




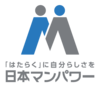








 失敗しにくい学び直しの始め方|資格を決める前の準備編
失敗しにくい学び直しの始め方|資格を決める前の準備編
 オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!
オンライン心理学教室4月開講! 実践カウンセラー育成スクールが新たにスタート。5月開講!
 メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
 心理学で、自分と誰かの人生を整える。「心」の専門家として歩み始める第一歩
心理学で、自分と誰かの人生を整える。「心」の専門家として歩み始める第一歩





